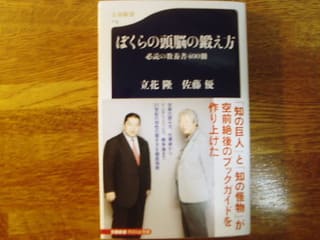
文春新書の新刊です。
猛烈な読書家である立花+佐藤の両氏により、古典200冊、新書・文庫200冊が選ばれた。
文春文庫 最初のページを「立ち読み」できます。
ここ数日、twitter (つぶやき)といわれる世界を覗いています。1つの記事の上限140字という一口メッセージです。多くのtwitterを読んだせいか、人生の残された時間をなにかどっしりとしたものを読んで終えたい・・という気持ちが沸いてきたときに見つけた新刊。
最初に、
立花、佐藤が選んだ各200冊、計400冊の本のリストをチェックする。
膨大な分野なので実際に読んでいるのはごく僅か。
立花は、殆どの本にはごく簡単なコメントか、コメントなし。その代わり、ごく一部の本には相当のページを割いている。(後述)
佐藤は、すべての本に数行のコメント。
本論は、2人による対談です。
この2人は、ともに現代の反権力・知の巨人ではあるが、意見が相違することも多くて迫力ある対談となっています。
400冊の本の紹介をここではできませんが・・・
若い世代の人には、こういう手引書をもとに猛烈に読書する体験をすることを薦めたいです。私が読んだことがあるのは、岩波文庫の哲学ものなどで、殆どは、1961年、当時の大学1年生のときに読んでいます。友人たちの議論の輪に加わりたいがために読みましたが、いま思うと、私の現在の読書習慣の基礎は、この1年間で形成されていますね。
2人が強調しているのは、
インターネットの時代で、膨大な情報は検索できるが、どのような概念で、どのような用語を検索するかは、読書による基礎的な教養によるという。
twitterを覗いて思うのは、
読書力で鍛えられたつぶやきもある反面、
「朝起きた」「・・・を食べた」「電車の中で前にいるおじさんは・・」という携帯電話によるメールのようなつぶやきも多い。
立花が
数ページにわたって紹介しているのは、
ドイツのヴァイツゼッカー大統領が、1985年5月8日、ドイツ降伏40周年に行った演説。pp.295-299.
戦争責任をめぐる原理的・倫理的な反省が最高責任者によって語られた。
私も、ドイツに3年いた関係で、この演説の原文をもっています。格調高い演説です。幾つかの邦訳があります。
いまの日本社会は、こういったけじめの議論を政治家がやっていませんね。
ドイツ人が殺したユダヤ人は620万人だったか。これに対して、日本が、中国や韓国で今次の戦争で殺した人は、1000万人をこえている。
【印象に残った箇所から】
以下、2人の対談から、私が記憶に残った箇所。
(人さまざまだと思いますが、2人の対談の白熱したことを思い出しながら・・)
・数学の重要性 p.37
・外務省の腐敗 p.52
・コーヒーハウスの役割 p.132
・社会のダークサイドを知識として知ること p.166
・ヨーロッパではナチスの優生学の関係もあり血液型で人を占うことはしない p.176
・「反貧困」の湯浅誠氏の評価は高い p.200
・今話題の勝間和代については、評価が分かれる p.204
・大学院の入学者の基礎学力レベルが低下している p.232
・日本では、ほんとうのエリートは海外の大学へ行っている p.238
・たこつぼ型の知識を克服するため、全体像をつかむ「教養」が必要だ p.242
→具体的なアイデアとして巨大書店の各コーナーを歩けと提案
猛烈な読書家である立花+佐藤の両氏により、古典200冊、新書・文庫200冊が選ばれた。
文春文庫 最初のページを「立ち読み」できます。
ここ数日、twitter (つぶやき)といわれる世界を覗いています。1つの記事の上限140字という一口メッセージです。多くのtwitterを読んだせいか、人生の残された時間をなにかどっしりとしたものを読んで終えたい・・という気持ちが沸いてきたときに見つけた新刊。
最初に、
立花、佐藤が選んだ各200冊、計400冊の本のリストをチェックする。
膨大な分野なので実際に読んでいるのはごく僅か。
立花は、殆どの本にはごく簡単なコメントか、コメントなし。その代わり、ごく一部の本には相当のページを割いている。(後述)
佐藤は、すべての本に数行のコメント。
本論は、2人による対談です。
この2人は、ともに現代の反権力・知の巨人ではあるが、意見が相違することも多くて迫力ある対談となっています。
400冊の本の紹介をここではできませんが・・・
若い世代の人には、こういう手引書をもとに猛烈に読書する体験をすることを薦めたいです。私が読んだことがあるのは、岩波文庫の哲学ものなどで、殆どは、1961年、当時の大学1年生のときに読んでいます。友人たちの議論の輪に加わりたいがために読みましたが、いま思うと、私の現在の読書習慣の基礎は、この1年間で形成されていますね。
2人が強調しているのは、
インターネットの時代で、膨大な情報は検索できるが、どのような概念で、どのような用語を検索するかは、読書による基礎的な教養によるという。
twitterを覗いて思うのは、
読書力で鍛えられたつぶやきもある反面、
「朝起きた」「・・・を食べた」「電車の中で前にいるおじさんは・・」という携帯電話によるメールのようなつぶやきも多い。
立花が
数ページにわたって紹介しているのは、
ドイツのヴァイツゼッカー大統領が、1985年5月8日、ドイツ降伏40周年に行った演説。pp.295-299.
戦争責任をめぐる原理的・倫理的な反省が最高責任者によって語られた。
私も、ドイツに3年いた関係で、この演説の原文をもっています。格調高い演説です。幾つかの邦訳があります。
いまの日本社会は、こういったけじめの議論を政治家がやっていませんね。
ドイツ人が殺したユダヤ人は620万人だったか。これに対して、日本が、中国や韓国で今次の戦争で殺した人は、1000万人をこえている。
【印象に残った箇所から】
以下、2人の対談から、私が記憶に残った箇所。
(人さまざまだと思いますが、2人の対談の白熱したことを思い出しながら・・)
・数学の重要性 p.37
・外務省の腐敗 p.52
・コーヒーハウスの役割 p.132
・社会のダークサイドを知識として知ること p.166
・ヨーロッパではナチスの優生学の関係もあり血液型で人を占うことはしない p.176
・「反貧困」の湯浅誠氏の評価は高い p.200
・今話題の勝間和代については、評価が分かれる p.204
・大学院の入学者の基礎学力レベルが低下している p.232
・日本では、ほんとうのエリートは海外の大学へ行っている p.238
・たこつぼ型の知識を克服するため、全体像をつかむ「教養」が必要だ p.242
→具体的なアイデアとして巨大書店の各コーナーを歩けと提案


























この二人の対談は興味がありますが、とても身近な人とはいえないのでまだ読んでいません。
読まなくてはなりませんね。