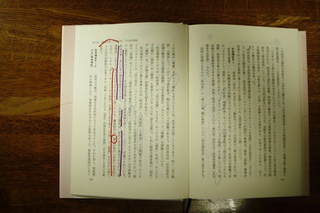
【今日で最終回です】
吉田久一『新・日本社会事業史』(勁草書房、2004)を読んできました。
今日は、第15章で最終回です。(写真は、そのさわり部分)
1980年代から2004年(本書執筆)まで。同時代史となり、書き方が難しい。
2004年以降今日までの変化も大きい。
吉田久一先生は、1949年度以来、さまざまなコースで社会福祉の歴史を講じてこられた。4単位、30回で終えるように本書も構成されている。
豊富な情報量で、このブログではキーワード風にごく簡単に全体の流れを紹介したにすぎません。
【座標軸のない日本の社会福祉】
これまでの章でも触れられてきたが、
○ 西欧社会事業史と比較すると、日本の場合、連続性が乏しい。
○ 日本福祉実践史で、世界に誇るべきものもあった。 p.342
○ 政策は(ヨーロッパと比較して)十分ではないのに、方法論だけは欧米の優れたものを導入してきた。 p.342
○ 従来の方法との「交渉→変革→定着」がなく、「改革」よりも「変化」「変更」
○ 利用者と実践的「主体者」の関係 p.345
(日本では)時代と社会に規定されながら「循環関係」にある。
例として、鎌倉時代の一遍など。
「社会」を否定しながら、しかも「」「ハンセン患者」を通じて生き返る「平等」と「循環」(その近代的解釈が必要)
【感想】
具体的な政策、人物、著書などが挙げられていて有用です。
考察の部分はやはり難解です。一読してわからないです。あるいはその文脈がかもしだす「気分」だけはわかるというべきか。
吉田久一先生とは、日本社会事業大学がまだ原宿にある頃、古ぼけた図書館でよくお会いした。今から思えば、もっと先生のご本を読み、お聞きしておけばよかった。
社会福祉法(2000年)については、社会的責任が希薄、「社会福祉の定義がない」などと批判しておられる。p.338
個別法である介護保険法のあとに普遍法である社会福祉法ができたところに社会福祉政策そして社会福祉学の観念性が現れている、と私は思います。
社会福祉士及び介護福祉士法(1987年)については、1行で片付けているp.335
が、ここには吉田先生の社会福祉への理解の特質が現れている。カリキュラムが公定され、歴史的な考察などが後退することを予見されていたからとも思いますが、(批判されるにせよ)もう少し、書いておいて欲しかった。
ともかくにも「社会福祉学」の水準を具体的に示すものだからです。
*このシリーズでは、毎回、50前後のアクセスをいただきました。ご愛読ありがとうございました。
これからは、時間があれば、先生のより本格的な著書に向かうか、北条泰時とか明恵などの個別の思想を学びたいです。それを現代にどう活かすか。
吉田久一『新・日本社会事業史』(勁草書房、2004)を読んできました。
今日は、第15章で最終回です。(写真は、そのさわり部分)
1980年代から2004年(本書執筆)まで。同時代史となり、書き方が難しい。
2004年以降今日までの変化も大きい。
吉田久一先生は、1949年度以来、さまざまなコースで社会福祉の歴史を講じてこられた。4単位、30回で終えるように本書も構成されている。
豊富な情報量で、このブログではキーワード風にごく簡単に全体の流れを紹介したにすぎません。
【座標軸のない日本の社会福祉】
これまでの章でも触れられてきたが、
○ 西欧社会事業史と比較すると、日本の場合、連続性が乏しい。
○ 日本福祉実践史で、世界に誇るべきものもあった。 p.342
○ 政策は(ヨーロッパと比較して)十分ではないのに、方法論だけは欧米の優れたものを導入してきた。 p.342
○ 従来の方法との「交渉→変革→定着」がなく、「改革」よりも「変化」「変更」
○ 利用者と実践的「主体者」の関係 p.345
(日本では)時代と社会に規定されながら「循環関係」にある。
例として、鎌倉時代の一遍など。
「社会」を否定しながら、しかも「」「ハンセン患者」を通じて生き返る「平等」と「循環」(その近代的解釈が必要)
【感想】
具体的な政策、人物、著書などが挙げられていて有用です。
考察の部分はやはり難解です。一読してわからないです。あるいはその文脈がかもしだす「気分」だけはわかるというべきか。
吉田久一先生とは、日本社会事業大学がまだ原宿にある頃、古ぼけた図書館でよくお会いした。今から思えば、もっと先生のご本を読み、お聞きしておけばよかった。
社会福祉法(2000年)については、社会的責任が希薄、「社会福祉の定義がない」などと批判しておられる。p.338
個別法である介護保険法のあとに普遍法である社会福祉法ができたところに社会福祉政策そして社会福祉学の観念性が現れている、と私は思います。
社会福祉士及び介護福祉士法(1987年)については、1行で片付けているp.335
が、ここには吉田先生の社会福祉への理解の特質が現れている。カリキュラムが公定され、歴史的な考察などが後退することを予見されていたからとも思いますが、(批判されるにせよ)もう少し、書いておいて欲しかった。
ともかくにも「社会福祉学」の水準を具体的に示すものだからです。
*このシリーズでは、毎回、50前後のアクセスをいただきました。ご愛読ありがとうございました。
これからは、時間があれば、先生のより本格的な著書に向かうか、北条泰時とか明恵などの個別の思想を学びたいです。それを現代にどう活かすか。


























ケアマネの集まりにでると、よく「制度に振り回される」ということを言い合います。
でも、制度がかわっても、支援の本質はかわらないだろう。制度を使うのは、我々生活者自身。では、そのことを「頭」ではなく「からだ」にしみこませるにはどうすればよいのだろうと思っていました。
そのときに、一つには「歴史を知る」ということも大事なのだと思うようになりました。
人それぞれに歴史があるように、制度・施策にも過去があり、未来があるのだろう・・・と。
イギリスやアメリカから輸入されてきたケアマネジメントを真似するだけでなく、日本のこれからにむけて進化させていくためには、欧米での歴史を知ると共に、日本の歴史を知ることも必要なのだと、このシリーズを読ませていただきながら思いました。そして、私の読みたい本リストに登録させていただきました。
しかし・・・私には、クリティークしながら本や論文を読む力はないな、と感じたのも事実で、ちょっとだけ
職場を変わっても、支援する立場の人の発言に
残念に思うことには変わりはありません。
リーダー的な立場の人にも残念に思う発言が
あります。
もちろん他人事ではありません。
吉田先生の研究を読み続けることで受け取るものはとても多いと思います。
どりーむ さん
コメントありがとうございます。
正直のところ
実力不足で
毎日冷や汗ものでした。
学ぶことと、意見を持つことを
分けながら、やはり自分の意見・スタンスを確認していく作業が重要ですね。
縦割りの制度の仕組みを覚えるのが社会福祉学だ・・ということのないよう
とくに私のような教師は自戒しています。
最近では、現場出身の教員も増えてきましたが
今後も一層現場でしか語れないことが次の世代に伝わって欲しいですね。
ところで養護施設と福祉施設の違いが良く理解できません。
私にはどちらも福祉のような気もしないではないのですが。
コメントありがとうございます。
社会福祉学の場合こそ
一般の市民の皆さんに
明快にやさしく説明できないといけない
と思っています。
ですから、質問いただくこと大歓迎です。
吉田久一先生も
「社会福祉法」という法律を指して
「社会福祉事業」の定義がない、と批判されています。
学問で定義が明確ではない時には
しばしば法律用語が内容を決めることに・・
同じような意味なのですが
歴史的に「慈善」→「養護」→「福祉」
と発展してきたように思います。(私の説!)
「養護」が現在の法律に出てくる例:
・「児童養護施設」社会福祉法2条2項2号
・「養護老人ホーム」同法2条3項3号
「福祉施設」とだけ書かれた法令の用語例は、
社会福祉関係ではないと思います。
*「○○福祉施設」はある。
皮肉なことに、年金や健康保険の法律に「福祉施設」という概念がありますのでややこしい。
*「厚生年金病院」とか「社会保険病院」などのことで、最近は廃止の方向ですから、法令用語としても死語になる日が近い。