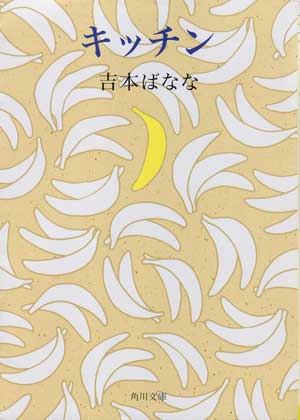今にして思えば、私の中学・高校時代は、あらゆるセンスの言語のシャワーだった。
わけわかんない堅い本や新書や古典文学や翻訳文学もライトノベルも読んだし、小学校の頃から国語の教科書の文章はわりと読むほうだったし
なにより友人たちの語彙とセンスが良かった。
笑いを取るための言葉の選び方、重ね方。
ウィットとユーモアに富んだ会話の数々。
私は語彙ばかりは豊富だったけれども、なにしろオリジナリティに欠けた人間なので、
彼女たちの驚くべき表現力と、切り取られた言葉のおかしさに、抱腹絶倒の毎日だった。
残念ながら、今では素敵な語彙を持ち合わせている友人はせいぜい2人ほどしかいないし(そもそも私は友人が少ないので分母が小さい/自分のセンスの欠如は当然棚に挙げている)
悪口を言いたいわけではないけれども、騒々しい男性陣が取る笑いもつまらないわけではないけれども(おそろしくつまらない、だけに留まらず不愉快であることも当然、あります)だいたいがセンスはいまいち。
センスで訴えるというよりも、ちょっと暴力的なくらいの勢いで笑わせようとしてくる姿勢が気に入りません。
先日、中学・高校時代の同級生が「人間関係の焼き畑農業」という表現をしたときには、愛の告白をしそうになった。感動のあまり。
そんなふうに、センスの良い文章から遠ざかっていた私の枯渇が、ゲリラ豪雨のごとき充ち満ちた出会いを得る。
平野紗季子。
彼女のブログ(http://fatale.honeyee.com/blog/shirano/)にすっかりやられてしまって、当然バックナンバーは全て読んだ。(ブログ中に登場していた森茉莉の「貧乏サヴァラン」も買った。)
この本はそのブログを抜粋して書籍化したもの。
ずっと我慢していてようやく手に入れた(プレゼントしていただきました)。
生きててよかった、の瞬間である。
食を体験するということの、果てしなさ。
マカロンを手で潰しちゃうとか、食べ物の破壊の瞬間であるとか、食パンに顔埋めたいとか、
内包された膨大なエネルギーと、それを的確に表現する言葉のチョイス、一緒に体験しているような生々しさ鮮烈さ、いっそ官能的。
おいしい文章の嵐、なにそれ!!の連続。
読むと「分かる分かる」って言いたくなるんだけれども、既に圧倒的に先んじられている。
私の感性は後追いをするばかり。くやしい。
脱帽いたしました。
もとより足下にも及ばないのは承知でも、言いたくなる「脱帽です」。
万が一ご本人に会うことがあったら、「いつもブログ読んでます、本も持ってます、大好きです、これからも頑張って下さい」くらいの凡庸なつまらないことしか言えないんだろうなあと思うと、がっかりだけれども。
この本(この方)の素晴らしさをぜんぜん表現できない私は圧倒的負け犬だけれども(もとから表現したいわけではなくて、言い散らしたいだけだったりする)
せめてこの素敵さを見いだしたという点では褒めてあげたい。
ごちそうさまでした。

わけわかんない堅い本や新書や古典文学や翻訳文学もライトノベルも読んだし、小学校の頃から国語の教科書の文章はわりと読むほうだったし
なにより友人たちの語彙とセンスが良かった。
笑いを取るための言葉の選び方、重ね方。
ウィットとユーモアに富んだ会話の数々。
私は語彙ばかりは豊富だったけれども、なにしろオリジナリティに欠けた人間なので、
彼女たちの驚くべき表現力と、切り取られた言葉のおかしさに、抱腹絶倒の毎日だった。
残念ながら、今では素敵な語彙を持ち合わせている友人はせいぜい2人ほどしかいないし(そもそも私は友人が少ないので分母が小さい/自分のセンスの欠如は当然棚に挙げている)
悪口を言いたいわけではないけれども、騒々しい男性陣が取る笑いもつまらないわけではないけれども(おそろしくつまらない、だけに留まらず不愉快であることも当然、あります)だいたいがセンスはいまいち。
センスで訴えるというよりも、ちょっと暴力的なくらいの勢いで笑わせようとしてくる姿勢が気に入りません。
先日、中学・高校時代の同級生が「人間関係の焼き畑農業」という表現をしたときには、愛の告白をしそうになった。感動のあまり。
そんなふうに、センスの良い文章から遠ざかっていた私の枯渇が、ゲリラ豪雨のごとき充ち満ちた出会いを得る。
平野紗季子。
彼女のブログ(http://fatale.honeyee.com/blog/shirano/)にすっかりやられてしまって、当然バックナンバーは全て読んだ。(ブログ中に登場していた森茉莉の「貧乏サヴァラン」も買った。)
この本はそのブログを抜粋して書籍化したもの。
ずっと我慢していてようやく手に入れた(プレゼントしていただきました)。
生きててよかった、の瞬間である。
食を体験するということの、果てしなさ。
マカロンを手で潰しちゃうとか、食べ物の破壊の瞬間であるとか、食パンに顔埋めたいとか、
内包された膨大なエネルギーと、それを的確に表現する言葉のチョイス、一緒に体験しているような生々しさ鮮烈さ、いっそ官能的。
おいしい文章の嵐、なにそれ!!の連続。
読むと「分かる分かる」って言いたくなるんだけれども、既に圧倒的に先んじられている。
私の感性は後追いをするばかり。くやしい。
脱帽いたしました。
もとより足下にも及ばないのは承知でも、言いたくなる「脱帽です」。
万が一ご本人に会うことがあったら、「いつもブログ読んでます、本も持ってます、大好きです、これからも頑張って下さい」くらいの凡庸なつまらないことしか言えないんだろうなあと思うと、がっかりだけれども。
この本(この方)の素晴らしさをぜんぜん表現できない私は圧倒的負け犬だけれども(もとから表現したいわけではなくて、言い散らしたいだけだったりする)
せめてこの素敵さを見いだしたという点では褒めてあげたい。
ごちそうさまでした。