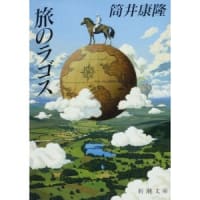読書を続けていると、たまに、
はじめに読んだときにはさっぱり分からなかった小説のことが、手に取るように分かる瞬間が降ってくることがある。
平坦な道を歩いていたはずなのに、ふと一歩踏み出すと山の頂上の見晴らしだったというような瞬間。
はっきりと覚えているのは川端康成の「伊豆の踊り子」で、たしかそれが降ってきたのは受験を控えた高校三年生の時だったように思う。
遠くから踊り子を見つめている学生が、今自分の中にいる、ときりきり感じた。
先日またその瞬間があって、それが吉本ばななの「幽霊の家」(『デッドエンドの思い出』のなかの短編のひとつ)だった。
あの小説の世界が、消しゴムほどの大きさのジオラマのようにきちんと美しく私の中におさまって、私はその世界をすみずみまで知っている、と思った。
私の中に小説がすっぽり入り込んだような、私自身がすとんと小説の中に入りこんだような、何重にも入れ子になった奇妙な世界だった。
その勢いのままこの本を読んだ。
あらすじに全然覚えがなかったので、中学生のころ私がちらっと読んで苦手に思っていたのは本作ではなく、「TSUGUMI」だったのかもしれない。
あるいは、もしかしたら「TSUGUMI」でなく本作を先に読んでいたら、吉本ばななへの認識は変わっていたかもしれない。
吉本ばななが好きな友人がいたけれども、彼女の中にはこんな景色があったんだな。
今はほとんどFacebookでしか動静を知ることがないけれども、今更になって彼女のことをまた知ることになる。
私は今も昔も感情的で、感情にまかせて物事を突き詰めて考えるのが好きで、なおかつ頑固なので、ふわりとした優しいお話を苦手とする傾向がある。
覇気のある主人公がぐいぐい進んでいくお話が好きだった。
あたりまえのことをもっともらしく語られるのは馬鹿っぽくしらじらしくて嫌いだし、そういうことは心に秘めていてこそ美しいと思っている。
だから吉本ばななが苦手だったんだろうな、と今になると分かる。
優しくて、けなげな小説である。
そして弱さと孤独を残酷なほど正確に描ききった小説だと思った。
喪失感をこんなにつぶさに描いた小説は、あまり読んだことがない。
私はほとんど身内の死に直面したことがないのだけれども(なにしろ祖父母が4人とも健在である)、それでも昔よりはいくらか人の死について知った。
おそろしい事件や辛い病気の話を聞くたびに、自分あるいは自分の身近な人間の死、への恐れが年々リアルに、強くなっている。
あわてて考えに蓋をせずにはいられないほど、みじめな想像である。
その日が来るのが可能な限り遅くあってほしいとねがいながら、何事もないように生活している人間には、ちょっとこたえる読書だった。
この作品が実体験に基づいたものだとしたら(間違いなく、何らかの形では実体験であるはずだ)、よく書けたものだと思う。
お守りとして本棚に置いておきたい本であるけれども、その一方で、もし私が親しい誰かを亡くしたらある程度立ち直ってからでないとこの作品は読めないだろうな、と感じた。
次に続くものがなにもないと思いながら、時間が流れていく。
当たり前なのに、こんなに悲しい。
人生って、辛いんだ。
人生って、悲しいことばっかりだ。
なんで生きていなければいけないのか、なんていう問いを発するでもなく、ただ流れる時間を悼むこと。
光ったり暗くなったりしながら、昼や夜のなかを歩いて行くということ。
作品の中にあった、透き通っていくという表現が一番しっくりくるんだろうな。
なんとなく、ようやく、吉本ばななの書きたい世界の奥のところが、私にも分かってきたような気がしている。

はじめに読んだときにはさっぱり分からなかった小説のことが、手に取るように分かる瞬間が降ってくることがある。
平坦な道を歩いていたはずなのに、ふと一歩踏み出すと山の頂上の見晴らしだったというような瞬間。
はっきりと覚えているのは川端康成の「伊豆の踊り子」で、たしかそれが降ってきたのは受験を控えた高校三年生の時だったように思う。
遠くから踊り子を見つめている学生が、今自分の中にいる、ときりきり感じた。
先日またその瞬間があって、それが吉本ばななの「幽霊の家」(『デッドエンドの思い出』のなかの短編のひとつ)だった。
あの小説の世界が、消しゴムほどの大きさのジオラマのようにきちんと美しく私の中におさまって、私はその世界をすみずみまで知っている、と思った。
私の中に小説がすっぽり入り込んだような、私自身がすとんと小説の中に入りこんだような、何重にも入れ子になった奇妙な世界だった。
その勢いのままこの本を読んだ。
あらすじに全然覚えがなかったので、中学生のころ私がちらっと読んで苦手に思っていたのは本作ではなく、「TSUGUMI」だったのかもしれない。
あるいは、もしかしたら「TSUGUMI」でなく本作を先に読んでいたら、吉本ばななへの認識は変わっていたかもしれない。
吉本ばななが好きな友人がいたけれども、彼女の中にはこんな景色があったんだな。
今はほとんどFacebookでしか動静を知ることがないけれども、今更になって彼女のことをまた知ることになる。
私は今も昔も感情的で、感情にまかせて物事を突き詰めて考えるのが好きで、なおかつ頑固なので、ふわりとした優しいお話を苦手とする傾向がある。
覇気のある主人公がぐいぐい進んでいくお話が好きだった。
あたりまえのことをもっともらしく語られるのは馬鹿っぽくしらじらしくて嫌いだし、そういうことは心に秘めていてこそ美しいと思っている。
だから吉本ばななが苦手だったんだろうな、と今になると分かる。
優しくて、けなげな小説である。
そして弱さと孤独を残酷なほど正確に描ききった小説だと思った。
喪失感をこんなにつぶさに描いた小説は、あまり読んだことがない。
私はほとんど身内の死に直面したことがないのだけれども(なにしろ祖父母が4人とも健在である)、それでも昔よりはいくらか人の死について知った。
おそろしい事件や辛い病気の話を聞くたびに、自分あるいは自分の身近な人間の死、への恐れが年々リアルに、強くなっている。
あわてて考えに蓋をせずにはいられないほど、みじめな想像である。
その日が来るのが可能な限り遅くあってほしいとねがいながら、何事もないように生活している人間には、ちょっとこたえる読書だった。
この作品が実体験に基づいたものだとしたら(間違いなく、何らかの形では実体験であるはずだ)、よく書けたものだと思う。
お守りとして本棚に置いておきたい本であるけれども、その一方で、もし私が親しい誰かを亡くしたらある程度立ち直ってからでないとこの作品は読めないだろうな、と感じた。
次に続くものがなにもないと思いながら、時間が流れていく。
当たり前なのに、こんなに悲しい。
人生って、辛いんだ。
人生って、悲しいことばっかりだ。
なんで生きていなければいけないのか、なんていう問いを発するでもなく、ただ流れる時間を悼むこと。
光ったり暗くなったりしながら、昼や夜のなかを歩いて行くということ。
作品の中にあった、透き通っていくという表現が一番しっくりくるんだろうな。
なんとなく、ようやく、吉本ばななの書きたい世界の奥のところが、私にも分かってきたような気がしている。