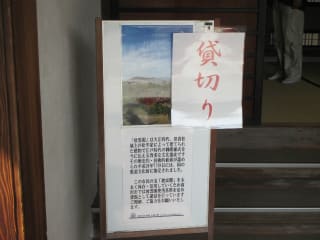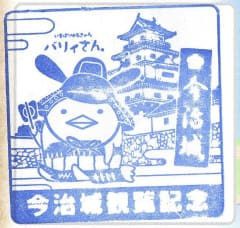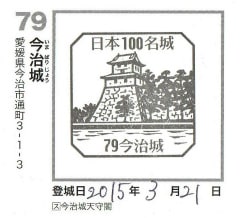披雲閣庭園【国指定名勝】を出て、北の丸へ。

月見櫓【国指定重要文化財】、

水手御門【国指定重要文化財】と渡櫓【国指定重要文化財】です。
北の丸付近は、松平頼重(徳川光圀の実兄)の代に埋立てがすすみました。
そして月見櫓は次代の頼常(光圀の実子で頼重の養子)の代に完成し、北の丸の隅櫓の役割を担うこととなりました。

月見櫓に入ります。
戦国時代の城郭建築に比べると、少しばかりですが傾斜が緩やかな階段。

櫓からの眺め。
北側は道路1本を挟んですぐに海、四国フェリーがなんとも間近に見えます。
高松城が海城であることを実感できます。

櫓の西側は野面積みの石垣と水路が続きます。
当時はこのあたりまでが海だったのですが、明治時代に埋立てがすすみ、石垣と道路の間に水路が残りました。
往時は海を隔てていた石垣、それにそって並び立つ松の木々もまた良し。

かつての海であった水路は、ここの水手御門で終わっています。
つまりここは海からの入城門、月見櫓は海からの出入りを監視する役割を担っていたのです。
高松城では、月見櫓は「着見櫓」とも表記されていたそうです。

前章で訪れた披雲閣【国指定重要文化財】と披雲閣庭園【国指定名勝】は、月見櫓からちょうど南側。

月見櫓から出て、水路近くまで来ました。
城外とあって、門と櫓はなかなかの威容を示しています。
月見櫓とその続櫓には第1階層に石落としが構えられ、またすべての櫓に鉄砲狭間が空いています。

続いて渡櫓に入ります。

ここでは城郭建築ではめずらしいのたぐり壁が見られます。
城郭建築では木造の壁板を土壁で覆う構造はよく見受けられます。
こうすることで建物の炎上を防ぐのですが、この波状の壁、そして露出している柱・・・?
櫓の外側は敵方の火攻めに備える必要があるので、壁板を土壁で完全に覆う必要がありますが、内側については出火のリスクはある程度下がります。
そのため土の量を節約するために波状の壁になっているそうです。
仮に櫓の中で出火しても、柱が燃え尽きることはめったにないそうです。
こののたぐり壁、城郭建築で現存している例はここと彦根城の佐和口多聞櫓だけだそうです。

水手御門、月見櫓を背にして、


城の北西にある水門へ。
高松城の北側は、埋立てにより海とは接しなくなりました。
この水門を通じてのみ、海とのつながりがあります。


屋根付きの

鞘橋から見た本丸。
野面積みの石垣がひときわ高く積み上がります。

いよいよ天守台へ。

天守台から眺める内堀。
濠の終末には水門が開いていて、その先の瀬戸内海に通じます。
左が二の丸、右が三の丸。
二の丸の石垣が、三の丸のそれよりも少しばかり高いことがわかります。

二の丸と、そこから架かる鞘橋です。
二の丸の向こうはJR高松駅の駅ビルです。

天守台の南東方向には、
「艮」は北東の方角を表します。
もともとは城の北東にあった隅櫓が、現在の地に移築されたものなので、玉藻公園の南東にありますが「艮」櫓の名称が残っています。

北東方向は月見櫓が・・・ちょいと見えにくいですなぁ。

お濠に泳いでいるのはクロダイ(チヌ)です。
クロダイは出世魚で、小さいものはチ●チ●、中くらいがチヌで、大きくなるとクロダイと呼ばれるそうです。
天守に到達したので、高松城の攻略、達成!!
ママチャリを停めた艮櫓付近に戻ります。

三の丸からの鞘橋。

同じく三の丸から、天守台と鞘橋。

高松城のシンボル・艮櫓。

ことでん越しの艮櫓を背にして、最後のうどん巡礼に旅立ちます。