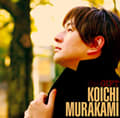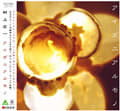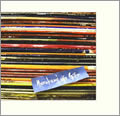夕刻の風の中に、夏の匂いが色濃くなってくるといくつか思い出すことがある。
その中のひとつが縁側の下の「蟻地獄」
少年の頃の話。
蝉の鳴き声を背後に聞きながら、縁側の下の柔らかい砂の少しくぼんだところを探す。
すり鉢状のくぼみを見つけると、次に小さめの蟻を探す。
そこらへんをうろついてる蟻は容易に見つけることが出来る。
指圧でつぶさないように優しく運ぶが、その後の行為はとても残酷。
くぼんでいるところへ、蟻を放る。
くぼみから必死に逃れようとする蟻めがけて砂が飛んでくる。
次の瞬間、砂の底からハサミが飛び掛かり蟻を掴む。
そして、体液を吸い尽くしたら、くぼみの外に抜け殻となった蟻を放り投げる。
「蟻地獄」という、世にも恐ろしい名前を付けられた幼虫。
その成虫は、とても繊細で儚い名前を付けられた「薄羽蜉蝣(ウスバカゲロウ)」
砂の中に隠れて、罠を仕掛けて、獲物をただひたすら待っている幼虫の姿は、灰色でグロテスク。
体長は1センチも満たない。
蟻には申し訳ないが、その時の自分は、決して残酷なことがしたいわけではなかった。
成虫の「薄羽蜉蝣」になってからの人生が、あまりにも短くて儚いなら、
せめて幼虫の間にいい思いをさせてやろうと考えたうえでの行動だった。
とはいえ、そこはやっぱり子供。残酷な好奇心があきらかに勝ってる。
餌をやっているつもりだが、逃げるものの姿と追うものの姿を瞬きもせずに見入っていた。
「脱け出せない苦しい状況」の例えとして使われている言葉の意味を、
理解するにはまだ早い年頃だが、その夏の経験からどれくらいのことを学んだだろうか。
少年のお陰でまるまると太った「蟻地獄」は、きっと、たくましい「薄羽蜉蝣」になって秋を迎えただろう。
蟻にとって地獄のようなやつの写真はありません、あしからず。
そういえば、安部公房の「砂の女」を読んだときは、もろに思い出したなぁ。
| Trackback ( 0 )
|