ブルーノート(BLUE NOTE)レーベルは、ジャズファンの間では言わずと知れた名門レーベルだ。 
もしも、このレーベルを「ジャズ好き親父が聴きそうな古いジャズばっかり」と思っている人がいるとしたら・・・、
それは非常にもったいない見方だ、と言ってしまおう。
上のような見識は間違っていないのだが、それ「だけ」ではない。今聴いても刺激的な、グルーヴに満ちた作品がたくさんあるのだ。
例えば、オルガンを用いたジャズ。あるいは、パーカッションを大胆に取り入れたジャズ。
これらがアシッドジャズ・シーンに与えた影響は、計り知れない。
アシッド・ジャズについて書くとき、どうしてもブルーノートのジャズ、とりわけオルガンジャズに触れないわけにはいかない。 
(↑こうした話題では必ずと言っていいほど出てくる『Alligator Boogaloo』。評論家センセイ方に取り上げられる嚆矢)
ブルーノートのオルガンジャズ諸作には、サンプリングソースとしてはもちろんのことだが、
Lonnie Smith『Move Your Hand』やJohn Patton『Understanding』など、それ自体が現在のクラブシーンで通用しそうなものも多数ある。
ブルーノートは、ジャズはもちろんヒップホップ・フリークにとっても「良質なネタの宝庫」として認知されているレーベルなのだ。
↑日本人DJのMUROが監修したコンピレーションも発売されている
特に近年は、70年代(いわゆるBN-LA時代)の諸作の再評価が著しい。
エレクトリック楽器を取り入れ、ファンク・ビートやソウル曲のカバーなどを積極的に行なっていた頃だ。
70年代をざっくり言ってしまうと、
Miles Davisがいわゆる「電気ジャズ」に傾倒し、Herbie Hancockはそれをよりポップなかたちで再構成し『Headhunters』を出した時代である。 
その時代のブルーノートは、なんといってもSKY HIGHプロダクションの功績が大きい。
彼らのプロデュースした Donald Byrd 『Steppin' Into Tomorrow』『Places And Spaces』やBobbi Humphrey 『Blacks & Blues』は、
ソウル、ファンクの名盤であるだけでなく、「定番」「お約束」なサンプリングソースでもあるのだ。


ブルーノートの影響力は、ヒップホップにとどまらない。
90年代、アシッド・ジャズレーベルやトーキン・ラウドレーベルにてバンド活動を行っていた連中(例えばTBNHやIncognitoら)が志向した音は、
この時代のブルーノートの音楽に大きな影響を受けていることが、楽曲から伺える。
このブログを始めたとき、最初の記事は Us3 だった。彼らもブルーノート出身のユニットだ。
彼らについては記事で触れたが、他にも Soulive や Medeski, Martin & Wood といったジャムバンド勢も
マイナーレーベルから発掘して、ブルーノートでメジャーデビューさせている。
現在のブルーノートは、NEW DIRECTIONなど若手のストレート・アヘッドなジャズを演る連中を支援する一方で、
上記の彼らのようなヒップホップ、ジャムバンド、それに St Germain や Marc Moulin といったテクノ/ハウス方面のクラブサウンドも
積極的に紹介している。
St Germain や Marc Moulin は、その音作りにオルガンを効果的に用いているし、Soulive や初期の MM&W に至っては、
オルガンがメイン楽器と言っても過言ではない(MM&Wはオルガンにこだわらない姿勢だが)。 (←NEW DIRECTIONS。若手によるトラディショナルなスタイルのジャズ作品も多くリリースしている)
(←NEW DIRECTIONS。若手によるトラディショナルなスタイルのジャズ作品も多くリリースしている)
 (←『The New Groove』はブルーノートの楽曲をヒップホップミュージシャンがリミックスしたコンピレーション)
(←『The New Groove』はブルーノートの楽曲をヒップホップミュージシャンがリミックスしたコンピレーション)
音楽のブームとしてのアシッド・ジャズはとうに去り、いわゆるジャズ・ヒップホップもさほど取り上げられるものではなくなった。
ハウス界隈でのいわゆるクラブジャズ(Jazzy Vibeとも呼ばれる)は、その多くが「上っ面だけジャズっぽい」、使い捨て楽曲だ。
真に音楽として踊れて、かつ長く聴ける(=鑑賞に耐えうる)「クラブ・ミュージックとしてのジャズ」が求められているような気がする。
「クラブ・ミュージックとしてのジャズ」を、このブログでは便宜上「アシッド・ジャズ」という呼称にまとめてしまっているが、
ブルーノート・レーベルには、今後もそうした「アシッド・ジャズのミュージシャン」を、トーキン・ラウドレーベルとともに
世に紹介し続けて欲しいと思う。










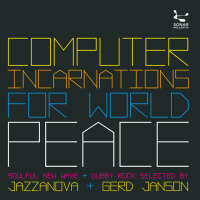

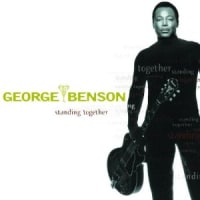



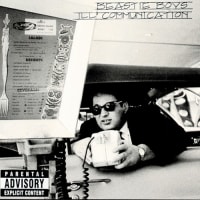


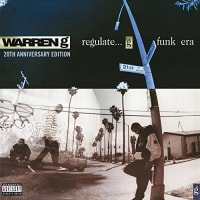
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます