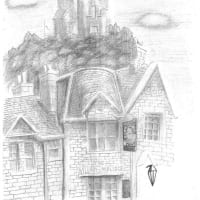なぜ東ユーラシア経済がこれから強いというのか? マクロ経済の外因的要因と内因的要因を考えれば解る
2008-09-17 21:23:00 | 時事マクロ経済DailyMacroEcn
今年の世界経済模様を見ていると、世界経済を一極支配してきたアメリカ合衆国経済の衰退とともにヨーロッパ経済の限界も露呈されてきました。 そして、今まで起用に立ち振る舞い2007年まで好景気を謳歌していたグレートブリテン(英国)も、この相関指数の高い2つの経済圏の不況の影響を受けております。
しかし、これでも欧米経済が絶対的な意味から衰退するというわけではなく、相対的に東ユーラシア経済圏に圧倒されるであろうという意味です。
まず、アメリカ経済の衰退の要因については、他のウェッブサイトでも多く述べらていますのであえて割愛させていただきます。
ヨーロッパ経済は既に物質資本を開拓しきっております。 そして、1990年代より人間資本という永遠に発展開発可能であると推測されている資本投資にと移行しました。 その資本投資理論について成功しましたヨーロッパですが、問題はマクロ経済レベルにおける経済計画および過度で過保護な社会福祉への投資に余念が無かった故に、一人頭の生産力そのものが減退しているということです。 マクロ経済レベルにおける批判は共通通貨とEU体制への批判にて多く述べてありますのでそこを閲読くださいませ。
欧州連合(EU)は、効率的労働力において東ヨーロッパ圏内からの輸入に頼るつもりであえてこれらの地域をEUに組み込んだわけですが、それでも同じ賃金において東アジア諸国にはかなわないでしょう。
あと、EU経済の落ち度は同時に社会民主主義の落ち度ということにもなりますね。 ジェンダーフリー政策などで安定した子育て教育を犠牲にし、過保護な社会保障のおかげで中産階級を含む労働者階級(中産階級のプロレタライゼーション(労働者階級化)を参照)の勤勉意欲を損失させている背景からもうかがえます。
その点、東アジア諸国は強い。 社会保障など既に当てにせずに、自分の力量こそが己が経済を支えていく力だと確信しているからです。 むろん、すべての社会保障を否定しているのではなく、ヨーロッパのように過保護に保障し財政政策による景気変動を無視して過度な社会投資を繰り替える制度に比べての話ですが。 とにかく、政府の所得や社会保障への過度な関与が少ないために、家族の絆が強く、そして常に浮浪になることへの不安感を胸に秘めているために、積極的に働く東アジア経済圏の個人は強い。
そして、その地域における資本投資の影響力の比較も参考になるでしょう。 まず、下の図をごらんください。 これは、横軸を時間軸に沿った資本力とし縦軸を横軸の時間よりも一足早い時期を表したものです。 つまり45°線上で重なる点はK(t)(横軸)=K(t+1)(縦軸)となります。 黒色で45°線以外に放物線を描いている線が外因的要因による資本拡大を示し、赤色で45°より角度の高い直線に伸びている線が内因的要因を示しています。

外因的要因とは、物質資本の成長度を示し、資本の投下つまり個人や企業、海外からの所得から流れるその経済地域への投資効力を意味します。 この外因的要因とは、投資し始めた経済地域は投資する分だけ成長が早いがある一点を超えると投資効果が弱まるという理論です。 そして、初期状態で投資効力に差がある場合は、『条件付』と呼ばれ、その経済地域の貯蓄率と在庫調整などの改善による影響です。 この理論であれば、貯蓄率と在庫調整率も、世界規模で外因的要因が広まれば、どこの経済地域も同レベルになり終いには時間軸を突き詰めていけば経済格差は狭まってくるということになります。
変わって内因的要因とは、主に人間資本の成長度とその相乗効果として現れる物質資本の発展を意味します。 たとえば、教育や生産過程における経験から学んだ能力というものは他人にも伝達することができるのです。 ですから、成長の度合いが一定かつ無限に伸びるというのです。 ですから、外因的要因と違って人間資本、つまり教育や職業訓練などへの投資が大きい先進国の方が発展度合いが高いということになります。
この外因的要因と内因的要因を組み合わせて考えると、上記の図のように、新興国であれば外因的要因である直接的な物質資本への投資が急激に行われます。 また、貧困国郡と違い、貯蓄と投資の循環がよろしく物流が大きいために在庫の残りも少ない新興国であれば外因的要因のインパクトは大きいです。 そして、より内因的要因に目をつけた欧米諸国においては、すでに外因的要因のインパクトは皆無であるために、教育や研究開発などの内因的要因へと目を向けているわけです。
そしで、現在、数多の東アジア人が欧米にて勉学に励み、その欧米の内因的効果である教育や社会環境から長所を盗み取ってくれば、彼らの故郷の経済地域にてその内因的要因を持ち帰ることができ、上昇中の外因的要因による経済発展に付け加えることができるのです。
現在、新興国といえども、やはり東アジア経済圏は発展途上でございます。 シンガポールの初代上級相のリー・クアンユー殿は、アジア諸国が独自の経済姿勢を維持できるような制度の立案を誇示してきましたが、長らくアメリカ合衆国経済の一極支配の維持のために虐げられてきました。 そして、東アジア圏にてあるべき経済体制である開発独裁を率先して実践してきたクアンユー殿率いる人民行動党政権シンガポールこそ、後進経済圏であるアジア圏のあるべき姿を披露してきました。 マレーシアやインドネシア、ベトナムが実質上、開発独裁を堅持してその安定した経済発展を促せたこともその経済政策モデルの成功例ともいえるでしょう。 そして、フィリピンやカンボジアなどが東アジア的な合理的開発独裁を敷くことができれば不安定な社会情勢も変革され、資本の安定的な成長が期待できるでしょう。 しかし、今までアメリカ合衆国の政府や外資系企業などの圧力がかかり、その中で東アジア諸国の独自の発展というものが妨げられてきました。 ですから、形式上の議会民主主義制度を利用して次々に傀儡政権を誕生させ、生かさず殺さずの腐敗した与党を君臨させて、その経済地域独自の独立成長というものを妨げてきました。
今回のアメリカ合衆国経済の崩壊をむしろチャンスと考え、リー・クアンユー殿の構想の実現を可能にすることも夢ではありません。
また、ロシア帝国を賞賛することは好きではありませんが、あえてロシア帝国は膨大な石油埋蔵量を含む豊富な地下資源を保有しております。 そのロシア帝国がパイプラインを東アジア経済圏に引くことが可能になれば、東アジア圏の優秀な物質資本および人間資本との提携が行われるでしょう。 地下資源以外に資本主義経済においてこれといって誇れるものが無いロシア帝国経済にとって、地下資源を担保に東アジア経済圏からの資本投下の見込みがあれば、ロシア帝国も甘い汁を吸えることになります。
この、東アジア圏とロシア帝国との利害関係が一致し、巨大な経済圏が生まれることも想定にいれておくべきですね。 これを新たな資本開拓地として東ユーラシア帝国構想とでも呼びましょう。