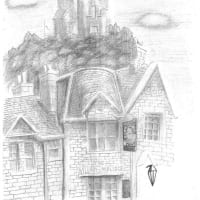画像:https://studyu.jp/feature/theme/game_theory/
この画像は、囚人のジレンマというもので、本来どちらも黙秘すれば刑が軽くなりお互いに得であるのにも関わらず、結局どちらも罪を自白してしまいお互い損な結末に誘導されてしまうという、経済学の数学で有名なゲーム理論である。
数学といっても数式では表せない課題としても有名である。
この囚人のジレンマの因人等はお互いに情報交換し共謀を計れる立場に無い場合、合理的に判断すればするほど、自分が黙秘し相手が裏切り自白されて自分が不利な立場になるからこそ、その事態を避けるために自白する。
たとえ暗黙の了解や掟があっても、掟を破り相手を裏切る方が得。
こちら既にAIの導入においても論争されている。
より演算能力が高ければ高いほど、この因人のジレンマと同じ傾向が強くなる。
サピエンス全史の著者、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書、「21 lessons for the 21st century」でも、自動運転車のAIに仕込む哲学が鍵になるとのこと。
ここから学べることは、知識や演算能力のみでは言動する動機が無い。その前提となる哲学を設定する必要がある。
これは金融経済においても同じことが言える。
AIの機械学習は超短時間における裁定取引においては最強である。
ただし、長期的において囚人のジレンマが金融市場でも起こる、合理的であればこそ更に。
市場活動が過熱気味の時には活動を控える態勢を取り始めなければならない。
しかし、こういう状況だからこそ一人引かず活動し続ける方が富を横取りできる。
そして、不況に入ったときにこそ、大勢っで一機に出資し底から脱出する(ニューディール政策が公的資金を投入してそれやった)必要がある。
ただ、そういう下降トレンドにあるときこそ出し抜いてショートセリング(空売り)仕掛けた方が得ということがあり、下降トレンドは加速する。
むろんここでAIや合理性を否定しているのではなく、これ等をより有効活用し文明と精神性の進化に役立てるためにこそ、このリスクを十分承知しなければならない。
だからこそ、AIを仕組んだり合理的な行動規範を伴うからこそ、「どのようにあるべきか」という哲学的思考と実践が必要になるのです。
ただ、神で無い限り真実に対する答えなど無い故に、完全な答えは出ず、それこそその仕込む側の「世界観」が鍵となる。
この画像は、囚人のジレンマというもので、本来どちらも黙秘すれば刑が軽くなりお互いに得であるのにも関わらず、結局どちらも罪を自白してしまいお互い損な結末に誘導されてしまうという、経済学の数学で有名なゲーム理論である。
数学といっても数式では表せない課題としても有名である。
この囚人のジレンマの因人等はお互いに情報交換し共謀を計れる立場に無い場合、合理的に判断すればするほど、自分が黙秘し相手が裏切り自白されて自分が不利な立場になるからこそ、その事態を避けるために自白する。
たとえ暗黙の了解や掟があっても、掟を破り相手を裏切る方が得。
こちら既にAIの導入においても論争されている。
より演算能力が高ければ高いほど、この因人のジレンマと同じ傾向が強くなる。
サピエンス全史の著者、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書、「21 lessons for the 21st century」でも、自動運転車のAIに仕込む哲学が鍵になるとのこと。
ここから学べることは、知識や演算能力のみでは言動する動機が無い。その前提となる哲学を設定する必要がある。
これは金融経済においても同じことが言える。
AIの機械学習は超短時間における裁定取引においては最強である。
ただし、長期的において囚人のジレンマが金融市場でも起こる、合理的であればこそ更に。
市場活動が過熱気味の時には活動を控える態勢を取り始めなければならない。
しかし、こういう状況だからこそ一人引かず活動し続ける方が富を横取りできる。
そして、不況に入ったときにこそ、大勢っで一機に出資し底から脱出する(ニューディール政策が公的資金を投入してそれやった)必要がある。
ただ、そういう下降トレンドにあるときこそ出し抜いてショートセリング(空売り)仕掛けた方が得ということがあり、下降トレンドは加速する。
むろんここでAIや合理性を否定しているのではなく、これ等をより有効活用し文明と精神性の進化に役立てるためにこそ、このリスクを十分承知しなければならない。
だからこそ、AIを仕組んだり合理的な行動規範を伴うからこそ、「どのようにあるべきか」という哲学的思考と実践が必要になるのです。
ただ、神で無い限り真実に対する答えなど無い故に、完全な答えは出ず、それこそその仕込む側の「世界観」が鍵となる。