新局面に入ったタイの政治←民主化と王政の抵抗
〈出典:国際問題10月号No.625P18~30玉田芳史著〉
権威と正当性が2006年の軍事データー前から揺らぎはじめ
クーデター後には消滅した
自由で公平な選挙で国家指導者を選ぶと言う民主政治のルールが
踏みにじられている
この混乱は何に起因するのであろうか?
1973年に大学生が憲法制定を求める運動に乗り出し支持を集めると
政権を支える王室と軍隊が離反した
1973年10月1日に軍隊の最有力ポストである陸軍総司令官に昇進
したばかりの新司令官は治安出動命令に従わなかった
首相の息子が率いる陸軍部隊などの発砲で70名を超える死者が出ると
1973年10月14日に
国王は首相に退陣を促し、後任には側近の判事を任命した
国王のお言葉は誰も公然と異を唱えることが出来ず
法的拘束力があるかのように流通する
10月14日政変以後は軍隊のジュニア・パートナーからシニア・パートナーへ
と変化した、軍隊は国王の意向を無視して政治に介入することが最早困難になった
1992年までは首相の人選に、国王が大なり小なり関与していた
首相は、
就任や地位保全を国王に大きく依存するのであれば国王に従順にならざるを得ない
このプーミポン国王の政治体制が1990年代から揺らぎはじめ
21世紀に入ると危機を迎えるようになる。
なぜ揺らぎはじめたのか?根本的理由は民主化であった。
1973年の10月14日政変は
タイ政治が民主化へ向かう扉を大きく開いた
しかしながら直ちに確立されたわけではなかった
◉2001年総選挙でタックシンが勝利して首相に就任した
彼は1997年憲法の規定を活かして指導力を発揮し
巧みな政権運営で高い人気を獲得した
1997年憲法は起草者が意図しないところで首相に二重の正当性を与えた
得票率に応じて順番に当選する拘束名簿式比例代表制を採用していた
比例区名簿の第1順位は首相候補である
有権者からすれば首相公選と実質的には等しかった
国民からの直接支持という意味での大統領的な正当性を備えることになる
タックシンはそうした正当性を喧伝し指導力強化に役立てた
また公約が重要になることを見越してマニフェストを提示した
それは具体的で魅力的であった
政権を握るとその多くを実行することで4年任期満了後の2005年総選挙で
下院議席の四分の三という空前の圧勝を収めた
選挙公約が空手形のそれまでの政党政治からの大きな様変わり
有権者にすればどの政党に投票するかによって生活が変化するようになった
◉1990年代半ばから地方分権が進んだ
有権者が選挙への執着を強めたのはタックシンのマニフェスト戦術のみならず
地方分権のお蔭もあった
1995年から設置が始まった区自治体を皮切りに地方分権が急速に進んだ
2003年には自治体の首長が住民の直接投票で選ばれるようになった
国政と地方政治とで4年間に少なくとも6度の選挙が実施される
自治体首長が有権者の方を向いて行動するようになった結果
有権者は誰に投票したかによって生活が変わることを実感し
選挙へのこだわりを強め
タックシン政権以後、
選挙政治は生活を左右するようになったため死活問題となった
総選挙の先送りや選挙結果を覆す軍事クーデターは
関係のない他人事ではなく、断じて容認出来ないことになった
◉国王は1973年の政変後にこう語った
「政治に空白状態が生じたときには国王は政治に全面的に介入出来る
10月14日がそうである。しかし介入で収拾が終われば国王は速やかに
政治から手を引かねばならない
救済に再び乗り出せるようにするためである」
政治介入の余地を残すために、より大きな権力を獲得し行使するために
意図的に憲法での明文化を避けてきた
制度課を避けたため国王の権力は青天井のもとで巨大化する可能性があり
他方では象徴としての元首へと変化する可能性を秘めている
◉タックシンの衝撃
タックシンも国王も国民の人気を気にかけていた
国王の方は局地的、単発的である
どこか特定の村に集中豪雨的に慈悲深く恩恵を施すというのが国王のやり方である
タックシンは全国一律に全ての村に政策として恩恵を施した
タックシンは国王を立てるどころか国王の影を薄くしていたことになる
勤王派から不満がでてくるのは当然であった
王党派が2005年総選挙に大きな衝撃を受けたことは想像に難くない
政党政権が4年任期を満了するのは史上初
2度続けて第一党になるのは1983年以来20年ぶりの珍事であった
タイラックタイ党(TRT)が政権を20年間担当すると言うタックシンの豪語
に現実味が感じられもしたため、打倒運動が2005年から本格化する
タックシンの民主的な正当性や高い人気が
君主国王の権威を損ねることへの懸念が如実に示された
2006年のクーデターは
タックシンの政界追放のみならず再来阻止をも目的としていた
具体的には選挙制度を改めて
大規模政党の登場を抑制し不安定な連立政権を再現しようとした
中選挙区制に戻した
首相への不信任案を容易に提出しうるように提出に必要な議員数を半減させて
1997年以前のように下院議員数の5分の1に戻した
政権の不安定化を狙って選挙区議員の入閣を許すことにもした
政治家が国民に受けのよい政策を打ち出して人気を獲得するのを制限する為に
政治家に都合の良いよい予算編成に厳しい規制を
さらに
政権が実施すべき基本政策を詳細に憲法に書き込み
立法府や執行政府が選択し得る政策に縛りをかけた
新しい政党法には選挙違反が解党理由となるという規定を新たに盛り込んだ
解党を容易にする狙いがあった
◉反タックシン「黄シャツグループ」
王党派の強い協力者は都市中間層→マスメディア、ジャ-ナリスト、知識人、NGO
暮らし向きのよい人たち
彼らは国会議員の構成を官選7割、民選三割に変更する新政治構想を提示
特権層の恐怖心につけ込む反民主化運動
「票の売買が残っているのはタイだけである」
「2007年総選挙ではタックシン派阻止の為に膨大な公的資金や資源が投入された」
「貧困層を愚かでドウショウもないとみなしている」
「彼らは子供を名門校へ、商売で契約を、袖の下を賢い行動と自負している」
「地方の有権者が投票を上手に活用するのを覚えたことが問題なのだ」
◉赤シャツの反撃→意義申し立てる庶民
王党派と言説を支配する中間層が協力すれば民主抑圧は難しくない筈だった
無知で貧困で政治無関心だと蔑視された庶民である
なぜ?庶民が異議を申し立てるのか?
無知蒙昧故にタックシンに買収されダマサレタのか?
農村部に登場した下位中間層、社会全体では農村下位中間層が多数派である、
マスメディアを通じ依拠する都市中間層は相対的に低下した
赤シャツ参加者は農村部中間層と都市下層から構成される多数派である
「2006年以降王党派や都市中間層が中心となって脱民主化闘争で踏みにじられた選挙
下位中間層はこれに納得がいかず赤シャツへと結集した」
【臣民から市民へ】2011年
赤シャツの怒りは、物言わぬ大衆から参政権を積極的に活用する市民に変わろうとする
矢先に選挙が軽んじられ対等な市民と認知されないことに向けられた
裁判所はタックシンの与党TRTを強引な解釈で解党に追い込み
同党幹部111名の政治職就任を5年間禁止した
安定政権登場阻止のため新憲法を起草して公布施行した
裁判所が与党解党判決を下す
赤シャツにすれば2005,2006,2007年の投票は1年も経たないうちに水泡に帰した
軍隊は赤シャツへの掃討作戦を迅速に展開した
90名余の死者、2000名近い負傷者
王党派と都市中間層は有権者の反発を招くことになった
赤シャツを虫けらのように虐殺しておきながらテロリストと決めつけることで
政権側が一切の責任を認めようとしないことへの怒りが高まった
反タックシン派が選挙軽視の言動を繰り返すほど
選挙重視派は選挙の重要性を一段と強く確信するようになった
◉王権の危機
タックシン批判が劇的に盛り上がったのは2006年1月
タックシンが自分の個人企業をシンガポール企業へ売却した時
国営企業でなく民間企業であるのに「売国」と罵られ
納税義務がないのに「脱税」を批判された
マスメディアが事実に反する報道で国民誤導に躍起となった
タイのメディアは自己規制の文化と刑法に設けられる不敬罪の厳罰規定ゆえに
王室の役割を議論することが出来ない
しかしながら赤シャツはラジオでオンラインで街頭で自宅で包み隠さず
議論するようになった
彼らは2006年以降の政争が王室と無関係ではないと感じているからだ
他方、黄シャツは絶えず王室奉戴によって言動を正当化しようとした
黄シャツに死者が出ると葬儀に王妃が出席した
2010年4月10日に軍隊がデモ隊掃討に乗り出して日本人カメラマンを含む
多数の死傷者を出す惨事になったとき
国王が事態の収拾や責任者の処分に乗り出すのではないか、と赤シャツは期待した
しかし、王室は沈黙を守った
軍隊が5月19日を期してデモ隊強制排除の準備に入った時
国王が介入して流血を阻止するのではないかと赤シャツは期待した
しかし、寺院に非難した人々までが狙撃され射殺されたにもかかわらず
国王は介入せず、発砲者を咎めることもなかった
期待を裏切られた赤シャツは
国王が反タックシン派の黒幕ではないかとの疑念を強め
敬愛の念を著しく低下させた
21世紀初頭の政変は国王の権威を傷つけたのである
主権者は国民である
しかしその主権を国王が行使する、その発送がプーミポン体制であった
だが近年の過剰な王室利用、馬脚を現すような政治関与、
先例や期待に反する政治非関与によって破綻を来しつつあるように思われる
引き金は政治の民主化であった
主権者は国民なのか君主なのか、われわれは市民なのか臣民なのか
と国民が自問しはじめたと言えよう
選挙価値を実感して
君主主権体制の臣民であることを止めるとき
選挙で表現された民意の否定に君主が利用されるのであれば
攻撃の矛先が君主に向けられることは避けられない
君主制が制度化されておらず、非制度的な政治介入に利用されるならば
危機にさらされるのは民主主義よりも君主制と言えよう
混乱を収拾するには
君主制と代議制民主主義の関係を安定させる必要がある
君主が隠微な政治関与を止めて専制支配を行なうのか
それとも象徴になるのか
君主制を存続させるには選択肢は後者しかなかろう
《たまだ・よしふみ 京都大学大学院教授》


















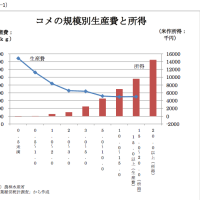

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます