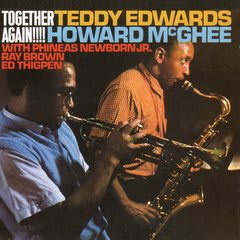Dizzy Gillespie and His Big Band in Concert
今年2017年は、ジャズのレコードが初めて作られた1917年からちょうど100年。
この、Original Dixieland Jass Bandのレコードはいきなりミリオンセラーになったそうだ。太古の昔から、絵画や文字でその当時の記録を残すことはできたが、音だけはレコードが発明されるまで記録に留めることはできなかった。クラシックと違って譜面に残されていないジャズの演奏は、レコードが無ければ当時の演奏の再現も難しい。音は悪くても貴重な演奏だ。
この史上初のジャズレコードが生まれた年1917年に誕生したジャズミュージシャンは沢山いるが、その一人がトランペットのディジーガレスピー。パーカーと共に、モダンジャズの原点であるビバップの創始者としても有名だ。
ガレスピーがミュージシャンとして本格的に活動を始めた1940年代、世の中はビッグバンドの全盛期。ガレスピーに限らず当時のジャズミュージシャンは皆ビッグバンドが仕事場であった。形にはまったジャズに満足できずに、仕事が終わった後のジャムセッションからビバップは生まれた。丁度、第2次世界大戦の真っ只中から戦後にかけてであった。戦争は多くの歴史・文化を失うが、大戦中でも戦場にならなかったアメリカ大陸だけは文化活動も途絶えることなく、却って革命的な変化が起こっていたということになる。
コンボの演奏形態としてのビバップが進化していった中、ビッグバンド好きのガレスピーは自らビバップオーケストラを作り、ビッグバンドが下火になった1956年まで自らのビッグバンドを率いていた。その後も、機会ある毎にレコーディングやライブで臨時編成のビッグバンドを率い、時には他のバンドのゲストとしてもよく参加した。根っからのビッグバンド好きであったのだろう。

先日、エリック宮城率いるブルーノートオールスタービッグバンドの新春ライブがあった。このバンドは最近ゲストプレーヤーを招くことが多いが、今回はガレスピーの生誕100年を祝って、ジョンファディスをゲストに招いてのライブであった。
宮城自身トランペットの第一人者であっても、今回のお題がガレスピーとなると、やはり一番弟子のジョンファディスが適役と考えたのだろう。実際のステージでも、ファディスが登場するとエリックは舞台を退き、プレーだけでなく、バンドの指揮もすべてファディスにお任せであった。
ジョンファディスも、若い頃はサドメルの一員として活躍し、近年ではカーネギーホールジャズオーケストラのディレクターを務めるなど、ガレスピー譲りは演奏だけではなく、
ビッグバンドバンドにも思い入れがあるようだ。
ステージではお馴染みのガレスピーナンバーを次々と繰り広げたが、得意のハイノートを駆使したプレーでバンドを引っ張るだけでなく、バックのオーケストラの演奏にも気を配っていた。ブルーノートオールスターズは百戦錬磨の日本を代表するプレーヤー揃い。しかし、ガレスピービッグバンドのノリを再現するには少々リハ不足だったかもしれない。最近では珍しいリフサンサンブルでの盛り上がり、そしてバラードの名曲アイリメンバークリフォードではバックのデリケートなアンサンブルに細かく指示を出していたのだが・・・。その中でファディスの期待に応えていたのは二井田ひとみの掛け合い。大先輩ファディスとのやり取りに多少困惑、そして気後れした感じはあったが、歌心あるプレーズで堂々と渡り合っていた。彼女のファンとしては嬉しい限り。
さて、このようなライブを聴くとオリジナルが聴きたくなる。リーモーガンやウィントンケリーがいた頃の、ニューポートでのライブがすぐに思い浮かぶが、やはり結成直後の演奏が原点だろう。
このアルバムは、ビバップの伝道師と言われたジーンノーマンが1948年に西海岸(パサディナのオーディトリアム)で行ったライブアルバム。ビバップのムーブメントは西海岸ではすんなりと受入れられなかったといわれるが、会場の盛り上がりは凄い。ジーンノーマンの功績は大きい。
ガレスピーのビッグバンドの特徴はもう一つ、ラテンサウンドを採り入れた所だ。それにはアレンジだけでなくパーカッションも大事。このライブにはキューバ出身のチャノボゾが参加しているのも価値がある。キューバからアメリカに来たのが、このライブの前年の’47年、翌年’49年の12月にはニューヨークのバーで射殺され、実際にアメリカで活躍した期間はほんの僅かであった。
ガレスピー以外のメンバーにも、テナーのジェイムスムーディー、バリトンのセシルペインなどがいてソロを繰り広げる。アレンジはガレスピーのオーケストラアレンジでは有名なギルフラーやタッドダメロン。やはり、バップオリエンテッドなモダンビッグバンドの原点はここにある。
1. Emanon Dizzy Gillespie / Milton Shaw 4:30
2. Ool-Ya-Koo Gil Fuller / Dizzy Gillespie 6:15
3. 'Round About Midnight B. Hanighen / T. Monk / C. Williams 3:35
4. Stay on It Tadd Dameron / Dizzy Gillespie 5:40
5. Good Bait Count Basie / Tadd Dameron 3:20
6. One Bass Hit Ray Brown / Gil Fuller / Dizzy Gillespie 5:05
7. I Can't Get Started Vernon Duke / Ira Gershwin 3:30
8. Manteca Gil Fuller / Dizzy Gillespie / Chano Pozo 7:35
Dizzy Gillespie (tp)
Dave Burns (tp)
Elman Wright (tp)
Willie Cook (tp)
William Shepherd (tb)
Jesse Tarrant (tb)
Cindy Duryea (tb)
Erney Henry (as)
John Brown (as)
Joe Gayles (ts)
James Moody (ts)
Cicil Payne (bs)
Nelson Boyd(b)
James Foreman (p)
Teddy Stewart (ds)
Chano Pozo (conga)
Produced by Gene Norman
Recorded live at Pasadene Civic Audorium, Calfornia on July 26,1948
今年2017年は、ジャズのレコードが初めて作られた1917年からちょうど100年。
この、Original Dixieland Jass Bandのレコードはいきなりミリオンセラーになったそうだ。太古の昔から、絵画や文字でその当時の記録を残すことはできたが、音だけはレコードが発明されるまで記録に留めることはできなかった。クラシックと違って譜面に残されていないジャズの演奏は、レコードが無ければ当時の演奏の再現も難しい。音は悪くても貴重な演奏だ。
この史上初のジャズレコードが生まれた年1917年に誕生したジャズミュージシャンは沢山いるが、その一人がトランペットのディジーガレスピー。パーカーと共に、モダンジャズの原点であるビバップの創始者としても有名だ。
ガレスピーがミュージシャンとして本格的に活動を始めた1940年代、世の中はビッグバンドの全盛期。ガレスピーに限らず当時のジャズミュージシャンは皆ビッグバンドが仕事場であった。形にはまったジャズに満足できずに、仕事が終わった後のジャムセッションからビバップは生まれた。丁度、第2次世界大戦の真っ只中から戦後にかけてであった。戦争は多くの歴史・文化を失うが、大戦中でも戦場にならなかったアメリカ大陸だけは文化活動も途絶えることなく、却って革命的な変化が起こっていたということになる。
コンボの演奏形態としてのビバップが進化していった中、ビッグバンド好きのガレスピーは自らビバップオーケストラを作り、ビッグバンドが下火になった1956年まで自らのビッグバンドを率いていた。その後も、機会ある毎にレコーディングやライブで臨時編成のビッグバンドを率い、時には他のバンドのゲストとしてもよく参加した。根っからのビッグバンド好きであったのだろう。

先日、エリック宮城率いるブルーノートオールスタービッグバンドの新春ライブがあった。このバンドは最近ゲストプレーヤーを招くことが多いが、今回はガレスピーの生誕100年を祝って、ジョンファディスをゲストに招いてのライブであった。
宮城自身トランペットの第一人者であっても、今回のお題がガレスピーとなると、やはり一番弟子のジョンファディスが適役と考えたのだろう。実際のステージでも、ファディスが登場するとエリックは舞台を退き、プレーだけでなく、バンドの指揮もすべてファディスにお任せであった。
ジョンファディスも、若い頃はサドメルの一員として活躍し、近年ではカーネギーホールジャズオーケストラのディレクターを務めるなど、ガレスピー譲りは演奏だけではなく、
ビッグバンドバンドにも思い入れがあるようだ。
ステージではお馴染みのガレスピーナンバーを次々と繰り広げたが、得意のハイノートを駆使したプレーでバンドを引っ張るだけでなく、バックのオーケストラの演奏にも気を配っていた。ブルーノートオールスターズは百戦錬磨の日本を代表するプレーヤー揃い。しかし、ガレスピービッグバンドのノリを再現するには少々リハ不足だったかもしれない。最近では珍しいリフサンサンブルでの盛り上がり、そしてバラードの名曲アイリメンバークリフォードではバックのデリケートなアンサンブルに細かく指示を出していたのだが・・・。その中でファディスの期待に応えていたのは二井田ひとみの掛け合い。大先輩ファディスとのやり取りに多少困惑、そして気後れした感じはあったが、歌心あるプレーズで堂々と渡り合っていた。彼女のファンとしては嬉しい限り。
さて、このようなライブを聴くとオリジナルが聴きたくなる。リーモーガンやウィントンケリーがいた頃の、ニューポートでのライブがすぐに思い浮かぶが、やはり結成直後の演奏が原点だろう。
このアルバムは、ビバップの伝道師と言われたジーンノーマンが1948年に西海岸(パサディナのオーディトリアム)で行ったライブアルバム。ビバップのムーブメントは西海岸ではすんなりと受入れられなかったといわれるが、会場の盛り上がりは凄い。ジーンノーマンの功績は大きい。
ガレスピーのビッグバンドの特徴はもう一つ、ラテンサウンドを採り入れた所だ。それにはアレンジだけでなくパーカッションも大事。このライブにはキューバ出身のチャノボゾが参加しているのも価値がある。キューバからアメリカに来たのが、このライブの前年の’47年、翌年’49年の12月にはニューヨークのバーで射殺され、実際にアメリカで活躍した期間はほんの僅かであった。
ガレスピー以外のメンバーにも、テナーのジェイムスムーディー、バリトンのセシルペインなどがいてソロを繰り広げる。アレンジはガレスピーのオーケストラアレンジでは有名なギルフラーやタッドダメロン。やはり、バップオリエンテッドなモダンビッグバンドの原点はここにある。
1. Emanon Dizzy Gillespie / Milton Shaw 4:30
2. Ool-Ya-Koo Gil Fuller / Dizzy Gillespie 6:15
3. 'Round About Midnight B. Hanighen / T. Monk / C. Williams 3:35
4. Stay on It Tadd Dameron / Dizzy Gillespie 5:40
5. Good Bait Count Basie / Tadd Dameron 3:20
6. One Bass Hit Ray Brown / Gil Fuller / Dizzy Gillespie 5:05
7. I Can't Get Started Vernon Duke / Ira Gershwin 3:30
8. Manteca Gil Fuller / Dizzy Gillespie / Chano Pozo 7:35
Dizzy Gillespie (tp)
Dave Burns (tp)
Elman Wright (tp)
Willie Cook (tp)
William Shepherd (tb)
Jesse Tarrant (tb)
Cindy Duryea (tb)
Erney Henry (as)
John Brown (as)
Joe Gayles (ts)
James Moody (ts)
Cicil Payne (bs)
Nelson Boyd(b)
James Foreman (p)
Teddy Stewart (ds)
Chano Pozo (conga)
Produced by Gene Norman
Recorded live at Pasadene Civic Audorium, Calfornia on July 26,1948
 | Dizzy Gillespie And His Big Band In Concert |
| クリエーター情報なし | |
| GNP Crescendo |