透明な空気と、グルグルまわる視界。光がやわらかい。自分がだれなのか、さっぱりわからない。今度はどんなファンタジー? モヤついた肉眼レンズに、三本のサークラインがぼんやり映った。灯は消えている。廃棄プラントのような脳内が、それでも自動的にスキャンされた。倉庫の寝室? NO。NGOの学校の寮? それもNOだ。騒音と振動がないのでヘリの中じゃない。ペルシャ模様の壁紙を張った天井に目のピントが合った。そこからアイボリー・ホワイトの丸い笠におおわれたサークラインが吊り下がっている。あんな天井、脳内アーカイブにない。頭はフカフカした枕にうずまっていた。フカフカの?
ミゲルの実家かな? でもあそこは畳に引いたフトンで、ベッドじゃない。まさか、チョウの寝室? 拉致された? 襲う不安。意識に厚みが増す。拷問台の上かも! でも頭はなんの抵抗もなく上がる。足元で白いカーテンレースがふくらんだ。窓が細くあけられ、おだやかな太陽光が散乱している。窓際に、曲線模様が浮きでた茶色の花瓶が置かれていた。ピンク、赤、青、白、黄色の、名前も知らない花がたくさん生けられている。どの花も小ぶりで、葉っぱのほうが大きいほどだ。花弁は向こうが透けるほどうすく、ながぼそい緑色の軸をもっていた。ミゲルと一緒にメジロの花屋さんで見たかけたのとも違う。ここは知らないところだ、100%!
起き上がろうとして気がついた。緩めだけど、やっぱり体が固定されている。チューブが肩と腕、足から何本も伸びていて、点滴棒と、何段にも積み上げられたブラック・ボックスにその先が連結されている。ようやく状況が呑みこめてきた。大量の点滴棒、見慣れない機械に取り囲まれている。なにかの液体が体に注入されつづけている。ブラックボックスにはパイロットランプが点滅し、緑色の帯が走っていた。数台のモニターに意味不明の波形が上下していた。
部屋の外でパタパタパタ……と音がする。パタパタパタはヘリの擬音語だけど、またちがうパタパタパタだ。おれ、なに考えてんのかな? 何もわからないってことをさ。廊下を急ぐスリッパみたいな音。ドバーンッ! ドアが勢いよく押し開かれた。あわてて目をつぶり、寝たふりをした。ヒーツジさんが一匹、ヒーツジさんが二匹……。
「リョウ、リョウ、わたし! わかる?」
えっ? 完全武装の兵士じゃなくて暗殺部隊でもなくて、メアリーみたいな? どんなファンタジーだよ、まったく!? そんなの、もう嫌だ! ヒーツジさんが四匹、ヒーツジさんが五匹……泣いてる。ヒックヒックって、しゃっくりあげて泣いてる。でも目ぇ開けたらメアリーは消えちゃうんだ。これが夢でも現実でも同じでね。見たら消えちゃう。本当にそこにいるみたいにメアリーの声が聞こえる。顔見たいけど、本当にそこにいたって目ぇ開けたら絶対消えちゃうんだ! ヒーツジさんが六匹、ヒーツジさんが七匹……。おまえの反応かなり幼児的じゃん? って中の声なんか全然無視だ。トラウマが大きかった。ツツツ……目じりを涙が伝った。
メアリー・アバターがこっちに来る。足音でわかる。よくできてんなー、このプログラム! うわ。何かやわらかいものが目じりをぬぐうよ。
「まだ痛い? かわいそう……」
目ぇ開けたい。会いたいよ! ジャカスカ涙がでる。うっ、なんて声もでる。声!? あれなんの音? ジィィィィ……ゴトトト……。ドタドタドタドタ……廊下のほうが急に騒々しくなった。へんな機械音と六個くらいの足音が接近する。ムカデ男の出現? ゴトゴトッ、キキーッ。急ブレーキの音。なんで? 部屋が人でいっぱいの気配。とうとう、おれは取り囲まれた。好きにしろ、おまえら。おれは逃げない。寝たふりだけは頑なにつづけた。
「どうだメアリー! 戻ったか、意識?」と男。
「まだみたい。ぜんぜん動かないの。植物人間になっちゃった!」
なんだ。なんなんだー、これ! ドスドスドスッとサイレンサーがうなる、と思ったら博士の声か? バイキング出身のあのバリトン、一回聞いたらだれだって忘れない。
「それ、わしへのあてつけに聞こえるがね。まあいい、ちょっと診てくれ」
「さっきから泣いてんの。どっか痛いんじゃない?」
衣擦れと足音。だれかがベッドサイドに近よってくる。
「まだ夢でも見てるんですかね」
おれの目玉がグギギギッとこじあけられ、ペンライトでパカッと照らされた。
「目がグリグリ動いてますよ! 瞳孔も通常にもどってます!」
うっせー、テメーのマスクした顔が見えてるもん。なんだって人の安眠を妨害するんだ。寝てないけど。仕方なく、おれはもうひとつの目も開けた。あ。メアリー、博士。博士は電動車椅子に乗ってる。あれはMAX15km/時でジグザグに走れるTG型高級車だ。東京グレース(日本女子車椅子バスケチーム)モデルの車にHONDA製ソーラー・バッテリーを積みこんだ陰のヒット商品。
「わーい。リョウが目を開けた!」
「意識、回復したか!」
「成功ですね博士! 歴史的な一瞬! おめでとうございます!」
人の目玉こじ開け専門のマスク男はポケットから携帯を取りだし、パシッとフラッシュさせた。
別のマスク・アバターがブラック・ボックスを調べ、手にしたバインダーのメモ用紙にボールペンで何か書いてる。一体なんなんだ、このプログラムは? メアリー以外に博士アバターと三体のマスク・アバターまで揃えて、動きもスムーズだし、部屋もバスケ車も隅々まで精巧に描けてる。けっこう高級な3Dソフト。ゲーマーにわけわかんない会話と、現地語・英語が入り乱れた使用言語が欠点だな。いつ終わんの、このゲーム?
「なんかいってる!」とメアリー・アバター。
「消えちゃうんだろ?」とおれ。
「何いってるんだ?」と博士アバター。
ブラック・ボックスをチェックしていたマスク・アバターが、顔の前でボールペンをチチチッと振った。
「うーん、社会心理学的にはですね……。いま検体は、精神的ダメージによる精神錯乱に陥ってるんじゃないですか? 消えるというのは、一種の幸福感だと思いますね。過去のデータによりますと、危機感や飢餓感などのマイナス・イメージなら長期にわたって尾を引く。ですが一般的に、プラス・イメージは水泡のように消えると認知されてるようです」
検体っていった? 検便のサンプルか、おれは!
携帯カメラを撮ったマスク・アバターがいう。
「それは時代の影響がありますよ。いまは不安だけが煽られる時代ですからね」
博士の車椅子に付き添っていた三人目のマスク女がおれの首に手をあて、脈をとった。バインダーにはさんだ書類に何かメモしてる。マスク女を押しのけて、メアリー・アバターが近づく。おれの頬を両手に包み、ダークブルーの目でじっと見つめる。
「もう、消えない!」
白い顔が接近して、メアリーのブロンドが顔にかかって額や頬をくすぐった。甘い香りがただよう。あたたかい液体がポタポタと顔に落ち、おれは目をつぶった。やわらかい唇が触れた。 《続》
戻る; ソウルキッズ …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8 …9 …10 …11 …12 …13 …14
ミゲルの実家かな? でもあそこは畳に引いたフトンで、ベッドじゃない。まさか、チョウの寝室? 拉致された? 襲う不安。意識に厚みが増す。拷問台の上かも! でも頭はなんの抵抗もなく上がる。足元で白いカーテンレースがふくらんだ。窓が細くあけられ、おだやかな太陽光が散乱している。窓際に、曲線模様が浮きでた茶色の花瓶が置かれていた。ピンク、赤、青、白、黄色の、名前も知らない花がたくさん生けられている。どの花も小ぶりで、葉っぱのほうが大きいほどだ。花弁は向こうが透けるほどうすく、ながぼそい緑色の軸をもっていた。ミゲルと一緒にメジロの花屋さんで見たかけたのとも違う。ここは知らないところだ、100%!
起き上がろうとして気がついた。緩めだけど、やっぱり体が固定されている。チューブが肩と腕、足から何本も伸びていて、点滴棒と、何段にも積み上げられたブラック・ボックスにその先が連結されている。ようやく状況が呑みこめてきた。大量の点滴棒、見慣れない機械に取り囲まれている。なにかの液体が体に注入されつづけている。ブラックボックスにはパイロットランプが点滅し、緑色の帯が走っていた。数台のモニターに意味不明の波形が上下していた。
部屋の外でパタパタパタ……と音がする。パタパタパタはヘリの擬音語だけど、またちがうパタパタパタだ。おれ、なに考えてんのかな? 何もわからないってことをさ。廊下を急ぐスリッパみたいな音。ドバーンッ! ドアが勢いよく押し開かれた。あわてて目をつぶり、寝たふりをした。ヒーツジさんが一匹、ヒーツジさんが二匹……。
「リョウ、リョウ、わたし! わかる?」
えっ? 完全武装の兵士じゃなくて暗殺部隊でもなくて、メアリーみたいな? どんなファンタジーだよ、まったく!? そんなの、もう嫌だ! ヒーツジさんが四匹、ヒーツジさんが五匹……泣いてる。ヒックヒックって、しゃっくりあげて泣いてる。でも目ぇ開けたらメアリーは消えちゃうんだ。これが夢でも現実でも同じでね。見たら消えちゃう。本当にそこにいるみたいにメアリーの声が聞こえる。顔見たいけど、本当にそこにいたって目ぇ開けたら絶対消えちゃうんだ! ヒーツジさんが六匹、ヒーツジさんが七匹……。おまえの反応かなり幼児的じゃん? って中の声なんか全然無視だ。トラウマが大きかった。ツツツ……目じりを涙が伝った。
メアリー・アバターがこっちに来る。足音でわかる。よくできてんなー、このプログラム! うわ。何かやわらかいものが目じりをぬぐうよ。
「まだ痛い? かわいそう……」
目ぇ開けたい。会いたいよ! ジャカスカ涙がでる。うっ、なんて声もでる。声!? あれなんの音? ジィィィィ……ゴトトト……。ドタドタドタドタ……廊下のほうが急に騒々しくなった。へんな機械音と六個くらいの足音が接近する。ムカデ男の出現? ゴトゴトッ、キキーッ。急ブレーキの音。なんで? 部屋が人でいっぱいの気配。とうとう、おれは取り囲まれた。好きにしろ、おまえら。おれは逃げない。寝たふりだけは頑なにつづけた。
「どうだメアリー! 戻ったか、意識?」と男。
「まだみたい。ぜんぜん動かないの。植物人間になっちゃった!」
なんだ。なんなんだー、これ! ドスドスドスッとサイレンサーがうなる、と思ったら博士の声か? バイキング出身のあのバリトン、一回聞いたらだれだって忘れない。
「それ、わしへのあてつけに聞こえるがね。まあいい、ちょっと診てくれ」
「さっきから泣いてんの。どっか痛いんじゃない?」
衣擦れと足音。だれかがベッドサイドに近よってくる。
「まだ夢でも見てるんですかね」
おれの目玉がグギギギッとこじあけられ、ペンライトでパカッと照らされた。
「目がグリグリ動いてますよ! 瞳孔も通常にもどってます!」
うっせー、テメーのマスクした顔が見えてるもん。なんだって人の安眠を妨害するんだ。寝てないけど。仕方なく、おれはもうひとつの目も開けた。あ。メアリー、博士。博士は電動車椅子に乗ってる。あれはMAX15km/時でジグザグに走れるTG型高級車だ。東京グレース(日本女子車椅子バスケチーム)モデルの車にHONDA製ソーラー・バッテリーを積みこんだ陰のヒット商品。
「わーい。リョウが目を開けた!」
「意識、回復したか!」
「成功ですね博士! 歴史的な一瞬! おめでとうございます!」
人の目玉こじ開け専門のマスク男はポケットから携帯を取りだし、パシッとフラッシュさせた。
別のマスク・アバターがブラック・ボックスを調べ、手にしたバインダーのメモ用紙にボールペンで何か書いてる。一体なんなんだ、このプログラムは? メアリー以外に博士アバターと三体のマスク・アバターまで揃えて、動きもスムーズだし、部屋もバスケ車も隅々まで精巧に描けてる。けっこう高級な3Dソフト。ゲーマーにわけわかんない会話と、現地語・英語が入り乱れた使用言語が欠点だな。いつ終わんの、このゲーム?
「なんかいってる!」とメアリー・アバター。
「消えちゃうんだろ?」とおれ。
「何いってるんだ?」と博士アバター。
ブラック・ボックスをチェックしていたマスク・アバターが、顔の前でボールペンをチチチッと振った。
「うーん、社会心理学的にはですね……。いま検体は、精神的ダメージによる精神錯乱に陥ってるんじゃないですか? 消えるというのは、一種の幸福感だと思いますね。過去のデータによりますと、危機感や飢餓感などのマイナス・イメージなら長期にわたって尾を引く。ですが一般的に、プラス・イメージは水泡のように消えると認知されてるようです」
検体っていった? 検便のサンプルか、おれは!
携帯カメラを撮ったマスク・アバターがいう。
「それは時代の影響がありますよ。いまは不安だけが煽られる時代ですからね」
博士の車椅子に付き添っていた三人目のマスク女がおれの首に手をあて、脈をとった。バインダーにはさんだ書類に何かメモしてる。マスク女を押しのけて、メアリー・アバターが近づく。おれの頬を両手に包み、ダークブルーの目でじっと見つめる。
「もう、消えない!」
白い顔が接近して、メアリーのブロンドが顔にかかって額や頬をくすぐった。甘い香りがただよう。あたたかい液体がポタポタと顔に落ち、おれは目をつぶった。やわらかい唇が触れた。 《続》
戻る; ソウルキッズ …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8 …9 …10 …11 …12 …13 …14












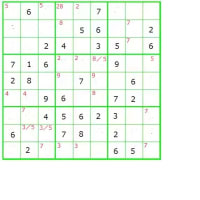
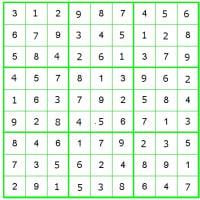
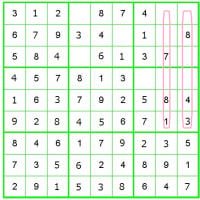
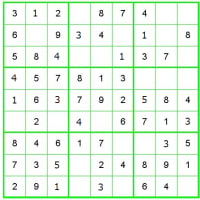
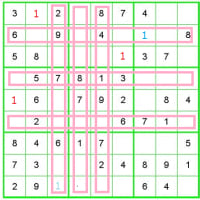
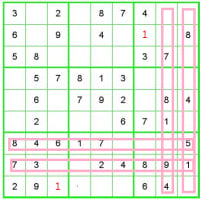
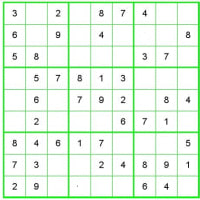

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます