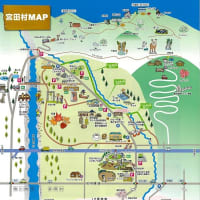その家の様子をうかがうには、家構えや表札もひとつだが、何といっても今は「車」である。地方ではとくにそれは顕在化する。どんなに大きい家構えでも、小さな家構えでも、車の台数はその家を現実化する。それをもってその家の家族を描き出す。誰もが免許を持つ時代であるからこそ、車の台数はそのまま家族構成につながる。いくらなんでも一人で3台も4台も車を持つことは、ふうはありえない。したがって基本的には車の台数=家族員数となり、そこに作業用の車をどう勘定するかとなる。我が家の場合も車の台数は4台である。ひとりずつ1台所有しているとすれば、もう1台は作業用の車、ようするに軽トラックはそれにあたる。農家の場合おおよそこのような姿を描くもので、「車」の台数は家族構成員プラスアルファ―なのである。例えばその家に5台車かあれは、家族構成員は4人か5人といったところ。前回記したように表札に何人記してあろうと、車の台数がその員数を下回れば、表札に記された家族の誰かは在宅ではないと捉えられる。ようは、今の地方では、車の台数が家族構成員数を如実に表しているということになる。
加えてその車の様相である。高級外車があれば、その家構えと照らし合わせて釣り合っているか、あるいは不釣り合いか、という見方になるだろう。家構えに比べて不釣り合いがあるとすれば、その背景に何があるか、ということになる。もちろんこうした事例は多くはない。そして当然のことであるだろうが、高級外車があって構えが立派なら、そのままその家を写し出していると、誰もが思うもの。人びとと不釣り合いな光景に違和感を覚え、釣り合っていれば納得するもの。日本の社会では、こうした家構えと表札と、そして車の台数、さらにはその車種をもって家々を様々に捉える。情けない話であるが、それが現実なのである。
家の構え、表札、そして「車」、と外見上の「家」をうかがってきた。そうはいっても外見=「家を表す」のは昔も今も変わらない。そして何といっても、今は車がその家のイメージに繋がる。誰とは言えなくても、その家のイメージが派手なのか地味なのかは、車で判断できる。そしてそこから家族構成員の年齢や、もしかしたら生業すらイメージされる。あとはその個人の性格をどの程度知っているか、ということになるわけで、最終的にはトータルな背景からその家を捉えることとなる。そしてそれがそのまま地域の特性となり、さらにはその地域の住みやすささえも描くことに繋がる。どうみても「貧しい」と思われる地域には、鬱積が溜まっていて、きっと地域社会には妬みや恨みさえも積み重なっていたりする。貧しい社会には貧しい心が疼いてしまったりする。致し方ない現実であり、それはなかなか解消できるものではない。地方の地域の悪い面を浮き彫りにし、その果てには意地悪や、村八分といった今では考えられないような現実が垣間見える。が、しかしそれが地方のちいきしゃかいであって、けして「絆」などという言葉はあてはまらないわけである。そうした背景を踏まえたうえで、わたしたちは地域へと踏み込んでいくのである。
終わり