
素晴らしき秋晴れの大阪。

日中は温かく、ウォーキングを兼ねて所用があった茨木市内に行って来たのですが、11、000歩ほど歩いただけで、汗びっしょりになっていました。
西河原公園や元茨木川緑地などあちらこちらで、プチ紅葉を楽しませてもらいました。
とっつあんなりに絵になる写真があれば、紹介します。
今日の1枚の写真は、先日の西国街道探訪で見かけた、プチ紅葉です。
これは、紅葉よりもヴォーリズ建築が素晴らしいようですが…。
ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories、一柳米来留 ( ひとつやなぎめれる )1880年10月28日 - 1964年5月7日)は、アメリカ合衆国に生まれ、日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家です。
建築家でありながら、ヴォーリズ合名会社(のちの近江兄弟社)の創立者の一人としてメンソレータム(現メンターム)を広く日本に普及させた実業家でもあります。
写真の建物は、昭和8年(1933) に建てられたそうです。

最近は温暖化が進み、「立冬」と言っても11月の初めはまだまだ秋ですネ。
しかし日中の陽射しは幾分弱まり、日暮れが早くなって朝夕には空気の冷たさを感じ始める頃です。
季節感がなくなって久しい現代人の暮らしですが、古来より大切にされてきた日本人の自然観はまだまだ残されているようです。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日11月13日(戊寅つちのえとら 友引)はこんな日です。
●「うるしの日」
平安時代の、文徳(もんとく)天皇の第一皇子惟喬(これたか)親王が京都・嵐山の法輪寺に参詣し、虚空蔵菩薩からうるしの製法、漆器の製造法を伝授されたのがこの日であるとされていることから、1985(昭和60)年に日本漆工協会が制定しました。
この日は、以前から漆関係者の祭日でした。日本の伝統文化であるうるしの美しさを今一度見直して日本の心を呼び戻すことを目的にしています。
●「空也忌」
平安中期の僧で踊念仏の開祖、空也上人の忌日です。
空也上人は天禄3年(972)9月11日に没しましたが、晩年に修行のため東国へ出立した際の遺言により、出寺の日とされる11月13日(陰暦)を開山忌とし、のち第2日曜に行われるようになりました。
毎年11月の第2日曜日に、空也上人を偲んで京都市中京区の空也堂(紫雲山光勝寺極楽院)で、開山忌(空也忌)の法要が営まれます。
王服(おうぶく)茶の献茶式の後、空也僧による歓喜踊躍(かんぎゆやく)念仏と重要無形民俗文化財の六斎(ろくさい)念仏焼香式が奉修されます。
●「茨城県民の日」
1871(明治4)年11月13日、廃藩置県によって茨城県が誕生したことに因んで、茨城県が明治100年にあたる1968年(昭和43年)に制定されました。
郷土の歴史を知り、より豊かな暮しと県の発展を願い、茨城の現在・過去・未来を見詰め直す日です。
●「いいひざの日」
寒さが増してひざが痛み出す時期に、コンドロイチンZS錠などの関節痛の薬を開発するゼリア新薬工業株式会社が、ひざ関節痛の治療や予防を広く呼びかけるために制定した日です。
日付の理由には覚えやすいように11と13で「いいひざ」と読む語呂合わせも含まれているそうです。
●「「霜月例大祭(ひめじ祭り)」11月13日~16日」
平安末期播磨国内174座の神々を合祀し、播磨国総社 射盾兵主神社とよばれるようになった11月15日を記念した祭礼で、ひめじ祭とし、播州地方最後の秋祭りが「霜月例大祭」です。
13日の「潮かき」から16日の「神輿巡行」まで、境内は大勢の参拝者で賑わいます。
播磨国総社、射楯兵主神社(いたてひょうずじんじゃ) 姫路市総社本町190 電話:0792-24-1111()![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は2196話です。「よかった!」と思われたら「季節・四季」ボタンをポチッとお願いします。













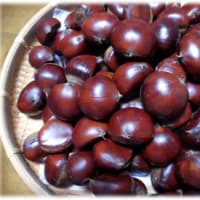






誰が見てもどこから見てもいいですね。
単に古いからいいという訳ではなさそうです。
残っていくだけの理由はありそうですね。
私は建築のことも美術のことも分かりませんが、感覚的に何か魅せられるものがあります。
ここも震災の時に一部壊れて無くなったそうです。
保存・維持して行くのも大変だと思います。
個展用最後の窯焚は如何でしたか。
青磁、白磁は、難しいのですね。