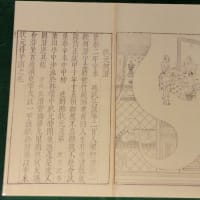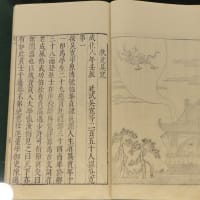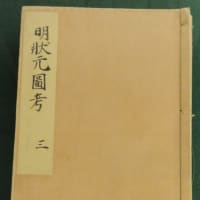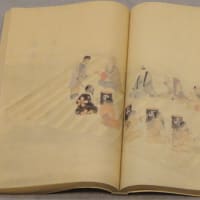藤森神社を後に京阪本線・墨染駅前の踏切を渡り墨染街道を西へ。
師団街道筋、墨染寺の隣りに「欣浄寺」(ごんじょうじ)がある。
寺の伝えによると寛喜2年(1230)から天福元年(1233)まで
道元禅師がこの地で教化に務め、当寺を創建したといわれる。
当初は真言宗であったが応仁の乱(1467)後に曹洞宗になり、
途中、浄土宗に改められるものの再び曹洞宗に改宗。
こちらの境内に「墨染井」(すみぞめい)がある。当地は深草少
将義宣の屋敷があったところと伝わり、池の東の藪道は“少将の通
い道”と呼ばれ、訴訟のある者が通ると願いが叶わないといわれて
いる複雑な道だ。またこの井戸は“少将の井”とも呼ばれている。
(京都市伏見区西桝屋町1038)
師団街道筋、墨染寺の隣りに「欣浄寺」(ごんじょうじ)がある。
寺の伝えによると寛喜2年(1230)から天福元年(1233)まで
道元禅師がこの地で教化に務め、当寺を創建したといわれる。
当初は真言宗であったが応仁の乱(1467)後に曹洞宗になり、
途中、浄土宗に改められるものの再び曹洞宗に改宗。
こちらの境内に「墨染井」(すみぞめい)がある。当地は深草少
将義宣の屋敷があったところと伝わり、池の東の藪道は“少将の通
い道”と呼ばれ、訴訟のある者が通ると願いが叶わないといわれて
いる複雑な道だ。またこの井戸は“少将の井”とも呼ばれている。
(京都市伏見区西桝屋町1038)