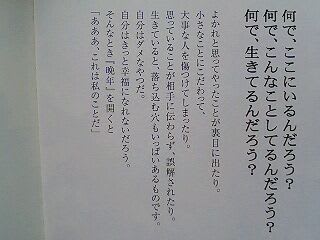
文豪ナビ 太宰 治, 新潮文庫編, 新潮文庫 (7550)た-2-0, 2004年
・太宰が好きである。しかしマニアというほどでもなく、新潮文庫で出ている分は全部読んだという程度。
・太宰治の解説本。『太宰作品ナビ』、『10分で読む「要約」』、『声に出して読みたい太宰治』、エッセイ、評伝、旅コラムなどなど、執筆陣も多彩。若者の活字離れ、を意識しているようで、やわらかめでとっつきやすい構成になっている。
・「内容に共感できる!」という感想が多いのですが、私の場合はあまりピンときません。内容よりもむしろ『天才』を感じさせる文章そのものに惹かれます。 全て「太宰万歳!!」的内容なので、アンチ太宰の声も聞いてみたいところ。
・「ダザイは、自分の実際の人生を美しい物語に書き上げることに絶えず失敗しつづけた。薬物中毒になったり、酒癖や女癖が悪かったり、社会改革の理想を捨てたり、女性と心中事件を何度も繰り返したり。彼は、まったく出来のよくない人生を生きた。」p.27
・「「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ。人モ家モ、暗イウチハマダ滅亡セヌ」(『右大臣実朝』)」p.28
・「色で言えば、ダザイに最もふさわしいのは、黒。でも、「黒い」と「暗い」は違う。ダザイの黒は、テカテカ光っている。アカルイ黒だ。黒光りのする黒だ。」p.28
・「彼は「壊す人」、すなわち、ザ・デストラクディブ・マン、ザ・デストロイヤーだった。ダザイは、ダザイらしい作風をも破壊しつづける永遠の冒険者だった。」p.31
・「ダザイの小説は、読者の一人一人の心の中の本当の顔を映し出す「鏡」のようなもの。」p.33
・「人間、失格。もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。(中略)自分には、幸福も不幸もありません。ただ、一さいは過ぎて行きます。(『人間失格』)」p.66
・「太宰治を読もう。 いや、ほんと、太宰治を読もうよ。 ここには、「ぼくたち」がいる。セコくて、自意識過剰で、周囲から浮いてしまうことを警戒しながらも他人とはひと味違う自分でありたくて、なのにそれがうまくいかずに落ち込んだりスネたりしている、そんな「ぼくたち」が、太宰治の小説には満載なのだ。(重松清)」p.70
・「太宰治の魅力は、危うさにある。(齋藤孝)」p.83
・「小説家は、何とも言葉にしにくい感覚を的確に言葉にする職業だ。しかもその微妙な感覚を他人の身体に入り込んだ形で表現する。(齋藤孝)」p.87
・「それだから、走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題ではないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っているのだ。」p.93
・「太宰は私たち皆がかすり傷のように持っている心の傷を、自ら切り開いて血を流してみせる。捨て身で、心の傷と傷をすりあわせようとしてくるのだ。(齋藤孝)」p.97
・「私など文字を連ねることで文章を作っていこうとしてしまう。線路を走る列車のように書いてしまう。太宰は違う。何をどう描きたいのかがはっきりとイメージされていて、そのイデアに向かって言葉を色や音色のように自由に使う。「富嶽百景」など、まさに言葉の絵画だ。(田口ランディ)」p.106
・「魂が濃い。そう思った。太宰のどの作品も込められた魂が濃い。(田口ランディ)」p.106
・「太宰治の作品は、もちろん文章としても素晴らしいけれど、特筆すべきなのは、作品に自分の命を注ぎ込んでいるところである。こんなふうに、作品に自分を投影しつづけたら、空っぽになってしまう。(田口ランディ)」p.112
・「太宰は、自分という人間を破壊したかったのだ。(島内景二)」p.119
・「そう、『走れメロス』や『富嶽百景』などの一時期を例外として、太宰は後味の良くない小説を書くことを恥じなかった。(島内景二)」p.128
・「(中原)中也と太宰は、飲み屋でなぐりあいの喧嘩をしている。中也の挑発のペースに、まんまと太宰がハマってしまったのだろう。(島内景二)」p.130
・「太宰のミジメな人生からしたたり落ちた小説が、なぜか読者の心を癒すのだ。これは、奇蹟だ。(島内景二)」p.132
・「「太宰治」というペンネームを使い始めたのは、昭和八年。二四歳からである。それ以前は、本名の津島修治をもじった「辻島衆ニ」や、いかにも労働者風の「小菅銀吉」「大藤熊太」などを用いていた。「山本周五郎」や「綿谷りさ」方式で、友人知人の名前を借用したこともあった。(中略)おそらくそれほど深い考えもなしに名のった名前だったが、名作を次々と発表し、芥川賞の候補に二度もなったりしたので、その名前で最後まで押し通したのだろう。(島内景二)」p.135
・「なぜなら、太宰の素顔は、ザ・デストラクティブ・マンなのだから。彼の生の声は、おそらく「みんな滅んでしまえ。滅びは楽しいぞ。俺も滅びたい」ではなかったか。(島内景二)」p.145
・太宰が好きである。しかしマニアというほどでもなく、新潮文庫で出ている分は全部読んだという程度。
・太宰治の解説本。『太宰作品ナビ』、『10分で読む「要約」』、『声に出して読みたい太宰治』、エッセイ、評伝、旅コラムなどなど、執筆陣も多彩。若者の活字離れ、を意識しているようで、やわらかめでとっつきやすい構成になっている。
・「内容に共感できる!」という感想が多いのですが、私の場合はあまりピンときません。内容よりもむしろ『天才』を感じさせる文章そのものに惹かれます。 全て「太宰万歳!!」的内容なので、アンチ太宰の声も聞いてみたいところ。
・「ダザイは、自分の実際の人生を美しい物語に書き上げることに絶えず失敗しつづけた。薬物中毒になったり、酒癖や女癖が悪かったり、社会改革の理想を捨てたり、女性と心中事件を何度も繰り返したり。彼は、まったく出来のよくない人生を生きた。」p.27
・「「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ。人モ家モ、暗イウチハマダ滅亡セヌ」(『右大臣実朝』)」p.28
・「色で言えば、ダザイに最もふさわしいのは、黒。でも、「黒い」と「暗い」は違う。ダザイの黒は、テカテカ光っている。アカルイ黒だ。黒光りのする黒だ。」p.28
・「彼は「壊す人」、すなわち、ザ・デストラクディブ・マン、ザ・デストロイヤーだった。ダザイは、ダザイらしい作風をも破壊しつづける永遠の冒険者だった。」p.31
・「ダザイの小説は、読者の一人一人の心の中の本当の顔を映し出す「鏡」のようなもの。」p.33
・「人間、失格。もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました。(中略)自分には、幸福も不幸もありません。ただ、一さいは過ぎて行きます。(『人間失格』)」p.66
・「太宰治を読もう。 いや、ほんと、太宰治を読もうよ。 ここには、「ぼくたち」がいる。セコくて、自意識過剰で、周囲から浮いてしまうことを警戒しながらも他人とはひと味違う自分でありたくて、なのにそれがうまくいかずに落ち込んだりスネたりしている、そんな「ぼくたち」が、太宰治の小説には満載なのだ。(重松清)」p.70
・「太宰治の魅力は、危うさにある。(齋藤孝)」p.83
・「小説家は、何とも言葉にしにくい感覚を的確に言葉にする職業だ。しかもその微妙な感覚を他人の身体に入り込んだ形で表現する。(齋藤孝)」p.87
・「それだから、走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う、間に合わぬは問題ではないのだ。人の命も問題でないのだ。私は、なんだか、もっと恐ろしく大きいものの為に走っているのだ。」p.93
・「太宰は私たち皆がかすり傷のように持っている心の傷を、自ら切り開いて血を流してみせる。捨て身で、心の傷と傷をすりあわせようとしてくるのだ。(齋藤孝)」p.97
・「私など文字を連ねることで文章を作っていこうとしてしまう。線路を走る列車のように書いてしまう。太宰は違う。何をどう描きたいのかがはっきりとイメージされていて、そのイデアに向かって言葉を色や音色のように自由に使う。「富嶽百景」など、まさに言葉の絵画だ。(田口ランディ)」p.106
・「魂が濃い。そう思った。太宰のどの作品も込められた魂が濃い。(田口ランディ)」p.106
・「太宰治の作品は、もちろん文章としても素晴らしいけれど、特筆すべきなのは、作品に自分の命を注ぎ込んでいるところである。こんなふうに、作品に自分を投影しつづけたら、空っぽになってしまう。(田口ランディ)」p.112
・「太宰は、自分という人間を破壊したかったのだ。(島内景二)」p.119
・「そう、『走れメロス』や『富嶽百景』などの一時期を例外として、太宰は後味の良くない小説を書くことを恥じなかった。(島内景二)」p.128
・「(中原)中也と太宰は、飲み屋でなぐりあいの喧嘩をしている。中也の挑発のペースに、まんまと太宰がハマってしまったのだろう。(島内景二)」p.130
・「太宰のミジメな人生からしたたり落ちた小説が、なぜか読者の心を癒すのだ。これは、奇蹟だ。(島内景二)」p.132
・「「太宰治」というペンネームを使い始めたのは、昭和八年。二四歳からである。それ以前は、本名の津島修治をもじった「辻島衆ニ」や、いかにも労働者風の「小菅銀吉」「大藤熊太」などを用いていた。「山本周五郎」や「綿谷りさ」方式で、友人知人の名前を借用したこともあった。(中略)おそらくそれほど深い考えもなしに名のった名前だったが、名作を次々と発表し、芥川賞の候補に二度もなったりしたので、その名前で最後まで押し通したのだろう。(島内景二)」p.135
・「なぜなら、太宰の素顔は、ザ・デストラクティブ・マンなのだから。彼の生の声は、おそらく「みんな滅んでしまえ。滅びは楽しいぞ。俺も滅びたい」ではなかったか。(島内景二)」p.145















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます