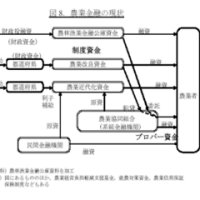たびたび言及することですが、「尊敬する人は誰ですか?」と問われたら真っ先に答えるのがこの服部正也。
素晴らしさは語りつくせませんが、この本はそんな彼の遺稿です。
ちなみに、著作は先のルワンダ中央銀行総裁日記とこの2冊のみです。
「途上国経済の均衡回復のための対症療法の品書き(メニュー)はおおむね決まっている。その品書きのうち何を、どの程度、どの順序で実施するかは、その途上国の不均衡の度合い(病状)ばかりでなく、病原の種類性質とその深刻さ、それに、患者である途上国の体力を考慮して定められるべきである。また、対症療法だけでは不十分で、不均衡の基本原因である病原を正しく診断して、その治療をも処方し、患者である途上国の体力増強の処置が必要である。そのためには、途上国の歴史と現状に関する知識が必要であり、そこから不均衡の根本的病原を分析し、速効性のある対症療法と併せて、国民の経済発展の体力を増進する施策を、国民の納得と協力を確保して実施しなければならない」
「これは、外国人からの情報を無視せよということではない。外国人からの情報は外国人村での伝承の受け売りであることが多いが、実体験であることもないわけではない。大事なことは、伝承の受け売りか、実体験であるかどうかを見極めることと、実体験の場合、体験した事実が、特殊なものであるか、一般的なものであるか、また、その体験に対する解釈が正しいのかどうかを、厳しく検討することである。しかし何といっても、現地の人たちとの対話が最も重要である。この現地人との対話が有意義にできるために、また、外国人からの情報を構成に解釈するために、まず、途上黒人と我々とは、いろいろの違いはあっても、二つの意欲を共有し、その意欲を実現するために、二つの属性が必要であることをつねに意識していなければならないと思う。その二つの属性の第一は、生存意欲であり、第二は発展意欲である。そして、それを実現するための属性は、自尊自立の精神と、合理性とである。これは自明のことのように見えるが、現実にはしばしば忘れられているのである」
「その場合、我々外国人はアフリカ人は合理的思考ができないと即断する傾向があるが、それは果たして正しいだろうか。ある人にとって合理的な行動は、その人が置かれている環境の認識に基づいて、その人が望む目的を達成するために、その人が使える最良の手段を選ぶことである。したがって、その人が置かれている環境はどんなものか、その環境を、その人はどう認識しているか、その人の望む目的は何か、それを達成するためにその人が利用できる手段としてはどんなものがあるのか、を知らなければ、その人の行動が合理的であったかどうかは判断できない。平たくいえば、相手の立場になって考えるということだが、この当たり前のことが、アフリカでは、アフリカ人が『後れている』という偏見のため、忘れられやすいのであり、そのため、アフリカ人に関する種々の誤解が広く信じられている。こうして、アフリカの発展に関する有意義な対話が出来ず、誤った政策の採用が勧奨、場合によっては資金供与を餌に強要され、あるいは途上国の発展に役立つどころか、かえってその負担を増加する『援助』案件が実施されている例が少なくない」
「ビールを作るバナナはやめて、コーヒーを植えよというベルギー人農業顧問のことを、何も分かっていないとルワンダ人が思っても仕方がなかろう。このような例はかなりあるので、先進国が先進国人だというだけで尊敬されてはいないのである。尊敬がなければ、まともな対話は不可能であり、こちらの意見は尊重されるわけはない。尊敬は相手の合理性を信じ、その納得を得ようとする態度と、意見を実施した結果の成功の実績の積み上げで始めて獲得できるものであるということを認識する必要がある。こちらは援助しているから感謝されるはずだという思い込みもアフリカ人との生産的対話を妨げるものである。誰でも恩着せられるのは不愉快なものである。アフリカ人とて例外ではない。もっと根本的に、いわれのない『恵み』を受けることは、自立自尊の心を持っている人にとっては、大変な屈辱なのである。そして、アフリカ人は大部分が自活農民として、自立自尊の民であることを忘れてはならない」
「そうしてルワンダの実情が判明するにつれて、経済学の諸概念を本来の定義で理解すれば、経済学の原理はルワンダ絵も通用することを『発見』したのである。経済学が合理低人間行動の学であることを考えれば当たり前のことではあり、これを『発見』下時には、喜びと同時に、こんな簡単なことを知るまでに苦労した自分の頭の悪さを痛感したものである。それでは、外国の大学で教育を受けたエコノミストや私がなぜ当惑したのか。それは教えられた学説が完全なものであると信じて、それで説明できない事実に直面すると、学説を見直すよりは、事実を無理に学説に合わせようとしたためだったと思う。どんな学説でも、完全であるわけではなく、学問はつねに進歩していく。事実を観察し、観察された事実を論理的に説明できる仮説を立て、新しい事実がその仮説によって説明できなければ、その仮説を組み替えるか、新たな仮説をたてていくという、科学的思考を私は怠っていたのである」
「しかし、政府は富を創造しないし、官僚の行動原理の基本は審査であり、経済活動の基本であるリスク・テイキングによる利益追求とは異質のものである。したがって、経済における政府の役割は、民間がその活力を発揮できる環境を整備することであるが、政府過信と民間蔑視から、政府が民間を規制し、あるいは政府自ら事業を営むことが広く行われた」
「問題は経済における民間と政府の正常なバランスをとることであり、政府の経済に対する無用の規制を撤廃し、政府の本来の役割に基づいた管制と権限を明確に定め、官吏が権限外のことに手を出さないようにする監視機構をつくることが必要であり、
それで充分である。官吏に経済指導の役割を担わせると、新しいレント・シーキンギの生じることは、わが国の経済活動を見ても、その危険が大きいのである」
「官僚は大所高所の議論が好きで、マクロ的分析に頼る傾向があり、途上国発展論の主流もマクロ的手法を使っている。しかし、マクロ的分析の主要手段である統計がアフリカの途上国ではきわめて不備であるので、マクロ的分析には限界がある。アフリカでは概して政府の組織も、官僚の水準も、まだ成長過程にあり、これに多くを望むことは無理な国が少なくない。しかし、より根本的には、後に中国共産党の創始者のひとりとなった陳独秀が『近代生活の生命は経済であり、生産の基本は個人の独立である』と述べたように、経済活動の担い手は個人なのである。経済発展は要するに富の蓄積であり、富は利益追求による個人の活動によって創造されるのである。政府は民間が創った富の一部を取り上げて、その適当とする用途に使用するのであって、富は創造しない。政府の役割は重要であるが、個人による富の創造がなければ、発展もなく、政府の活動もできない。そして個人の経済活動はミクロの世界なのである。アフリカの途上国開発や援助に関わる人たちが途上国経験について、効果のある適切な施策を提言できなかったのは、ミクロ経済学を軽視したためではないかと思われる。私の経験でも、経済発展の具体策を考案する上では、ミクロ経済学が有用であったし、また、国民個人個人の活力を動員する国民参加型の発展政策を採るに当たっては、特にミクロ経済学を採用する必要があると思われる」
どんな場所でも、当たり前のことを、実践していった結論。
「役人って、思ったほど難しくないんだなあ」
「役人って大変だなあ」
彼の本を読むたびに、2つの気持ちが生じます。
きっと原理原則は簡単でも、いざ実行するとなると難しいのでしょうね。
世の中はそんなキレイごとばかりじゃない?
この人はどんな世界でもキレイに取り組んで変えてきたんだから凄いんですよ。
あと20年ぐらいで、
同じことを「言える」だけじゃなく、
同じことを「やっている」人になりたいですね。いや、絶対なってみせるぞお。