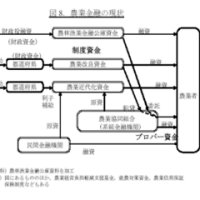二度目のレビューです。
一度目はこちらから。
ゼミの申込に当たって提出物が
「これまでにもっとも感銘を受けた書物についての感想文、あるいは関心のあるテーマと今後の研究計画(枚数自由)」
これまでにもっとも感銘を受けた書物といえば、これしかありません。
ということでもう一度、読み直していたのでした。
読めば読むほど、服部さんは凄い。
自分にとって、この本は教科書みたいになりつつあります。
役人になろうがなるまいが、こういう風に仕事がしたい。
ラバウルで終戦を迎え、戦後すぐの日本銀行に18年間務めた服部氏。
彼が当時のアフリカ最貧国・ルワンダに中央銀行総裁として、
「ルワンダの奇跡」といわれた経済成長の基礎を作った6年間の日記です。
「とにかく、引き受けた仕事なのだからやらなければならない。なるほど、中央銀行の現状は想像を絶するぐらいに悪い。しかしこれは逆に見れば、これ以上悪くなることは不可能であるということではないか。そうすると私がなにをやってもそれは必ず改善になるはずである。要するに何でもよいから気のついたことからどしどしやればよいのだ。働きさえすればよいというような、こんなありがたい職場がほかにあるものか。ベットのなかでこう考えつくと私は、苦笑しながらも安らかな気持で寝についた」
「日計帳で誤りを発見するのは当初は殆ど毎日のことであった。・・・しかしこの作業で気がついたことは、職員がいかに基礎的な知識に欠けているかということであって、」
「私はこの会談で、大臣はルワンダ経済、ことに外貨事情の窮状を本当には分かっておらず、また、二重相場制や現在の為替管理の経済に対する悪影響の認識も十分ではないと思った」
「ベルギーの技術顧問の人たちは、・・・が本当の理由であると思われた。商人(当時は外人のみ)のうち輸出をしている鉱山会社は・・・。コーヒーの輸出業者は・・・。輸入業者中、白人商社は・・・。一方、インド人商人は・・・。私は従来の外貨割当を調べたら・・・。しかし一番意外だったのは・・・。彼がもっともらしいことを言っているのは、ほかの人たちと同様損得の問題にすぎないことがわかった」
「しかしコルニュ総裁と話しているうちに妙なことに気がついた」
「・・・ではなかろうか。これは軽々に外人の主張ばかりを聞いてはいられない。案外ルワンダ人には外人にいえない本当の理由がある場合が多いのではないか。今後一見理屈に合わないような決定をルワンダ政府がした場合、まず政府にその本当の理由を聞きださなければならないと感じた」
「ハビさんにたいする派閥形成の非難は・・・。しかし、私が調べたところでは・・・。結局この一件に関するハビさん攻撃は・・・悪意ある中傷だったのである」
「しかし、このような私に対して攻撃的だったのデヴィルシャン氏が、なぜ取締役会で態度を一変したのだろうか。・・・私はもう一度取締役会の発言を振り返ってみた」
・・・すごーーくいっぱい話を聞いてます。というか「気づき」が鋭い。
しかし、別に無駄に話を聞いているわけではありません。
自分の中に知識と経験に裏打ちされた仮説がある。
それに合わないことをみんなが口々に言うものだから、気になって調べてしまう。
自分で合理的な理由を見つけるまで、決して妥協しない。
それが本質的な問題に根ざしていることが多い。
「ルワンダ人の福祉とは、ルワンダ人が望ましいと思うことを実現することである。また政策措置はルワンダ人がどのようにそれに反応するかの予見がなければ、意図する効果をあげるとはかぎらないのである。その意味で私は、与えられた六ヶ月の時間をまずルワンダ人を知ることにつかうことにしたのであって、日常の仕事、日々の生活のなかで、私は貪欲にルワンダ人についての知識を求めたのである」
「しかし、仕事上の接触をつうじて、ルワンダにいる外人の理解力についてだんだん疑問がでてきた。また彼らの論理が自己防衛の意図から組み立てられていることにも気がついてきた」
「私はそれからつとめてルワンダ当事者の意見を求めることにした。・・・私はできるだけ事前にルワンダ人出席者に会って意見を聞いたうえで出席し、ルワンダ人の意見を促し、ルワンダ人が有効に会議に参加し、その結果に責任を感じるように仕向けた」
「私が一番関心をもったのは、ルワンダ人は怠け者かどうかであった。・・・これは彼らが経済的に合理的に反応することを示すものではないか。私は非常に勇気付けられた」
「この発想から私は、国際通貨基金の通貨改革の論理を考え直した」
「私は各方面のルワンダ人に、コーヒーに対するルワンダ農民の考え方を聞いて廻った。その結果、・・・との確信を得た」
「・・・との答えだった。まさかと思い、政府の役人、農林省の外人顧問、ルワンダ経験の長い僧侶に聞いても同じ答えが返ってきた。しかしどうも納得できないので、質問を変えて・・・。どうも・・・ではないかと気がついた」
「これが解決できなければ通貨改革はできても、経済改革はできない。・・・一時は答申を全面的に書き直さなければならないかとまで思った。ある日床についてから、ふと、ルワンダ人が・・・を思い出した。・・・私はとび起きて「商業に関する構造的競争の導入」という題で・・・を書き上げた」
「理事に任命されて新しい眼でコーヒーのことを調べると、コーヒー局は勿論、農林省の外人顧問や、長年コーヒーの輸出に従事している外人商社が、いかにコーヒーに関する技術に欠けているかを痛感した」
「・・・してしまった。私が彼を呼んで事情を聞くと・・・」
「誰がための政策か」を明確にし、当事者の声を聞く。他の意見は聞かない。
自分が集めたピースから、構想を膨らませる。
構想と現状を比べ、足りないところを補う仕組みを考える。
足りないなら作るための施策を考える。それがなければ作る。作ったらどうなるかまた聞いてみる。
仮説の立案と、ニーズの発見、ニーズの確認、具体案の作成・・・
政策立案のゼミで言われたことと一緒でした。
何かの問題解決のために、誰かの幸福のために働くという使命感。
そのための一点の曇りも無い過程という正義感。
そして、自ら感じ、考え、実行し、改善するという充実感。
やりたいとか、楽しそうとか、かっこいい、とかそういう感情でも、ましてや論理でもないのですが
なにか大きな説得力を持ってそんな仕事がしたいということを再確認しました。
うん。
たとえ希望の場所で働けなくたって、こんな風に仕事をして、こんな風に生きたい。
「『あなたは、ルワンダ国民とその関心事とを知るため、(外人の)クラブ協会や、滞在期間が長いという理由で、当国の事情を知っていると僭称する人たちから聞きだすことをせず、直接ルワンダ人にあたって聞かれた。他の多くの技術援助員の考え方や、その作業を毒する偏見にわずらわされることなく、あなたはルワンダ人に相談してその意見を聞いた(中略)。あなたの基本態度は、ルワンダ国民のために働くのであるから、まずルワンダ人にその望むところを聞かなければならないということでした』 この送別の辞の大部分を占める、私の業績に対する讃辞には、私は感動はなかった。職務を立派に遂行することは俸給に対する当然の対価であって、あたりまえのことをしたからといって讃められることはない。しかし私のルワンダ人を理解しようとした努力を、ルワンダ人が理解してくれたことは、私の大きな喜びであり、私に対するルワンダ人の信頼が、単に外人崇拝とか地位に対する盲信によるものではなく、自分たちを理解しようとしている異国人の努力に対するものであったことを知った」
すごく謙虚なのは・・・目的に対して一途だからでしょう。
別にルワンダ人にどう思われようと構わないんです。彼らが幸せであればよい。
それ以外に関心が無い。
そのために日本から来ているんだから・・・そんな姿勢が大好きです。
「私は戦に勝つのは兵の強さであり、戦に負けるのは将の弱さであると固く信じている。私はこの考えをルワンダにあてはめた。どんなに役人が非効率でも、どんなに外人顧問が無能でも、国民に働きさえあれば必ず発展できると信じ、その前提でルワンダ人農民とルワンダ人商人の自発的努力を動員することを中心に経済再建計画をたてて、これを実行したのである。そうして役人、外人顧問の質は依然として低く、財政もまだ健全というにはほど遠いにもかかわらず、ルワンダ大衆はこのめざましい発展を実現したのである。後進国の発展を阻む最大の要因は人の問題であるが、その発展の最大の要素もまた人なのである」
また読みます。
21世紀の服部正也を目指しますよ!