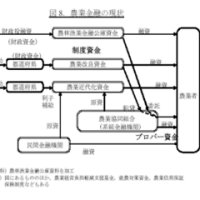(※写真は上田敦生の新訳版)
(※写真は上田敦生の新訳版)尊敬するあるオジサマに「仕事において一番影響を受けた本」を聞いたら、この本が出てきました。
初版はなんと1954年のこの本。未だに経営のバイブルなんですから驚きです。
大学で「経営管理」の授業を受けていますが、基本的に一緒です。
要約すれば、「事業とは、社会の発展の原動力であり、経営とは事業のために資源を結びつけ、方向を定め、機能させる機能」ということ。
利潤最大化のために働く組織じゃないんです。
時価総額の最大化のために稼ぐ組織でもない。
ミクロ的な対象を扱いながら、マクロの議論をしているのかもしれませんが、
そう考えるとすべての議論が合理的・倫理的・有機的につながるから不思議です。
利益も、人事管理も、組織作りも、イノベーションも、マーケティングも、会計も、事業計画も、人の成長も、すべて「社会のため」の手段なんですね。
具体的な手法として特に述べられているのは
「常に事業を問い、目標で管理し、なるべく権限を下に委譲する」ということ。
事業を問う、とは、対象を見失わないということ。何を作るか、何を売るかではなく、結果的に誰のどんな欲求を満たすのかを考える。人間の欲求は不変なので事業が廃れない。
目標で管理する、とは行動で管理しないこと。行動を指示するだけだとコストがかかる。工夫しない。つまならいし成長しない。だから明確で共感を得る目標を定め、それに向かって自ら努力させる。
なるべく権限を下におろす。これもコストとパフォーマンスの問題です。
今まで、ドラッカーの考え方は「従業員がどう幸せか」から生まれた人間中心主義的なもののイメージでしたが、それすらも社会に資する事業を行い続ける手段であるようですね。
下も読みますよ。