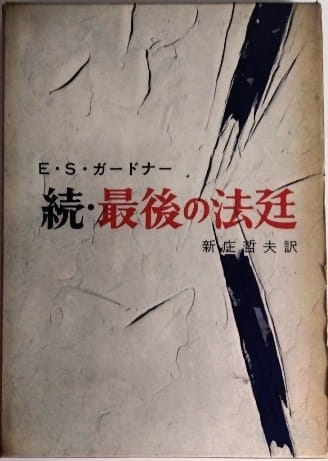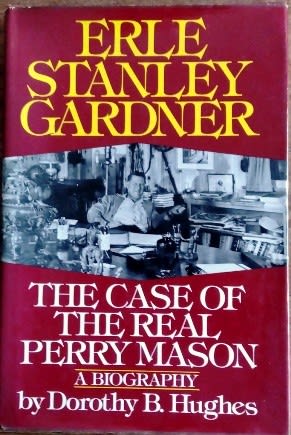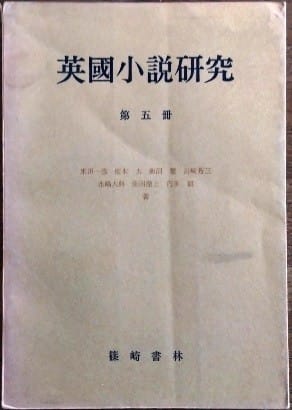祖父の旧蔵書を、図書館に返還する話のつづき(その2)。
★瀧川幸辰『刑法読本』(大畑書店、昭和7年=1932年)。
ボアソナードから始まって、ベッカリーア、フォイエルバッハら刑法学者の肖像画が数十ページごとに薄葉紙のカバーがかかって挿入されている。表紙は本当のクロス装で、箱入りのお洒落な本である。今どきこんなお洒落な概説書はないだろう。昭和7年と令和5年と比べて、どちらが豊かな時代だったと後世の人は思うだろう。
刑法学で論じられている「因果関係論」は実は「責任論」にすぎないという瀧川の通説批判に、大学時代のぼくは影響を受けた。瀧川の言う通りだと思った。後に平井宜雄『損害賠償法の理論』(東大出版会)に結実する法学協会雑誌の連載を読んで、ようやく納得できる因果関係論に出会った。瀧川の通説批判は『刑法読本』でも論じられているが(67~9頁)、ぼくが彼の因果関係論批判を知ったのは、『犯罪論序説』(有斐閣)によってだった。
『刑法読本』は、扉の口絵写真に写っている「刑罰からの犯人解放は、犯罪からの人間解放である」という色紙を手にするチャイナドレス姿の女性は誰なのだろう、という不思議な印象の方が中身より大きい。編集者時代に、京都大学出身で瀧川教授の教えを受けた世代の刑法学者に、「あの女性は誰ですか?」と伺ったことがあったが、先生は微苦笑されただけで答えてくれなかった。
『刑法読本』はなぜ発禁処分となったのか。内容的には、社会紊乱や国体変革の恐れなどない穏当な刑法の概説的記述に終始していると思うのだが、あの口絵の標語と、最終ページ(195~6頁)に書かれた同じ標語を敷衍した数行が資本主義、私有財産制の否定とみなされたのだろうか。
★瀧川幸辰『刑法史の或る断層面』(政経書院、昭和8年)
挿絵が入っていたり、本文各ページの下欄に欧文の脚注がついていたり、これもお洒落な本である。この本は祖父の蔵書の中でも、ぼくのお気に入りの1冊だった。法律書専門の古書店(目録)でもほとんど見かけない。
★瀧川幸辰『刑法と社会』(河出書房、昭和18年)
新聞や雑誌に書いた随筆を集めたものだが、最後の「中学校時代のある思い出」が面白い。
滝川は大阪北野中学時代に野球をやっていた。ところが当時の北野中学当局は、大阪朝日新聞の野球征伐論に便乗してか、野球を迫害したという。当時の朝日新聞は合理的な理由もなしに(中等)野球を批判していた時期があったのである。
滝川は成績は悪くなかったのに、成績不良者に対する早朝の早出および放課後の居残り勉強への参加を強制された。「自分より成績不良の者が指名されていないのに、自分を指名するのは不公平だ」と教師に抗議すると、教師は「お前は野球をやってるからだ」と言ったという。学校側が敵視する野球をやっているうえに、他校の野球部が白ユニフォームに地下足袋姿だったのに、当時の北野中学野球部は、神戸のアメリカ人チームに似たハイカラなユニフォームに、スェーターなどを着ていたのが学校側の気に障ったのだろうと滝川は書いている。そんな時代もあったのだ。朝日新聞はいつから高校野球礼賛論になったのか。
★イェリネク/大森英太郎訳『法の社会倫理的意義』(大畑書店、昭和9年=1934年)
「法は倫理の最低限」という標語で有名な著書であるが、もうしばらく手元にとどめておきたい。
★大森英太郎『刑法哲学研究』(関西学院大学法政学会、昭和29年)
著者の大森氏は、東北大学助手を経て、関西学院大学教授になったが、昭和18年、鳥取を旅行中に鳥取大地震に遭遇し、鳥取の宿舎で亡くなったとのことである。38歳だった。
★橋本文雄『社会法と市民法』(岩波書店、昭和9年)
★橋本文雄『社会法の研究』( 〃、昭和10年)
前者の表紙裏には「昭和九年九月十日午前六時四十分橋本君逝去、同十七日葬儀あり、秋霜の折」という祖父の書き込みがある(後者の年譜によれば9月16日死去とある)。後者は、著者の没後に恒藤恭・栗生武夫編で出版されたもので、恒藤の前書きによると、橋本が東北帝国大学で担当した「社会法」はわが国で初めて「社会法」を標榜した講義、講座であるという。
★尾高朝雄『実定法秩序論』(岩波書店、昭和17年)
奥付の著作権者が「京城帝国大学法学会 代表船田享二」となっている。扉の「尾高朝雄著」の下に「京城帝国大学法学会叢刊」とあるが、著作権まで大学に帰属していたようだ。尾高の『法の究極にあるもの』(有斐閣)は大学1年の時に読んだ。終わり近くまで共感しつつ読み進めたが、最後にどんでん返しを食らった思いがした。法の究極にはやはり政治があると今でも思っている。民主社会では、主権者たる人民がその政治を動かせるのだが。
★イェリング/三村立人訳『権利闘争論』(清水書店、大正4年=1915年)
「法の目的は平和である、しかしそこに至る手段は闘争である」という書き出しの一文(だけ)が有名である。三村訳では「権利の目的は平和に在り」とある。学生時代に読んだ日沖憲郎訳の岩波文庫版では「法」となっていた(1970年、定価は★1つ。ぼくが学生の頃は★1つは50円だった)。大正4年刊ということは、祖父は旧制高校生の頃に読んだのだろうか。
★ハンス・ケルゼン/阿武京二郎訳『規範学又は文化科学としての法律学--方法批判的研究』(大村書店、大正12年)
丁寧に読んだ形跡があり、祖父の独特の難読の字体で随所に書き込みがあった。大正12年は祖父が大学を出て2年目である。
★J・S・ミル/松浦孝作訳『精神科学の理論』(改造社、昭和15年)
この本は、ケルゼンよりさらに丁寧に読んでいる。社会学がテーマになっているからだろう。今回の書籍の中でも、一番に祖父の蔵書に戻さなければならない本かも知れない。
★田辺寿利『デュルケム社会学研究』(未来社、1988年)
祖父の没後に献呈を受けたものらしい。

以上の他にも、まだ中川善之助さんの著書などが何冊か残っていることを思い出した。
祖父は中川さんと同い年で、中学、高校、大学と同窓だった。学生時代から面識はあったが、親しく交流するほどではなかったようだ。中川さんはぼくが編集者をしていた雑誌の編集顧問だったこともあり、何度かお会いした。最後にお会いしたのは、亡くなられる前年の1974年の秋頃だったと思う。場所は九段の坂を登った所にあった「あや」(「綾」だったかも)という料亭だった。翌年暖かくなったら、先生を囲む座談会を先生ゆかりの金沢と仙台で開くことになった。
先生は、金沢の料亭「つば甚」の屏風を蹴破った四高生の昔話などを楽しそうに語っておられたが、翌1975年の3月20日、仙台に向かう上野駅で急逝されたため、この座談会は実現しなかった。
★中川善之助『略説身分法学』(岩波書店、昭和5年)
★ 同 『身分法の基礎理論--身分法及び身分関係』(河出書房、昭和14年)
★ 同 『身分法の総則的課題--身分権及び身分行為』(岩波書店、昭和16年)
★ 同 『妻妾論』(中央公論社、昭和11年)
★ 同 『法学協奏曲』(河出書房、昭和11年)
中川さんの本は軽妙な筆致で読みやすく、温故知新の新発見もあるのでしばしば参照してきたのだが、やはり祖父の旧蔵書と一緒の場所に置かれるべきだろう。
★栗生武夫『法の変動』(岩波書店、昭和12年)
★ 同 『一法学者の嘆息』(弘文堂書房、昭和11年)
『嘆息』の中には、有島武郎、柳原燁子らの恋愛と、最近(昭和10年頃)の宇野千代、福田蘭堂らの恋愛事件の比較論などがあったりして面白そうだが、もう過去の話である。ストリート・ガールと女給の区別の話などは戦前の裁判例を読む前提として知っておいて損はないのかもしれないが。
以上、ひとまず箱詰めは済ませておくが、発送はもうしばらく待って気持ちの整理がついてからにしよう。
2023年10月27日 記