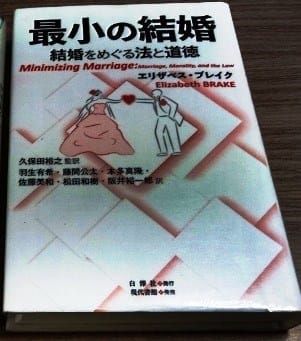きのう11月26日の夜、BS放送AXNミステリーで“主任警部モース”の最終回(第33話)をやっていた。
「悔恨の日々」(The Remorseful Days)というやつで、以前にも(何度か)見たが、また見た。
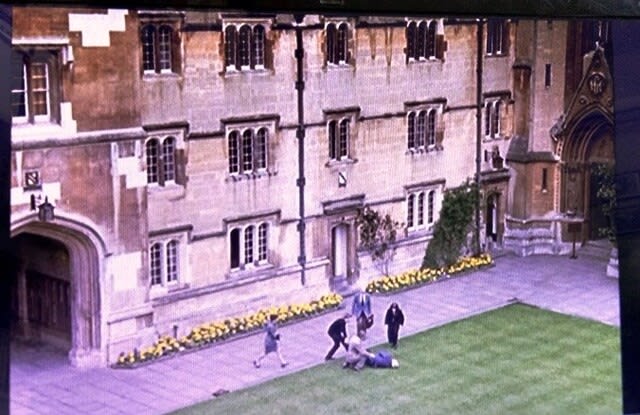
以前、「モース」のDVDが全35巻(メイキング・ビデオも2巻入っている)が7000円くらいだったので買った。字幕は英語だけで、残念ながらぼくの英語力では各シーン2行の英語字幕を読む前に場面が変わってしまう。かと言って音声だけではもっと聞き取れない。
仕方なく放置したままになっている。
ちなみに、このDVDの題名は“ Inspector Morse ”である。モース自身が“ chief inspector ”であることを強調するシーンがしばしば出てくるが、シリーズの最初の頃は平の“ inspector ”だったのだろうか。
ラストシーンは、“ ルイス警部 ”へのつながりを予告するかのようであり(ぼくだったら、最終回のタイトルは(ルイスに対する)「懺悔の日」にする)、ストレンジ警視正は(俳優の体型から)若き日のモースを主人公にした“ 刑事モース ”とのつながりを感じさせる。モースだけが繋がらないのだが。
* * *
11月17日の午後8時から、同じくBS放送AXNミステリー(560ch)で、“ 孤高の警部ジョージ・ジェントリー ”を見た。
チャンネルを回していたら、偶然この番組をやっていた。こんな時間帯にやっていたとは知らなかった。久しぶりである。
第25話、最終回だった。
「新しい時代」というタイトルだが、時代は保守党ヒース政権時代らしいから1970年から~74年ころ、舞台は労働争議で揺れるニューカッスルである。
警察内部の腐敗、政治家と警察の癒着をジェントリーが暴くというストーリーだが、癒着が疑われる政治家は明らかに保守党であり、刺客は政府の意向を受けたMI5(元MI5だったか)メンバーである。
21世紀に入ってからの作品とはいえ、よくぞ国営放送BBCがこのような番組を放映できたと感心する。わがNHKでは考えられない。政権交代が実際にたびたび起こる二大政党制のおかげか。

ジェントリー役のマーティン・ショウは、数年前にイギリスへ行ったときに、ピカデリー・サーカスの劇場で“ Twelve Angry Men ”(12人の怒れる男たち)の主演を演じていた。有名な舞台俳優らしいが、部下のバッカスを演じていた役者も有名な俳優らしい。
イギリスのテレビドラマは、舞台出身の俳優たちの演技力のおかげで、わがテレビ番組とは一味もふた味も違う仕上げになっている。

最終回の結末は意外だった。
12月末にまた再放送があるらしい。
2020年11月18日、27日 記