
10日と間が空いていない公演同士でこんなに差があっていいものなのでしょうか?というよりも、こんなに差が出得るものなんでしょうか?
、、、いやー、びっくりしました&おそろしかったです、まじで。
決して簡単ではないレオノーラという役で、なかなかに優れた、しかもパッションのある歌唱を聴かせて印象的なメト・デビューを果たしたユーと、
長いキャリアで幾度となくアズチェーナ役を歌った中でも、彼女をこれまでフォローして来た私が、
これまでで最高の出来だったんじゃないかと思うほど壮絶な歌唱を聴かせたザジックのおかげで、
先週末のマチネの『トロヴァトーレ』が大変にエキサイティングな公演であったのは、感想にも書いた通りです。
あれから約一週間、本来Aキャストでメト・デビューを果たす予定だった(にもかかわらず、病欠で任をユーに譲ることになった)
カルメン・ジャンナッタジオがシーズン二度目の公演から舞台に立っていることを知り、
ここはやはり彼女も聴いておかねば、、ということで、再びメトにやって参りました。
前回はずっと立って見ているとはいえ、30ドルかそこらのチケット代であんな良い公演を見せてもらって、なんか申し訳ない気すらしてくるほどでしたし、
今日は仮にジャンナッタジオがすっ転んでも、少なくともザジックがちゃんといるわけだし、
座って鑑賞しようかな、、、という思いも一瞬頭をかすめたのですが、こういうのを虫の知らせというのでしょうか、
ま、ジャンナッタジオがとても聴いていられないほどひどいという可能性もゼロではないし、何があるかわからん、、、ということで、今日もスタンディング・ルームです。
前回鑑賞した公演を思い出しながら、”しかし、ザジックの先週の歌唱はほんと素晴らしかったから、あれを越えるのは難しいだろうなあ、、。
もしかすると、彼女を長らく応援して来た身としては、あれを彼女の最後のアズチェーナとして記憶に留めた方が幸せだったかな、、。”
などと考えているうちに、カリガリ博士が指揮台に登場して来ました。
前奏の部分で、先週の公演よりも少しオケの音が重いので、お疲れモードかしら、、?とも思いましたが、
彼らは歌手の歌の内容が良い時はそんな時でもすぐに追いついて来るのをこれまで何度も聴いたことがあるので大して心配していなかったのですが、
フェランド役のロビンソンが、伯爵家にまつわる不吉な話を語る部分のうち一番恐ろしい箇所といってよい、
E d'un bambino, ahimé l'ossame
bruciato a mezzo, fumante ancor!
(そして、ああ、子供の骨は半分焦げて、そこからまだ煙がくすぶっていた!)
のbruciato a mezzoが繰り返される最初の方で思いっきり言葉を噛んでしまって余計な音が増えてしまったためにオケの演奏とずれまくり、
カリガリ博士はそれですっかりパニックしてしまったのか、立て直し方が全くわからないのか、
ロビンソンの歌うパートが終わって合唱が入ってくるところでオケが自力でその混乱を抜け出すまで、全くなすすべなし、、の体で立ち尽くしているではありませんか。
まさか、この指揮者、、、。
一般に優れた歌劇場と言われている劇場のオケはどこもそうだと思いますが、
良いキャストが揃っていれば、指揮者が無能でもオケが勝手に上手く演奏してくれる時があって、
それで助かっている・得している指揮者の名前を挙げよ、と言われたら、すぐに頭に浮かんで来る人が何人もいます。
そういう時は、はっきり言って、私が指揮台に立って腕を振り回していても多分同じ結果が出て来るでしょう。
先週の演奏は、もしかすると、この、私が指揮台に立っても大丈夫な状態になっていたのかもしれない、、、。
指揮者ってのは、力のないキャストが失敗をしてしまったり(また、力のある人でも稀に失敗をすることはあるでしょう)、
力はあっても老齢や妙な自信とエゴから自分勝手な歌唱を出してくる歌手(キャリア末期のパヴァロッティや最近のネトレプコ、
ただ、ネトレプコの場合はそれだけでなくて、技術の鍛錬や声質がレパートリーで求められる最低限を満たしていない、ということも理由にあると思いますが。)
にも対処していかねばなりませんが、もしかすると、この指揮者はそういった修整・調整能力のない指揮者なのかも、、、。
舞台が始まってまだそう時間が経っていないうちからこんなことになって、嫌~な予感が立見席のMadokakipの周りに渦巻いて来ました。

いよいよレオノーラ役のジャンナッタジオの登場。
上は彼女のFacebookから借用して来た、今回の『トロヴァトーレ』の衣装合わせの時に撮影したと思しき写真ですが、
見てお分かりの通り、小柄で華奢ななかなかの美人です。
いや、なかなかどころか相当美人と言ってよく、おそらく彼女自身も彼女のエージェントもそれをセールス・ポイントにしていかねば!とばかりに、
彼女のFacebookもファッション・モデルのそれか?と思うほどに、そのルックスを強調した写真のオン・パレードです。
確かに、どんな種類のどんな時代・スタイルの衣装でも似合っていて、それはオペラが視覚も含めた舞台芸術であることを考えるとプラスであることは間違いありません。
また、ネトレプコやガランチャの美人さがどことなく大造りなのに比べると、日本人にも受けやすい繊細なタイプの美人です。
彼女のその美人さは、当然のことながらルックスの良いアーティストに目がないゲルブ支配人の目に留まるところとなり、
オープニング・ナイトの『愛の妙薬』のライブ上映(オープニング・ナイトのライブ上映はリンカーン・センターのプラザとタイムズ・スクエアのみで行われる)でも、
『オテロ』に登場するルネ・フレミングと共にフューチャーされて、司会のデボラ・ヴォイトにインタビューされたり、
上演後のパーティーにネトレプコらと一緒に写真に納まっていたり、と、メト・デビューの歌手としては破格の待遇を受けているのですが、
おそらくその時にイヴニング・ドレスのような薄着で一気に気温の下がったNYの夜を外で過ごしたりしたのが、
風邪をこじらせて初日を降板しなければならなくなった理由なんじゃないかと思います。
歌手には出演するどの公演も貴賎なく常に全力を尽くして欲しい、と思うのがオーディエンス心というものですが、
やはり歌手にはこの公演は絶対外してはいけない、今出来ることをこの公演で100%、いや願わくばそれ以上、を発揮せねばならない、という特別な公演というのがあって、
メト・デビューというのは間違いなく、そういった”外せない公演”の一つだと思うのです。
彼女の歌を聴く前から小言で申し訳ないですが、本来メト・デビューになっていたはずの先週の公演を休まなければならなくなった、
これだけで、私は”駄目だな、、この人は、、。”とちょっと思ってしまいます。
人間は誰でも風邪をひいたり、具合が悪くなったりするものですが、メト・デビューの日にそれをやってちゃいかんのです!
運が悪かった、、というかもしれませんが、運も実力のうち、とは良く言ったもので、
そういう隙があるから、その間にユーが力を発揮して、NYのオーディエンスに”面白い素材の歌手が出てきたぞ。”と注目され、
メディアからも軒並み好意的な評を受け、
たった一公演遅れでメト・デビューを果たしたジャンナッタジオは彼女のことを良く知らないオーディエンスの話の隅にあがることもなく、
もちろん彼女の公演に改めて評が出ることはないので仮に彼女の歌が素晴らしかったとしてもそれが広く伝わることもなく、、ということになってしまうのです。
あれだけ期待されて特別なお膳立てまでしてもらっておいて、なんてもったいない。
彼女はレイラ・ジェンチェルが先生&メンターだった時期があるらしく、そのジェンチェルが、
”メトで歌わなかったことをとても残念がっていた”ことから、
メト・デビューを決めた、というようなことが彼女のFacebookのページに書いてありましたが、
”メトで歌う”ってことは単に舞台に出て行って、口を開けて、舞台をつとめる、ってことだけじゃないんですよ。
メトで歌うからには、自分という歌手を世界によりよく知ってもらって、より広いオーディエンスにリーチ・アウトする、
そのための始まりの場所なのだ、という気構えがないと。
ユーが良かったのは、彼女の歌唱から、こういった目的意識、良い意味での野心が漲っていたことです。
またジェンチェルが言わんとしていたことは、”メトで歌うことでNYの観客に自分の実力を生で感じでもらえなかったことが残念だった”のであって、
単に”メトに登場す”という記録をバイオに残すためだけにメトで歌いたかった、と言っているわけでは決してないでしょう。

まあ、歌を聴く前からあれこれ言うのも何ですから、歌を実際聴いてみましょう。
ということで、その彼女の歌なんですが、うーん、、、何ていうのか、、
ジャンナッタジオの歌唱からは、上で書いたような、良い意味での野心が全く感じられないですねえ。
別にこれが駄目でも次があるわ、ってな感じ?(その点、ユーはこの機会を逃してはいけない!という使命感みたいなのがありました。)
イタリアでそこそこ成功しているからなんでしょうか、、なんか、のんびりしてますよ、彼女は。
声や歌に関しては、まだ彼女が風邪から完全には回復していない可能性もあることは念頭に置いておかないといけないと思いますが、
まず、レオノーラ役で求められるテッシトゥーラにおける彼女の声はあまり魅力的ではないですね。
サイズはややユーより小さいですが、それ自体はあまり問題ではなく、むしろ響きというのか、その辺にあまり個性がないのが辛いし、
中音域以上は比較的ドライな音なのに、低音域にちょっと今のネトレプコを思わせるねっとりとした響きが混じるのが嫌だな、と思います。
イタリア人のよく訓練されている歌手はどの音域も割とすぱっと音が出て来る人が多いという思い込みが私にはあるので、
彼女のことを良く知らずにこの辺の音だけ聴くと、ロシア圏出身の歌手なのかな?と勘違いするくらいです。
ただし、この役で求められる最高音域あたりや、彼女が自分の意志で入れている高音、これは線は細めですが、ものすごく綺麗な響きが聴ける時があって、
彼女自身、高音域・もう少しテッシトゥーラが高めの役の方が歌っていてより心地良く、楽なのかな、と感じる部分はありました。
(やはりFacebookに、ジェンチェルが『トロヴァトーレ』を歌う際には取り入れていたという、Dフラットの音を含むカデンツァを、
今回彼女へのトリビュートとして、取り入れている、とも書いています。)
このことから、レオノーラ役ではなく、もっと他の役に適性があるのかもしれないな、という風にも思います。
しかし、もし、一点だけ、私が彼女の歌のどうしても苦手!なところをあげるとするならば、
リズムのapproximation、ここに尽きるかもしれません。
そう、彼女の歌にはリズムによるパルスが欠けていて、”大体このあたり”的な感じで歌っているような感じがするのです。
音を転がしたり、そういうことはきちんと出来ているので、技術の問題ではなくて、リズムに関しての、生まれもったたセンスや能力の(無さの)問題なのかな、と思うのですが、
今日の歌だけからだと、彼女は正確に歌う、ということがどうにもこうにも出来ない人のように見受けました。
歌手が、感情の表現の目的のために、ある箇所だけ、少しだけ前のめりで歌う、またはためて歌う、ということは当然良くありますが、
良い歌手の場合、まず正しいビートが歌の中にあって、前のめりで・ためて歌っていながらも、
この基本のビートが常にその後ろに感じられる、ここがポイントで、
だからこそ、観客にも、ああ、ここは怒りの表現のために前に出たんだな、とか、迷い、あるいは、深い愛情を表現するために溜めて歌っているんだな、
ということがはっきりわかるわけです。
その後ろのビートが常にぐにゃぐにゃしていたら、本人はタメたり前のめりに歌っているつもりでも、その意図は全然観客には伝わってこなくて、
リズム感のない歌手だな、という感触だけが残ってしまいます。
ユーはジャンナッタジオよりもきちんとしたリズム感を持っている上に、そういうタメや前のめりを多用しないんですが、
ジャンナッタジオの方はなぜだか音色でなく圧倒的にリズムの揺らしで感情を表現しようとすることが多く、
指揮者がこれに応えられるような、”ここはこう歌って!!”という圧倒的な指示を出せる人で、しかも彼女が緩くなった時にはさっとサポート出来る人ならまだ良いですが、
カリガリ博士は前例で見た通り、そのあたりがからっきしなので、二人してごちゃごちゃとリズムを乱しまくって、オケを混乱状態に陥れていました。
それからとどめをさすような感じになりますが、彼女はこんなに美人なのに、演技が無茶苦茶下手くそなのにびっくりしました。
写真なんかではすごくフォトジェニックに写っているので、すごく意外だったです。
舞台で動いている時に、自分がどのようにオーディエンスに見えているか、ということを本能的に感じる能力が不足しているし、
動きのテンポや間も悪い。
先週の公演の感想にも書きました通り、このマクヴィカーの『トロヴァトーレ』は、決して演技するのが簡単な演出ではありません。
背景はシンプルで固定しているし、合唱を除くと極めて登場人物が少なく、
しかも演技力の無さを誤魔化したり、せかせかと立ち演じています、という振りを可能にするような、
今○○して、次はXXして、、というような忙しい連続したコリアグラフィーもありません。
要は、自分で、少ない動きをテンポや間を上手く使いつつ、客に説得力をもって見せなければならない。
だから、マクヴィカー版『トロヴァトーレ』は体の動きの美しさ、間、テンポといったものに欠けている歌手にとっては地獄のように苦しい演出なのです。
それにしても、いくら今オペラ界がビジュアル重視になって来てると言ったって、演技が出来ないのでは美人の意味なし!

先週の公演ではプロの公演に一人アマチュアが混じっているのかと思うような歌唱を繰り広げていたマンリーコ役のヒューズ・ジョーンズ。
正直言っていいですか?なんか、このテノール、見てて・聴いてて腹が立って来るんですよね。
歌手に対してこういう気持ちになることって、私の場合、本当稀、というか初めてじゃないかな?
メトに来る歌手のほとんどは、やはりそれなりに力のある人で、力のある人というのは自分の力をやっぱり良くわかっているんです。
昨シーズンの『ジークフリート』で急に降板したギャリー・レーマンに替わって表題役をつとめた若モリス(ジェイ・ハンター・モリス)なんかも、
舞台を見るまでは”大丈夫なんかいな、、”と思いましたが、
ちょっと一本頭のネジがゆるいように見えて、実は意外と冷静に自分の出来ること、出来ないことを判断しながら歌っているのには感心しましたし、
カーテン・コールでオーディエンスから大きな拍手が出ても、特に馬鹿喜びするでもなく、割りと淡々とした様子なのを見ると、まともな歌手なんだな、と思いました。
先週の公演は公演全体としてとてもエキサイティングだったので、メディアの評も、女性陣(ユーとザジック)を絶賛、
ヴァサロはパー(もちろん、頭がくるくるパーのパーではなく、ゴルフで使うのと同じ意味のpar)、と来て、まあ、ここまでは妥当な評なんですが、
ここで4人が主役の作品で、ヒューズ・ジョーンズだけ落とすのは気の毒だろう、、ということなんでしょう、
彼もパー、みたいな書き方になっていて、これは私がヴァサロだったら絶対切れるよな、という評なんですが、
まあ、メトに来る歌手なら、批評家が気を使ってそうしてくれたことくらい、読み取るよな、と思ってました。
それが、どうしたことでしょう。
あの評をまともに受け取っているのか、今日の彼は”俺って結構いけてる。”とでもいうような自信満々&得々とした様子で歌っているではありませんか!
アルマヴィーヴァ伯爵かと思うような声でマンリーコを歌っているところも、嫌といえば嫌なんですが、
その上にジャンナッタジオの上を行く自由奔放なリズム!!!
しかも、彼のリズム感のなさは間違いなく技術の不足によるもので、発声のきちんとした基礎も出来ていないし、
何をどう間違ってこんなテノールがメトの舞台に立てることになったのか?
自分の完全なる力の不足を恥ずかしがるどころか、気づいている様子もなく、気持ちよさげに妙な音で歌い上げている(←これこそが二流歌手である証)
のを見ていると、どうしようもない田舎もん(であるために、きちんとした比較対象がない)か、それこそ頭のネジがとんでいるんだと思います。
一幕でまともな歌を歌っているのはルーナ伯爵役のヴァサロだけ、、、助けてくれーっ!!!!

二幕。ザジックも登場することだし、ここで取り返してもらわないと。
で、アンヴィル・コーラス。
なーんかまた演奏の足取りが重たくなっているけど、これは何?オケ?指揮者?
やがて、舞台上で上半身裸の男性たちがどんちゃんと槌を振り下ろす(←ゲイのオペラファン垂涎のシーン)のと一緒に歌われる
Chi del gitano i giorni abbella? (ジプシーの男達の一日を明るくするのは誰?)の部分で、
あれあれあれあれ~~~~~ オケピの演奏と裸のお兄さんたちの槌が下りるタイミングがどんどんずれて行ってますよ~。
そして、それを修整しようとあせるカリガリ博士!!
しかし、これは舞台にいる裸のお兄さん達と合唱とオケピにいるオケのメンバー全員に指示を飛ばさなければならないという超難問!!
こんなことが、当然カリガリ博士の手に負えるわけもなく、
オケの中には何か舞台でおかしなことが起こっとる!と自主的に調整しようとしているセクションがあれば、
カリガリ博士の指示がそれに追いついていないのを見て当惑しているセクションもあり、
La zingarella!(それはジプシーの娘!)に至るまでには、オケが大崩壊、大脱線、、、それをまたしてもなすすべなく見守っているカリガリ博士、、、。
つい、”見事にやっちまいましたね、博士。”と声の一つもかけたくなるような出来です。
いやー、メトのアンヴィル・コーラスでこんな見事な大脱線、私、初めて聴きました。
そもそもどうしてそんな風にずれていってしまったわけ??と不思議に思っている間に、また繰り返しで同じ箇所がやって来てどきどきしましたが、
さすがに同じミスは出来ない!とばかりに、異様に大きな振りで舞台上とピットに指示を出すカリガリ博士が涙を誘いました。
もうこうなったらザジックに頑張ってもらわねば!
アンヴィル・コーラスに続けて始まる”Stride la vampa 炎は燃えて"
!?!?!?
最初のフレーズから思いっきりピッチが狂ってる!!!!
っていうか、、、Stride la vampa! La folla indomita の全部の音(おおげさでなく本当に、、)がずれてるので移調かと思いましたよ。
しかし、こんなにたくさんの音数にわたってオケを無視して一人移調、、、すごいなあ、、って感心してる場合か!っての。
いや、しかし、待てよ。何か声が違わないか?これ、ザジックじゃないよね?絶対にザジックじゃなーーーーい !!!!!
!!!!!
(そりゃそうだ。ザジックは絶対にこんなミスしないもの。)
そして、続くcorre a quel foco lieta in sembianza!もまた一人移調、、、本当すごいなあ、、、ってまた感心してしまったじゃないですか。
しかし、ならば、Who the hell is she!?!?!?!
開演前にプレイビルを見た時はスリップ(キャスト・チェンジを知らせるための細長い紙)は入ってなかったのに!!!
Madokakip、ぼー然。
いや、確かに先ほどは先週の歌唱をザジックのアズチェーナの最後の記憶として留めておくのもよいかも、、なんて思ってしまいましたよ。
だから、ばちが当たったのかしら。でもだからといってこんな歌を聴くために今日ここに来たのではないのに、、、。
このメゾの歌は本当あまりにひどくて聴くに耐えなかったので多くは語りますまい。
(マンリーコとの対話のシーンで出て来る高音も、途中で怖くなったのか、周りの音もろともわけのわからん音に下げて歌っていて、しかも音符の長さも無茶苦茶で、何それ、、、?って感じでした。)
Madokakip、しょぼーん。
結局、私のプレイビルからスリップが抜け落ちていただけだったようで、インターミッション中に改めてもらったプレイビルにきちんと入っていたお知らせによると、
このメゾはムツィア・ニオラーゼという歌手で、ここから二つ上の写真が彼女なんですが、
マリインスキー劇場のプロフィールページに掲載されているところを見るとゲルギエフの息のかかった歌手なのかもしれません。
いやー、でも今日は立ち見にしておいて本当よかった、、、良い座席に座ってたら憤死するところでした。
結局、4人の中でまともに歌っていたのは一幕の後もヴァサロだけ。
カリガリ博士は今日は至るところでなすすべなく立ち尽くしてぼーっとしたり、かと思うと
”君が微笑み Il balen del suo sorriso”では、異常にまったりとフレーズを長めにとったりして、
もう半分正気を失っている感じなんですが、これ、バリトンは歌うの大変だろうなあ、、と思いながら聴いていたんですけれども、
よくヴァサロが食い下がって、良い歌唱を聴かせていました。
その上、ゆっくりなのを逆に利用して、先週の公演では入れていなかった高い音を含んだオーナメテーションを二度入れてたりして、
おぬし、やるな、、という感じだったんですが(このあたりのオーナメテーションの処理の上手さを聴くと、
彼はベル・カント作品でも手堅い結果を出していたのを思い出します。)
何を思ったか、カリガリ博士が終盤にいきなり脈絡なく曲のテンポをあげてしまって、これにはヴァサロもびっくり!
Madokakipなどは”こいつ、今日、ドラッグでもやってんじゃねえだろうな?”と思わず疑惑の目を向けてしまったほどです。
さすがにヴァサロもゆっくりなフレージングからいきなりギアを切り替えるのが間に合わなかったようで、
軽くオケとミスコーディネーションになってしまったのが、それまですごく良い内容の歌唱だっただけに残念でした。
きちんとまともに歌っている歌手の歌までおかしくするカリガリ博士、、、嗚呼。
こんな内容でしたので、もうインターミッションで帰ってしまおうかな、とも思ったのですが、ここまで来たら、
私の好きな”恋はばら色の翼に乗って D'amor sull'ali rosee”でのジャンナッタジオの歌唱も聴いておこう、と、いうわけで、
その”恋は~”なんですが、、、あっぷあっぷ感が少ない、また、高音でピアノの音を出せていたのはユーより良かったと思いますが、
ピッチのコントロールが上手く行っておらず、トリルはほとんど存在してしません、って感じのそれでしたし、
先週の公演の感想の中で紹介したカラスの音源で言うと3’26”あたりにある高音から、するするする、、、と下がってくる音型、
高音はほとんどアタックしただけで、すぐ下りて来てしまったし、その後の音の動きもなんだかぎこちなくてがっかりしました。
今日の彼女の歌からは、ユーよりエキサイティングなものはほとんど何も感じられなかったです。
”これぞ立ち見の利点”とばかりに、このアリアが終わってすぐに心おきなくオペラハウスを後にした私ですが、
その後、友人から実はその後にこそ、今日の公演のハイライトがあったと聞いて、早くオペラハウスを出過ぎたー!と後悔した私です。
ただ、そのハイライトというのが、カリガリ博士が再び歌手とのコーディネートに失敗し、オケを崩壊させ、
今度という今度はオケが数秒完全停止してしまった、という内容であるので、後悔すべきかどうかは微妙なところですが。
Gwyn Hughes-Jones (Manrico)
Carmen Giannattasio (Leonora)
Mzia Nioradze replacing Dolora Zajick (Azucena)
Franco Vassallo (Count di Luna)
Morris Robinson (Ferrando)
Hugo Vera (Ruiz)
Maria Zifchak (Inez)
Brandon Mayberry (A Gypsy)
David Lowe (A Messenger)
Conductor: Daniele Callegari
Production: David McVicar
Set design: Charles Edwards
Costume design: Brigitte Reiffenstuel
Lighting design: Jennifer Tipton
Choreography: Leah Hausman
Stage direction: Paula Williams
SR right front
OFF
*** ヴェルディ イル・トロヴァトーレ Verdi Il Trovatore ***
、、、いやー、びっくりしました&おそろしかったです、まじで。
決して簡単ではないレオノーラという役で、なかなかに優れた、しかもパッションのある歌唱を聴かせて印象的なメト・デビューを果たしたユーと、
長いキャリアで幾度となくアズチェーナ役を歌った中でも、彼女をこれまでフォローして来た私が、
これまでで最高の出来だったんじゃないかと思うほど壮絶な歌唱を聴かせたザジックのおかげで、
先週末のマチネの『トロヴァトーレ』が大変にエキサイティングな公演であったのは、感想にも書いた通りです。
あれから約一週間、本来Aキャストでメト・デビューを果たす予定だった(にもかかわらず、病欠で任をユーに譲ることになった)
カルメン・ジャンナッタジオがシーズン二度目の公演から舞台に立っていることを知り、
ここはやはり彼女も聴いておかねば、、ということで、再びメトにやって参りました。
前回はずっと立って見ているとはいえ、30ドルかそこらのチケット代であんな良い公演を見せてもらって、なんか申し訳ない気すらしてくるほどでしたし、
今日は仮にジャンナッタジオがすっ転んでも、少なくともザジックがちゃんといるわけだし、
座って鑑賞しようかな、、、という思いも一瞬頭をかすめたのですが、こういうのを虫の知らせというのでしょうか、
ま、ジャンナッタジオがとても聴いていられないほどひどいという可能性もゼロではないし、何があるかわからん、、、ということで、今日もスタンディング・ルームです。
前回鑑賞した公演を思い出しながら、”しかし、ザジックの先週の歌唱はほんと素晴らしかったから、あれを越えるのは難しいだろうなあ、、。
もしかすると、彼女を長らく応援して来た身としては、あれを彼女の最後のアズチェーナとして記憶に留めた方が幸せだったかな、、。”
などと考えているうちに、カリガリ博士が指揮台に登場して来ました。
前奏の部分で、先週の公演よりも少しオケの音が重いので、お疲れモードかしら、、?とも思いましたが、
彼らは歌手の歌の内容が良い時はそんな時でもすぐに追いついて来るのをこれまで何度も聴いたことがあるので大して心配していなかったのですが、
フェランド役のロビンソンが、伯爵家にまつわる不吉な話を語る部分のうち一番恐ろしい箇所といってよい、
E d'un bambino, ahimé l'ossame
bruciato a mezzo, fumante ancor!
(そして、ああ、子供の骨は半分焦げて、そこからまだ煙がくすぶっていた!)
のbruciato a mezzoが繰り返される最初の方で思いっきり言葉を噛んでしまって余計な音が増えてしまったためにオケの演奏とずれまくり、
カリガリ博士はそれですっかりパニックしてしまったのか、立て直し方が全くわからないのか、
ロビンソンの歌うパートが終わって合唱が入ってくるところでオケが自力でその混乱を抜け出すまで、全くなすすべなし、、の体で立ち尽くしているではありませんか。
まさか、この指揮者、、、。
一般に優れた歌劇場と言われている劇場のオケはどこもそうだと思いますが、
良いキャストが揃っていれば、指揮者が無能でもオケが勝手に上手く演奏してくれる時があって、
それで助かっている・得している指揮者の名前を挙げよ、と言われたら、すぐに頭に浮かんで来る人が何人もいます。
そういう時は、はっきり言って、私が指揮台に立って腕を振り回していても多分同じ結果が出て来るでしょう。
先週の演奏は、もしかすると、この、私が指揮台に立っても大丈夫な状態になっていたのかもしれない、、、。
指揮者ってのは、力のないキャストが失敗をしてしまったり(また、力のある人でも稀に失敗をすることはあるでしょう)、
力はあっても老齢や妙な自信とエゴから自分勝手な歌唱を出してくる歌手(キャリア末期のパヴァロッティや最近のネトレプコ、
ただ、ネトレプコの場合はそれだけでなくて、技術の鍛錬や声質がレパートリーで求められる最低限を満たしていない、ということも理由にあると思いますが。)
にも対処していかねばなりませんが、もしかすると、この指揮者はそういった修整・調整能力のない指揮者なのかも、、、。
舞台が始まってまだそう時間が経っていないうちからこんなことになって、嫌~な予感が立見席のMadokakipの周りに渦巻いて来ました。

いよいよレオノーラ役のジャンナッタジオの登場。
上は彼女のFacebookから借用して来た、今回の『トロヴァトーレ』の衣装合わせの時に撮影したと思しき写真ですが、
見てお分かりの通り、小柄で華奢ななかなかの美人です。
いや、なかなかどころか相当美人と言ってよく、おそらく彼女自身も彼女のエージェントもそれをセールス・ポイントにしていかねば!とばかりに、
彼女のFacebookもファッション・モデルのそれか?と思うほどに、そのルックスを強調した写真のオン・パレードです。
確かに、どんな種類のどんな時代・スタイルの衣装でも似合っていて、それはオペラが視覚も含めた舞台芸術であることを考えるとプラスであることは間違いありません。
また、ネトレプコやガランチャの美人さがどことなく大造りなのに比べると、日本人にも受けやすい繊細なタイプの美人です。
彼女のその美人さは、当然のことながらルックスの良いアーティストに目がないゲルブ支配人の目に留まるところとなり、
オープニング・ナイトの『愛の妙薬』のライブ上映(オープニング・ナイトのライブ上映はリンカーン・センターのプラザとタイムズ・スクエアのみで行われる)でも、
『オテロ』に登場するルネ・フレミングと共にフューチャーされて、司会のデボラ・ヴォイトにインタビューされたり、
上演後のパーティーにネトレプコらと一緒に写真に納まっていたり、と、メト・デビューの歌手としては破格の待遇を受けているのですが、
おそらくその時にイヴニング・ドレスのような薄着で一気に気温の下がったNYの夜を外で過ごしたりしたのが、
風邪をこじらせて初日を降板しなければならなくなった理由なんじゃないかと思います。
歌手には出演するどの公演も貴賎なく常に全力を尽くして欲しい、と思うのがオーディエンス心というものですが、
やはり歌手にはこの公演は絶対外してはいけない、今出来ることをこの公演で100%、いや願わくばそれ以上、を発揮せねばならない、という特別な公演というのがあって、
メト・デビューというのは間違いなく、そういった”外せない公演”の一つだと思うのです。
彼女の歌を聴く前から小言で申し訳ないですが、本来メト・デビューになっていたはずの先週の公演を休まなければならなくなった、
これだけで、私は”駄目だな、、この人は、、。”とちょっと思ってしまいます。
人間は誰でも風邪をひいたり、具合が悪くなったりするものですが、メト・デビューの日にそれをやってちゃいかんのです!
運が悪かった、、というかもしれませんが、運も実力のうち、とは良く言ったもので、
そういう隙があるから、その間にユーが力を発揮して、NYのオーディエンスに”面白い素材の歌手が出てきたぞ。”と注目され、
メディアからも軒並み好意的な評を受け、
たった一公演遅れでメト・デビューを果たしたジャンナッタジオは彼女のことを良く知らないオーディエンスの話の隅にあがることもなく、
もちろん彼女の公演に改めて評が出ることはないので仮に彼女の歌が素晴らしかったとしてもそれが広く伝わることもなく、、ということになってしまうのです。
あれだけ期待されて特別なお膳立てまでしてもらっておいて、なんてもったいない。
彼女はレイラ・ジェンチェルが先生&メンターだった時期があるらしく、そのジェンチェルが、
”メトで歌わなかったことをとても残念がっていた”ことから、
メト・デビューを決めた、というようなことが彼女のFacebookのページに書いてありましたが、
”メトで歌う”ってことは単に舞台に出て行って、口を開けて、舞台をつとめる、ってことだけじゃないんですよ。
メトで歌うからには、自分という歌手を世界によりよく知ってもらって、より広いオーディエンスにリーチ・アウトする、
そのための始まりの場所なのだ、という気構えがないと。
ユーが良かったのは、彼女の歌唱から、こういった目的意識、良い意味での野心が漲っていたことです。
またジェンチェルが言わんとしていたことは、”メトで歌うことでNYの観客に自分の実力を生で感じでもらえなかったことが残念だった”のであって、
単に”メトに登場す”という記録をバイオに残すためだけにメトで歌いたかった、と言っているわけでは決してないでしょう。

まあ、歌を聴く前からあれこれ言うのも何ですから、歌を実際聴いてみましょう。
ということで、その彼女の歌なんですが、うーん、、、何ていうのか、、
ジャンナッタジオの歌唱からは、上で書いたような、良い意味での野心が全く感じられないですねえ。
別にこれが駄目でも次があるわ、ってな感じ?(その点、ユーはこの機会を逃してはいけない!という使命感みたいなのがありました。)
イタリアでそこそこ成功しているからなんでしょうか、、なんか、のんびりしてますよ、彼女は。
声や歌に関しては、まだ彼女が風邪から完全には回復していない可能性もあることは念頭に置いておかないといけないと思いますが、
まず、レオノーラ役で求められるテッシトゥーラにおける彼女の声はあまり魅力的ではないですね。
サイズはややユーより小さいですが、それ自体はあまり問題ではなく、むしろ響きというのか、その辺にあまり個性がないのが辛いし、
中音域以上は比較的ドライな音なのに、低音域にちょっと今のネトレプコを思わせるねっとりとした響きが混じるのが嫌だな、と思います。
イタリア人のよく訓練されている歌手はどの音域も割とすぱっと音が出て来る人が多いという思い込みが私にはあるので、
彼女のことを良く知らずにこの辺の音だけ聴くと、ロシア圏出身の歌手なのかな?と勘違いするくらいです。
ただし、この役で求められる最高音域あたりや、彼女が自分の意志で入れている高音、これは線は細めですが、ものすごく綺麗な響きが聴ける時があって、
彼女自身、高音域・もう少しテッシトゥーラが高めの役の方が歌っていてより心地良く、楽なのかな、と感じる部分はありました。
(やはりFacebookに、ジェンチェルが『トロヴァトーレ』を歌う際には取り入れていたという、Dフラットの音を含むカデンツァを、
今回彼女へのトリビュートとして、取り入れている、とも書いています。)
このことから、レオノーラ役ではなく、もっと他の役に適性があるのかもしれないな、という風にも思います。
しかし、もし、一点だけ、私が彼女の歌のどうしても苦手!なところをあげるとするならば、
リズムのapproximation、ここに尽きるかもしれません。
そう、彼女の歌にはリズムによるパルスが欠けていて、”大体このあたり”的な感じで歌っているような感じがするのです。
音を転がしたり、そういうことはきちんと出来ているので、技術の問題ではなくて、リズムに関しての、生まれもったたセンスや能力の(無さの)問題なのかな、と思うのですが、
今日の歌だけからだと、彼女は正確に歌う、ということがどうにもこうにも出来ない人のように見受けました。
歌手が、感情の表現の目的のために、ある箇所だけ、少しだけ前のめりで歌う、またはためて歌う、ということは当然良くありますが、
良い歌手の場合、まず正しいビートが歌の中にあって、前のめりで・ためて歌っていながらも、
この基本のビートが常にその後ろに感じられる、ここがポイントで、
だからこそ、観客にも、ああ、ここは怒りの表現のために前に出たんだな、とか、迷い、あるいは、深い愛情を表現するために溜めて歌っているんだな、
ということがはっきりわかるわけです。
その後ろのビートが常にぐにゃぐにゃしていたら、本人はタメたり前のめりに歌っているつもりでも、その意図は全然観客には伝わってこなくて、
リズム感のない歌手だな、という感触だけが残ってしまいます。
ユーはジャンナッタジオよりもきちんとしたリズム感を持っている上に、そういうタメや前のめりを多用しないんですが、
ジャンナッタジオの方はなぜだか音色でなく圧倒的にリズムの揺らしで感情を表現しようとすることが多く、
指揮者がこれに応えられるような、”ここはこう歌って!!”という圧倒的な指示を出せる人で、しかも彼女が緩くなった時にはさっとサポート出来る人ならまだ良いですが、
カリガリ博士は前例で見た通り、そのあたりがからっきしなので、二人してごちゃごちゃとリズムを乱しまくって、オケを混乱状態に陥れていました。
それからとどめをさすような感じになりますが、彼女はこんなに美人なのに、演技が無茶苦茶下手くそなのにびっくりしました。
写真なんかではすごくフォトジェニックに写っているので、すごく意外だったです。
舞台で動いている時に、自分がどのようにオーディエンスに見えているか、ということを本能的に感じる能力が不足しているし、
動きのテンポや間も悪い。
先週の公演の感想にも書きました通り、このマクヴィカーの『トロヴァトーレ』は、決して演技するのが簡単な演出ではありません。
背景はシンプルで固定しているし、合唱を除くと極めて登場人物が少なく、
しかも演技力の無さを誤魔化したり、せかせかと立ち演じています、という振りを可能にするような、
今○○して、次はXXして、、というような忙しい連続したコリアグラフィーもありません。
要は、自分で、少ない動きをテンポや間を上手く使いつつ、客に説得力をもって見せなければならない。
だから、マクヴィカー版『トロヴァトーレ』は体の動きの美しさ、間、テンポといったものに欠けている歌手にとっては地獄のように苦しい演出なのです。
それにしても、いくら今オペラ界がビジュアル重視になって来てると言ったって、演技が出来ないのでは美人の意味なし!

先週の公演ではプロの公演に一人アマチュアが混じっているのかと思うような歌唱を繰り広げていたマンリーコ役のヒューズ・ジョーンズ。
正直言っていいですか?なんか、このテノール、見てて・聴いてて腹が立って来るんですよね。
歌手に対してこういう気持ちになることって、私の場合、本当稀、というか初めてじゃないかな?
メトに来る歌手のほとんどは、やはりそれなりに力のある人で、力のある人というのは自分の力をやっぱり良くわかっているんです。
昨シーズンの『ジークフリート』で急に降板したギャリー・レーマンに替わって表題役をつとめた若モリス(ジェイ・ハンター・モリス)なんかも、
舞台を見るまでは”大丈夫なんかいな、、”と思いましたが、
ちょっと一本頭のネジがゆるいように見えて、実は意外と冷静に自分の出来ること、出来ないことを判断しながら歌っているのには感心しましたし、
カーテン・コールでオーディエンスから大きな拍手が出ても、特に馬鹿喜びするでもなく、割りと淡々とした様子なのを見ると、まともな歌手なんだな、と思いました。
先週の公演は公演全体としてとてもエキサイティングだったので、メディアの評も、女性陣(ユーとザジック)を絶賛、
ヴァサロはパー(もちろん、頭がくるくるパーのパーではなく、ゴルフで使うのと同じ意味のpar)、と来て、まあ、ここまでは妥当な評なんですが、
ここで4人が主役の作品で、ヒューズ・ジョーンズだけ落とすのは気の毒だろう、、ということなんでしょう、
彼もパー、みたいな書き方になっていて、これは私がヴァサロだったら絶対切れるよな、という評なんですが、
まあ、メトに来る歌手なら、批評家が気を使ってそうしてくれたことくらい、読み取るよな、と思ってました。
それが、どうしたことでしょう。
あの評をまともに受け取っているのか、今日の彼は”俺って結構いけてる。”とでもいうような自信満々&得々とした様子で歌っているではありませんか!
アルマヴィーヴァ伯爵かと思うような声でマンリーコを歌っているところも、嫌といえば嫌なんですが、
その上にジャンナッタジオの上を行く自由奔放なリズム!!!
しかも、彼のリズム感のなさは間違いなく技術の不足によるもので、発声のきちんとした基礎も出来ていないし、
何をどう間違ってこんなテノールがメトの舞台に立てることになったのか?
自分の完全なる力の不足を恥ずかしがるどころか、気づいている様子もなく、気持ちよさげに妙な音で歌い上げている(←これこそが二流歌手である証)
のを見ていると、どうしようもない田舎もん(であるために、きちんとした比較対象がない)か、それこそ頭のネジがとんでいるんだと思います。
一幕でまともな歌を歌っているのはルーナ伯爵役のヴァサロだけ、、、助けてくれーっ!!!!

二幕。ザジックも登場することだし、ここで取り返してもらわないと。
で、アンヴィル・コーラス。
なーんかまた演奏の足取りが重たくなっているけど、これは何?オケ?指揮者?
やがて、舞台上で上半身裸の男性たちがどんちゃんと槌を振り下ろす(←ゲイのオペラファン垂涎のシーン)のと一緒に歌われる
Chi del gitano i giorni abbella? (ジプシーの男達の一日を明るくするのは誰?)の部分で、
あれあれあれあれ~~~~~ オケピの演奏と裸のお兄さんたちの槌が下りるタイミングがどんどんずれて行ってますよ~。
そして、それを修整しようとあせるカリガリ博士!!
しかし、これは舞台にいる裸のお兄さん達と合唱とオケピにいるオケのメンバー全員に指示を飛ばさなければならないという超難問!!
こんなことが、当然カリガリ博士の手に負えるわけもなく、
オケの中には何か舞台でおかしなことが起こっとる!と自主的に調整しようとしているセクションがあれば、
カリガリ博士の指示がそれに追いついていないのを見て当惑しているセクションもあり、
La zingarella!(それはジプシーの娘!)に至るまでには、オケが大崩壊、大脱線、、、それをまたしてもなすすべなく見守っているカリガリ博士、、、。
つい、”見事にやっちまいましたね、博士。”と声の一つもかけたくなるような出来です。
いやー、メトのアンヴィル・コーラスでこんな見事な大脱線、私、初めて聴きました。
そもそもどうしてそんな風にずれていってしまったわけ??と不思議に思っている間に、また繰り返しで同じ箇所がやって来てどきどきしましたが、
さすがに同じミスは出来ない!とばかりに、異様に大きな振りで舞台上とピットに指示を出すカリガリ博士が涙を誘いました。
もうこうなったらザジックに頑張ってもらわねば!
アンヴィル・コーラスに続けて始まる”Stride la vampa 炎は燃えて"
!?!?!?
最初のフレーズから思いっきりピッチが狂ってる!!!!
っていうか、、、Stride la vampa! La folla indomita の全部の音(おおげさでなく本当に、、)がずれてるので移調かと思いましたよ。
しかし、こんなにたくさんの音数にわたってオケを無視して一人移調、、、すごいなあ、、って感心してる場合か!っての。
いや、しかし、待てよ。何か声が違わないか?これ、ザジックじゃないよね?絶対にザジックじゃなーーーーい
 !!!!!
!!!!!(そりゃそうだ。ザジックは絶対にこんなミスしないもの。)
そして、続くcorre a quel foco lieta in sembianza!もまた一人移調、、、本当すごいなあ、、、ってまた感心してしまったじゃないですか。
しかし、ならば、Who the hell is she!?!?!?!
開演前にプレイビルを見た時はスリップ(キャスト・チェンジを知らせるための細長い紙)は入ってなかったのに!!!
Madokakip、ぼー然。
いや、確かに先ほどは先週の歌唱をザジックのアズチェーナの最後の記憶として留めておくのもよいかも、、なんて思ってしまいましたよ。
だから、ばちが当たったのかしら。でもだからといってこんな歌を聴くために今日ここに来たのではないのに、、、。
このメゾの歌は本当あまりにひどくて聴くに耐えなかったので多くは語りますまい。
(マンリーコとの対話のシーンで出て来る高音も、途中で怖くなったのか、周りの音もろともわけのわからん音に下げて歌っていて、しかも音符の長さも無茶苦茶で、何それ、、、?って感じでした。)
Madokakip、しょぼーん。
結局、私のプレイビルからスリップが抜け落ちていただけだったようで、インターミッション中に改めてもらったプレイビルにきちんと入っていたお知らせによると、
このメゾはムツィア・ニオラーゼという歌手で、ここから二つ上の写真が彼女なんですが、
マリインスキー劇場のプロフィールページに掲載されているところを見るとゲルギエフの息のかかった歌手なのかもしれません。
いやー、でも今日は立ち見にしておいて本当よかった、、、良い座席に座ってたら憤死するところでした。
結局、4人の中でまともに歌っていたのは一幕の後もヴァサロだけ。
カリガリ博士は今日は至るところでなすすべなく立ち尽くしてぼーっとしたり、かと思うと
”君が微笑み Il balen del suo sorriso”では、異常にまったりとフレーズを長めにとったりして、
もう半分正気を失っている感じなんですが、これ、バリトンは歌うの大変だろうなあ、、と思いながら聴いていたんですけれども、
よくヴァサロが食い下がって、良い歌唱を聴かせていました。
その上、ゆっくりなのを逆に利用して、先週の公演では入れていなかった高い音を含んだオーナメテーションを二度入れてたりして、
おぬし、やるな、、という感じだったんですが(このあたりのオーナメテーションの処理の上手さを聴くと、
彼はベル・カント作品でも手堅い結果を出していたのを思い出します。)
何を思ったか、カリガリ博士が終盤にいきなり脈絡なく曲のテンポをあげてしまって、これにはヴァサロもびっくり!
Madokakipなどは”こいつ、今日、ドラッグでもやってんじゃねえだろうな?”と思わず疑惑の目を向けてしまったほどです。
さすがにヴァサロもゆっくりなフレージングからいきなりギアを切り替えるのが間に合わなかったようで、
軽くオケとミスコーディネーションになってしまったのが、それまですごく良い内容の歌唱だっただけに残念でした。
きちんとまともに歌っている歌手の歌までおかしくするカリガリ博士、、、嗚呼。
こんな内容でしたので、もうインターミッションで帰ってしまおうかな、とも思ったのですが、ここまで来たら、
私の好きな”恋はばら色の翼に乗って D'amor sull'ali rosee”でのジャンナッタジオの歌唱も聴いておこう、と、いうわけで、
その”恋は~”なんですが、、、あっぷあっぷ感が少ない、また、高音でピアノの音を出せていたのはユーより良かったと思いますが、
ピッチのコントロールが上手く行っておらず、トリルはほとんど存在してしません、って感じのそれでしたし、
先週の公演の感想の中で紹介したカラスの音源で言うと3’26”あたりにある高音から、するするする、、、と下がってくる音型、
高音はほとんどアタックしただけで、すぐ下りて来てしまったし、その後の音の動きもなんだかぎこちなくてがっかりしました。
今日の彼女の歌からは、ユーよりエキサイティングなものはほとんど何も感じられなかったです。
”これぞ立ち見の利点”とばかりに、このアリアが終わってすぐに心おきなくオペラハウスを後にした私ですが、
その後、友人から実はその後にこそ、今日の公演のハイライトがあったと聞いて、早くオペラハウスを出過ぎたー!と後悔した私です。
ただ、そのハイライトというのが、カリガリ博士が再び歌手とのコーディネートに失敗し、オケを崩壊させ、
今度という今度はオケが数秒完全停止してしまった、という内容であるので、後悔すべきかどうかは微妙なところですが。
Gwyn Hughes-Jones (Manrico)
Carmen Giannattasio (Leonora)
Mzia Nioradze replacing Dolora Zajick (Azucena)
Franco Vassallo (Count di Luna)
Morris Robinson (Ferrando)
Hugo Vera (Ruiz)
Maria Zifchak (Inez)
Brandon Mayberry (A Gypsy)
David Lowe (A Messenger)
Conductor: Daniele Callegari
Production: David McVicar
Set design: Charles Edwards
Costume design: Brigitte Reiffenstuel
Lighting design: Jennifer Tipton
Choreography: Leah Hausman
Stage direction: Paula Williams
SR right front
OFF
*** ヴェルディ イル・トロヴァトーレ Verdi Il Trovatore ***



















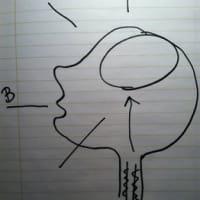
>今日もスタンディング・ルームです。
先見の明あり! オペラヘッズたるもの当然のことなのかもしれませんね。
ところで、ここまで崩壊した舞台といjのは、演奏者が一番わかっていると思います。 ま、一部勘違いの方もいらっしゃるようですが、カーテンコールって通常通りだったのでしょうか? ブーイングはなかったのかしら?
>遠くからわざわざMET詣でしている観客もいるわけですから、その方たちにはご愁傷様としかいえませんね
そう、最近ではオペラ鑑賞こそが、世界の中で一番のギャンブルなんじゃないか、、という気がしてます。
>カーテンコールって通常通りだったのでしょうか? >ブーイングはなかったのかしら?
レオノーラのアリア直後にオペラハウスを出てしまったので、どんなカーテンコールだったのか、わからないんです、、。
そうですね、早く退場してしまうと、観客の反応が確認できない、というデメリットがあるのでした、、、。
ただ、メトは本当に歌に関してはブーイングが出ないですねえ、、
ニオラーゼの歌なんか、間違いなくブーイングの域に達していると思いますが、
(まじめにあんなに長い間、オケを無視して完全な移調状態になっている歌唱、はじめて聴きました、、。)
Stride la vampaの後は普通に拍手が出てました。
私は歌には絶対にブーを出さないことにしているので(歌手でわざと失敗しにメトに来ている人はいないと思うので、、というのが理由ですが、その代わり、わざと作品を歪める演出家連中は容赦なくブーイング!です。)、ブーイングしませんでしたが、さすがに拍手はしなかったです。