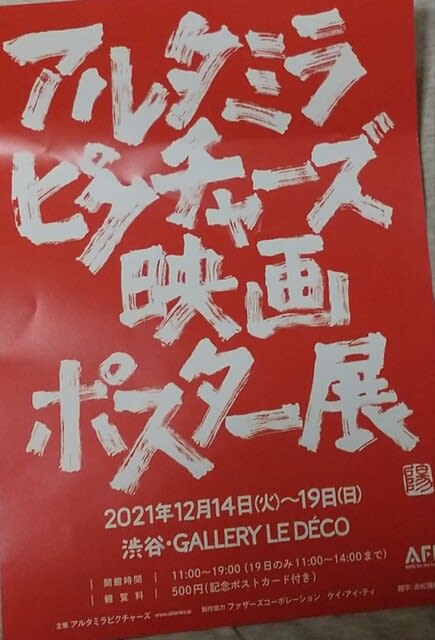ブラックパンサーというと、メディアや官製によるテロリストのイメージが強かったが、それに対する抗議とFBIの方こそ一方的な暴力で弾圧したことを描く。
ちゃちなコソ泥を見逃す代わりにS(スパイ)として組織に送り込むのは洋の東西を問わず官憲の手口だが、そこから元はこれといって思想的な背景がなかったウィリアムがブラックパンサーのリーダー・フレッド・ハンプトン に感化されて目覚めていくのと、反対にそばにいるだけで裏切り続ける展開が平行する。典型的なアンビバレント(二律背反)。
ユダというともちろんキリストを裏切った弟子なわけだが、一方で「ジーザス⋅クライスト⋅スーパースター」で描かれたキリストを愛しすぎたために自分の手で葬りその罪をかぶる自己犠牲のキャラクターのイメージもあり、実際それに近いのではないかという最近の研究の結果も耳にしたことがある。
ウィリアムの末路はユダとはまた違うのだが、アンビバレントを背負い続けているので、単純にハッピーともアンハッピーともいえない。
フレッド役のダニエル・カルーヤの、黒人たちのプライドを取り戻させるカリスマの表現が見事(アカデミー助演男優賞)。
FBIの連絡役のジェシー・プレモンスはなんか見た顔だと思ったら、「すべての美しい馬」(00)でマット・デイモンの少年時代をやっていたというのに苦笑。なるほどデイモンに似てるのね。
悪名高いFBI長官エドガー・フーバーを演じているのが実生活ではばりばりのリベラルのマーティン・シーンというのが面白い。役者とは自分とは真逆の人間をやりたくなるものなのか。











 - YouTube
- YouTube