専修大学の方から、ご質問いただきました。
(もし、このブログをご覧になっている方、おりましたら
「今日の出欠票の裏にあった質問への回答アップされてたよ」
とお友達にお伝えください^-^)
「不合理な区別かどうかを判断する枠組みは、
どう設定すべきでしょう?
高橋先生の教科書などでは、問題となっている
権利の内容などを考慮して決定するとのことなのですが。
しかし、平等権を区別されない権利とすると、
問題となっている権利の内容って関係ないのでは・・・?」
はい^-^>
ええ、実は私、平等権の専門家です。
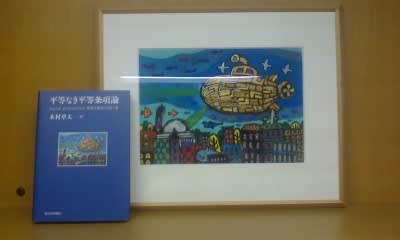
『平等なき平等条項論』をよろしく^-^>
あ、しつこい。
失礼いたしました。
では、まいりましょう。
判例の枠組みは、
平等権
=区別されない権利
→区別はどんな法令でも生じるので、大した価値ではない
→よって、もっとも緩やかな審査基準。
一方、アメリカの判例の影響を色濃く受けて形成された多数説は、
上記の枠組みを前提としつつ、
1 基本的権利に関する区別の論理
重要な権利に関する区別については、
(例えば、公務員と一般人の政治活動に関する区別については)
実質的に問題になっているのは、
区別されない権利よりも重要な権利(表現の自由など)の制限なので
厳格審査基準。
2 疑わしき区別の論理
また、自分の努力では変えられない属性(人種や門地による区別)については、
不合理性が推定されるので、
目的の正当性(場合によっては重要性)と
事実上の関連性(実質的関連性)を要求する厳格な合理性の基準。
→ちなみに、こういう不合理が推定される区別を、
アメリカでは「疑わしい区別」
日本では「14条1項後段列挙事由に基づく区別」
ドイツでは「人の区別」などといいます。
→ちなみに、アメリカでも日本でも、
平等権について、LRA=必要性の審査はしないのが普通です。
多分、ある区別(非嫡出子と嫡出子の法定相続分の区別)を解消しても、
なんらかの区別(子供と兄弟姉妹の法定相続分の区別)が残るのが普通なので、
ある平等権制約(法令が区別すること)について、
LRA(法令が区別を全くしないこと)を想定することが極めて困難だから、
ってことなのかなと。
で、
▲高橋先生は、1の基本的権利セオリーをとります。
しかし、むかしから、1の論理には
△「だったら、その権利(表現の自由)などを直接主張しろよ!」
という、まさにおっしゃる通りの批判が、
(アメリカにも、日本にも)あります。
私も、1の論理は好みませんので、多数説は採りません。
(『平等なき平等条項論』十三章参照)
▲しかし、高橋先生ら多数説は、憲法に明文のない重要な利益もあり、
それをまもるのが14条1項のやくめだ、ということで、
1の論理を維持。
・・・。
△しかし、そういうことなら、13条をつかえばいいじゃん。
(ちなみにアメリカには13条みたいな条文がないので
平等条項つかわざるをえない、という事情が一応ある。)
という実戦例があります。
なので、おっしゃるとおりに理解して頂ければよいと思います。
ただ、有名な多数説なので、もちろん、1の基本的権利の論理、
理解し、覚えておかれるべきかと思います。
ではでは^-^.
(もし、このブログをご覧になっている方、おりましたら
「今日の出欠票の裏にあった質問への回答アップされてたよ」
とお友達にお伝えください^-^)
「不合理な区別かどうかを判断する枠組みは、
どう設定すべきでしょう?
高橋先生の教科書などでは、問題となっている
権利の内容などを考慮して決定するとのことなのですが。
しかし、平等権を区別されない権利とすると、
問題となっている権利の内容って関係ないのでは・・・?」
はい^-^>
ええ、実は私、平等権の専門家です。
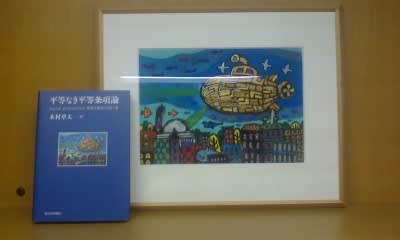
『平等なき平等条項論』をよろしく^-^>
あ、しつこい。
失礼いたしました。
では、まいりましょう。
判例の枠組みは、
平等権
=区別されない権利
→区別はどんな法令でも生じるので、大した価値ではない
→よって、もっとも緩やかな審査基準。
一方、アメリカの判例の影響を色濃く受けて形成された多数説は、
上記の枠組みを前提としつつ、
1 基本的権利に関する区別の論理
重要な権利に関する区別については、
(例えば、公務員と一般人の政治活動に関する区別については)
実質的に問題になっているのは、
区別されない権利よりも重要な権利(表現の自由など)の制限なので
厳格審査基準。
2 疑わしき区別の論理
また、自分の努力では変えられない属性(人種や門地による区別)については、
不合理性が推定されるので、
目的の正当性(場合によっては重要性)と
事実上の関連性(実質的関連性)を要求する厳格な合理性の基準。
→ちなみに、こういう不合理が推定される区別を、
アメリカでは「疑わしい区別」
日本では「14条1項後段列挙事由に基づく区別」
ドイツでは「人の区別」などといいます。
→ちなみに、アメリカでも日本でも、
平等権について、LRA=必要性の審査はしないのが普通です。
多分、ある区別(非嫡出子と嫡出子の法定相続分の区別)を解消しても、
なんらかの区別(子供と兄弟姉妹の法定相続分の区別)が残るのが普通なので、
ある平等権制約(法令が区別すること)について、
LRA(法令が区別を全くしないこと)を想定することが極めて困難だから、
ってことなのかなと。
で、
▲高橋先生は、1の基本的権利セオリーをとります。
しかし、むかしから、1の論理には
△「だったら、その権利(表現の自由)などを直接主張しろよ!」
という、まさにおっしゃる通りの批判が、
(アメリカにも、日本にも)あります。
私も、1の論理は好みませんので、多数説は採りません。
(『平等なき平等条項論』十三章参照)
▲しかし、高橋先生ら多数説は、憲法に明文のない重要な利益もあり、
それをまもるのが14条1項のやくめだ、ということで、
1の論理を維持。
・・・。
△しかし、そういうことなら、13条をつかえばいいじゃん。
(ちなみにアメリカには13条みたいな条文がないので
平等条項つかわざるをえない、という事情が一応ある。)
という実戦例があります。
なので、おっしゃるとおりに理解して頂ければよいと思います。
ただ、有名な多数説なので、もちろん、1の基本的権利の論理、
理解し、覚えておかれるべきかと思います。
ではでは^-^.


















①一つ目は14条1項後段列挙事由と審査基準の関係です。この事由に着目した区別をする場合、厳格な基準によるべきであると耳にします。自由権に対する制約では権利の重要性、規制態様から審査基準を設定します。しかし、列挙事由による区別の審査基準の設定を考える際にはこのような視点はでてきません。よく耳にするのは、列挙事由は歴史的に不合理な差別が行われてきたものだからとか、本人の意思では変えられないからとか、疑わしいから、といった、自由権に対する制約の審査基準を考える時とは異なる要素を見て審査基準を設定するようです。しかし、こうした考えは目的的といいますか、何か恣意的な感覚を拭えません。怪しいから厳格に審査するというのはおかしくて、中立に審査するべきではないでしょうか。上記の自由権の審査の場合は、中立的に審査基準を設定できていると思います。恣意的と思うのは私の理解が不十分が故のことなのでしょうか。
②二つ目は、積極的差別是正措置と審査基準との関係です。耳にするのは、例え列挙事由に該当するとしても厳格に審査すると違憲になる可能性があり、そうしないためにやや緩やかな基準を設定するべきとか、歴史的に差別されてきて、それを是正する必要があるから審査基準は緩やかにすべきとか、少数派を優遇しているだけだから多数派はまずいと思えば元に戻せる、というものです。これもまた自由権制約の審査基準を設定する際の権利の重要性、規制態様といった要素とは違う視点で設定しています。これも何か先に合憲にしたいという結論ありきというか、恣意的で目的的な感覚を拭えません。こうした感覚は私の理解不足に由来するものなのでしょうか。自由に対する審査基準を設定する場合は中立的で大変納得できるのです。
で、なんでそういう問題が生じるかというと、
平等権との関係でいわゆる厳格審査が要請される区別というのは、
差別的意図が疑われたり、
差別助長効果が疑われる区別なのですよ。
なので、差別的意図が疑わしいとは言い難い
積極的是正措置について、
人種による区別だという「形式」だけに着目して
厳格審査をすることに違和感が生じるわけです。
そんなわけで、私は、平等権と差別されない権利を
区別してそれぞれ別の問題と扱うべきという立場です。
詳しくは『平等なき平等条項論』、
簡単にはジュリスト1400号の論文を
ご参照ください。
再びですが一つ質問させてください。(先生のご著書に触れられておりましたらまだ未確認ですので申し訳ございません。)
一点疑問なのですが、「疑われる」と厳格に審査すべき、というのは何故でしょうか。厳格に審査すれば違憲になりやすく緩やかに審査すれば合憲になりやすいという対応関係があると思います。それくらい基準の選択は、合憲違憲の結論に直結しかねないものなのですから、選択の基準は「疑わしい」かどうかでなく、基準選択の時点・段階で判断できる、中身のある客観的な要素(自由権の審査のように)に着目して判断すべきではないのでしょうか。その「疑い」は、審査基準を選択する過程・段階では、実際は疑ったとおりなのか、単なる裁判所の誤解なのか、まだわからないと思いますので、基準選択のときに疑わしいかどうかに着目して基準を選ぶのは、それこそ裁判所の偏見で、合憲違憲の結論まで決めてしまうことになりかねないのではないかと思うのです。
先生御推薦の教科書、論文は是非読ませていただきます。写真でみる限り表紙がとても斬新です。内容も楽しみです。
まず、「疑わしい区別」厳格審査の法理は、
日本の判例の採用するものではありません。
アメリカ連邦最高裁の法理は、
人種に基づく区別は、類型的に、目的との関連性がないことが多いので、
関連性がないという推定(違憲の推定)をおき、
関連性があることが明確に論証できる場合にのみ
合憲としよう、というものです。
「厳格な審査」という言葉はいろいろ意味がありますが、
ここでは違憲の推定という意味ですね。
「疑わしい」というのは、
人種による区別が経験的に目的達成に役だっていないことが多い
という程度の意味です。
「疑わしい」ことは、アメリカでは違憲の推定を置くのに
十分な理由だと考えられております。
勉強になりました。ありがとうございます。先生のご著書も読ませていただきます。
合憲の推定を置かない審査の意味だと思いますが、
平等権では一般に、合憲の推定を置いて審査するので、
疑わしい区別とか、特別にそれを外す類型を
設けるんですよね。
なぜ、平等権では一般に合憲の推定を置かないのか、
という点については、ちょっと考えてみてください。
じっくり考えるとわかる問題です
なかなか難しいですが、法律はある目的を達成するために制定されますから、多くの法律はその適用を受ける対象が、自ずと一定範囲の者に限られる、という事態が生じると考えられます。
消費税のように区別なく国民一般に課されるものは例外なのかもしれません。
そして憲法が法律を制定すること自体認めている以上、国民の何かに着目して、線引きして区別することは本来的に予定されていると考えられるのではないでしょうか。それ故裁判所としても、何か区別が生じていても通常は目くじらをたてることはなかろという目で審査すればよいのですが、ただ、中には不合理な区別が紛れ込んでおり、それを排斥する必要があります。これまでの歴史をみますと、不合理な区別は特に後段列挙事由に着目した区別であったことが多いと考えられます。後段列挙事由に該当する場合は類型的に怪しいと考えられるため、裁判所はその場合はしっかりと審査すべきである。
じっくり考えるとこういうことではないか、と思いました。
模範解答
照英さま、いかがでしょうか?
参考にしていただけて、
とてもうれしいです