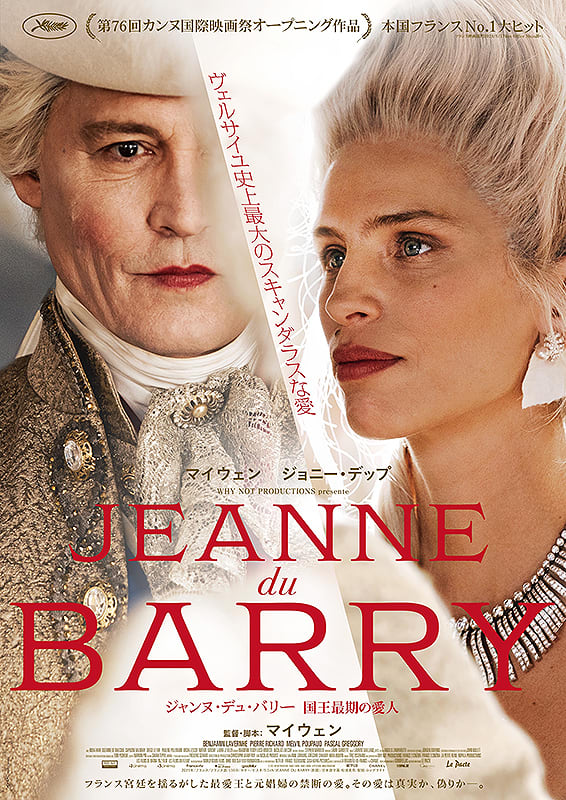ソウルで幼馴染として育った男女が12歳で離ればなれとなり、24年ぶりにニューヨークで再会を果たすという物語。
ソウルに暮らす12歳の少女ソヨンと少年ヘソンは互いに恋心を抱いていたが、ソヨンは親の都合でカナダに移住してしまう。ソヨンはノラという英語名になり、24歳でへソンとネットで再会するが、リアルに会えないままに再びすれ違う。36歳でニューヨークで会った時、ノラは米国人アーサーと結婚していた…
予告編を観た時、これは私が好きなストーリーだと思って期待したのですが…
予想したほどには感動しませんでした。
何故だ!?
アカデミー賞の作品賞、脚本賞にノミネートされたというのに。
この冒頭のバーの3人のシーンには、ワクワクしたのですが。

この作品のテーマは「イニョン(縁)」か。
この言葉は映画の中に何度も出て来るし、タイトルの「パストライブス(Past lives)」は、日本語で前世の意味。
へソンは「この人生自体が前世だったなら。イニョンがあれば来生でまた逢おう」と言うのです。

しかしそれは、私にはどうも女々しく聞こえてします。
そもそも12歳という子供の時の初恋なんてママゴトのように私には思えてしまうし、いつまでもそれを引きずるヘソンには呆れてしまう。
そしてもっと好きになれないのは、ソヨン(ノラ)。
24歳でネットで再会し盛り上がったのに、彼女は唐突にやり取りを断ち切る。
その理由は、自分は移住して頑張ってきたのに、(へソンとやり取りしている今)ソウルに行くことばかり考えてしまう、こんなことしている場合じゃないというもの。
そういう心境に至るには移民としての苦労がさぞあったのでしょうが、映画ではそれは描かれない。
結局この人は上昇志向で、すべてをそれに優先させたのだと。
米国人アーサーと結婚したのも、グリーンカード欲しさでないとは断言できないでしょう。
という訳で、私はヒロインをあまり好きにはなれなかったのです。
ラストシーン、階段でノラを待つアーサーの姿には泣けました。
「パスト・ライブス」公式HP











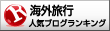







 (2018.7.)
(2018.7.)