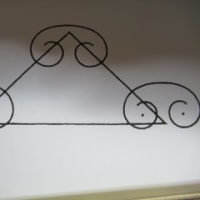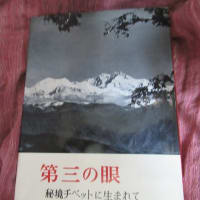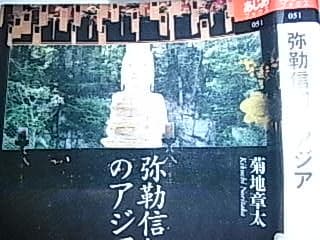
ペルシアのミトラス神と弥勒は、なんらかの関係があるのだろうか、といったことを考えています。
引き続き、菊地章太氏の「弥勒信仰のアジア」という本を紹介させていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
著者は、以前“学研「ム―」の「弥勒の大予言」”という記事で取り上げた仏教経典「法滅尽経」を、「疑経」であるけれど、中国の弥勒信仰の特徴を有するものとして考察しています。
*****
(引用ここから)
弥勒信仰を変質させた疑経の一つに「法滅尽経」がある。
釈迦の教えが滅びようとする時の有様を語った経典である。
その描写が大変リアルなため、いくつもの仏教文献に引用された。
そのため、古くから疑経とみなされながらも、今日まで伝えられてきた。
敦煌からも写本が一つ発見されている。
おそらく5世紀の終わりか6世紀の初めに、北魏で作られたものであろう。
「世界はいつか破局を迎える」という考え方は、中国には古くからあった。
それは中国思想の主流とはならなかったが、さまざまな文献に語られていた。
儒教のいわば異端思想とでも言うべき「しんい」の文献には、世界の破局についての予言が頻繁に見られる。
「しんい」とは儒教の経典にかこつけて、神秘的な予言を説いたものである。
西暦紀元の前後から盛んになった。
たとえばこのような予言が残されている。
・・・・・
「百世を経た後、地面は盛り上がって、山山は消えてなくなる。
風も吹かず、雨も降らず、寒さ暑さも訪れず、そのため大地の実りがない。
人々は土を食らうようになる。
その時には、人々は自分の母親は分かっても、父親を知らない。
そのような時代が千年続いた後、天下に危急が迫り、どよめき荒れ狂うだろう。
その有様は知りようもない。」
・・・・・
ここで異変が始まるのは、「百世を経た後」だと言う。
ある時間の切れ目に世界の破局が訪れる、という予言は「しんい」に遅れて成立した道教にも受け継がれた。
「洞淵神呪経」という道教の経典がある。
・・・・
「大いなる時の終わりが近づいている。
政治は乱れ、人々は叫び声をあげている。
風雨は時節にかなわず、五穀は実らなくなる
人々の心は凶悪になり、お上にたてついて反乱をおこす。
父も子も兄弟も騙し合って、国を滅ぼすに至る。
盗賊がのさばり、罪もない人々を殺害する。
疫病が流行し、90種もの病気がはびこるだろう。」
「役人は利益ばかり求めて、人々を労わろうとしない。
人々は叫び声をあげて、恨みを抱くまでになって、天下は憂いに満ちる。
太陽と月は軌道を変え、五穀は実らず、人々は土地を捨ててさまよう。
その時大洪水が襲うだろう。」
・・・・
ここでは「大いなる時の終わり」に至ることが、破局の原因となっている。
自然災害も悪政も、その結果としてとらえられる。
未来のある時、人間世界が危機に陥り、自然界までそれに連動する。
そういう思想が中国にはあり、「しんい」の文献に語られ、道教経典においても繰り返し説かれていた。
そのような世界の破局についての予言が、仏教の疑経において、法滅の危機と結びついたのである。
(引用ここまで・続く)
*****
中国思想といえば、老荘思想、道教が思い浮かびます。
その、混沌の中にある宇宙の秩序と循環の法則が思い浮かびます。
道教であれば、革命思想はあるにせよ、世界の終わる時とは、世界の表象が循環して、次の新しい世界が始まる時だ、という思考であるだろうと思っていました。
なので、本書が指摘するように、道教には、宇宙の変化を不可逆なものとして、破滅ならまさに破滅として、捉える側面があるということ、またその点を重視すべきであるという指摘を、大変興味深く思いました。
宇宙には、不可逆なことがあるのかもしれません。
人の心性には、世界の不可逆な変化の認知力があるのかもしれません。
たいていの予言というものが嫌われるのは、そこにまつろう希望を砕くような悲観的な雰囲気があるからでしょうけれど、なんらかの真実があるのかもしれないと思います。
「洞淵神呪経」など、道教の予言書の原典を読んでみたいと思いつつ、なかなか読むことが叶わずにいます。
 wikipedia「しん緯」より
wikipedia「しん緯」より
讖緯(しんい)とは、古代中国で行われた予言のことであり、讖緯の説、讖緯思想などと呼ばれている。
元来は、讖と緯とは別のものである。
讖とは、未来を予言することを意味しており、予言書のことを「讖記」などと呼んでいる。
それに対して、緯とは、儒教の経典に対応する「緯書」と呼ばれる書物群を指すものである。
しかし、後には、この二者はともに予言を指す言葉と、それを記した書物として、併せて用いられるようになり、「讖緯」という用語が予言を指すようになった。
『隋書』「経籍志」には、
説者又た云う、孔子は既に六経を叙し、以って天人の道を明らかにするも、後世には、その意に稽同すること能わざるを知り、
別に緯及び讖を立て、以って来世に遺す。
と見えている。
讖緯説が著しく発展したのは、王莽の新の時代である。
王莽の即位を予言する瑞石が発見された、とされ、王莽自身も、それを利用して漢朝を事実上簒奪した。
儒教の経書に対する緯書が後漢代にも盛んに述作され、それらは全て聖人である孔子の言として受け入れられた。
後漢の光武帝も、讖緯説を利用して即位している。
また、春秋戦国時代の天文占などに由来する讖記の方も、緯書の中に採り入れられて、やがては、それらも、孔子の言であるとされるようになった。
当時の大儒者であった鄭玄や馬融らも、緯書を用いて経典を解釈することに全く違和感を持っていなかった。
よって、五経に対する緯書は言うに及ばず、当時は経典の中に数えられていなかった『論語』に対する『論語讖』というものまで述作されるに至った。
その一方で、桓譚や張衡のような、讖緯説を信じない者は不遇をかこった。
讖緯の説は、その飛躍の時代である王莽の新の時代以来、王朝革命、易姓革命と深く結びつく密接不可分な存在であったため、時の権力からは常に危険視されていた。
よって、南北朝以来、歴代の王朝は讖緯の書を禁書扱いし、その流通を禁圧している。
 関連記事
関連記事
ブログ内検索
弥勒 15件
弥勒下生 6件
法滅尽 3件
ミトラス 6件
仏教 15件
終末 15件
道教 7件
中国 15件
大洪水 15件
予言 15件
太陽 15件
(重複しています)
引き続き、菊地章太氏の「弥勒信仰のアジア」という本を紹介させていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
著者は、以前“学研「ム―」の「弥勒の大予言」”という記事で取り上げた仏教経典「法滅尽経」を、「疑経」であるけれど、中国の弥勒信仰の特徴を有するものとして考察しています。
*****
(引用ここから)
弥勒信仰を変質させた疑経の一つに「法滅尽経」がある。
釈迦の教えが滅びようとする時の有様を語った経典である。
その描写が大変リアルなため、いくつもの仏教文献に引用された。
そのため、古くから疑経とみなされながらも、今日まで伝えられてきた。
敦煌からも写本が一つ発見されている。
おそらく5世紀の終わりか6世紀の初めに、北魏で作られたものであろう。
「世界はいつか破局を迎える」という考え方は、中国には古くからあった。
それは中国思想の主流とはならなかったが、さまざまな文献に語られていた。
儒教のいわば異端思想とでも言うべき「しんい」の文献には、世界の破局についての予言が頻繁に見られる。
「しんい」とは儒教の経典にかこつけて、神秘的な予言を説いたものである。
西暦紀元の前後から盛んになった。
たとえばこのような予言が残されている。
・・・・・
「百世を経た後、地面は盛り上がって、山山は消えてなくなる。
風も吹かず、雨も降らず、寒さ暑さも訪れず、そのため大地の実りがない。
人々は土を食らうようになる。
その時には、人々は自分の母親は分かっても、父親を知らない。
そのような時代が千年続いた後、天下に危急が迫り、どよめき荒れ狂うだろう。
その有様は知りようもない。」
・・・・・
ここで異変が始まるのは、「百世を経た後」だと言う。
ある時間の切れ目に世界の破局が訪れる、という予言は「しんい」に遅れて成立した道教にも受け継がれた。
「洞淵神呪経」という道教の経典がある。
・・・・
「大いなる時の終わりが近づいている。
政治は乱れ、人々は叫び声をあげている。
風雨は時節にかなわず、五穀は実らなくなる
人々の心は凶悪になり、お上にたてついて反乱をおこす。
父も子も兄弟も騙し合って、国を滅ぼすに至る。
盗賊がのさばり、罪もない人々を殺害する。
疫病が流行し、90種もの病気がはびこるだろう。」
「役人は利益ばかり求めて、人々を労わろうとしない。
人々は叫び声をあげて、恨みを抱くまでになって、天下は憂いに満ちる。
太陽と月は軌道を変え、五穀は実らず、人々は土地を捨ててさまよう。
その時大洪水が襲うだろう。」
・・・・
ここでは「大いなる時の終わり」に至ることが、破局の原因となっている。
自然災害も悪政も、その結果としてとらえられる。
未来のある時、人間世界が危機に陥り、自然界までそれに連動する。
そういう思想が中国にはあり、「しんい」の文献に語られ、道教経典においても繰り返し説かれていた。
そのような世界の破局についての予言が、仏教の疑経において、法滅の危機と結びついたのである。
(引用ここまで・続く)
*****
中国思想といえば、老荘思想、道教が思い浮かびます。
その、混沌の中にある宇宙の秩序と循環の法則が思い浮かびます。
道教であれば、革命思想はあるにせよ、世界の終わる時とは、世界の表象が循環して、次の新しい世界が始まる時だ、という思考であるだろうと思っていました。
なので、本書が指摘するように、道教には、宇宙の変化を不可逆なものとして、破滅ならまさに破滅として、捉える側面があるということ、またその点を重視すべきであるという指摘を、大変興味深く思いました。
宇宙には、不可逆なことがあるのかもしれません。
人の心性には、世界の不可逆な変化の認知力があるのかもしれません。
たいていの予言というものが嫌われるのは、そこにまつろう希望を砕くような悲観的な雰囲気があるからでしょうけれど、なんらかの真実があるのかもしれないと思います。
「洞淵神呪経」など、道教の予言書の原典を読んでみたいと思いつつ、なかなか読むことが叶わずにいます。
 wikipedia「しん緯」より
wikipedia「しん緯」より 讖緯(しんい)とは、古代中国で行われた予言のことであり、讖緯の説、讖緯思想などと呼ばれている。
元来は、讖と緯とは別のものである。
讖とは、未来を予言することを意味しており、予言書のことを「讖記」などと呼んでいる。
それに対して、緯とは、儒教の経典に対応する「緯書」と呼ばれる書物群を指すものである。
しかし、後には、この二者はともに予言を指す言葉と、それを記した書物として、併せて用いられるようになり、「讖緯」という用語が予言を指すようになった。
『隋書』「経籍志」には、
説者又た云う、孔子は既に六経を叙し、以って天人の道を明らかにするも、後世には、その意に稽同すること能わざるを知り、
別に緯及び讖を立て、以って来世に遺す。
と見えている。
讖緯説が著しく発展したのは、王莽の新の時代である。
王莽の即位を予言する瑞石が発見された、とされ、王莽自身も、それを利用して漢朝を事実上簒奪した。
儒教の経書に対する緯書が後漢代にも盛んに述作され、それらは全て聖人である孔子の言として受け入れられた。
後漢の光武帝も、讖緯説を利用して即位している。
また、春秋戦国時代の天文占などに由来する讖記の方も、緯書の中に採り入れられて、やがては、それらも、孔子の言であるとされるようになった。
当時の大儒者であった鄭玄や馬融らも、緯書を用いて経典を解釈することに全く違和感を持っていなかった。
よって、五経に対する緯書は言うに及ばず、当時は経典の中に数えられていなかった『論語』に対する『論語讖』というものまで述作されるに至った。
その一方で、桓譚や張衡のような、讖緯説を信じない者は不遇をかこった。
讖緯の説は、その飛躍の時代である王莽の新の時代以来、王朝革命、易姓革命と深く結びつく密接不可分な存在であったため、時の権力からは常に危険視されていた。
よって、南北朝以来、歴代の王朝は讖緯の書を禁書扱いし、その流通を禁圧している。
 関連記事
関連記事
ブログ内検索
弥勒 15件
弥勒下生 6件
法滅尽 3件
ミトラス 6件
仏教 15件
終末 15件
道教 7件
中国 15件
大洪水 15件
予言 15件
太陽 15件
(重複しています)