

最近、その日で消えちゃうasahi.comの社説(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup、2013年 4月 26 日(金))。
隣国といったどんな関係を築きたいのだろう? 「ガリレオ」流に云えば、「さっぱり分からない!」、である。
いま、靖国に参拝し、周辺諸国にどんなアピールをしたいの? それを安倍首相が「言論の自由の確保」的な、「脅しに屈しない」的な言葉で擁護する神経がこれまた、「さっぱり分からない!」、である。「「侵略」かどうか議論がある」、なんて口にするのは異常でしょう。一体どこぞの学会でそんな議論をしているの? 番犬様・アメリカからも小言を言われる始末。自公政権は、隣国と戦争するような関係を作りたいのだろうか? 核を保持し、戦争できる国にしましょう、とでも思っているのだろうか? 元東京〝ト〟知事の軽はずみな尖閣諸島購入事件のような挑発行為。私人なら、こっそり行ったらいいのでは? 「菅官房長官は、今回の閣僚たちは「私人としての参拝」と説明するが、政府の要職にある立場で公私は分かちがたい」。カメラを引き連れてか、わざとカメラが来るように仕向けてるのかどうか知らないが、諸外国にまで大きく報道されておいて、私人もヘッタクレもないのでは?
『●『合祀はいやです。こころの自由を求めて』読了(1/3)』
『●『合祀はいやです。こころの自由を求めて』読了(2/3)』
『●『合祀はいやです。こころの自由を求めて』読了(3/3)』
『●『抵抗人名録 私が選んだ77人』読了(1/2)』
『●無断合祀』
================================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_top_pickup、2013年 4月 26 日(金)】
2013年 4月 26 日(金)付
靖国と政治―静かな参拝のためには
靖国神社は、遺族や国民が静かに参拝する場である。
今回、参拝して近隣国の反発を招いた麻生副総理・財務相は06年、こんな一文を朝日新聞に寄せている。
〈靖国をめぐる論争が過熱し、英霊と遺族から魂の平安を奪って久しい。
鎮魂の場という本旨へ復すべきだ。そのためには靖国を、
政治から無限に遠ざけねばならない〉
その通りだと思う。であればこそ、その方策を考えるのが政治家の務めではないのか。
閣僚や国会議員が大挙して参拝し、中国や韓国と激しい応酬を繰り広げるのは、遺族らにとっても本意ではあるまい。
安倍首相は国会答弁で「国のために尊い命を落とした英霊に尊崇の念を表するのは当たり前。どんな脅かしにも屈しない」と強調した。
首相自身は参拝しなかった。そのことの意味が中国や韓国に理解されていない、との思いかもしれない。
だが、遺族や国民が自然な感情で戦没者を悼むのと、閣僚らの参拝を同列に論じることはできない。
それは、この神社が持つ特殊な性格による。
靖国神社には戦没者だけでなく、先の戦争を指導し、東京裁判で厳しく責任を問われたA級戦犯が78年に合祀(ごうし)された。それ以降、昭和天皇は靖国を参拝しなかった。
戦前の靖国神社は、亡くなった軍人や軍属を「神」としてまつる国家神道の中心だった。境内にある施設「遊就館」は、いまも戦前の歴史を正当化した展示をしている。
私たちは社説で、首相や閣僚の靖国参拝に反対してきた。日本が過去の過ちを忘れ、こうした歴史観を後押ししていると国際社会から受け止められかねないからである。
さらに首相や閣僚による公式参拝は、憲法の政教分離の規定からみても疑義がある。
菅官房長官は、今回の閣僚たちは「私人としての参拝」と説明するが、政府の要職にある立場で公私は分かちがたい。
首相は23日の参院予算委員会で、植民地支配や侵略への反省とおわびを表明した村山談話について「侵略という定義は学界的にも国際的にも定まっていない。国と国の関係でどちらから見るかで違う」と語った。
侵略を否定するかのような発言を繰り返せば、近隣国のみならず、欧米諸国の不信も強まることになる。
歴史を踏まえぬ政治家の言動が、静かな参拝を妨げる。
================================================================================











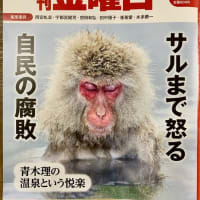

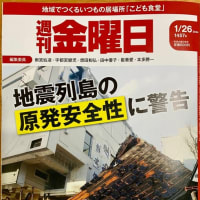

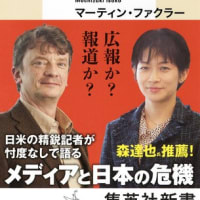
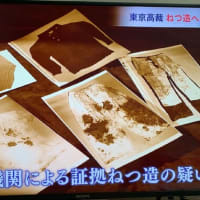







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます