みなさんは小学校の頃の授業について何か覚えているでしょうか?私は、四、五年生まで落ちこぼれだったせいでしょうか、前に書いた遊びなどは覚えているのに授業についてはほとんど覚えていません。嫌なことなどは記憶から消し去っているのでしょうか、不思議なことです。そんな中で、覚えているのは三年生の時の掛け算九九と、六年の時の学芸会。
①最後まで?の九九
今回はそのかけ算九九です。
かけ算は今は二年生でやりますが、当時は二年生と三年生に分けて教えられていたと思います。それでも、かけ算は三年生になってもなかなか覚えられなくて、放課後残されて、校舎裏の崖に登って、日向ぼっこしながら練習したものです。一階建ての校舎で裏に用務員室があり、そこから裏山に登れるのでした。何しろ早生まれで身長も一番低かったので幼かったのでしょう。同じように残された数人で、遊び半分だったのかと思います。教室には誰がクリアしたかが分かるようにグラフのような物に書いていたと思いますが、肝心の九九は最後までクリアしたのかどうか?です。
高学年になっても、たとえば7×6はすぐ分かっても6×7は一瞬考えてひっくり返して答えるということが続きました。
②こんな通知表!
こんな調子でしたから低中学年の時の通知表はほとんどアヒル(2)でした。(その頃は五段階相対評価で、優、良上、良、良下、可と表示されて途中から54321に変更されましたが、地方によって違うかもしれません。通知表はまだ保管!)
行動の欄も「いつもおちつかない。」とたった一行ですから、よほど先生を手こずらせたんでしょうね。(こんなたった一行の書きなぐりは今だったら大変ですね。当時は、親も自身の不明、わが子の不明をまず考えたのでしょうね。親からはまずゴツンとお目玉でしたから)
三月の早生まれということで親は諦めていた節もありましたが、それでも、私が生まれた年に出征し戦死した兄が優秀だったのでため息交じりにこぼされたことを覚えています。
③実物を使った授業で九九
後年、教職に就いた時にも、この経験はいつもほろ苦く思いだされました。
そのために、何とか面白く授業したいと思い、まずふだんの生活でかけ算を使う場面を設定して進めました。
一箱に8個入っているキャラメルを4箱買いました。全部で何個買ったことになるでしょう?という問題でやりました。何個入りとなっている実物探しをいっぱいしました。
こうして実物を毎回のように持ち込み、覚えたら食べられるものは食べてしっかり繰り返し覚えると。友だち同士グループになってゲームのように唱えていったり、家族も巻き込んだりの取り組みで、多くの場合、全員合格という所まで時間かけました。
全員合格の日にはお祝いパーティーをして喜び合いました。この時も、子どもの頃の自分だったら、きっと最後の子だろうなあと思いながら。
④「水道方式」との出会いが救ってくれた
私は幸い、算数を単なる暗記物から、実際に即して考え、基本から応用へと辿る水道方式の考えの研究会で学びました。「一あたりの数」(車にタイヤ4個、自転車にタイヤ2個など)を基本にかけ算をとらえ、実物をもとに考えさせるのでした。
今でこそ教科書にも当然のように取り入れられている考えですが、暗算中心の算数が当たり前の当時は、革新的な考えなので、教科書通りではないとずいぶん管理職に責められました。
なお、水道方式の算数は東工大教授の遠山啓が提唱したもので数学教育協議会で全国の先生たちが研究を進めました。当初は異端のように扱われましたが、今では一般的になって教科書では水道方式の用語も消えて当然のように記述されています。今、発行されている多くの数学の本でも遠山啓氏の本:「数学の学び方・教え方」「数学入門」(上下二冊)ともに岩波新書。
こうして教育の分野でも、新しい考えや教え方が始めはどのように扱われ、それが一般化するにはいろいろな難関があったことを体験することになりました。
⑤子どものころの経験で教育改革?
大人が教育問題を語る時には、往々にして自分の子どものころの経験をもとにしていることが多いと言われます。私の場合にも、九九ができなくて残された記憶があってできない子の気持ちをいっぱい体験したことから、さまざまな研究会に通うことになったのでしたが・・・。
今日の小学校から英語英語と騒ぐ国会議員も、子どもの頃はきっと苦手だったのでは・・・・と思ってしまいます。
自主的な活動を旨とする総合学習の時間を削除したり、国語教育も不十分といわれるのに低学年から英語をと主張し、子どもからも学校からも余裕をなくしてしまう教育改革を主張する人々もトラウマにとらわれているのでしょうか。なぜ足元を固めないで、グローバル、グローバルと踊るのでしょうね。
皆さんは?
①最後まで?の九九
今回はそのかけ算九九です。
かけ算は今は二年生でやりますが、当時は二年生と三年生に分けて教えられていたと思います。それでも、かけ算は三年生になってもなかなか覚えられなくて、放課後残されて、校舎裏の崖に登って、日向ぼっこしながら練習したものです。一階建ての校舎で裏に用務員室があり、そこから裏山に登れるのでした。何しろ早生まれで身長も一番低かったので幼かったのでしょう。同じように残された数人で、遊び半分だったのかと思います。教室には誰がクリアしたかが分かるようにグラフのような物に書いていたと思いますが、肝心の九九は最後までクリアしたのかどうか?です。
高学年になっても、たとえば7×6はすぐ分かっても6×7は一瞬考えてひっくり返して答えるということが続きました。
②こんな通知表!
こんな調子でしたから低中学年の時の通知表はほとんどアヒル(2)でした。(その頃は五段階相対評価で、優、良上、良、良下、可と表示されて途中から54321に変更されましたが、地方によって違うかもしれません。通知表はまだ保管!)
行動の欄も「いつもおちつかない。」とたった一行ですから、よほど先生を手こずらせたんでしょうね。(こんなたった一行の書きなぐりは今だったら大変ですね。当時は、親も自身の不明、わが子の不明をまず考えたのでしょうね。親からはまずゴツンとお目玉でしたから)
三月の早生まれということで親は諦めていた節もありましたが、それでも、私が生まれた年に出征し戦死した兄が優秀だったのでため息交じりにこぼされたことを覚えています。
③実物を使った授業で九九
後年、教職に就いた時にも、この経験はいつもほろ苦く思いだされました。
そのために、何とか面白く授業したいと思い、まずふだんの生活でかけ算を使う場面を設定して進めました。
一箱に8個入っているキャラメルを4箱買いました。全部で何個買ったことになるでしょう?という問題でやりました。何個入りとなっている実物探しをいっぱいしました。
こうして実物を毎回のように持ち込み、覚えたら食べられるものは食べてしっかり繰り返し覚えると。友だち同士グループになってゲームのように唱えていったり、家族も巻き込んだりの取り組みで、多くの場合、全員合格という所まで時間かけました。
全員合格の日にはお祝いパーティーをして喜び合いました。この時も、子どもの頃の自分だったら、きっと最後の子だろうなあと思いながら。
④「水道方式」との出会いが救ってくれた
私は幸い、算数を単なる暗記物から、実際に即して考え、基本から応用へと辿る水道方式の考えの研究会で学びました。「一あたりの数」(車にタイヤ4個、自転車にタイヤ2個など)を基本にかけ算をとらえ、実物をもとに考えさせるのでした。
今でこそ教科書にも当然のように取り入れられている考えですが、暗算中心の算数が当たり前の当時は、革新的な考えなので、教科書通りではないとずいぶん管理職に責められました。
なお、水道方式の算数は東工大教授の遠山啓が提唱したもので数学教育協議会で全国の先生たちが研究を進めました。当初は異端のように扱われましたが、今では一般的になって教科書では水道方式の用語も消えて当然のように記述されています。今、発行されている多くの数学の本でも遠山啓氏の本:「数学の学び方・教え方」「数学入門」(上下二冊)ともに岩波新書。
こうして教育の分野でも、新しい考えや教え方が始めはどのように扱われ、それが一般化するにはいろいろな難関があったことを体験することになりました。
⑤子どものころの経験で教育改革?
大人が教育問題を語る時には、往々にして自分の子どものころの経験をもとにしていることが多いと言われます。私の場合にも、九九ができなくて残された記憶があってできない子の気持ちをいっぱい体験したことから、さまざまな研究会に通うことになったのでしたが・・・。
今日の小学校から英語英語と騒ぐ国会議員も、子どもの頃はきっと苦手だったのでは・・・・と思ってしまいます。
自主的な活動を旨とする総合学習の時間を削除したり、国語教育も不十分といわれるのに低学年から英語をと主張し、子どもからも学校からも余裕をなくしてしまう教育改革を主張する人々もトラウマにとらわれているのでしょうか。なぜ足元を固めないで、グローバル、グローバルと踊るのでしょうね。
皆さんは?










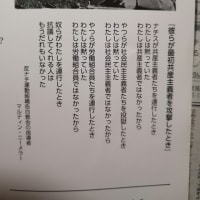









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます