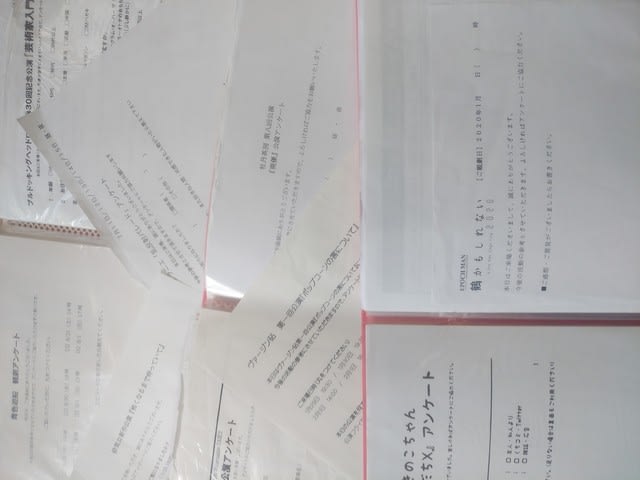
いよいよ質問の分析も最後です。
質問その4 劇団の作品をみたことがあるか
リピーターの数を把握できる質問で、重要だと思います。35団体が採用。
質問の仕方は
・(団体名)の公演をご覧いただくのは・・・
・過去に当劇団の公演をご覧になったことはありますか
・今までに(団体名)の公演を観たことはありますか
・これまでにご覧いただいた公演を教えてください。
・いままでの公演でご覧になったものはございますか
などで、
選択肢にパターンがあります。
■選択肢1 ある・ない(今回がはじめて) の2者択一パターン 10団体
■選択肢2 過去の上演作品を列挙し観た作品を選ばせる 18団体
■選択肢3 観劇回数を選択または記入させる 5団体
■選択肢4 公演作品名・第○回公演を書かせる 2団体
■選択肢1 ある・ない(または今回がはじめて)
選択肢としては、ある( )・ない(今回がはじめて)の2者択一で、ある場合は作品名を自由記述させます。
作品名を書くのは正直面倒。正確なタイトルを思い出せないのも何か後味が悪いですし、観劇した全ての作品を記入する気はしません。
■選択肢2 過去の作品を列挙
そこで、過去の作品を列挙して○をつけさせる団体が18団体あります。
これは、
・毎公演観に来る、観客数として計算できるリピーター
・不定期に観に来る観客数
・昔観ていた客が戻ってきた傾向
・新たな観客
が把握でき、継続的に測定することでリピーター具合がわかります。
デメリットとしては、すべての過去作品を挙げると紙面のスペースを割くことです。そこで過去数年間の作品だけを挙げて、残りは「それ以前」の選択肢を設ける団体が2団体あります。
■選択肢3 観劇回数を選択または記入される
<実例>
・はじめて・2回・3回~5回・6回以上
数字を記入させることは、リピーター具合が一目でわかるメリットがあります。
しかし、過去の観劇作品数をその場で正確に思い出せるかは疑問ですし、「観劇回数」とすると同じ作品を繰り返し見ている人は、すべての数を記入する恐れもあります。
なにより、いつからの観客かなど傾向が分析できないため、データを活かしきれないと思います。
●一番好きな作品を書かせる
回数を選択させたうえで、3回以上を選択した場合に「一番好きな作品を」記入させる団体が1団体ありました。これはリピーター具合というよりは、客層が期待するテイストがわかるかもしれません。
■選択肢4 公演作品名・第○回公演を書かせる
「ある・なし」がなく、公演作品名や第( )回公演作品として、公演回数を記載させるアンケートがありました。これも選択肢1と同じで負担感があります。
ところで、アンケートとは離れますが、過去作品の一覧はありがたい情報で、当日パンフレットに記載してほしいぐらいです。劇団HPをみればわかるかもしれませんが、受動的に観劇の都度、最新版が手に入るとありがたい。
過去作品の一覧は、物販で過去作品の台本やDVDを売る団体がある中、いつ頃の作品かなど購入の目安にもなりますし、観劇者や演劇関係者とその団体について話しをする際、観たことがない作品の話になったときにこうした一覧があると役に立ちます。団体と観客の距離を縮める有効な情報です。
質問その5 本公演に興味をもった理由・決め手
「その2 公演を知った方法」と同じようですが、少し聞き方が違います。観客は単に「公演を知った」から観にいくわけではなく、観に行く動機があるはずです。情報の入手方法を細かく聞くよりは、この質問の仕方の方が把握したい情報を得られるのではないかと思います。21団体が採用。
なので、「公演を知った方法」と「公演に観に行く決め手」をあわせて質問する団体もあります。
●質問の仕方
<実例>
・この公演に興味を持たれた理由は何ですか?
・観劇を決めた理由
・観に来たきっかけを教えてください
・ご来場のきめては?
などです。
このうち「観に来たきっかけ」を質問するアンケートの中には、「公演を知ったきっかけ」の趣旨で質問しているものがありますが、こちらに分類しました。
●選択肢
<実例>
・カンパニーが好き
・好きな劇団だから
・出演者のファン
・役者( )
・○○の脚本だから
・○○の演出だから
・関係者の過去公演をみて
・タイトル
・企画内容
・作品が気になったから
・チラシ、ポスター
・SNSでの評判、噂
・友人、知人に薦められた、誘われた
・劇場
・料金
など、公演を知った方法とは選択肢の書き方に違いがみられます。
質問その6 次回作の企画等のリサーチ
リサーチしたい内容としては
■1 次回以降の公演の参考 2団体
■2 出演してほしい役者 1団体
■3 団体に期待する企画・イベント・グッズ 10団体
■4 過去の企画やイベントでまたやってほしいこと 1団体
などがありました。
■1 次回以降の公演の参考
「死体役として観たい役者はいますか」「次は何色の作品が観たいですか」などその団体の特色に関連づけた質問で、回答方法は自由記述です。
■2 出演してほしい役者
自由記述の感想・要望の欄に書きそうな内容を質問にしています。
■3 団体に期待する企画・イベント・グッズ
イベントやグッズ販売は、企画する団体にとって重要な収入源になるのでニーズを把握できる質問です。これに関連して、団体のグッズをもっているかという質問をした団体が1団体ありました。しかし、アンケートをとらなくてもグッズの売れ行きは売上データからわかりますし、アンケートの記入時間を考えると、価値のある質問なのかは疑問です。
■4 過去の企画やイベントでまたやってほしいこと
これも公演とは別にオフ会などのイベントを企画する団体にはニーズを把握できる質問です。
質問その7 お気に入りの役者は誰ですか
出演者以外の役者の名前が複数あがるような回答が期待できれば、出演のオファーをするなどデータの利用価値があるかもしれませんが、劇団のファンや出演者目的の観客は、その劇団員や出演者の名前を記入しそうです。そうであれば応援扱いの予約数の方がシビアに数値化されます。
そのため「劇団員や出演者以外で、今後、観たい役者はいますか」のような質問なら、記入者は注目する役者さんを団体にPRしているようで、「役者を応援する」ことにつながる感じがします。
質問その8 観劇の実態に関する質問
観劇の動向に関する質問で、
■1 観劇の頻度 5団体
■2 よくみる劇団・WEB・番組など 5団体
■3 平日は何曜日に観劇にいきますか 1団体
■4 観劇WEBをみますか 1団体
■5 余暇はどのように過ごすか 1団体
■6 今回の作品は何回見る予定ですか 1団体
などの質問がありました。
■1 観劇の頻度
5団体が質問しています。
おもしろいのは回答の選択肢。団体ごとにバラバラです。
<実例>
・月に3回以上、月に2回、2月に1回、3月に1回、半年に1回、その他
・年間1本、年間2~4本、年間5~9本、年間10~19本、年間20本以上
・週に1回、月に1回、年に数回、それ以上、今回がはじめて
・月に1回、3月に1回、1年に1回、2~4月に1回、ほとんどみない
・自由記入 1団体
で月間の本数をきく団体があれば、年間できく団体もあります。
意外だったのは、年間の観劇数に対する団体の意識です。実例にある「月に3回」で考えた場合では年間36本。100本を超えるヘビー観劇者はもちろん、50本を超える観劇者も想定から外れています。36本というのは、私の場合では、1月~2月の観劇回数にしかなりません。
とここであえて記載するのは、観劇をしていると、これまでに観た作品と同じテーマでそれよりも伝わらない描き方なのに語る主宰さんがいて、観客は観客なりに眼が肥えているよと思うことがあります。
数多く観る客がその団体を観に来たというのは、それなりに期待しているからです。
なので、観劇数を把握するのであれば、もう少し選択肢を考えないと実態がみえてこないと思います。
聞くとしても「昨年は何本程度みましたか(自由記入)」ぐらいで良いでしょう。
■2 平日は何曜日にみますか
土日以外の平日に公演する時の参考になりそうな質問ですが、もしこのデータが欲しければ目的にあった細かい質問をした方がいいかと思います。
例えば、「お仕事がお休みの日は何曜日ですか」「月曜日に上演したら観にきますか」 などです。
■3 よくみる劇団・WEB・番組の情報
客層がどのような界隈の団体が好みなのか、どんなことに関心があるのかなどがわかります。
広報としては、チラシの折込先や宣伝先などの検討材料にはなるとは思いますが、作品内容に影響させるべきものではないでしょう。
小劇場演劇では作演家が描きたいものを上演し、それを観たいし、それが受け入れられなければ戯曲家としてのあり方を考えればよく、客に寄せて置きにいく必要もないでしょう。
■4 観劇WEBをみますか
観劇者の実態調査ならともかく、団体のアンケートとしてデータが役立つのか不明です。
■5 余暇はどのように過ごしますか
いまひとつ何に使いたい質問かわかりませんが、「観劇」と記入する人数を把握することで、演劇がどのくらい生活の一部なのかはわかるかもしれません。
■6 今回の作品は何回見る予定ですか
これは同一作品のリピーターがいることを前提にした面白い質問で「この人、また観にきてくれたのか」はわかります。
質問その9 個人情報(観劇者の属性)に係る質問と、個人情報保護に関する文言
■1 公演案内の希望 68団体
■2 観劇者の属性(プロフィール) 36団体
■3 メルマガの希望 4団体
■4 WSの案内希望 1団体
■5 個人情報管理に関する記述 48団体
■1 公演案内の希望
●質問の仕方
3つのパターンに分類されます。
(1)希望の有無を選ばせる 32団体
<実例>
・個人情報欄の冒頭に「次回以降の公演情報を 希望する 希望しない」
・個人情報欄の中に「DM希望 する ・ しない 」
・欄の最後に「今後のイベントのお知らせをメールでお送りしてもよろしいでしょうか YES・NO」
など、「はい・いいえ」を選択させます。
このうち、希望の有無とあわせて「すでに届いている」を入れている団体が15団体。
<実例>
「今後、公演の案内を希望しますか? □希望する □すでに届いている □希望しない」
さらに「すでに届いている」選択肢に加え、「初めて記入する」「以前書いた」「以前書いたが届いていない」「DMを解除したい」「住所変更」の選択肢を設ける団体もあります。
重複入力を防ぎたいなど団体が顧客データの管理に苦労されている感じが伝わります。一方、観劇者としては「DMの解除」は必要かもしれません。
この質問の仕方は、DMの送付するしないにかかわらず、個人情報を収集することになります。なかには「希望されない方は、よろしければお名前のご記入をお願いします」と添える団体があります。
また住所やメールアドレス以外にも年齢・職業・性別などを記入させる団体があり、必要な情報なのか疑問に思います。
(2)希望する人のみに書かせる 25団体
<実例>
・公演の案内を希望されますか? ご希望の方はお手数ですが、下記への記入をお願いします
・次回の公演などのお知らせをお送りさせていただきます。よろしければお名前等ご記入ください。
希望する場合のみ、個人情報を記入させます。必要最小限の個人情報を収集する観点から好感が持てます。
(3)書いたら強制的に案内する 9団体
これは記入欄の下に、「公演のご案内等をお送りさせていただく場合がございます。ご了承ください。」「いただいた情報は公演情報・活動情報のご案内以外には一切使用しません」などサラッと書いている場合です。
個人情報管理の徹底が求められる現在では、希望の有無など本人の意思確認は必要なのではないでしょうか。また家族に見られたくないなど、メールはいいが郵便は望まない人がいるかとも思うので、メールなのか郵送(ハガキ・フライヤー送付)なのかを明確にしたうえで、住所かメールアドレスの必要な情報を収集すべきです。
■2 プロフィール(属性)を書かせる
DMの案内をしない、あるいはDMの案内を希望する場合は氏名や住所・メールアドレスを記入させ、これとは別に、性別や年齢などのプロフィールの記入を求める団体が36団体ありました。
●質問の仕方
<実例>
・差支えなければ、プロフィールをご記入ください
・差し支えなければ、下記事項にご記入ください
・よろしければ答えられる範囲で以下の項目にお答えください
・(なにも説明なく記入欄だけある)
●記入内容
・氏名 25団体
・性別 24団体
・年齢 18団体
・年代 11団体
・住所 6団体
・住んでいる地域 5団体
・メールアドレス 8団体
・電話番号 1団体
・誰ときましたか 1団体
・何人できましたか 1団体
・演劇経験 1団体
・劇場までの時間 1団体
このうち、特徴的なのは年齢と住所は質問の仕方です。
年齢では、
・年齢を記入 18団体
・世代を選択(10代・20代・30代・40代・それ以上) 11団体
住所では
・住所を記入 6団体
・地域を選択 5団体
関東や東京・埼玉など都道府県の地域を選びます。
細かく年齢や住所を記載させる必要はないので、情報が欲しければ世代や地域で十分とおもいます。
プロフィールは顧客情報管理が目的でしょうが、DMの案内以外に何故細かく管理する必要があるのか、どこまでが必要な情報なのか曖昧なままのような気がします。
■3 メルマガの希望
■4 WSの希望
メルマガを発信する団体であれば必要な質問で4団体が採用。
WSの案内について希望をとる団体は、観劇にきた役者さんとの繋がりを探している事情がうかがえます。
■5 個人情報保護に関する記述
個人情報を収集・管理するにあたっては、個人情報の管理に厳格さが求められます。
個人情報の取り扱いに関する文言を記載していた団体は48団体。まだまだ重要性が浸透していないといえます。
●記載内容
<実例>
・お預かりしました個人情報は適切に管理し、○○以外の第3者へ提供することはありません
・本アンケートでご記入いただいた個人情報は本アンケートに関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません
・ご記入いただいた個人情報は公演のご案内をお送りする以外には使用いたしません
など。
企業であれば個人情報の管理規程を設けるのが当たり前ですが、団体がどのように住所や氏名を管理しているか、どこまでがみることができるのかなどは知りようがないので正直怖いところがあります。
例えば「ご記入いただいた個人情報は公演のご案内をお送りする以外には使用いたしません」とありますが、住所が書かれたままアンケートの感想を主催者以外が読みまわしただけで、この一文に抵触します。
現状では少なくとも個人情報に関する記述をしていれば、その慎重さを理解していると考えるしかありません。
●団体が必要とする最低限の情報しか収集しないのが基本
考え方としては、職業や学校名は必要なのか、年齢を聞く必要があるのか、聞くとしたら具体的な年齢までいるのか、E-MAILしか送らないのに住所はいるのかなど、一つひとつの情報を収集する理由を精査する必要があるといえます。
その結果、記入項目も精査され、記入の負担軽減にもつながります。
次回は、いよいよ、こんなアンケートならどうだろうと試作してみたことを綴ります
アンケートの考察 書きたくなるアンケートとは (連載その5)
⇒ こちら












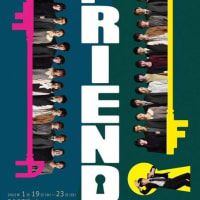







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます