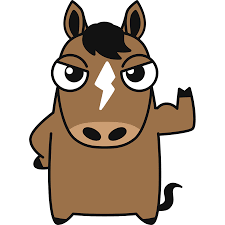JRAジャパンC「3歳ダービー以下」地に落ちた国際レース。昨年「7位→46位」評価急落の原因は「外国馬ゼロ」だけではない
昨年のジャパンC(G1)で問題提起された外国馬ゼロ問題だが、ついに危惧されていたことがIFHA(国際競馬統括機関連盟)発表の2019年世界のトップ100GⅠレースにより、公の形で世界的に認知されてしまった。
これにより公開された内容は10ヶ国37競馬場のG1レースがリストに名を連ね、1位は過去5年で4回目となるフランスの凱旋門賞(126.25)、2位はイギリスのキングジョージⅥ世&クイーンエリザベスステークス(125.75)、3位は同じくイギリスのプリンスオブウェールズステークス(124.25)となっている。(IFHA発表)
注記:( )内の数値は年間レースレーティング、【世界のトップ100GⅠレース】とは、前年の年間レースレーティングの上位100競走(2歳を除く)をランキングしたもの。
日本の主だったレースでは5位宝塚記念(122.25)、6位有馬記念(122.00)、13位天皇賞(秋)(120.75)、22位安田記念(120.00)、32位東京優駿(日本ダービー)(118.75)、36位皐月賞(118.50)、46位ジャパンC(118.00)と続いた。
違和感があるのは東京・芝2400mで開催されるジャパンCと東京優駿の比較だ。競馬の最高峰と言われる東京優駿とはいえ、3歳馬のレースであることに変わりはない。古馬一線級の集まるジャパンCのレーティングが上になるのは過去の例を見ても順当である。
近年を遡ってみても19年7位ジャパンC、67位東京優駿、18年12位ジャパンC、65位東京優駿、17年12位ジャパンC、65位東京優駿とジャパンCが常に東京優駿より上の順位で古馬の面目を保っていた。
それだけに例年だと60位台半ばである東京優駿が32位と大幅に順位を上げた側面はあれど、ジャパンC の46位という順位は例年に比べていかに低い評価がされていたのかが顕著に表れたものといえるのではないか。
これまで数多く議論されたとはいえ、改めて問題提起を振り返ってみたい。
2005年アルカセットの勝利を最後に14年連続で日本馬が勝利。外国馬の出走頭数も年々減少をたどり、ついには出走なしとなったのが2019年のジャパンC。
もはや「世界に通用する馬づくり」をスローガンに創設された、日本初の国際レースの肩書きも今となっては虚しく響く。
賛否両論はあってもその大きな原因として議題に上がるのは、超高速化しつつある“ガラパゴス馬場”の存在が大きい。
当分の間、更新されることはないと思われていた89年ホーリックスのレコードを2005年にアルカセットが2分22秒1で更新したことにも衝撃を受けたが、2018年アーモンドアイの走破時計2分20秒6はいくらなんでも速過ぎると感じたのは当然だろう。
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/gj/2020/01/post_138427.html
Copyright c Business Journal All Rights Reserved.
このレースは6着までが従来のレコードを上回る2分21秒6、7着ハッピーグリンでさえ0.1差の2分22秒2で走破している。これですらかつてのホーリックスのレコードと同じなのだからいかに時計の出る馬場状態だったかはうかがい知れる。
その一方で日本馬の多くが挑戦するヨーロッパの馬場はソフトな馬場で、地力勝負となることが多い。昨年も凱旋門賞に挑戦した馬たちはキセキ7着、ブラストワンピース11着、フィエールマンにいたってはブラストワンピースからさらに15馬身後方の12着に終わった。
レース後の関係者のコメントでもキセキに騎乗したC.スミヨン騎手は「パリロンシャンの馬場は特殊で、この粘りの強い馬場はキセキには適していませんでした」と述べ、フィエールマン騎乗のC.ルメール騎手も「馬場が重すぎて走りにくかったので、加速できませんでした。やはりもっと速い馬場が良いです」と日本の馬場との違いを敗因にあげている。
これでは外国馬の関係者からすれば立場が逆の見方となるのが日本の高速馬場であり、日本馬の悲願となっている凱旋門賞などのレースに比べるとジャパンCはそこまでしてほしいタイトルではなくなったというのが現実的だ。
また、馬場以外では単純に「日本の馬が強くなったから」という意見もある。外国の一流馬を積極的に取り入れ、日本競馬のレベルは世界に通用するところまで来たというのはわかる話だ。外国馬関係者にしても引退後に種牡馬になるクラスの馬をわざわざ馬場適性のない日本で走らせて評価を下げるリスクを冒す必要性がない。
さらにはジャパンCの現在の賞金3億円という額も、1着賞金8億円のドバイワールドカップなど、高額賞金レースがいくつも増えた。国際的にもはやそれほど高額ではなくなっている。
ではJRA側の見解はどうだろうか。「スポーツ報知」の取材で後藤正幸JRA理事長が語った内容が以下である。
後藤理事長は「馬場の違いについては、世界各国で同じ馬場ではないし、天候だって変わるもの。それを主な理由にするのは違うと思う(一部抜粋)」と馬場の違いについては否定的な見解を述べている。
次に主な理由として「やはり日本の調教馬の資質が非常に上がってきた。それを海外の関係者が、十分に認知するようになったというのもあるでしょう。各国の競馬主催者の間での勧誘の競争が、激しくなってきたと思う(一部抜粋)」と後藤理事長は馬場の違いよりは日本馬が強くなったことを評価していた様子だ。
それ以外で気になったのは検疫について「検疫制度に関しても、少々リスクを冒してでも競馬場で国際検疫ができるような仕組みを作らないといけないというので、新たに東京競馬場の内馬場に国際検疫厩舎を作ることを決めた。手放しのまま現状で来てくださいというつもりはありません」と、現状の打開策としては具体的な取り組みにも触れられていた。
JRAとしても現状のまま、手をこまねいて黙っているわけではないという危機感を持っていることは伝わった。ジャパンCの威厳を取り戻すためにも、世界的にも魅力的なレースとして評価されることを願いたい。
日本のレースに海外馬が参戦できる国際レースが
調べてみたらびっくりするほど多い
マジ驚いた
だって
今年は仕方ないとしても、過去にも海外馬が参戦した国内レースの事なんかほとんど出てこないだろ?
昔むかしには、そういえば安田記念を勝ったハートレイクとか言うのが京王杯AHだったかを使ったとかの記事を見たが
安田記念に関しては過去ハートレイク、フェアリーキングプローン、ブリッシュラックの3頭の外国馬が勝った歴史がある
スプリンターズSでも
サイレントウィットネス、テイクオーヴァーターゲット、ウルトラファンタジーが勝っている
JCは10頭以上外国馬が勝ってると思うがJCD時代はどうだったのかな
それが最近は外国馬の参加がどのレースでもほとんど見られなくなったし、JCDは消滅
JCもこのままだと消滅w
有馬記念も国際レースの筈だが過去、参加した馬いたっけ?
宝塚は数年前のワーザーが記憶に残ってるくらいだ
日本の芝コースは固いとか言われているが、それも大きな原因だろうがJDCが先に消滅した理由は違うだろ?
日本の競馬界のシステムに問題があるんじゃないのか
検疫の長さの問題は前から言われていたが今回はゲートの問題が指摘されたり
時期的な事も言われてたり
しかも賞金的にもそれほど魅力のある額じゃ無くなった事もあるが
個人的には今以上の賞金にする価値が見いだせないな
ドバイやサウジみたく潤沢なオイルマネーがあるならいいが、大借金国日本が、そんな無理してまでメンツを保つ必要あるのか?
世界に置ける競馬グレード1国を維持したいんだろうが、外国馬が参戦しにくい環境を作っておいて何をかいわんやだわ
マジ思う
JCはこれ以上外国馬参戦にこだわるな
そして賞金額は下げろ・・・・と
日本で一番のレースは有馬記念
これでいいやんけw
、