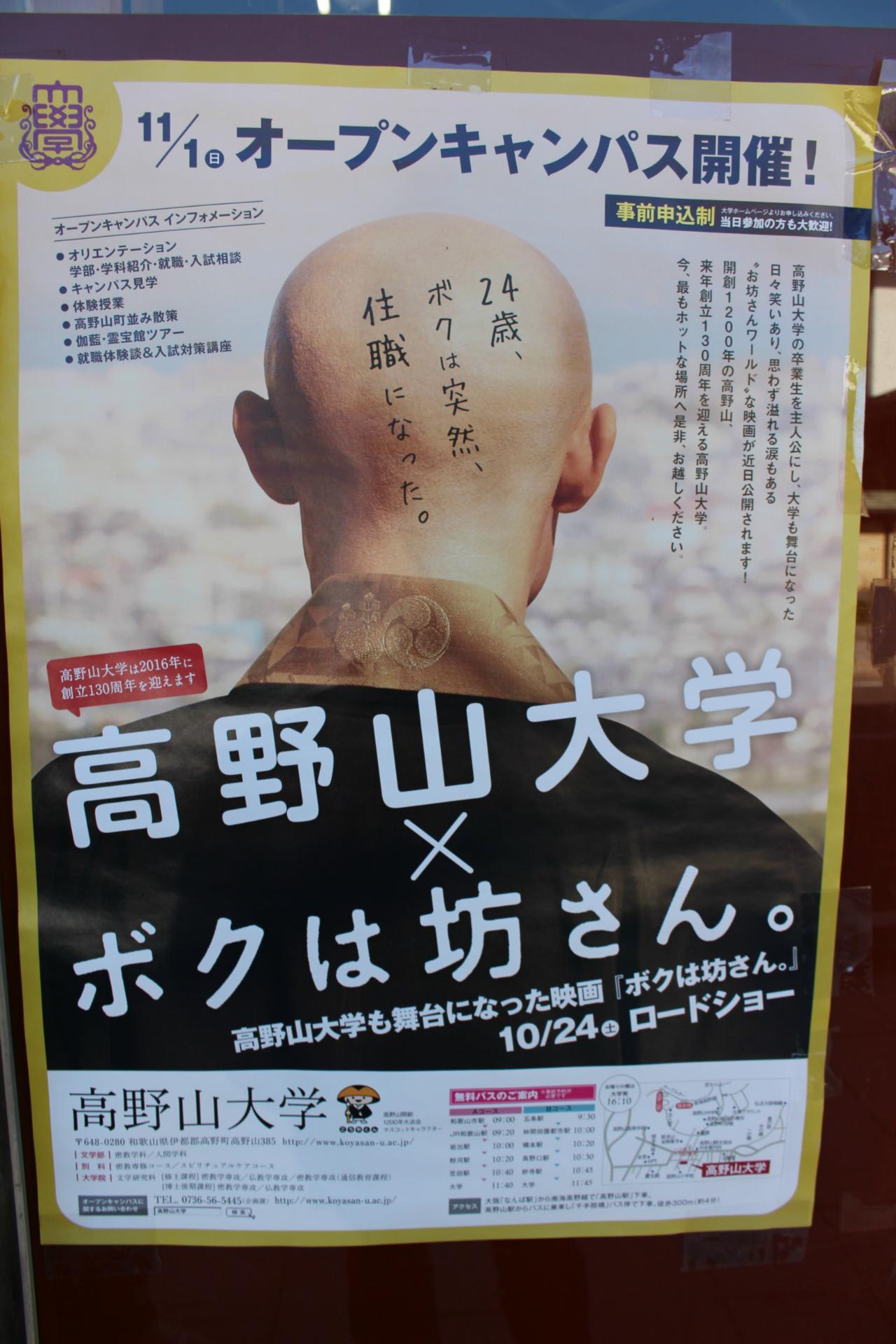極楽橋からはケーブルカーに乗ります。

さあ出発です。
高野山ケーブル
中間点では、上下線が行き違います。
高野山ケーブル
高野山駅は、南海電鉄のホームページによれば、
四季を通じて全国各地から参拝客が訪れる世界遺産 “高野山"の玄関口。高野山電気鉄道当時の昭和5年(1930)6月に開業し、高野山開創1150年祭を翌年にひかえた昭和39年(1964)12月、輸送力増強のためケーブルカーの2両連結運転を開始しました。プラットホームはコンクリート製の階段になっており、駅の地下室に据えられた出力400キロワットの巻上機2台でケーブルカーを上下に動かしています(運転速度は秒速3メートル)。標高867メートルに位置し、駅前と山内各所をバスで結ぶ、当社の代表的な観光駅です。
ということで、ケーブルカーは結構な高さを上ります。

ここからは、バスです。
南海の専用道を通り、女人堂から、奥の院へ向かいます。

女人堂を過ぎると、高野山の灯篭が。
高野山が女人禁制のころ、高野七口と呼ばれる七つの入り口には、高野山に入ることを 許されなかった女性が高野山を遥拝するための参籠所としてそれぞれ女人堂が設けられていました。
現存するのはこの不動坂口に残るこの女人堂だけだそうです。


高野山奥の院には有名な武将のお墓が点在します。
織田信長、豊臣家、徳川家、明智光秀、石田三成、伊達政宗、武田信玄・勝頼、上杉謙信。
誰もが一度は耳にしたことがある武将たちの名が連なります。
そんな奥の院の雰囲気を味わうには、バスで奥の院の終点まで行かず、手前の奥の院口で降りましょう。
荘厳な杉の中を2キロほど歩いて向かいたいです。