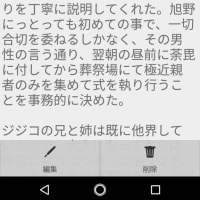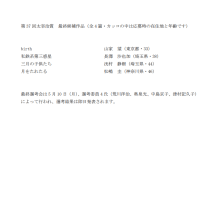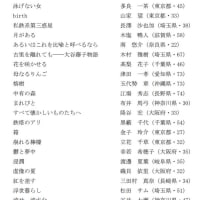手紙を読み終えて一呼吸置いてからページを揃えて元の通りに畳んでいると,ニコニコと微笑みながらハーデット氏は幸せそうに話し始めた。
「こんな手紙を息子から貰うなんて・・・」
3年ほど前,ジェイソンは大学を出るとすぐに軍隊に志願したのだという。それはハーデット氏にとっては思いも寄らないことで,最初は強く反対したが,強気の息子を宥めることができなかった。それで仕方なく,軍隊の厳しさを身に染みて分かっている彼が根回しをして,安全な事務職に息子が配属される様に画策した。そのことが返って息子の気持ちを逆撫でして親子の関係に多少なりとも亀裂が入った様だ。以来,ジェイソンは父親との連絡を絶ち,まるで反抗するかの様に敢えて危険な任務に就く事を希望し続けたそうだ。それでも,この年の最初に勃発した湾岸戦争で,彼が所属する部隊への派遣命令は下されなかったらしい。ハーデット氏には本当に身に覚えのないことであったが,ジェイソンはそれも父親の策謀なのだと思い込んでいた様だ。
「ジェイソンさん,怪我が大したことないといいですね」
僕は手紙をゆっくりとハーデット氏に返した。
「ありがとう,ソーヤン。・・・泣いてるのですか」
「いえ・・・」
僕の両目からは無意識に涙が零れ落ちていた。その時の僕は,ホッとしたせいか,さっきまでの緊張の糸が完全に解けて全身が弛緩していく様な感覚を覚えていた。
「やさしい息子さんですね・・・。僕も日本の両親を思い出しました」
「・・・やはりあなたは・・・」
そう言いかけたハーデット氏は,僕の涙に釣られたのか,胸ポケットから取り出したハンカチで目元を拭いながら手紙を仕舞った。
「いや,もういいのです」
「ハーデットさん・・・?」
「ソーヤン,息子に会ってもらえますか」
「僕もジェイソンさんに会いたいです」
「そうですか,それは光栄です」
「クリスマスの週は・・・確か28日が土曜日ですね。どうですか」
「必ず」
「ではこの時間にここで・・・」
ハーデット氏は2,3度頷いてから,テーブルを両手でポンと叩くと,「飲み直しませんか。私に奢らせてください」と言ってカウンターに向かおうとしたが,思い立った様に名刺を僕に差し出した。
「遅ればせながら・・・」
僕は名刺に記された名前を見てようやく合点がいった。僕が“Wimpy”と呼ばれていたように,ジェイソンの源氏名が“Victor”だったんだ。思い起こせば,赤いベレー帽にサングラスを掛けたイギリス兵,そして気味の悪い笑い声を上げる,僕たちが「ガードマン」と呼んでいた連中の1人は同一人物だった。ああ,そう言えば確か喘息もちだと言っていたっけ。
「ビクター・ハーデットさん?」
「ええ。息子に劣らず大それた名前をつけられたものです。よろしく」
ニッコリと微笑んだ老人はそう言い捨ててから大勢の客の間を縫ってカウンターの方へ進んだ。
勝利という意味の“victory”を想起させる名前は,まるで僕の仇名の“wimpy”とは正反対のイメージを持っていた。僕は決してジェイソンが思う様な英雄じゃない。僕のことを何度も助けてくれたビクターこそが英雄ではないのか。複雑な心境で自分が何者なのかも未だ分かっていない僕は自分自身に問いかけた。。
「Are You Wimpy?」
それから深呼吸を1つしてから自答した。
「Sure, I am.」
そう呟くと,僕は込み上げる笑いを抑える事ができなかった。リアノは,よくもまぁピッタリの名をつけてくれたものだ。その通り,僕は何も成し遂げられないただの弱虫なんだ。
手紙にも書いてあったが,ジェイソンは僕の心情を計るためにライフルに弾丸を込めなかった。ならば父親の名前を使うことでハーデット氏の心情を計っていたのだろうか。そうでなければ,父親の名前を騙ることはないだろうに。
円山さんを探す目的で2度目のミッションに参加した僕だったが,その望みは叶えられず失望の内に帰国した。僕は想像を絶する過酷な状況に置かれ,自分自身が生きていくことすら危ぶまれていた。帰国直前に行方不明になったビクターのことも気がかりだったが,そのビクターがこうして生き延びていて,しかも円山さんの情報を手に入れてくれたというのは朗報だった。ただ,その時の僕は円山さんの様子を詳しく知るのを少し恐れていたかもしれない。僕が偶然目にしたあの新聞には鬼のような形相の円山さんが写っていたからだ。円山さんは間違いなくイレイナの為に武器を取った。それはイレイナを守る為か,それとも・・・。いずれにしても僕とは違うベクトルを彼は抱えていた。アジャやイーゴを失った僕の心には悲しみと同時に怒りと絶望が渦巻いていたはずだが,それは決して僕のことを復讐の路へとは駆り立てなかった。もしそれが僕のような不信心な者への神様の思し召しで,最愛の人たちを失った空虚を埋めるような新しき出会いを授けてくれたのならば,それは何と我が身の幸いなることかと思っていた。そんな僕にとって円山さんの心情はいかなるものか計り知れぬものがあった。
「Cheers!」
ハーデット氏と僕はグラスを頬まで上げて,この日の出会いを祝福し合った。ドロリとしたギネスの舌触りの向こうから爽やかな炭酸が僕の口の中の傷を微かに刺激するのと同時に殴られた顎の左側がズキズキと疼いた。ハーデット氏は一気に飲み干したパイントグラスをコンという乾いた音をさせながら優しくテーブルの上に置くと,気持ち良さげにフーっと息を吐いて微笑みかけた。それはあの「神の息吹」とは似ても似つかない生に満ちた勢いを湛えていた。僕の様子を伺う彼の視線に煽られる様に,僕も残りのビールをゴクゴクと飲み尽くした。僕はハーデット氏と同じように息を吐いてグラスを彼のグラスの脇に並べた。そして「皆さんのところへ戻りましょう」というハーデット氏の合図で僕たちは何事も無かったかの様にテーブルを後にした。外の気温は下がりつつあったが,ブランズウィックは客の熱気でポカポカと暖かかった。あと3週間ほどで新しい年を迎えようという週末は,賑やかな雰囲気の中で蕩ける様に過ぎていくのだった。
-THE END-