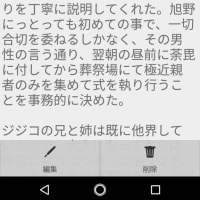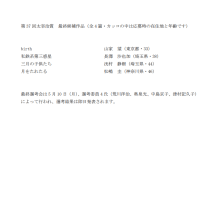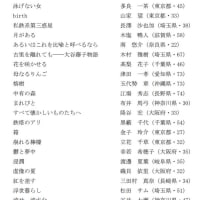「ね、ね、ジジコの話してよ」
夏来という女生徒が授業を進ませてたまるかとばかりに切り出した。この高校の定時制で教鞭を執り始めて丸1年が過ぎようというのに、旭野は相変わらず生徒達のペースに巻き込まれて、年度初めに計画した内容を熟せずにいた。そんな状況に若干の焦りはあったものの、わざと旭野に教科書を開かせまいとする生徒達が、これまで貯めてしまった単語練習の宿題に一生懸命に取り組んでいるのを知っていたから、旭野自身も敢えて策略に乗ってみるのも良い気がしていたし、雑談の方が偉そうに英文法を解説しているより自分の性に合っていて楽しいというのが本音といったところだった。
「ジジコか・・・。もう、ネタ切れなんじゃない?」
「じゃ、同じ話でもいいからさ」
このクラスの生徒達は誰もが複雑な家族の出で、夏来なんかは「アタシには種違いの弟が2人いて・・・」なんて気楽に語り始めるものだから、旭野もついつい自分の身の上話をひけらかしてしまったのが運の尽きだった。本来教えなければならない教科書をそっち退けて、人生相談をしたりエンカウンター張りにお互いに話し合ったりして時間を潰すことが多くなっていたから、英語というよりは道徳か学活といった雰囲気が漂っていた。ここで「ひけらかす」と言ったのは、教室では何かと自分の“不幸自慢”が飛び交うような有様を呈していて、ある種の「不幸対決」の様相を呈していたということだ。
旭野も自分自身が他の友達よりも特別な子供時代を過ごしてきたことを心のどこかで自負としていて、彼らが持ちかける日々の憂いなど「大したことない」なんてあしらいつつ、ついぞ自分の人生を振り返って語ることがあった。それでも、旭野は、そういった身の上話も結局は体験した本人しかわからないことがほとんどで、そんな風にお互いに声に出して鬱憤を晴らすというエンカウンターなのだという事にも納得していた。
“ジジコ”というのは旭野の亡くなった父親のことだ。所謂「破天荒」な父親で旭野の次男が誕生する前年に海の事故で突然亡くなったから、その年13回忌を迎えたばかりだった。ジジコは次男が旭野の女房の身体に宿っていることすらも知ることなく死んだ。
ジジコが亡くなったとき、旭野は中学校の臨時講師として働いていて、1年契約ではあったけれどやったこともない野球の部活も持たされて土日もなく毎日朝早くから深夜まで働いていたから、既に2ヶ月以上ジジコが住む鹿嶋の実家に足を運んでいなかった。自宅から車で50分ほどかかる実家には女房が気遣って長男を連れて時々遊びに行っていたが、「久々に休みができたから」とジジコが死んだ週末には一家で出掛ける約束をしていた。実は、女房の懐妊報告が目的でもあった。
水曜日に台風が去ったばかりで、ジジコはまだ波が荒い海に出て旭野たちに海の幸を振る舞おうと考えていたのだろう。堤防から波に浚われて沖で漁船に引き上げられた時、ジジコは必死で小さなクーラーボックスにしがみついて辛うじて波間に浮かんでいたという。
鹿嶋警察署から電話をもらった時間、3年生の副担任をしていた旭野はまだ高校受験の面接指導の最中だった。丁度その時期に、電話で警察や弁護士を騙った教員をターゲットにした詐欺が横行していたから、父親が溺死したという唐突な話に最初は耳を貸さなかった旭野も、父親の車のことを詳しく説明されて一気に真実味を帯びてくるのを感じた。
「何も身分を証明するものがなくてですね、ポケットにあったトヨタ車のキーが手がかりだったものですから・・・」
ジジコが流された堤防は元々立ち入り禁止で、それでも良い漁場だという口コミで釣り好きには人気の場所だった。事故が起きて警察が来た途端、同じ場所で釣りに興じていた輩が一斉に散った様で、たった1台だけ堤防下の道路に駐車されたままだったマークⅡとその鍵が合ったのだという。車の中にあった免許証で顔を確認し間違いないということで、最初は実家の母親のところに直接出掛けたのだが信じてもらえず、その母親からインターホン越しに旭野の方に連絡してくれと頼まれたという顛末だった。
信じたくない話だったし、臨時講師というのは教諭達に比べ年齢に関係なく弱い立場にあったから、そう簡単には私用で早退するなどと言い出せるはずもなく少々躊躇っていると、電話を取り次いだ事務員に怪訝な顔で警察から何の用か尋ねられて説明すると、流石に内容が内容だけに「すぐに退勤しなさい」という命令が校長から下された。後に残した生徒達のことも気になったが、未だ警察の話を信じ切れず半信半疑のまま旭野はそそくさと実家に向かった。
2日ばかり早くなってしまった約束の再会だったが、警察署に近付くにつれて疑惑の念が少しずつ偽りであって欲しいという願望に変わって、旭野は車のハンドルを握り締めながら「まさか。そんなことあるわけない」と幾度となく自分自身に言い聞かせていた。
数年前に実家の両親と仲違いして家を飛び出していた十歳年上の腹違いの姉に電話すると、彼女も実家に向かっているところだと言っていた。電話の向こうで泣いているのがわかって、それが旭野には不思議で仕方なかった。なぜなら、旭野自身もジジコから随分と酷い目に合わされていたし、義姉に至ってはジジコとは犬猿の仲で、事ある毎に「早く死ねばいいのに」などと口走っていたからだ。それどころか、酔った勢いでパタークラブを取り出して既に寝床に入ったジジコの頭を小突いてやろうかなんて冗談すら言う始末だった。だから、義姉の啜り泣くような声に白けた様な気分にすらなって、「嘘であって欲しい」と願いながらも、旭野自身は冷静さを取り戻してひたすらに職場からは2時間弱かかる目的地を目指していた。