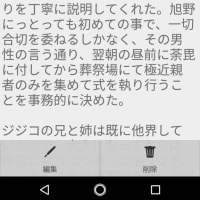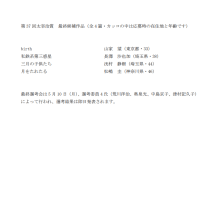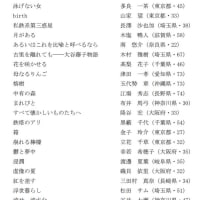1時間ほどすると,ごった返した人の河は途切れ始め,車列は再度舗装路へと戻って若干ではあるが快適さを取り戻した。それでも時折すれ違う車や一団を避ける様にして道を外れるもんだから,その激しい揺れの度に舌を噛みそうになりながら更に1時間ほど我慢していると,コンクリートだけで仕立てられた無機質な3階建ての建物の脇で車が停車した。
僕たちが荷台から降りようとしていると,木材で拵えたライフルのオモチャを抱えた小さな男の子たちが3人,トラックの後ろ側に回り込んで何かを叫んだ。
ゲイリーがとっさに両手を掲げて降参したので,僕もそれに習って子供たちに微笑みかけると,彼らが嬉しそうに「ダダダダ・・・」と口で銃声を真似ながら走り去った。道を行き交う車や人は疎らだったけど,辺りは有事とは思えないくらい静かで小鳥が囀りながら飛び交ってるのさえ確認できた。通りの向こう側でも人々が談笑していて町は平和そのものだった。
僕は少しホッとしてゲイリーと軽く微笑み合いながら赤いベレー帽の兵士達に続いて建物の中へ進んだ。
部屋には業務用の机がいくつか並べられていて完全武装をした制服姿の男が数人談笑していたが,僕たちが入室した途端黙り込んで一斉にこちらを睨んだ。その迫力に戸惑う僕たちに気づいたラフな白シャツを着た小太りの男性が入り口近くのカウンターで手招きしながら英語で話しかけてきた。
「ようこそ警察署へ」
僕たちは愛想の良いその男性の指示に従ってバインダーに綴じられた一覧表にサインをして,滞在についての説明を英語で5分ほど受けた。
「でかけてみますか」
男性が振り替えって自国語で呼び掛けると,奥の方で休憩していた警官というより兵士といった装備の4人が勢い良く立ち上がって壁の棚に立て掛けてあるカラシニコフを1丁ずつ手に取って弾装を1度引き抜いて確認してから一斉に装着した。その時の軽いカシャンという金属音が気持ち良く揃ったので感心していると,偶々目が合った若い兵士がニヤリとして首を捻って「ついてこい」といった具合に僕たちを先導した。彼らに促されるようにして表に出ると,小振りなラーダニーヴァ2台に僕たちが乗り込んで,その後からどっしりとしたランドローバーが続く流れになっていた。僕はゲイリーと1台目に乗り込んだ。フロントシート全体を前に倒して乗り込むと,思っていたより広い車内とトラックの荷台とは比べ物にならないフカフカのリアシートに感激したのも束の間,まだ「ガードマン」たちとは落ち合っていなかったことを思い出して,同行している武装警官が僕たちの安全を保証するものではないことに何となく不安を感じていた。
出発して30分ほど市中を巡ると,ちょっとした商店街の様な通りで,僕たちの車の助手席の「警官」が運転士と軽く会話を交わした後,停車した場所より50mくらい後ろの花屋にかけて行った。すると,運転士が後部座席の僕たちに向かって,たどたどしい英語で「奥方の誕生日プレゼント」を買いに行ってるんだと説明してくれた。
庁舎での最初の印象とは異なる警官達のおおらかな態度にある種の安心感を覚えて軽く胸を撫で下ろしていると,今度は舗道を歩いていた2人組の少女が車に近付いてきて,よれよれの紙箱の中に5つほど並べてあるクッキーを見せてきた。僕は手動式の窓を開けて彼女たちの話を聞こうとしたが,土地の言葉だったから全くわからない。ポカンとしてるのを見かねた運転士が単語単位で英語に訳してくれたのだが,詰まるところ彼女達が持っているクッキーを買って欲しいということらしい。
僕はブリュッセルで貰った3枚の紙幣のことを思い出して,どうせ使い道も分からなかったから,その1枚をポケットから出して渡すと,彼女たちは驚いた様な表情をして箱を2つ共乱暴に僕に預けて紙幣をもぎ取ったかと思うと甲高い歓声を上げて去って行った。彼女らの幸せな様子が嬉しくなって,僕が片方の箱の中に敷かれていた紙にクッキーを全て包んで腰ベルトにぶら下がっていたバッグにしまっていると「ずいぶん高いクッキーだな」と鼻で笑いながら呆れた様に運転士が言った。ゲイリーも首を振りながらクスクスと笑った。
その時だった。
突然後ろの方からズシーンという爆音が轟いて車体が前方に一瞬フワッと浮かんだ。シートバックに頭を押し付けられる様な衝撃を感じて,僕は思わず両手でヘルメットを押さえて伏せた。数秒の間,車のボディに砂の様な物が降り注いでいる音がしていた。
すぐに人々の悲鳴が響いてきて,それに混じってタタタタという先程の子供達の声真似とは違った機械的で冷たい本物の銃声が遠くで鳴り始めた。気が動転して祈る様な気持ちだったのか,なぜか警察署の前でふざけていた子供達を思い出しながら後ろを振り替えると,数十メートル奥の方で大きな火柱が上がっていて,そこから大勢こちらへ向かって走ってくるのが目に入った。
運転士が慌てて車から降りて折り畳んでいたライフルの銃床を伸ばしながら民衆とは逆の方へ走って行ってしまった。ゲイリーも彼を追おうとしたがシートの倒し方が分からなかったらしく,僕が倒した助手席側から2人共ヘルメットを車の天井にガツンガツンとぶつけながら順番に飛び出した。
僕たちが警官達と同じ方向に走ろうとしていると,最後尾にいたイギリス兵たちが車の窓から腕を出して「だめだ」と叫んでいた。僕が理由を問いただすと「これは関わるな。彼らに任せろ」と怒鳴っていた。
そうこうしている間にも表情をなくした民衆が青白い顔で大慌てで逃げて来る。遠くから聞こえる銃声がどんどんと増える一方で,悲鳴は止んで人々がただ黙って走って逃げていく足音だけがパタパタと聞こえて不気味だった。
僕たちが荷台から降りようとしていると,木材で拵えたライフルのオモチャを抱えた小さな男の子たちが3人,トラックの後ろ側に回り込んで何かを叫んだ。
ゲイリーがとっさに両手を掲げて降参したので,僕もそれに習って子供たちに微笑みかけると,彼らが嬉しそうに「ダダダダ・・・」と口で銃声を真似ながら走り去った。道を行き交う車や人は疎らだったけど,辺りは有事とは思えないくらい静かで小鳥が囀りながら飛び交ってるのさえ確認できた。通りの向こう側でも人々が談笑していて町は平和そのものだった。
僕は少しホッとしてゲイリーと軽く微笑み合いながら赤いベレー帽の兵士達に続いて建物の中へ進んだ。
部屋には業務用の机がいくつか並べられていて完全武装をした制服姿の男が数人談笑していたが,僕たちが入室した途端黙り込んで一斉にこちらを睨んだ。その迫力に戸惑う僕たちに気づいたラフな白シャツを着た小太りの男性が入り口近くのカウンターで手招きしながら英語で話しかけてきた。
「ようこそ警察署へ」
僕たちは愛想の良いその男性の指示に従ってバインダーに綴じられた一覧表にサインをして,滞在についての説明を英語で5分ほど受けた。
「でかけてみますか」
男性が振り替えって自国語で呼び掛けると,奥の方で休憩していた警官というより兵士といった装備の4人が勢い良く立ち上がって壁の棚に立て掛けてあるカラシニコフを1丁ずつ手に取って弾装を1度引き抜いて確認してから一斉に装着した。その時の軽いカシャンという金属音が気持ち良く揃ったので感心していると,偶々目が合った若い兵士がニヤリとして首を捻って「ついてこい」といった具合に僕たちを先導した。彼らに促されるようにして表に出ると,小振りなラーダニーヴァ2台に僕たちが乗り込んで,その後からどっしりとしたランドローバーが続く流れになっていた。僕はゲイリーと1台目に乗り込んだ。フロントシート全体を前に倒して乗り込むと,思っていたより広い車内とトラックの荷台とは比べ物にならないフカフカのリアシートに感激したのも束の間,まだ「ガードマン」たちとは落ち合っていなかったことを思い出して,同行している武装警官が僕たちの安全を保証するものではないことに何となく不安を感じていた。
出発して30分ほど市中を巡ると,ちょっとした商店街の様な通りで,僕たちの車の助手席の「警官」が運転士と軽く会話を交わした後,停車した場所より50mくらい後ろの花屋にかけて行った。すると,運転士が後部座席の僕たちに向かって,たどたどしい英語で「奥方の誕生日プレゼント」を買いに行ってるんだと説明してくれた。
庁舎での最初の印象とは異なる警官達のおおらかな態度にある種の安心感を覚えて軽く胸を撫で下ろしていると,今度は舗道を歩いていた2人組の少女が車に近付いてきて,よれよれの紙箱の中に5つほど並べてあるクッキーを見せてきた。僕は手動式の窓を開けて彼女たちの話を聞こうとしたが,土地の言葉だったから全くわからない。ポカンとしてるのを見かねた運転士が単語単位で英語に訳してくれたのだが,詰まるところ彼女達が持っているクッキーを買って欲しいということらしい。
僕はブリュッセルで貰った3枚の紙幣のことを思い出して,どうせ使い道も分からなかったから,その1枚をポケットから出して渡すと,彼女たちは驚いた様な表情をして箱を2つ共乱暴に僕に預けて紙幣をもぎ取ったかと思うと甲高い歓声を上げて去って行った。彼女らの幸せな様子が嬉しくなって,僕が片方の箱の中に敷かれていた紙にクッキーを全て包んで腰ベルトにぶら下がっていたバッグにしまっていると「ずいぶん高いクッキーだな」と鼻で笑いながら呆れた様に運転士が言った。ゲイリーも首を振りながらクスクスと笑った。
その時だった。
突然後ろの方からズシーンという爆音が轟いて車体が前方に一瞬フワッと浮かんだ。シートバックに頭を押し付けられる様な衝撃を感じて,僕は思わず両手でヘルメットを押さえて伏せた。数秒の間,車のボディに砂の様な物が降り注いでいる音がしていた。
すぐに人々の悲鳴が響いてきて,それに混じってタタタタという先程の子供達の声真似とは違った機械的で冷たい本物の銃声が遠くで鳴り始めた。気が動転して祈る様な気持ちだったのか,なぜか警察署の前でふざけていた子供達を思い出しながら後ろを振り替えると,数十メートル奥の方で大きな火柱が上がっていて,そこから大勢こちらへ向かって走ってくるのが目に入った。
運転士が慌てて車から降りて折り畳んでいたライフルの銃床を伸ばしながら民衆とは逆の方へ走って行ってしまった。ゲイリーも彼を追おうとしたがシートの倒し方が分からなかったらしく,僕が倒した助手席側から2人共ヘルメットを車の天井にガツンガツンとぶつけながら順番に飛び出した。
僕たちが警官達と同じ方向に走ろうとしていると,最後尾にいたイギリス兵たちが車の窓から腕を出して「だめだ」と叫んでいた。僕が理由を問いただすと「これは関わるな。彼らに任せろ」と怒鳴っていた。
そうこうしている間にも表情をなくした民衆が青白い顔で大慌てで逃げて来る。遠くから聞こえる銃声がどんどんと増える一方で,悲鳴は止んで人々がただ黙って走って逃げていく足音だけがパタパタと聞こえて不気味だった。