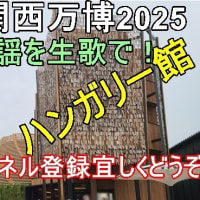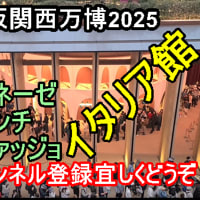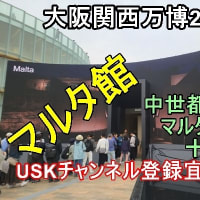八重垣神社の宝物殿には、893年に巨勢金岡が描いたといわれる6神像の板絵3枚が残されている中央にはスサノヲとクシナダヒメ、右に天照大神とイチキシマヒメ、左にはアシナヅチとテナヅチが描かれている。巨勢金岡といえば、以下のように平安夢柔話のなかに登場する人物である。ちなみに、八重垣神社の宮司、佐草俊邦氏は素戔嗚命とクシナダヒメの子、アオハタサクサヒコの子孫であるという。
春日権現験記絵といって最高峰の大和絵の話で、宮廷絵師の高階隆兼によって描かれた全20巻の絵巻である。神がひき起こす不思議な出来事の数々が57の物語で表されている。春日大社はもちろん藤原氏の氏社で、春日権現験記絵には氏社の摂社・若宮大社の前に貞慶が春日明神の勧請のために詣でている姿が第16巻に描かれている。この貞慶を描かせたのは時の左大臣・西園寺公衡で、藤原氏一族の繁栄を祈願して製作させた。近年、本絵巻の構成や詞書の内容に貞慶執筆の春日信仰にまつわる説草が深く関係していることが明らかになった。ところで、時の左大臣の家系を遡ると蒼蒼たる面々を見つけることができる。藤原1000年の栄華を誇った道長の系統ではなく閑院流藤原氏の系統にあたり、祖は藤原師輔の十二男・公季です。ついでなので公季について記載すると、母は醍醐天皇皇女康子内親王。伊尹・兼通・兼家・高光・為光の異母弟ということになります。公季は生まれて間もなく母を失い4歳で父を失います。そこで、姉の安子(村上天皇皇后)に養われ、親王たちと同じように内裏で育てられます。内裏で育ったため、「自分は高貴な生まれだ」という自負があったようで、妻も皇族・有明親王(醍醐天皇皇子)の娘です。康保四年(967)に叙爵し、永観元年(982)に参議、長徳元年(995)に大納言となり、その後道長政権下で内大臣を長く勤め、最終的には太政大臣となっています。居住していた邸宅にちなんで閑院と号し、その後裔が「閑院流」と呼ばれることとなります。この閑院第は、二条大路南、西洞院大路西に所在し、もと左大臣藤原冬嗣第で、巨勢金岡が水石を配した名所であり、これを公季が伝領したと伝えられます。(『拾芥抄』中)。公季は、孫に当たる実成女が当時の大納言藤原能信(道長男)と結婚した際、この第宅を能信に譲り、彼自身は息子の実成の第に移っています。藤原実資はこのことに関し、太政大臣たる者が旧居を捨て、小宅に移るのは後代の謗りを忘れたものとする深覚(公季の同母兄)の非難に同調し、たとえ譲るにしても同居し、一生閑院を去るべきではないと日記に書き遺しているという。「平安夢柔話より抜粋」