また、車の運転の話題です。
エンジンブレーキをエンブレというそうです。
前の車がエンブレを使うとウザイと思う人もいるようです。
そんなニュースを見てブログを書く気になりました。
私は、エンジンブレーキを多用しています。
できるだけフットブレーキは使わないようにしています。
オートマチックになってから、エンジンブレーキが利かないので不便です。
下り坂では、シフトダウンすることが多いです。
そういえば、yarisというブログも書きました。
車を運転する時は、広い道だともっとスピードが出せるのにと思いますが、白バイによる検挙やネズミ捕りが嫌なので、そんなにスピードを出しません。
昔は25㎞/hを超えると免停になるようなので、そこまでにしました。
最近は、制限速度から10キロ超えたぐらいでも捕まるとニュースに書いてあるので、あまりスピードは出しません。
単にお金を払うのが嫌なだけです。
人が歩きそうなところでは、どうしても飛び出しとかあるので、あまりスピードを出したくありません。
家の玄関の前で、「あれをするのを忘れていた」と思い出して、門から飛び出したということもありました。
高齢者の行動は、小さい子供の行動と同じようです。
小さい子供を見るとスピードを落とす人は多いと思いますが、高齢者を見て、スピードを落とす人は少ないようです。
住宅地でスピードを出す人は、結構いますが、人が飛び出してこないとよいけど、と思ってしまいます。
結局、広い道では、スピードは出ますが、制限速度近辺の一定の速度で走るしかないと思っています。
高速道路でなければ、60㎞/h、50㎞/h、40㎞/hぐらいで走ります。
50㎞/hと思えば、±10㎞/hなら、ほとんど一定の速度で走っているように思います。一定の速度と言っていますが、50㎞/hの値になるようには、走れません。あおり運転されるのが嫌なので、速度は微妙に変えますが。
私は、運転する時は、だいたい制限速度で走ります。今はあおり運転とかあるので、人が出てきそうにないところでは、10㎞/hはオーバーするかな?
どこでもそんな速度しか出せないので、ほとんど一定速度で走っています。
どの車でも、普通の道を100㎞/hで走ると、暴走していると言われるので、隣の車より10㎞/h程度早いだけではないでしょうか?
でも、隣の車よりちょっとでも前に行こうと競っているように見えることもあります。
燃費の問題もあるので、制限速度内でできるだけ一定速度で走るようにしています。
下り坂ならエンジンブレーキで降りますが、上り坂では、一定の速度を保つように、アクセルを、ふかし気味にします
というように走っていると、不思議な車を見かけます。
上り坂では、だんだんスピードが落ちてくる車がいるようです。
あおりたくなりますが、そんなことはしません。
そんな車に限って、下り坂では、スピードがつくみたいです。
いつも、アクセルを同じ程度しか踏んでいない?
登りは、自然とスピードが落ちるし、下りは、スピードが出る?
そんな車がいると、その車の前後は走りたくないので、離れるようにします。
ついて行っても、登りで追いついて、下りで離されることになります。
トラックは荷物を積んでいるので仕方ないと思います。
乗用車で、スピードが落ちてくるのは、アクセルをいつも一定の量だけ踏み込んでいるから?
そんな車を見かけないですか?
横断歩道について調べようと思ったきっかけは、朝日新聞の記事を見たことでした。
「ドライバーが標識見えないのに、『違反』。長野県警で不適切検挙73件」という記事を見ました。他の報道各社でも、長野県警が発表したことを書いているみたいでした。
その記事を理解するのが、私には難しかったです。
私が理解したことを書きます。正しいかは知りません。
横断歩道は、地面に書いたゼブラ模様で表していると思っていました。どうもかってにそう思っているだけで、こんな横断歩道のマークが、その手前に必要なようです。

また、この先に横断歩道があるというひし形マーク(ダイヤマーク)を地面に書くこともあるみたいです。
横断歩道の標識は必要みたいですが、ひし形マークは、必要とは、書いてありませんでした?
朝日新聞には、長野県 東敦賀町の交差点と書いてありました。
写真も載っていました。
googleマップで、東敦賀町 長野市で調べてみました。
下図のマップが出てきました。

ストリートビューと合わせて見ると、たぶん、ココス長野柳町店からセブンイレブン長野鶴賀店に向かう通りが、北長野通りが交わる交差点のことのようです。
記事にもあるように信号のない交差点みたいです。
この地図では、5差路になっているように見えます。
5差路になっていますが、直角に交わっているとして、こんな図を書いてみました。
TBSに書いてあったのが、わかりやすかったのですが、そのままコピーできないし、交差点が違うようなので、慣れていませんが、作ってみました。

朝日新聞には、左側から車が右折する前に、横断歩道の標識が見えないと書いてありました。たぶん、見えないというより横断歩道の標識がなかったのではないかと思います。
縦の通りが北長野通りです。
もともと、北長野通りだけにしか横断歩道がなく、標識も北長野通りにしかないようです。記事には、何もそのことには書いてありませんでした。
前方に横断歩道があれば、横断歩道の標識も付けるのだと思います。
普通の交差点は、このようになっていると思います。

横断歩道が4方向にあるので、それぞれの道に横断歩道の標識があるみたいです。それで直進するときはもちろん、右折や左折するときも、標識が見えるようになっています。
北長野通りを横切っている道には、横断歩道はないみたいです。
そうなると標識もないみたいです。
それが問題になったのかと思います。
車が右折した時に歩行者の横断を邪魔したというので、捕まって?、反則金も払ったようです。
右折する場合に備えて横断歩道の標識がいるように書いてありました。
右折したときに、横断歩道の標識が見えないからといって、右折する車のために横断歩道の標識を付けるのは、無駄でしょう。
ゼブラマークで十分ではないかと思います。
話は変わりますが、日本では、交通標識は、とっても多いと思います。
各国比較があれば、日本は断トツの一位になるのでは?
さらに標識を増やすことを考えなくても良いのでは?
最近気が付いたのですが、狭山ニュータウンは、ほとんどの道が最高速度が40㎞/hになっているようです。それで、狭山ニュータウンから泉北ニュータウンに接続する道も最高速度が40km/hになっているみたいです。2車線の道路ですが。ときどき交通取り締まりもしているようです。
40㎞/hの標識がたくさんついています。
どこかに、狭山ニュータウンと泉北ニュータウンは40km/hになりました。と広報すれば、良いだけでは?
40㎞/hのゾーンの入り口には、大きく40㎞/hになりましたとか看板は必要だと思いますが。
そういえば、海外のカーナビには、速度制限が表示されているのもありました。何年か前に乗ったレンタカーには、ありました。
ヨーロッパでは、10㎞/hを超えただけで、カメラで撮られると聞きました。詳しくは知りませんが、レンタカー屋に請求がいくみたいで、レンタカーを借りるときに、クレジットカードも登録しました。
でも、大丈夫みたいでした。
集落があると30㎞/hになりますが、それが終わったという標識だけあって、次は何㎞/hとかは書いてありません。気になりました。
日本のカーナビでは、制限速度が表示されるというのはあまり聞いたことありません。標識を認識できるような機能を追加するとか見た記憶があります。
たくさん標識があるので、見落としても、カーナビに出ていないという人が現れるのを警察やメーカーは恐れている。クレーマーは、どこでもいる?
それはさておき。
日本では、こんな交差点は、たくさんあるように思います。
他の県警では調べていないだけ?
記事では、群馬県で、同様の不備が見つかったので、長野県警が昨年の12月から調査を始めたそうで、3月に発表したそうです。
ひょっとしたら、警官を派遣して、交差点を調べた?
ストリートビューでもわかると思うけど。
話は変わりますが、狭い道から、大きな道に出るのは、私は苦手です。トラブルが多いので、嫌いです。
特に一方が、渋滞していると、こっちが優先だと思って、渋滞していない方は、平気でスピードを上げる車がいます。そんなに急いでいるのでしょうか?
毎日が日曜日の高齢者とは違うと思います。
そういう車の運転手に限って、こんなとこから車が出てくるとは思わなかった、というのではないかと想像します。
今は、テレマチックス自動車保険に入っています。来年度の保険料は、安くなると思って入っています。急アクセル、急ブレーキは、できるだけしないようにしています。
急ブレーキは、交差点の信号の変わり目で時々あるようですが・・・
他の車を見ていると、速度にもよりますが、結構、信号が黄色に変わっているのに、前の車についていくのが多いみたいです。
そこで止まると、急ブレーキになることが多いです。
まさか、保険会社が、そういう走りを推奨している?
まあ、前の車についていくので、トラブルが起こる可能性は少ないと思います。
狭い道から大きな通りに出るときは、車が来ているけど、出ることができると思って出ると、どうしても急アクセルになるみたいです。
大きな道に出るときは、車が来ないことを確認してから、ゆっくり、急アクセルと言われないように出ています。
問題となっているのと同じような交差点が見つかったそうです。
そんなことしないといけないのか?と私は疑問に思いました。
それで、横断歩道について調べてみました。
以前に、「運転免許の定年化」というシリーズを3つほど書きました。
その3では、高齢者の交通事故死が多いと書きました。
第1当事者になる人も、年齢ともに徐々に増えるみたいです。
でも、第2当事者が増えるようです。
たぶん、体力的な問題、判断の遅れとかがあるのではないかと思います。
その2で見た死亡事故2021を見ていただけると、最初のページに令和3年の死者数が2636人と書いてあります。昔?は交通事故死者は1万人とか言ったものです。減りました。
死亡事故2021のp3にある表2-1-2 年齢層別死者数の推移 によると、令和3年で、65歳以上は、1520人亡くなっているそうです。57%以上です。多いと思いませんか?
その中でも、歩行中に交通事故で亡くなる人が多いようです。
表2-2-10 歩行中の年齢層別死者数の推移というのがあります。
2021年でも65歳以上で、722人亡くなっているそうです。
表2-3-1 年齢層別・状態別人口10万人当たり死者数の推移
状態別というのは、自動車乗車中、自動二輪車乗車中、原付乗車中、自転車乗車中、歩行中、その他みたいです。
自動車乗車中、自動二輪車乗車中、原付乗車中、自転車乗車中では、第1当事者の場合と第2当事者の場合があります。
歩行中に第1当事者になる可能性は低いと思います。
歩行中は、みんな第2当事者というか被害者になるのでしょうか?
内閣府が、交通安全白書というのを作っています。
全部見ていませんが、何度か高齢者の話題になっているようです。
警察庁の統計の中に「令和3年における交通事故の発生状況等について」という資料がありました。
p2には、「国別状態別30日以内死者数の構成率比較(2020年)」構成率の比較ですが、歩行者の死亡事故は、ヨーロッパやアメリカに比べて多いみたいです。
他の国では、車の事故が多いとも言えます。
車と歩行者の関係については、ヨーロッパと日本ではだいぶ違うように思います。
日本では、隣の車より、ちょっとでも前に行こうとしているように見えます。
ヨーロッパは、順番があれば、それを守ろうとするみたいです。
表題と変わってしまいました。
高齢者ばかりの世の中になれば、高齢者は、小回り良くは期待できないので、順番を守った方が、世の中は円滑に動きそうです。
いろいろな理由で府道38号線を通ることが多くなりました。
でも、府道38号線を全部走ったことはありません。
もちろん、部分的には、府道38号線を走っていますが、府道38号線の全部を走ったことになるかは、わかりません。たぶん、全部は走ってないと思います。
泉北緑道での42.195㎞のコースを見つけたら、1日で歩いてみたくなります。
同じように、府道38号線も、全部走ってみたいと思いました。
wikipediaにも書いてあるように、府道38号線は、富田林泉大津線とも言うそうです。
泉北ニュータウンを通るところは、泉北1号線と言われているそうです。
大阪府道208号堺泉北環状線とも重複しているようです。
泉北1号線や泉北環状線なら知っているとうれしくなりました。
やはり、全体を走ってみよう。
googleマップでは、
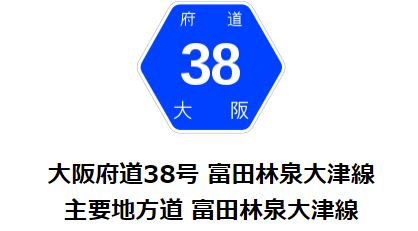
と表示されています。道路に富田林泉大津線と書かれていることもあります。
また、いつ頃の地図かわかりませんし、出典も不明ですが、このような地図も見つかりました。

昔から興味があったみたいです。
泉北1号線と泉北環状線から、泉大津、富田林に行く道のように見えました。
一方、泉北1号線をwikipediaで調べると、
大阪府道34号堺狭山線の臨海石津町交差点(堺市西区、大阪府道29号交点) - 泉ケ丘駅前(堺市南区)間、及び、大阪府道38号富田林泉大津線の泉ケ丘駅前 - 室堂町北交差点(和泉市、国道480号交点)までの通称。
だそうです。
大阪府の道路は通称が使われることが多いようです。
道の雰囲気も、深井駅の手前から、泉ヶ丘駅周辺を通て、光明池までは、同じような印象ですが、そこから、かなり印象が違います。
終点と思われる、フタツ池までは、泉が丘駅周辺と、だいぶ印象が違います。
泉北1号線として考えるのではなく、別々の府道と考えている人がいるように見えます?
泉北1号線は、国道480号線と交わる室堂の交差点まで行っているみたいです。
泉北1号線を光明池で出て、伏尾町、伏尾町中の交差点を越えて、国道480号を行き、泉大津の戎町交差点まで行きます。そこで、旧国道26号線に右折して、松ノ浜北の交差点から、戻ろうとしました。
それで、38号線の、別線と書いてある、大阪府和泉市伯太町 - 泉大津市松之浜町 間も行けると思っていました。
ちなみに、戎町は、府道38号線の終点だそうです。
戎町に行くことを泉大津に行くと言っても、「下り」とか言わないと思います。そろそろ「上り下り」を使うのをやめたら?
順調に、戎町の交差点まで行きました。
旧の国道26号線(府道204号線を北に走り、松ノ浜を超えて、松ノ浜北の交差点まで来ました。
どうも交差点で右折することを考えていないという交差点でした。強引に曲がりましたが、南海電車の線路があり、超えることはできそうにありませんでした。
結局、松ノ浜まで戻って、南海電車の線路を超えて、また38号線に入りました。
ここは、臨海道路まで出て、松ノ浜西で右折するのが正解だったみたいです。
一応、これで完走したとしました。
一方、富田林に行くには、310号線と交わる、松ヶ丘郵便局前の交差点付近がややこしそうです。
たぶん、推測ですが、旧の府道38号線の道幅が狭いので、バイパスを作ったみたいです。バイパスと思われる道は広いです。
西高野街道をちょっと通り、草沢の交差点に出てくる道は、府道38号線とは書いてありませんでした。
松が丘郵便局前の交差点を通る道は、旧の道も、バイパスもgoogleマップには、府道38号線と表示されています。
勝手に旧道と名付けた道を通って、勝手にバイパスと名付けた道に出て、端まで行きました。
wikipediaには、
起点は、大阪府富田林市錦織東3丁目(国道170号交点)とありましたが、外環のことではなく、旧の170号線のことでした。
wikipediaによると、
国道170号線は、新旧2本の道路が並行しており、いずれも国道指定されている。国道の新道が開通すれば、旧道は国道の指定を外されることが多い日本の国道のなかでも、その旧道が国道指定をいまだ解かれていない珍しい路線でもある。
だそうです。それで、どちらの交差点まで行くのか混乱が起きるみたいです。
無事に、府道38号線をほとんど完走しました。
光明池や槙塚台西交差点を出てから、帰ってくるまで1時間もかかりませんでした。
コメントをいただいたことにより、データの見直しました。
運転免許の定年化(その2)にまとめました。
データを見ると、免許保有者10万人当たりで事故を起こす確率(第1当事者になる確率)は、若い人と高齢者が多いようです。
5歳の年齢幅では、令和3年では、約300人ぐらいが事故を起こしているように見えます。
ちょっと大胆かもしれませんが、35歳から69歳までは、5歳幅で300人ぐらいずつです。
令和3年では、70~74歳では、336.0人、75~79歳では、390.7人、80~84歳では、429.8人、85歳以上では、524.4人と増えていきます。
一方、16~19歳(他は5歳分のデータですが、ここは4歳分のデータなのでしょう)では、1043.6人です。20~24歳では、605.7人です。
結局、高齢者になっても、若い人の事故率を超えることはありません。
まあ、どこまで許されるかという問題はありますが・・・。事故率が、若い人の事故率を超えないのであれば、運転免許の定年制は、このデータだけでは必要ないと思います。
その前に、運転免許がとれる年齢を引き上げないと・・・
一方免許保有者10万人当たりの死亡事故を起こすのは、増減はありますが、3人以下とみました。交通事故はほとんどの年齢層で、5歳幅で300人ぐらい起こしていますが、死亡事故を起こすのは、そのうち大体3人ぐらいです。
25~74歳までが、5歳ごとに見ると3人以下です。
ところが、75~79歳では、3.80人、80~84歳は、6.77人、85歳以上 11.84人になっています。3人を超えています。
若い人では、16~19歳が、9.69人、20~24歳が、3.55人です。
しつこいようですが、年齢層の幅を変えるなら、もう一度、死亡事故件数を合算して、免許保有者の合算で割ることが必要です。
85歳以上では、16~19歳の死亡事故率を超えていますが、年度によって超え方が違うようです。でも、多くの年で、85歳以上は16~18歳の死亡事故率を超えているようです。
結局、年齢を重ねると、交通事故も死亡事故も増えるのですから、定年制を設けるという案は、必要かと思います。
何歳で定年にするかは、事故率や死亡事故率からだけでは、計算では、出せないと思います。運転免許を返納したら認知症が増えるというのが正しければ、考えなければいけない問題と思います。
免許保有者は、70~74歳では、6,750,581人です。
75~79歳では、3,474,119人、80~84歳では、1,906,616人です。
85歳以上では、717,739人です。
後期高齢者の75歳になったり、80歳を超えたら、免許を返納する人がいるようにみえます。
80歳とかで、一旦、定年化で運転免許をなくして、自信があるとか、運転しないといけないという人は、再受験できるようなシステムを作ったら良いのかと思います。
私も含めて、お金がかかると嫌がる人がいますが、運転試験場で受験すると費用もかからないと思います。受験する人が、足が悪くて、試験場まで行けなかったりして・・・
試験で落ちたなら、免許取得も諦められると思います。
お金持ちは、自動車学校に行ったりして・・・
その時は、自動車学校を卒業しても、実技試験免除とかいうシステムをなくすのでしょうね。年齢によっては・・・
一度書きましたが、自動運転の車が安く出てくると、状況は変わると思います。
今は、自動運転がでてきそうな時期なので、定年化は難しいのではないかと思います。
高齢者が、加害者になる死亡事故は、多いですが、とんでもなく多いかというと、私は、そこまで多くないと思います。
でも、交通事故で死亡する高齢者は多いみたいです。
その話は、次のブログで。
「運転免許の定年化」というブログを書きました。
最近、とっても忙しかったので、そのブログに澤田武弘 さんからコメントをいただいていたのですが、対応できませんでした。
やっと、一段落して、コメントをチェックしました。
私が確認したところでは、コメントに指摘されているように元の記事に誤りがあったと思います。ブログにそのまま転送したので、おかしいとコメントをいただきました。確認することが必要との指摘も受けました。
その原因を私なりに調べました。私の備忘のためブログです。
元の記事は、MSNニュースやYahooニュースからのリンクを張っていましたが、なくなっているのもあるようなので、元の記事からのリンクです。
①の記事です
②の記事です。
①の解説は、定年化に賛成のようです。事故の統計を使って、いろいろ必要だと説明されていました。
でも、言いたかったのは、高齢者でも運転できるような安全な環境を作らないといけないということのように思います?
②の解説では、「免許返納を早まるな」と書いてありました。
また、高齢者の事故率が高いというデータはないとも言われていました。
免許返納すると、出歩くのが減って、認知症になる確率が2倍になるそうです。
それも含めて考えて、免許返納を家族と相談しないといけないと書いてありました。
事故率については高いというデータはないとだけ書かれていました。
データについては、高齢者の死亡事故が多い、高齢者の事故が多いというデータはないというまったく反対の考えをされていますので、興味を持ちました。
それなのに、データの検証が十分ではなかったのは、反省しています。
コメントの返信に書いたように、①のデータの処理が間違っていると思います。割とよくありそうな間違いなのに、気づかなかった私が悪いと思っています。
正月に書いたので、現在のように忙しくはなく、単に、データを検証するのに、必要な知識がなかっただけと思います。
それまで、警察庁の統計を見たことなく、第1当事者と、第2当事者があるので、よくわからない統計だとも書きました。
表によっては、第1当事者と明記してあるのもあります。
①の検証では、それを使っているようです。
そのあたりも、以前のブログでは、ぐちゃぐちゃに書いてしまったようです。
データについては、下記に書きます。
警察庁のホームページを見ると、
下の方に「統計」という項目があります。
その中に「道路の交通に関する統計」があり、そこに「交通事故発生状況」というのがあります。
さらに「集計結果」には、まず、「用語の解説」がありました。
「統計表」というところのデータがいろいろ並んでいますが、クリックするのは、色が変わっている最終更新日の日時のところです。
「年報」の項目を見てもらうと、下の方に、
【交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について】
【交通事故の発生状況について】があります。
それぞれの令和3年分を、①では使われているようです。
実は、それぞれの書類には、「令和3年中の交通死亡事故の発生状況及び 道路交通法違反取締り状況等について」とか、「令和3年中の交通事故の発生状況」 とかの表題がついています。年度がついているのと、微妙に表現が変わっています。
ここでは、文書のファイル名を使って、「死亡事故2021」とか「全事故2021 」とか表現するようにします。
余計に混乱することになるかな?
私は、pdf版をダウンロードしました。excel閲覧用、csvと記載されたのもありました。
私のWindows10では、どちらでもExcelが立ち上がりました。
ちなみに、年報の項目には、【交通事故死者数について】というのが、先にありましたが、そこには必要なデータはないようです。
【交通事故の特徴について】の方が、いろいろデータがありました。また、後程。
②については、データはないということしか書かれていませんが、①については、データを出して示されています。
交通事故は、一般的には加害者と被害者がいます。
高齢者の事故が問題になるのは、アクセルとブレーキを踏み間違えたりすることで、若い人を事故で死なせることがあるからだと思います。
高齢者による単独事故で、自分が死ぬだけなら、あまり問題にならなかったと思います?
でも、警察的には第1当事者と第2当事者がいて(たぶん、事故によっては第3、第4・・・といるのだと思います)、それぞれの過失割合を警察が判定するのだと思います。
交通事故も死亡事故も、年ごとに、だんだん減ってきているようです。
①の解説では、免許保持者10万人当たりの事故件数は若い人が多いが、死亡事故については、高齢者の方が多いと書いてありました。
事故件数については、「全事故2021」にあります。
pdf版のp23の「表3-1-1 原付以上運転者(第1当事者)の年齢層別免許保有者10万人当たり交通事故件数の推移」です。
「原付以上運転者(第1当事者)」と明記されています。一般的には、加害者の数だと思います。正確には、過失割合の大きい方を数えたのだと思います。
表3-1-1は、推移と書かれているのは、令和3年以前のものもあるからと思います。

表3-1-1は、第1当事者の免許保有者10万人当たりの交通事故件数です。
表3-1-2は、第1当事者の年齢層別の交通事故件数です。
表3-1-2の事故件数を表3-1-1にある免許保有者数で割って、10万人をかけたものが、10万人当たりの交通事故件数になります。
表3-1-1の下に、(再掲)と書かれた部分があります。
そこまでは、5歳ごとの年齢層に分割していましたが、その年齢層を、16~24歳、65歳以上、70歳以上、75歳以上、80歳以上にして、10万人当たりの交通事故件数を計算したものだと思います。
同じデータを使っているので再掲とされたと思います。
全部ではありませんが、いくつかは、実際に電卓を使って確認しました。
①では、10代後半が飛びぬけて多く約1043件、次いで20歳~24歳が約605件でした。70歳~74歳336件、75歳~79歳390件と書いてありました。上記の表から確認できます。
令和3年では、各年齢層では、10万人当たり約300人が事故を起こしているようです。30~35歳から65~69歳では、約300人です。そこから年齢が下がっても、上がっても、事故率も増えるようです。
一方、死亡事故は、下記のようになります。

表の説明は、「全事故2021」と同じです。
同じように再掲があります。
①の解説では、
事故件数の多かった若いドライバー(16歳~29歳)の死亡事故件数を足したところ15.74件。これに対し、65歳以上を足すと187.17件と若者の10倍以上にも上る。
と書いてありました。
死亡事故2021からすると、16~19歳は、9.69件、20~24歳は、3.55件、25~29歳は、2.50件です。
合計すると、15.74件です。計算は合っていると思いました。
65歳以上を合計すると、27.78件でした。
でも、免許保有者10万人に対する事故の件数なので、単なる合計では?
と思いましたが、15.74件は正しいとコメントの返事を書いてしまいました。
一方、187.17件ではなく、27.78件ですと返事に書きました。
でも、10万人当たりの死亡事故件数ですから、年齢層の合計ではなく、平均にしないといけないように思います。
65歳以上の187.17件は、どこかを合計すると、そうなるように最初は思ったのですが、結局、どこを足したら良いのかわかりませんでした。
ちょっと年齢層が広いですが、16~24歳は、4.49件です。それより少なくなるはずです。
65歳以上は、3.64件と再掲に書いてありました。
高齢者による死亡事故は、多いとは言えないように思います。
でも、80歳以上になると、2倍以上になるみたいです。
また、第1当事者に限定しなければ、高齢者の死亡事故は多いみたいです。
別のブログで。
というニュースがありました。
もうそろそろ運転免許を返納しても不思議ではない年齢です。
年上の知り合いにも、何人か免許を返納した人が出てきました。
老化は人によって違うと思いますが、私の場合は、例えば、登山でも、ふらつくことが多くなったように感じています。
新型コロナで金剛山に行く回数が減りました。
ふらつきの対策として、ストックを持つことが増えました。投稿するために、ストリートビューを撮影することも増えました。片手でストック、片手で360度カメラを持つのは、難しいです。
一方、もの忘れも増えました。私の場合は、です。
極端に言えば、ちょっと前のことも別の刺激があれば、忘れる可能性があるようです。
例えば、交差点で右を見て、車を確認しても、何か刺激があれば、左を見て、車がこないと思ったら、右から車が来ているのを忘れて、交差点に進入してしまいそうです。まだ、実際には、ありませんが。
そろそろ、いつどうなったら運転をやめるか考えないといけないような状況です。
自動運転の車が、安く発売されたら、気が変わるかも。
せめて歩行者がいない高速道路だけでも、自動運転出来たらかなり状況が変わると思います。
この定年制のニュースの根拠になっているのは、警察庁交通局が、2022年に発表した、「令和3年中の交通事故の発生状況」 と「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況」 のようです。
交通事故だけ見ると、若い人が起こすのが多いようですが、死亡事故を見ると、高齢者が多いと書いてありました。
身体能力が関係していると書いてあります。
「原付以上運転者の免許保有者10万人当たり交通事故件数」という項目があります。
年齢別にみると、10代後半が飛びぬけて多く約1043件、次いで20歳~24歳が約605件でした。70歳~74歳336件、75歳~79歳390件、10代と20代、70代以上をまとめた数字をみても免許証を取り立ての若者たちのほうが事故を起こしている割合は高いそうです。
一方、死亡事故の件数は若いドライバーに比べ、高齢ドライバーのほうが圧倒的に多いそうです。 「原付以上運転者の免許保有者10万人当たり死亡事故件数」から見た件数は次の通り。事故件数の多かった若いドライバー(16歳~29歳)の死亡事故件数を足したところ15.74件。これに対し、65歳以上を足すと187.17件と若者の10倍以上にも上るそうです。
このニュースでは、高齢ドライバーは若いころのように身体が動かない現状をきちんと理解して、より用心して運転する必要がありますと書いてありました。誰しも老いは訪れる。とはいえ、高齢になったからといきなり注意して運転できるものではない。若い頃からいかに運転に対する安全意識を心がけるかが必要なのだと締めくくっていました。
一方で、こんなニュースもありました。
「65歳以上の高齢者による車の事故率が、他の世代に比べて特別高い」というデータは、今のところ出てきていません。 と言い切っていました。
車の運転をやめた人が要介護になるリスクは2.09倍というのが根拠になっているようです。
いつまでも運転してよいとは言っていなくて、免許返納の時期は家族と相談して決めておくと書かれていました。
想像ですが、警察庁以外に、こんなデータを集めているところはないと思います。ひょっとしたら保険会社も?
同じ出典のデータなのに、事故率が違うのは、どうしてか疑問に持ちました。
警察庁の報告を見ようと思いました。
「令和3年中の交通事故の発生状況」で検索すると、
令和3年における交通事故 の発生状況等について - 警察庁
統計表という警察庁のWebサイトもありました。
月報、半年報、年報があり、「令和3年中の交通事故の発生状況」 と「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況」もありました。面倒なので、それぞれはpdf版をダウンロードしました。
運転免許の定年化というニュースのデータが正しそうだという所まで確認しました。(正しいかちゃんと確認したわけではないです)
これが日本のもともとのデータと思いますが、違う結論になるのは、どうしてなのか?疑問を持ちました。
第1当事者と第2当事者という言葉が出てきました。
警察庁の用語の解説には、
「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。
交通事故には、加害者と被害者がいるように思いますが、警察的には、第1当事者と第2当事者がいて、当事者が車を運転していたのか、歩いていたのかで分けて数えているようです。加害者と被害者を一緒に数えている。
高齢者が加害者になることを非難されているのに、加害者と被害者を合計して事故にあった人が多いというデータしかないのなら、「65歳以上の高齢者による車の事故率が、他の世代に比べて特別高い」とは言えないのかと思います。
でも、データがないから事故率が高いと言えないというのもどうかと思いました。
令和3年における交通事故の発生状況等についてを見ると、歩行者の交通事故死が、他の国に比べても、以上に多いのが気になりました。
そういえば、歩道がない道を歩くと、近くをスピードを出して通る車があります。離れて通る車もありますが、対向車が来ると、そのまま近づいてきます。
ちゃんと歩いていたらよいのですが、バランスが悪くなっていますので、よろけることも考えられます。
よろけたら、車の方に倒れることも考えられます。
クルマの運転ですが、以前に書いたものを再度、出します。
今も考えは変わっていません。
山道において集落があると30㎞/hや40km/hに制限されることがあります。制限速度以内の速度で走ると煽ってくる車があります?
でも、集落以外の部分でも、速度を制限しているようにもみえます。
また、泉北ニュータウンの道は、2車線ですが、左折しようと信号を出すと、後ろの車は、右車線に出る車が多いです。そんなにブレーキを踏むのが嫌なのでしょうか?
ハンドルも大きく切りたくない、ブレーキも踏みたくないとなったら、私は、免許を返上します。
自動車保険をテレマチックス自動車保険という名前の保険に変えたことを書きました。
最近は、そんな自動車保険の広告をよく見ます。
私が入っている保険ではスピード、アクセル、ブレーキをチェックするみたいです。
具体的には、スピードは速度超過、アクセルは急加速、ブレーキは急ブレーキをチェックするみたいです。
全体的には、A、B、Cの3段階があるみたいです。Aなら安全運転のように見えます。BとかCが良くない?
なお、リアルタイムに、そんな指摘をしてくれるのではなく、終わってからレポートみたいな連絡がアプリにあるみたいです。
そのレポートには、走行経路が表示されていて、速度超過の区間、急アクセルの地点、急ブレーキの地点が表示されます。
実際に運転した結果は、だいたいAだと言いたいところですが、BとかCも時々あります。
私のスマホを、登録してあるので、そのスマホが車にある時は、結果が出ます。嫁さんが一人で運転しているときは、評価されません。
送迎で泉が丘駅に行くときには、距離が短いからか?、結構厳しめに出るように思います。
遠出したときは、ブレーキがきついと感じても、急ブレーキの指摘はないこともあります。評価は距離によって違うようにも思っています。
個々の項目についてですが、速度超過は、場合によっては、反則金とかを払わないといけなくなります。金欠の私としては、できるだけ、20km以上の速度超過はしません。(運転を始めた時に、20km/hがポイントと聞きました。若い時に、白バイにロックオンされた時も、20km/hオーバーなら違反にはなりませんでした)
急アクセルですが、店から道に出るとき、近づいてくる車があっても、今なら、出ることができると思う時があります。
そういう時は、急アクセルになることが多いみたいです。
見えている車が通り過ぎるまで待つようにしたら、急アクセルは減りました。
十分に前に出ることができると思う時でも、一瞬、間を置くようにしました。
急ブレーキは、今もまだあります。
前の車の動きにびっくりした急ブレーキはないと思っています。
どうも、信号機がある交差点で、前の信号が赤になったら、短い距離でも止まろうとするみたいです。
それが急ブレーキになるようです。
家族は、横に乗っていても、信号の赤で止まっただけで急ブレーキではないと思っているみたいです。
でも、例えば、観光バスに乗っていても、バスは、このままではぶつかると思わないと、急ブレーキをかけないですね?普通に乗ったら、急ブレーキはない。
乗客も多いので、いつも同じようなペースでブレーキをかけているみたいです。
信号の前で赤信号になっても、いつものペースのブレーキでは止まれないと思うと、そのまま交差点に入るみたいです。
私は、赤信号で交差点に入らないのは良いことだと思いますが、ほかの人から見ると、ちょっと無理して止まっていることになるのかなあ?
こうしてみると、結構、余裕をもって運転するようになりました。
よく言っているだけで、遅いだけかな?
業務用のドラレコとかを売り出したみたいです。
同じような機能がついているみたいです。
運転は、個人でしているところがありましたが、自動車保険や、企業がこういうのを使うようになると、皆さん、ゆったりと走るようになる?
右左に車線を変えながら、前に進んでいく車を見ることがあります。というか、そんな車が多いように思います。
そんなことしても、着く時間は、たいして変わらないのにと思って見ています。
そういうのも、急アクセル、急ブレーキをチェックされるこんな装置が出てくると減っていくと思います。
先日、車を出そうとエンジンをかけようとしましたが、かかりませんでした。
速度計の横にあるエンジン警告灯、油圧警告灯、充電警告灯がついたままです。水温警告灯も青くついていました。赤なら水温が高いということですが、エンジンをかけた後は青くついているものです。その青でした。
結局、エンジン警告灯、油圧警告灯、充電警告灯がついていました。
エンジンが止まったら、どんな警告灯が付くのか知りません。
しばらく待って、再びエンジンをかけたら、問題なくかかりました。
エンジンがかからないのは困るので、見てもらおうと、そのまま販売店に持って行きました。
車を買うときは、いろいろ安全装置が付いている車を買いました。
ちょっと運転にも自信がなくなった時期でした。
メーカーはセーフティーサポートと言っているみたいです。(メーカーがばれる?)
車の前面には、レーザーレーダーと単眼カメラ、後方は超音波センサーがあるようです。取扱説明書を見ました。
あまり、そういうことには、熱心なメーカーではないと思ったのですが、たぶん、そんなセンサーを作るメーカーがあり、そんなのを買ってきてつけたのだと思います。パネルには、それなりの、警告灯が必要ですが・・・。
販売店に行くと社長さんが出てきて、センサーがついているので、窓の曇りとかで検知できないときは、エンジンがかからないようになっているという説明を聞きました。
なんとなく、そうかと思って、話を聞いただけで帰ってきました。
取扱説明書を見ると、フロントウィンドーガラスのレーザーレーダーや単眼カメラの前部が曇ったり、結露したり、凍結したりするとシステムが一時的に作動しなくなることがあります。と書かれていました。
対策は、フロントデフロスターで曇りなどを取り除いてくださいとありました。
エンジンがかからないのに、フロントデフロスターは動かないのでは?と思いましたが、面倒になり、その時になったら考えたら良いと思いました。
ところが、昨日、同じようにエンジンがかからなくなりました。
エンジン警告灯、油圧警告灯、充電警告灯が赤くついたままです。
エンジンはかかりません。
販売店に電話して同じことが起こったと言いました。
ついでに、警告灯の点灯をいわないといけないと思って、ついている警告灯をすべて言いました。
その後で、電話がかかってきて、ハンドルロックがかかっているようですが、それではエンジンはかかりませんと言われてしまいました。
確かに、ハンドルをゴソゴソ動かしてからエンジンをかけると、エンジンはすぐにかかりました。
どうも、エンジンがかからないので、またセンサーが曇ったり、結露したりという同じことが起こったと信じてしまったようでした。
ハンドルロックのランプをみても、気が付きませんでした。
ハンドルロックがかかってエンジンがかからなかったことは、ハンドルロックがでた頃にたくさんありました、今でもある?
説明が悪かったとは思いませんが、おかしいと持って行ったときに、何もしてくれないのは、よくないかも知れません。
何もしなくても、ソフトを最新にしましたとか言ってもらえると、次に同じような問題が起こっても、安心して対応できるように思います。
なんでも良いので対応するということは重要なのでしょうか?
もしくは、若ければ、パニックになって電話することもなかったのに。
歳はとりたくないものです。
自動車保険は、あいおいニッセイ保険に入っています。タフ・くるまの保険という名称の保険です。毎年保険を更新することが必要ですが、毎年11月が切り替えの時期です。
11月からの保険の案内が送られてきました。タフ・見守るクルマの保険プラス というのも選択できるみたいでした。
専用ドライブレコーダーや専用端末を取り付けると、その結果に応じて、自動車保険を継続する時に、保険料を引いてくれる可能性がある保険みたいです。
たぶん、去年の契約の時には、そんな自動車保険はなかったと思うので、読んでみました。(ちなみに昨年の案内は残っていませんので、実際はどうか知りません)
自動車保険の保険料は、車を乗るときの必要経費みたいに思っていますが、少しでも安いのを探しているつもりです。
タフ・見守るクルマの保険プラスには、専用のドライブレコーダーを取り付けるのと専用端末を取り付けるのがありました。それぞれ名称が違うみたいです。タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)とタフ・見守るクルマの保険プラスSみたいです。専用ドラレコと専用端末にします。
無事故の割引率によって違うのだと思いますが、専用ドラレコを利用するのは、年間1万円ぐらい保険料が高くなります。
一方、専用端末だけを取り付けるのは、年間1000円ぐらいアップするだけで、継続した場合、場合によっては保険料が、8%も下がることがあるみたいなので、その保険を選択しました。
具体的にどうしているかとかの詳しい説明はなかったけど、保険料の増加分は少しで、来年以降保険料が減る可能性がありそうなので、思い切って変更しました。代理店に電話して聞いても良くわかりませんでした。
だんだん年をとると、こういう確認がいい加減になります。特殊詐欺とか気を付けなければ・・・。
後で調べてみると、このような保険は、テレマティクス自動車保険と言うそうです。
いろいろな保険会社がテレマティクス自動車保険を出しているみたいです。
今までは、走行距離に応じて、ポイントがかえってきたり、保険料を下げたりしていたみたいですが、だんだん運転特性(速度超過する、急ブレークを踏む、急アクセルする)ことで保険料を変えるようになっていくみたいです。
専用端末を契約したら、端末が送られてきました。
ダッシュボードの上に置きました。たぶん?(覚えていません)、両面テープで止めました。
電源ケーブルとかありません。ケーブル類はなにもついていません。
電池が入っているそうで、装置ごと交換するのかな?
スマホには、専用のアプリを入れることが必要です。
スマホとは、Bluetoothでつながるみたいです。
店とかで止まると、そこまでのレポートが送られてきます。
レポートは、リアルタイムではありません。ちょっと遅れてスマホに送られてきます。
1月単位でも、レポートが出るみたいです。
現在10月ですが、8月のレポートがあります。
評価は、A、B、Cを見ました。D、Eがあるのか知りませんが、ないのでしょうね?
走ったコースが表示されます。今までは、正しいコースでした。
コースのどこで、速度超過したか?、急アクセルを踏んだか?急ブレーキをかけたかわかるようになっています。
思い当たることが多いです。
評価項目ですが、スピード、急アクセル、急ブレーキみたいです。
スピードですが、昔から制限速度を20km/hも超えないように走っています。
今では、どうなのか知りませんが、以前は25km/hを超えて捕まると反則金が高いと言われていました?もう古い話?
それで、高速道路でも、25km/hオーバーを守っています。
どうもその程度なら、問題にはならないようです。
クルマの流れに従って走ってくださいという由のことが書かれたレポートが来ます。
一度だけ、高速道路と高速道路の間の制限速度が低いところで、そのままの速度で走ったら、速度超過とレポートに出ました。
アクセルも、ガソリンがもったいないように思うので、強く踏むことはありません。
でも、店から、狭い道から、広い道に出るとき、車が来ているけど、出れそうと思うときがあります。
そんな時は、できたら、広い車を走っている車を邪魔したくないので(どっちか言うと追突されるのが嫌なので)、急加速することがあります。
それが、急アクセルとレポートに出ることがあります。
最近は、車が来てなくて、余裕を持って出れる時にしか、広い道に出なくなりました。
私の場合は、急ブレーキのレポートが多いです。
そんなに急ブレーキをかけているつもりはありませんが、急ブレーキと判定されることが多いみたいです。
例えば、曲がって、歩道を人が歩こうとしたら、止まります。
それを急ブレーキになるときもあるみたいです。歩行者を見つけるのが遅いのでしょう。
たぶん、普段からブレーキを踏むのが強いのだと反省しています。
なお、8月の月間レポートはAでした。
レポートは、運転が終了してから時間が経ってからスマホに届きます。
端末からの情報をスマホ経由で送って、センターで処理した後、レポートをスマホ経由で受け取るのだと思います。9月分の月間レポートはまだです
実査に端末からどのぐらい情報を送っているのかわかりません。
スマホは、GPSを有効にするのが条件みたいですから、電力消費の多いという噂のあるGPSは、スマホのGPSを利用しているのかなあ?
急加速、急ブレーキも、GPSで検知しているのでしょうか?
たぶん、衝撃を検知するぐらいの機能は持っているのだと思いますが、それ以外はスマホの機能を利用しているのかなあ?一度、専用端末を分解してみたい。
これを書くのに、もう一度案内を見てみたら、実は、8%安くなるのは、読み間違いだと知りました。
Aランクで8%引き、Bランクで4%引き、Cランクで、値引きなしとかいてあるので、その通り、読んでいましたが、スタートするときは、Bランクだそうです。結局、4%しか保険料を引かれないようです。
高齢化社会と言うのに、小さい字で注記ばかりして、正確には書いてあるけど、見た時の印象を変えるのは、認められているのでしょうね・・・









