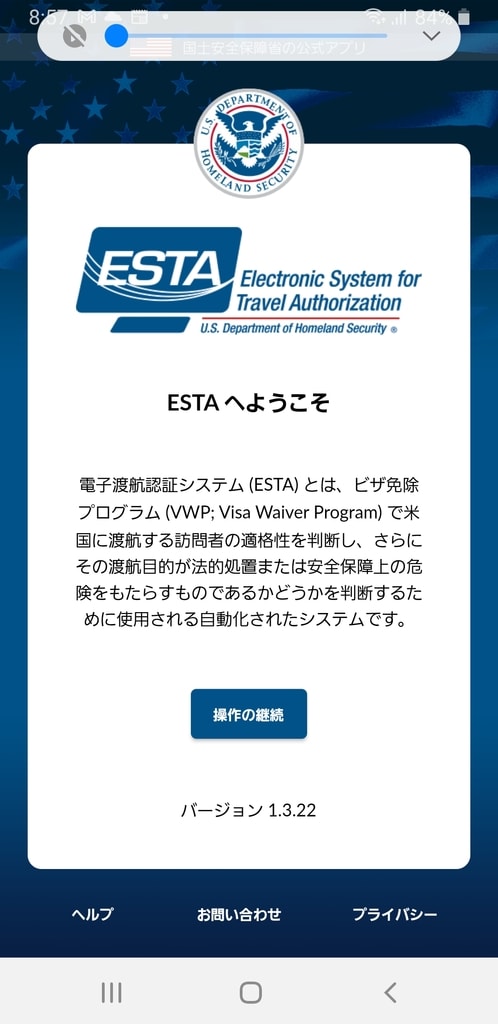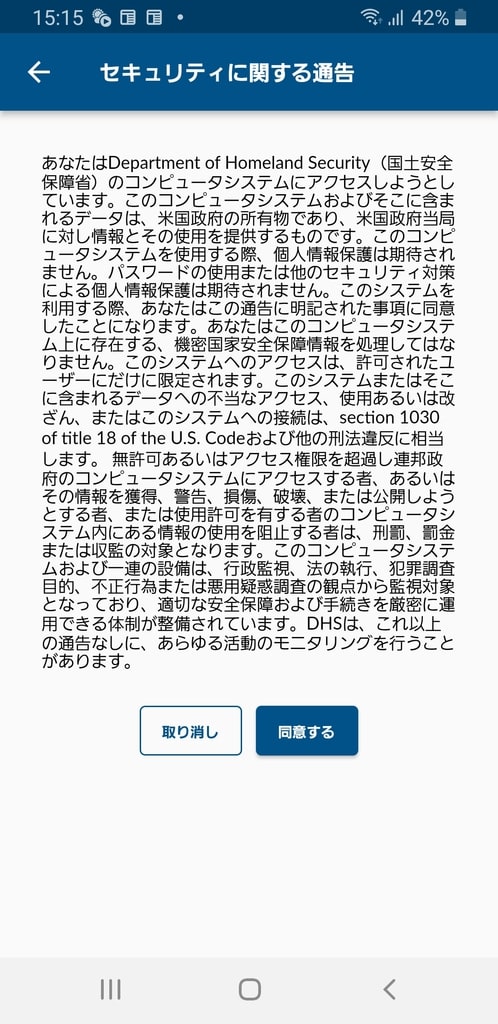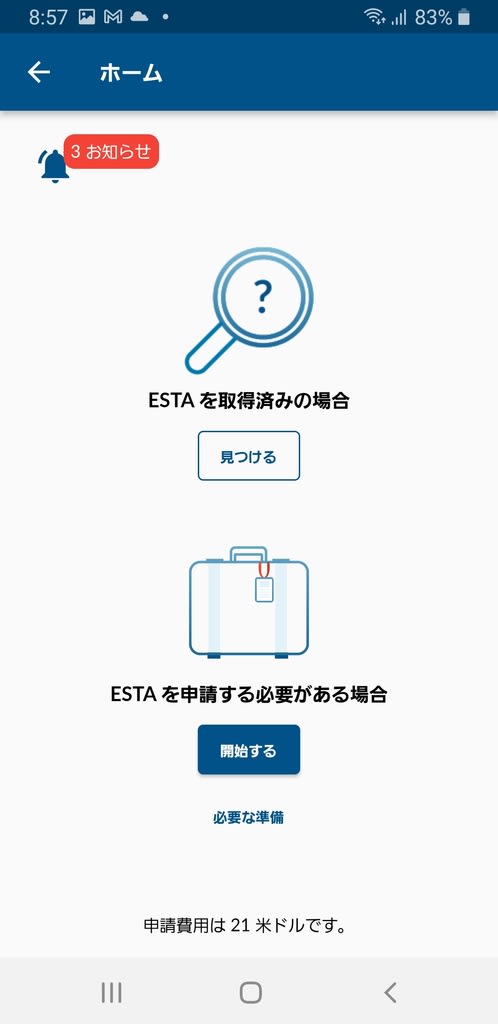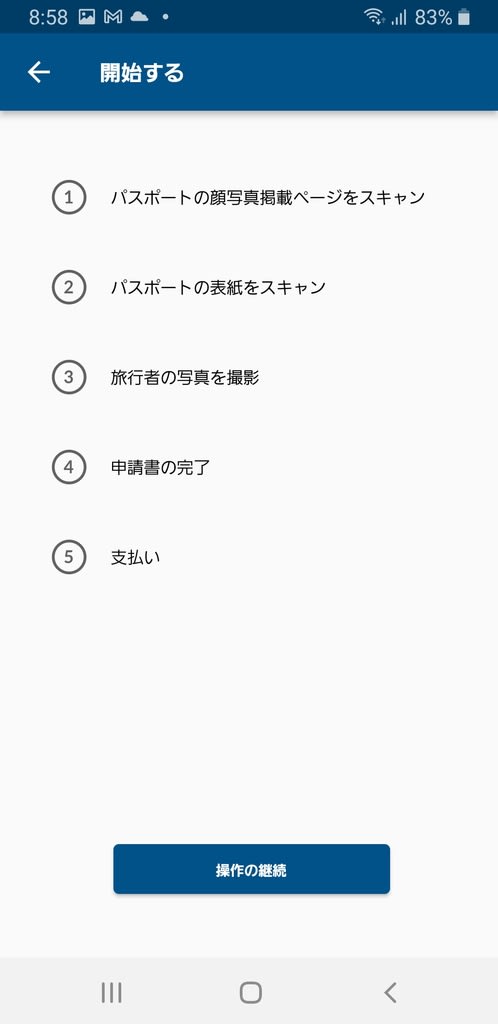母が亡くなり、相続人になりましたので、相続について調べました。
相続額と相続人を確定することが必要みたいです。
金持ちの家は知りませんが、だいたい普通は、遺産が、どこにあるか聞いているように思います。
預貯金なら銀行ですし、通帳を見たら、大体の金額がわかります。
以前と比べて、金利が高くないので、書いてある金額とそんなに違わないと思います。
必要なら残高照会とかできるみたいです。でも、相続人であることの証明はいる場合もあるみたいです。
有価証券なら、証券会社です。
土地は、相続税評価額が決まっているようです。
路線価が決められているみたいです。
相続税を払う必要があるかどうかは、国税庁が要否判定コーナーを作っているみたいです。
相続人を調べるには、被相続人(死んだ人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要なようです。戸籍謄本の束と書いてあるのもありました。
そのうち変わるようですが、戸籍謄本が必要になれば、本籍地の市区町村役場に、戸籍謄本を請求することが必要になります。
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度というのができているみたいです。それを利用しました。戸籍謄本の束を集めることは必要ですが、法定相続情報一覧図 を作成して、堺東の法務局(泉北ニュータウンの住民なら)に持っていけば、確認して、数日たってから法定相続情報一覧図のコピーを送ってもらえるみたいです。
法務局では、予約制と書いてありました。その通り電話したら、予約はないので、直接来てくださいと、その時には言われました。
法定相続一覧図のひな形は、下記にありました。様式はエクセルで作られていますので、エクセルが動くパソコンが必要かと思います。他のソフトでは試していません。私のパソコンにはエクセルが入っていました。
母の場合は、戸籍謄本の束を頼むのに、5000円ぐらいかかりました。
さらに追加の戸籍謄本を頼むのは、躊躇しました。
法定相続一覧図のコピーは無料です。複数部を頼みました。
郵送料はかかりますが、コピー自体は無料でした。
レターパックを買ってきて、それに自分の名前を書いて窓口に提出しました。
レターパックは、370円のと570円のがあります。
こういう時に、レターパックで送るのは便利です。
普通に送るときは、370円のレターパックを使っています。
受け取り側では、郵便受けに入れてもらえます。
A4の封筒に、折れてはいけないと思って厚紙を入れると、すぐに140円になります。厚紙の重さによると思いますが。特定記録を入れると、300円になってしまいます。
レターパックなら、郵送料込みで370円ですし、しっかりしているため厚紙をどこから探すかとか考えなくてもよいので、便利です。
でも、法務局の郵便局には、570円のしか売っていませんでした。
泣く泣く570円のを買って持っていきました。
後から考えると、ポストに入れるだけ(370円の場合)と手渡しが違うのだと思います。レターパックの570円は書留と同じようになる?
銀行とかに相続の資料を送るときには、戸籍謄本の束の代わりに法定相続情報一覧図を送ればよいみたいです。
銀行によっては、16歳または婚姻(初婚)から死亡までのつながる戸籍謄本(または、除籍謄本。以下、戸籍謄本等)と書いてあるのがありました。
出生というところが16歳または婚姻(初婚)に変わっていました。不思議に思いました。
戸籍には、生年月日が書いてありますので、16歳かどうかはわかると思います。でも、16歳から妊娠すると決めているようにも見えます?初婚かどうかは?どうしてわかるのでしょうか?出生からの戸籍謄本を確認して、初婚かわかるので、やはり出生から死亡までつながる(連続する)戸籍謄本が正しいように思いました。
子供の時に、戸籍謄本とか、戸籍抄本とか聞いたことがありました
戸籍については、あまり知らなかったので、調べてみました。
wikipediaにも、戸籍について説明があります。
「戸籍(こせき)とは、戸(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。
かつては東アジアの広い地域で普及していたが、21世紀の現在では日本と中華人民共和国と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。」
そこにも書いてありますが、多くの国では、個人の登録管理制度になっているみたいです。戸籍のような家族単位の国民登録制度は、存在しないそうです。
たぶん、戸籍簿という書類?は本籍地の市区町村役場にあったのだと思います。
現在は、家族が単位です。
子供が生まれたら、戸籍に追加されますし、結婚すると除籍されます。
今の戸籍から消されて、新しい夫婦の戸籍になるようです。
死亡しても、戸籍から消されます。戸籍から消すのを除籍というそうです。
戦後に、今の家族単位に変わったそうです。
それまでは、家制度とか言って、家長という人が、家を守っていたようです。
家長が、引退したり、死んだりすると、長男が家長を引き継いだようです。
だいたい、いつの世の中でも、誰に家を継がせるかは、大きな問題だと思います。まして遺産が多くなると、問題だったと思います。
親にすると子供の中でできるだけ優秀なものに継がせたいと思います。
でも、そうすると、揉め事が増えるみたいです。お家騒動と書いてありました。
wikipediaの長子相続の項には、江戸時代までは、明確に定まった相続法はなかったと書いてありました。
徳川家康が、長子相続を決めたとか聞いたことがあります。
揉め事が増えるよりは、馬鹿でも長子と決めた方が、揉め事が減ると見たのでしょうか?徳川家康は、戦国時代の武将ですが、生まれる時代が違ったら、平和主義者になったかも?
明治以降、富国強兵のために家制度を強化したとありましたが、富国強兵と家制度がどのようにつながるのかわかりませんでした。
たぶん、進駐軍は、それを嫌がって、家制度をやめて家族制度に変えたと思います。
憲法改正がにぎやかになりました。富国強兵に近いことを言う人もいます。
憲法改正で、戸籍を変えて、家制度を復活するということを言う人は少ないみたいです。いない?
世の中の動きが違うし、票にならないと思うからでしょうか?
天皇制も長男が継ぐということになっていると思います。
家制度が、効力を有していたのは、明治憲法下で民法が規定された1898年7月16日から戦後までの48年9か月半の期間だったとwikipediaには書いてありました。でも、長子相続は江戸時代から続いていたようなので、日本人にはなじみのシステムなのかも知れません。
戸籍簿のコンピュータ化もありました。
一般的には、平成6年に戸籍法が改正され、戸籍のコンピュータ化が可能になったそうです。
それまでは、紙ベースだったので、字の間違いもあったそうです。
母の字は、祖父が届け出のときに間違えたという噂がありました。
パソコンで見る字とは微妙に違っています。
それが平成6年の戸籍改製でパソコンの字に変わりました。
画数が多いので、まだ、私には、書きにくいですが、パソコンの字の通り書けばよくなりました。
このように、戸籍が法律によってつくりなおされることもあるみたいです。
それを改製とか言うみたいです。
改製した時は、その時までに除籍した人は戸籍に乗らないようです。
連続した戸籍謄本を確認して、他に相続人がいないのか確認していると思います。
こんなに大事な戸籍簿なので、副本というのがあるそうです。副本はバックアップ?
もともとは、正本は市区町村に備えて、副本は、管轄法務局に置くと決められていたそうです。副本は、1年に1度磁気テープで送られるそうです。
東日本大震災では、4市町村の役場の戸籍正本がなくなったそうです。仙台法務局気仙沼支部に戸籍副本が残っていたので、復元できたそうです。
でも、これを契機に、3か所に副本サーバーを設置し、毎月、市区町村は副本データを送るそうです。
一方、時間がたって、戸籍に乗っているすべての人が除籍されても、戸籍は保存されるみたいです。載っている人がすべて除籍されたのは、除籍謄本というみたいです。
除籍謄本は、100年間請求できるみたいです。つまり戸籍に載る人が誰もいなくなっても100年間保存されているようです。本当かは知りません。
戸籍簿に書いてある全事項証明書を、戸籍謄本というみたいです。
コピー機がない時代には、手書きして写していたみたいです。(wikipediaの戸籍に書いてありました)
誰か一人だけのコピーは、戸籍抄本というみたいです。
最近は、戸籍謄本、戸籍抄本とは言わずに、全部事項証明書、個人事項証明書というみたいです。