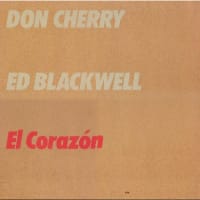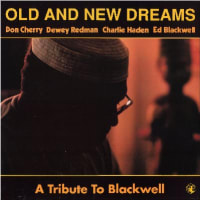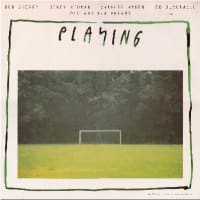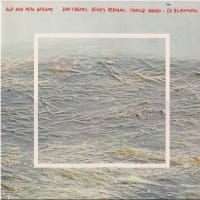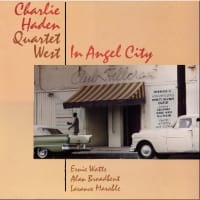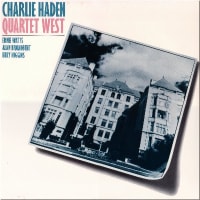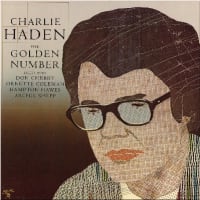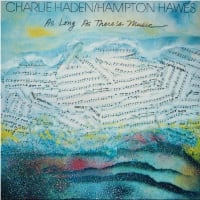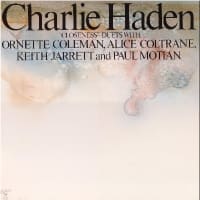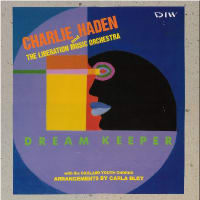内田正男、能田忠亮、コンピュータ
「日本の暦」 『暦』広瀬秀雄(編) ダイヤモンド社 1974/12/12 『暦の語る日本の歴史』 そしえて 1978/03/01 『こよみと天文・今昔』 丸善 1981/12/25 「日本の暦法」 『天文学史』中山茂(編) 恒星社厚生閣 1982/01/25 『暦と時の事典』 雄山閣出版 1986/05/05 『日本暦日原典』 雄山閣出版 1975/07/10 『暦と日本人』 雄山閣出版 1976/02/10 2刷 『暦のはなし十二ヵ月』 雄山閣出版 1991/12/05
 広瀬秀雄、前山仁郎、桃裕行による宣明暦の研究は、前山仁郎の物故により頓挫しかけたのであるが、内田正男の努力により『日本暦日原典』として結実した。この暦日表は従来使用されていた『三正綜覧』の不備を補い、まさしく原典としての存在価値を高めている。桃裕行亡き後、古典籍による施行暦日との照合は内田正男により継続されており、その成果は『日本暦日原典』の改版(現在4版)に反映されている。先学の成果を踏まえての堅実な研究であることが、書籍リストからうかがえる。その分、新しい研究テーマを想起することは少ないが、日本の暦を考える上での基幹文献といえる。
広瀬秀雄、前山仁郎、桃裕行による宣明暦の研究は、前山仁郎の物故により頓挫しかけたのであるが、内田正男の努力により『日本暦日原典』として結実した。この暦日表は従来使用されていた『三正綜覧』の不備を補い、まさしく原典としての存在価値を高めている。桃裕行亡き後、古典籍による施行暦日との照合は内田正男により継続されており、その成果は『日本暦日原典』の改版(現在4版)に反映されている。先学の成果を踏まえての堅実な研究であることが、書籍リストからうかがえる。その分、新しい研究テーマを想起することは少ないが、日本の暦を考える上での基幹文献といえる。 内田正男の代表的著作は言うまでもなく『日本暦日原典』である。ところがこの著作、新刊では時々、在庫切れを起こすのである。わたしが捜し求めたのもそのタイミングであった。神保町で探しあぐね、見付けたのが池袋の八勝堂書店である。第3版が出ていた時期であったが初版であった。暦法計算には初版で十分であると判断し、高価であったが入手した。その本に挟まっていたのが右図の読者カードと名刺。新城新蔵門下で、薮内清の先輩にあたる人物である。能田氏がお亡くなりになり、遺族が蔵書の整理をして関東に流れたものと思う。古書店でこんな物にまで価値を見いだし値段を付けたのではあるまいし、まあ、面白い物が挟まっていたものである。次に能田忠亮の著作を挙げる。なお代表的著作としては「東洋天文学史論叢」がある。
内田正男の代表的著作は言うまでもなく『日本暦日原典』である。ところがこの著作、新刊では時々、在庫切れを起こすのである。わたしが捜し求めたのもそのタイミングであった。神保町で探しあぐね、見付けたのが池袋の八勝堂書店である。第3版が出ていた時期であったが初版であった。暦法計算には初版で十分であると判断し、高価であったが入手した。その本に挟まっていたのが右図の読者カードと名刺。新城新蔵門下で、薮内清の先輩にあたる人物である。能田氏がお亡くなりになり、遺族が蔵書の整理をして関東に流れたものと思う。古書店でこんな物にまで価値を見いだし値段を付けたのではあるまいし、まあ、面白い物が挟まっていたものである。次に能田忠亮の著作を挙げる。なお代表的著作としては「東洋天文学史論叢」がある。『暦と迷信』 英進社 1949/04/25 「天文年代学」 『天文学の応用』鈴木敬信(編) 恒星社厚生閣 1958/02/28 『暦』 至文堂 1958/06/20 『漢書律暦志の研究』復刻版 臨川書店 1979/02/15 薮内清(共著)
『日本暦日原典』に話を戻す。初版には次のような附録が添付されている。以降の版には無いと思う。事実4版を手に取ったが無かった。円形の計算尺によりヒントを得たと思える干支と暦日の換算具である。OKITAC 5090D のプログラミングで苦労をなされた著者のアイデアと想うが、漢字も画像も音も使える今の環境なら如何に、『日本暦日原典』を作り上げたのであろうか?
なお『日本暦日原典』を購入する際には、必ず最新版をお求め下さい。暦日編の古典籍との照査は勿論、暦法編においても微妙な改訂が行われています。

2005/03/21 ものずき烏 記
(2005/03/20)復刊ドットコムで『暦の語る日本の歴史』の印刷所情報を求めていたので提供した。