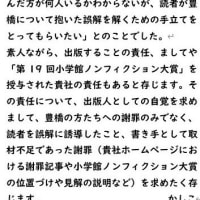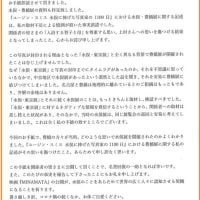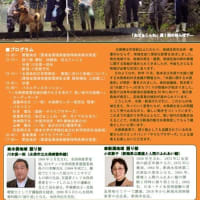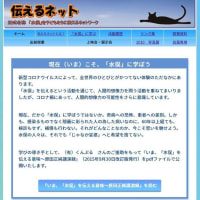ダブルヘッダーの出前はつらいかも
~ 8年目を迎えた大野北小への出前 ~
~ 8年目を迎えた大野北小への出前 ~
2011年2月17日
3,4時限 5年2,3組
5,6時限 5年1,4組
相模原市立大野北小学校5年生4クラス
ランチルームにて
3,4時限 5年2,3組
5,6時限 5年1,4組
相模原市立大野北小学校5年生4クラス
ランチルームにて
 直木賞作家・中島京子さんと行った学校
直木賞作家・中島京子さんと行った学校相模原市内では、南大野小学校に次いで8年前から毎年、出前に行かせてもらっているのが大野北小学校です。
2007年度の出前のときには、トヨタ財団のニュースレターで取り上げてくれて、取材の方も同行されました。そのとき、ライターとして同行されたのが、中島京子さん。すでに小説を書かれていましたが、去年、『小さいおうち』で直木賞を受賞された方です。ああ、直木賞作家となる方と、この小学校でいっしょに給食をいただいたよなぁ、と、思い出しつつ伺いました。
毎年うかがっているありがたさで、伺うとすでにランチルームは昨年と同じセッティングができあがっていました。大野北小は、1階のランチルームを使って行わせてもらっているので、写真パネルの搬入もしやすく、準備がしやすい学校ですが、手助けが嬉しかったです。

去年と同じ体型で出前を始めました
 お父さんもお母さんも生まれていないころのこと
お父さんもお母さんも生まれていないころのこと出前授業のとき、水俣病公式確認の「1956年5月1日」を覚えてもらうようにしています。小学校5年生の子どもたちにははるか昔のことでしょう。
ふと気づいて、このところ「みんなのお父さんやお母さんは生まれていた?」と投げかけると、「生まれてな~い!」と返ってくるのがいつもになりました。「おばあちゃんなら生まれていたよ」と付け足されて、年月の長さを改めて感じます。
そして、改めて気づいたことがあります。
2004年の最高裁の判決のとき、2009年の特措法成立のとき、あるいは、2010年に「ほっとはうす」のみなさんが環境省に直接お願いに行ったとき、と、子どもたちに写真を見せて、子どもたちが生まれたあとに起きたできごと、今年になってからのことを伝えているときに、ふと、気づいたのです。この写真を撮ることができたのは、子どもたちに導かれたから、だと。
「子どもたちに伝える」ために、見たいと思い、知りたいと思い、出向いたことで撮ることができました。目撃することができました。出会うことができました。
子どもたちと向き合うことのフィードバックが、私をその場に立ち合わせてくれたのです。やっぱり、子どもたちこそ、導き手なのでした。

好奇心いっぱいで、手元のPCをのぞきこむ子どもたち
 ダブルの出前はシンドイけれど・・・
ダブルの出前はシンドイけれど・・・いつも、もっとおだやかで、ゆっくり、言葉少なく、子どもたちに伝えられないか、と思っています。
それなのに、「この世に、自分の病気を子どもに身代わりになってもらいたい親なんていない」と言い立てるとき、「とても大切な学びと思うから、いちばん大切なみなさんにお伝えしたい」と言うとき、声を高くしてしまいます。恥ずかしいな、と思い、そんな偉そうなこと言える人間じゃないのに、と思い、子どもたちに伝え終えると、自分で自分のことがいやになります。なので、連日に出前があるときなど、なるべく自分の心を見ないようにしたりするのです。
この日は、ダブルで出前。子どもたちの顔がちゃんと見えることを大切に思うので、4クラスいっしょに、とは思いませんでした。連日の出前もそれはそれで大変だし、1日でおさめるように出前の時間を取ってくれた学校側には感謝しかありません。う~ん、でも、へたり込むように疲れちゃったなぁ・・・。
今は亡き杉本栄子さんが言っていました。出前を終えて帰ってくると、とてもつらくなる、ともらしたとき、「そうか、それを聞いて安心した。そうなら、伝えていってください」と。
私は、水俣病の傷みや苦しみを知りません。自分で自分を問わなければ、その傷みも苦しみも想像していけません。想像しても想像しきれないことに、なおも思いを馳せようとするとき、それを人間的想像力、と呼ぶような気がします。

出前授業が終わっても、子どもたちは写真を見続けてくれました。
これは、胎児性水俣病の半永さんの写真集をのぞきこむ子どもたち。