このところ一日中眠くて眠くて
ダラダラと過ごしているのですが…
そのダラダラさと比例するように(?)
読書のほうはサクサクすすんでいます
というわけで、6月になってから読んだ本は↓

○小路幸也著「シー・ラブズ・ユー」
以前読んだ「東京バンドワゴン」の続編です。
読み終えてしまうのがもったいなくて、ちびちびと読んでいたのですが
これもすごく心温まるお話しでした。★★★
○伊藤たかみ著「指輪をはめたい」
伊藤たかみさんの作品は初めて読みました。
高田馬場やらゲームのライターやら…
私にとっては懐かしいような設定で、読みやすかったです。★☆☆
○恩田陸著「光の帝国 常野物語」
○恩田陸著「蒲公英草紙 常野物語」
常野物語シリーズ?を一気に読みました。
光の帝国のほうは、いくつかのエピソードを集めた短編集で、
蒲公英草紙のほうは長編です。私は長編のほうが面白かったです。
★★☆
立て続けに4冊を読んでいてちょっと驚いたのが、
偶然にも「指輪をはめたい」と「蒲公英草紙」に「辻占」という言葉が
出てきたということなんですよ
「辻占」って知ってましたか?
私は全然知らなかったのですが、Wikiから引用するとー
「辻占(つじうら)とは、日本で行われた占いの一種である。
元々の辻占は、夕方に辻(交叉点)に立って、通りすがりの人々が話す言葉の内容を元に占うものであった。この辻占は万葉集などの古典にも登場する。類似のものに、橋のたもとに立って占う橋占(はしうら)がある。夕方に行うことから夕占(ゆうけ)とも言う。偶然そこを通った人々の言葉を、神の託宣と考えたのである。辻は人だけでなく神も通る場所であり、橋は異界との境をなすと考えられていた。京都・一条堀川の戻橋は橋占の名所でもあった。」
ということなのだそうです…
最初に「辻占」が出てきたときに、「へ~そういう占いがあったんだ~」と
新発見に喜んでいたら、すぐまた別の本にも「辻占」が…って、
ちょっとビックリしますよね~?
昨日の夕方外出した時に、交差点で信号待ちをしていてふと「辻占」のことを
思い出しました。
他人の話していることなんて、そうそう耳にははいらないんじゃあ?と
思っていたのですが、すれ違った人たちの話し声が少しだけ聞こえました。
「あ~~!!あったねぇ懐かしい~!!」
さて、これはどう受け取ったらいいのでしょうか

ダラダラと過ごしているのですが…
そのダラダラさと比例するように(?)
読書のほうはサクサクすすんでいます

というわけで、6月になってから読んだ本は↓

○小路幸也著「シー・ラブズ・ユー」
以前読んだ「東京バンドワゴン」の続編です。
読み終えてしまうのがもったいなくて、ちびちびと読んでいたのですが
これもすごく心温まるお話しでした。★★★
○伊藤たかみ著「指輪をはめたい」
伊藤たかみさんの作品は初めて読みました。
高田馬場やらゲームのライターやら…
私にとっては懐かしいような設定で、読みやすかったです。★☆☆
○恩田陸著「光の帝国 常野物語」
○恩田陸著「蒲公英草紙 常野物語」
常野物語シリーズ?を一気に読みました。
光の帝国のほうは、いくつかのエピソードを集めた短編集で、
蒲公英草紙のほうは長編です。私は長編のほうが面白かったです。
★★☆
立て続けに4冊を読んでいてちょっと驚いたのが、
偶然にも「指輪をはめたい」と「蒲公英草紙」に「辻占」という言葉が
出てきたということなんですよ

「辻占」って知ってましたか?
私は全然知らなかったのですが、Wikiから引用するとー
「辻占(つじうら)とは、日本で行われた占いの一種である。
元々の辻占は、夕方に辻(交叉点)に立って、通りすがりの人々が話す言葉の内容を元に占うものであった。この辻占は万葉集などの古典にも登場する。類似のものに、橋のたもとに立って占う橋占(はしうら)がある。夕方に行うことから夕占(ゆうけ)とも言う。偶然そこを通った人々の言葉を、神の託宣と考えたのである。辻は人だけでなく神も通る場所であり、橋は異界との境をなすと考えられていた。京都・一条堀川の戻橋は橋占の名所でもあった。」
ということなのだそうです…

最初に「辻占」が出てきたときに、「へ~そういう占いがあったんだ~」と
新発見に喜んでいたら、すぐまた別の本にも「辻占」が…って、
ちょっとビックリしますよね~?

昨日の夕方外出した時に、交差点で信号待ちをしていてふと「辻占」のことを
思い出しました。
他人の話していることなんて、そうそう耳にははいらないんじゃあ?と
思っていたのですが、すれ違った人たちの話し声が少しだけ聞こえました。
「あ~~!!あったねぇ懐かしい~!!」
さて、これはどう受け取ったらいいのでしょうか
























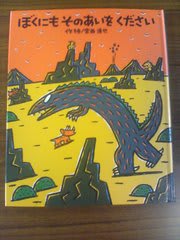



 もう、これは願望ですね(笑)
もう、これは願望ですね(笑)






