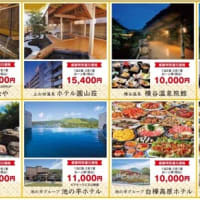いつまでたっても暑い日が続いております。
さて、本日”佐久地域の観光と素材(財)を活かしたこれからの観光とまちづくり”というテーマでシンポジウムが開催されました。
基調講演としてJTBの清水常務と特別講演としてジャーナリストの向笠さんのご講演のあとパネルディスカッションを行うというプログラムです。
結局は人がやるものであり、やる気やふるさとを大事にする意識の問題が重要なのでしょう。
今、佐久の実態を考えたときに高速道路などのインフラの整備されましたが、一方、それがもとで景観を損ね土地を売ったり貸したりというようなことや大型店舗を中心とする生活の流れなど本来の生業から離れているのと都会化が良いことだと考えれているような風潮も事実であります。
佐久の文化づくりの原点は素晴らしいものの成功例を点で表現することではなく、佐久の人や全体が面でおもてなしの気持ちや外部の人を受け入れるという姿勢の意識レベルを引き上げることではないかなと考えます。
恥ずかしいことではありますが、まずは基本に帰り、小学生からも指摘されているごみのポイ捨てや飲酒運転など誰もが不快感を感じる部分のモラル向上というより、当たり前が普通にできるところから始めることが必要でしょう。
それと我々、事業を営むものは売ってナンボです。行政のようにイベントの実施、カタログ作成すること自体が、行政の成果であり評価されるのだと思われますが、儲けて税金を払う我々には、効果がはっきりしない広告宣伝活動であり収入という結果を出さなければ、とても評価される対象とはなりえません。
住民は、シンポジウムをやったこと自体が最終ではありませんし成果とはみません。ここから、行動はどんなことができるかがポイントです。
この点も、シンポジウムの個別テーマとして参加者による分科会形式で本音の議論を掘り下げて欲しかったところです。
私は仕事の関連で30年ほどの間に佐久と東京を何回か引越ししましたが、外部から見る目と佐久住民の目をもっているつもりです。
繰り返しになりますが、本日のこのテーマを掘り下げると佐久の日常の生活や今ここにあるものを大事にしたり、磨き上げることであろうと痛切に感じます。
歯に衣を着せぬJTB清水常務と松本大学の佐藤先生のお話は外部の方の意見としてありがたくまた痛烈なパンチを浴びる思いでした。これを感じない住民や行政であれば発展の道どりは遠いものでしょう。(写真なし)
最新の画像[もっと見る]