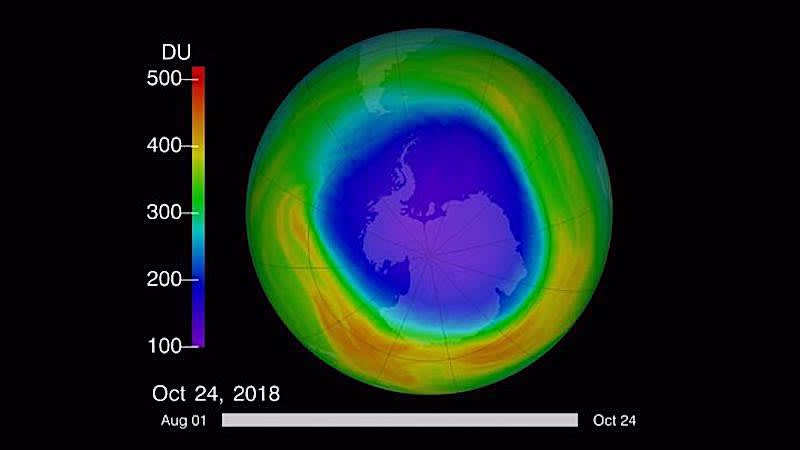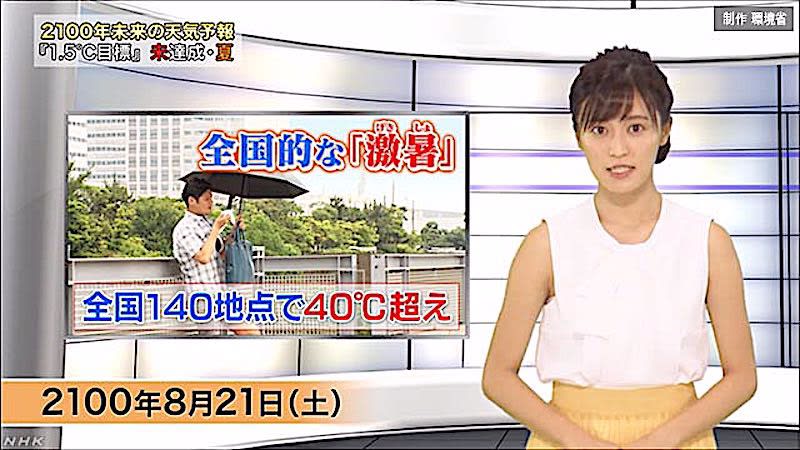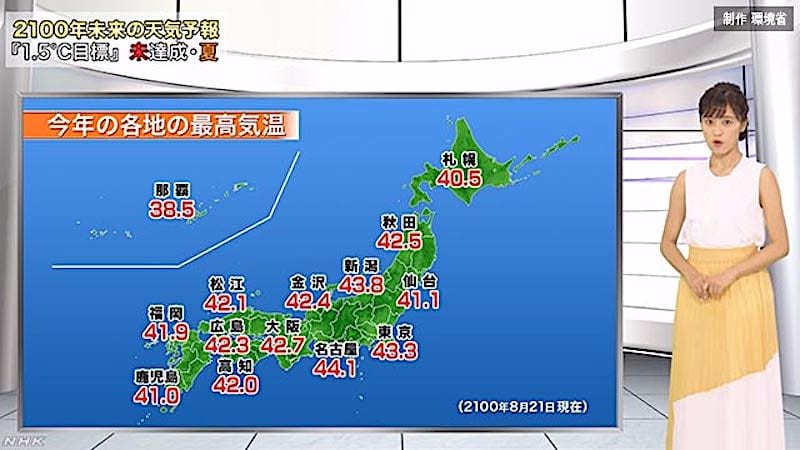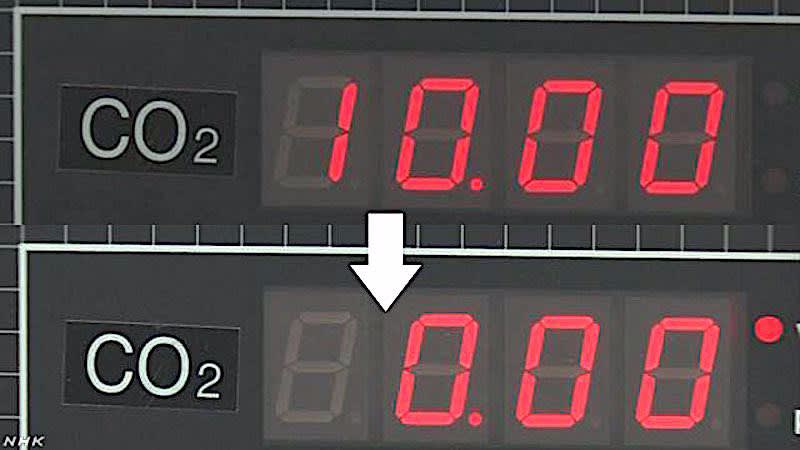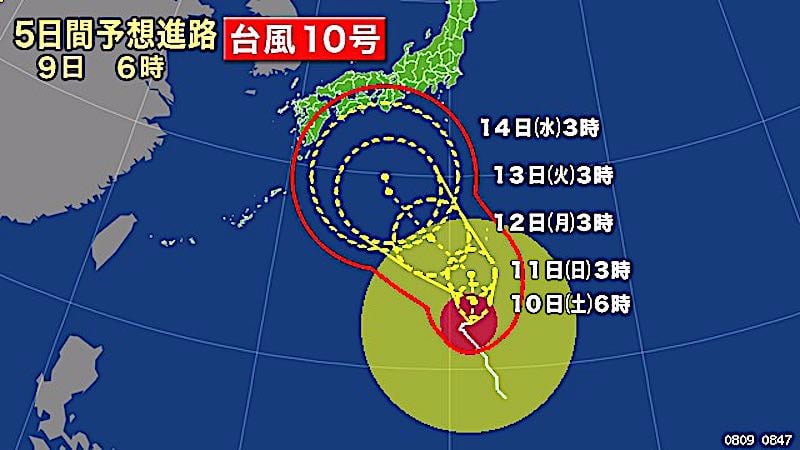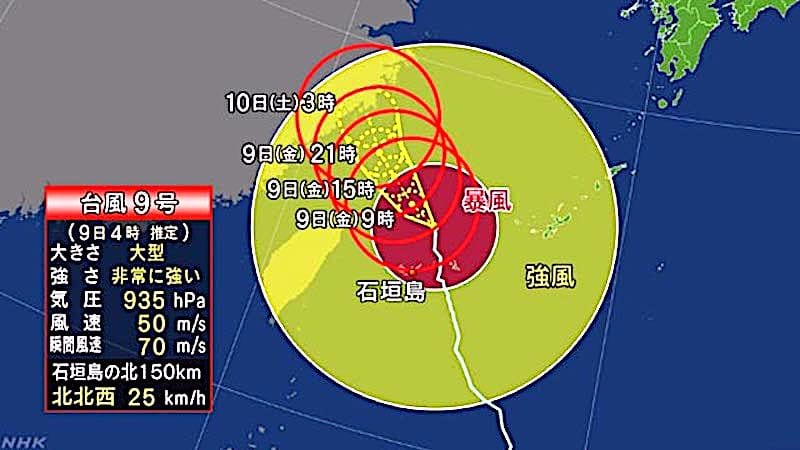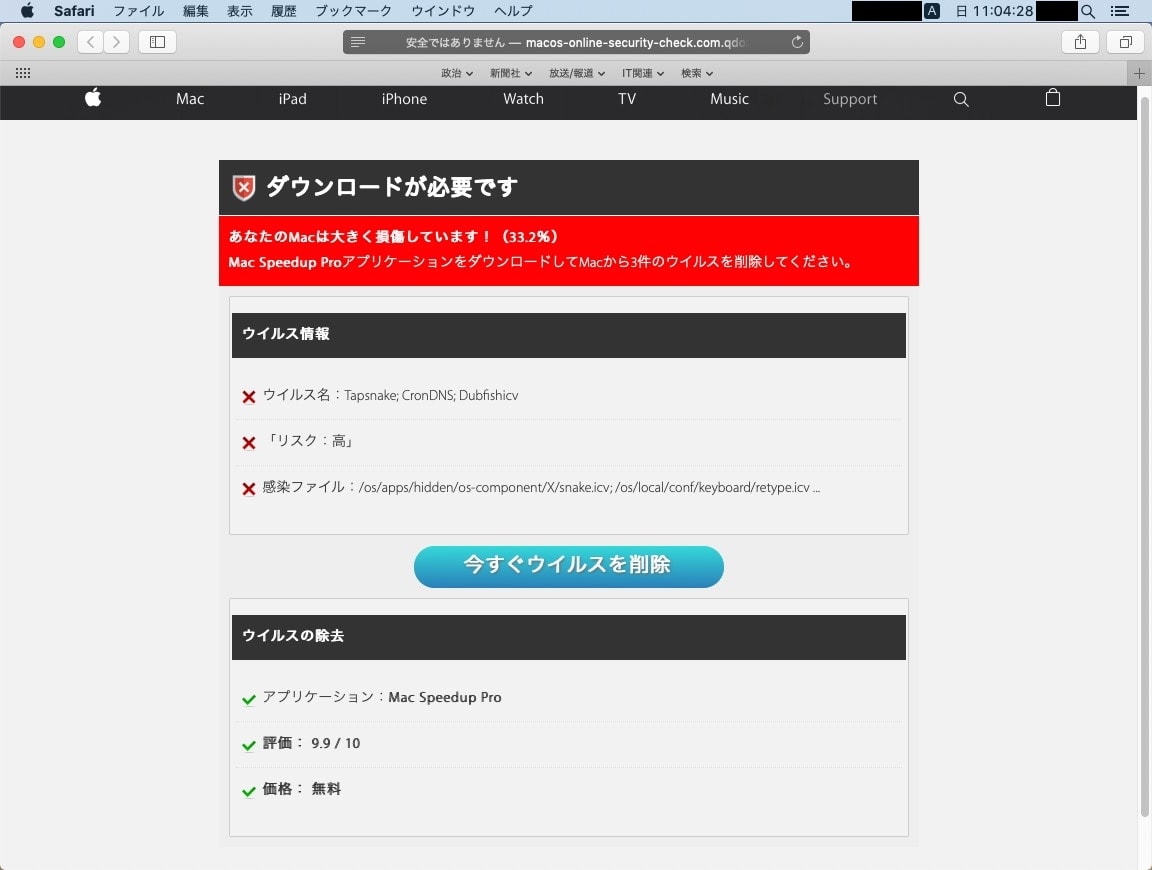以前、イスラエルに現れた有名なUFOの動画。
動画を参照。
【神様?!】エルサレム神殿上空に突然現れた発光体(UFO?!)
92,570 回視聴•2011/02/08
https://www.youtube.com/watch?v=EsOgapHSVV4
エルサレム上空に突如現れた未確認飛行物体UFO
2,000 回視聴•2018/07/10
https://www.youtube.com/watch?v=qBsmPSqX4_A
この映像については、現地の複数の人が、多くの動画で保存し、アップロードされている動画だ。
この飛行物体について、仮に、安倍政権、安倍氏や菅官房などは、どのように考えるか?!。
人間が作った、いわゆるドローンだと思うのか?!。
ドローンの場合、一気にこのスピードで、垂直発進できますか?!。
この映像ひとつ見れば、「人間以外の高等な能力を有する生物が設計し作り上げた!」、としか言いようがない。
現状の地球で、このような「輝く、超高速な飛行物体、作れますか?!」と言う事だ。
それは、「地球以外の高等な生物が存在している!」と言う事にも結びつく。
* 個人的に思うが、イスラエルと米国は、「UFOのテクノロジー」を「既に軍が管理している」と思える。
UFOが、墜落した物体(戦闘機?)を攻撃している動画。
【衝撃動画】UFOがイスラエル軍の戦闘機に爆破される驚愕の瞬間映像!!カナダの安全保障最高機密を知る政府高官が生生しく真実を暴露する...
316 回視聴•2018/03/21
https://www.youtube.com/watch?v=K5PSqlQcnfo
【衝撃動画】UFOがイスラエル軍の戦闘機に爆破される驚愕の瞬間映像!!カナダの安全保障最高機密を知る政府高官が生生しく真実を暴露する.
293 回視聴•2017/10/02
* 最初の映像は合成だと思うが、それ以外の映像は合成ではないと思える映像もある。複数の戦闘機がUFOを護衛するように飛行している映像。TR3Bのような飛行物体も写っている。
https://www.youtube.com/watch?v=EBUUrZv4lGQ
イスラエルが、「UFOのテクノロジー」を所有していると言う事は、米国も同じと言える。
米軍は、TR3Bと言うこれまでにない飛行物体を製造し所有している。


TR3Bの後継機?(合成写真)。一見本物か?!、と思えるほどの出来栄えの良いCGモデルだが、「影の状態」を見れば、CG合成だと、一発で判断出来る。人々の影の位置を考えれば、左側に伸びているが、このことを基に考えれば、飛行物体の影の位置が真下になっており不自然だ。TR3Bは実際にあるが、これはCGの合成写真と言える。しかし、将来的に、これが後継機種として出てくる可能性はある。
https://www.dailymotion.com/video/x6mf6na


これもCGだ。影の方向がバラバラだ。
https://i0.wp.com/pbs.twimg.com/media/DdSgvXzV0AAZBXl.jpg?w=680&ssl=1
https://www.dailymotion.com/video/x6mf6na
本物と思われる動画。(最初の明確な映像と戦車が写っている映像はCGの可能性がある。)
TR 3B Astra
288,602 回視聴•2015/08/27
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=L0QdJgHXBA0&feature=emb_logo
「不明な飛行物体」についての関連する投稿。
05/03 皇居周辺で飛行していた飛行物体は、本物のUFOなのでは?!~ 「紅白点滅」、「場所的な事」を考えれば、「皇室を祝ってくれている可能性」が高い。
2019年05月03日 22時30分22秒 | 社会
https://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/6b14271006325dc7008274ddefdb93e5
世耕大臣は、「思考が固すぎる!」~ おもしろ!「物体の空中浮上技術」~ 原理は本人もわからないらしい。
2018年07月25日 07時48分30秒 | 科学/ハイテク
https://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/8a2fcb3bac2ee113207192bcb958166a
* この空中浮遊技術は、TR3Bの初期技術なのかもしれない。
沖縄の上空に「カラフルなUFOの集団」が出現!(動画付き)。
2014年01月26日 05時50分05秒 | 科学/ハイテク
https://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/821007a4a38e45e49b4b2bbf2dd957ec
ロンドンにUFO出現!~何処かで見たような、、、そうそう、福島・新宿のUFOと似ている!。
2011年07月02日 15時12分31秒 | 科学/ハイテク
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/91c91804f0a49686f86256ba136af6a6
ソーラープレイン~太陽光だけで、26時間連続飛行成功!/中国でUFO出現?、空港が一時閉鎖に。
2010年07月09日 06時08分31秒 | 科学/ハイテク
http://blog.goo.ne.jp/torl_001/e/352c339698641116c0f87b66409c76a9
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12/24 追加記事。
バンクシー氏の新作、「パレスチナ暫定自治区」の「ベツレヘム」で、公開!。


エルサレム神殿上空に突然現れた発光体のような作品になっている。非常に興味深い作品だ!。
個人的には、「バンクシーさん」と、「一度だけ」話した事があるかもしれない。
25年くらい前だったか?、バンクシーさんは、「秋葉原」に来たと思う。
当時、私は、秋葉原の「とある店」で働いていたが、店に来た一人の外国人の客に対して、「Apple系のSoftware」の話を、一通り説明した後、「(店の外の)「壁に、絵を描いても良いですか?(Can I draw on the wall?)」」と突然、質問してきた。
背丈が非常い高い(190cmくらいだったか?)、非常に真面目そうな外国人の青年だった。
そのような事を「うる覚え」だが記憶している。
その当時、「あなたの名前は何と言うのか?!」、と私が問うと、「バンクシー」と述べていた。
その当時、私は全くバンクシーさんの作品について「全く知らなかった」ので、店の壁に絵を描く事については、「私は、経営者ではなかったので、「それは承諾できない」(No!)」と言う趣旨を述べた。
しかし、その日の夕方だったか?、店の壁に、「ネズミの絵が書いてある!」と言う事を述べていた、同社の女子社員がいたのを記憶している。
仕事が忙しすぎたので、私はその絵を見る事が出来なかったが、上司であった当時の部長が、「絵をシンナーで消した」と言う話を「業務が終わってから」後になって聞いた。
別の経理の女子社員は、部長に対し、「それは、バンクシーさんの作品ですよ!」と言う事を知っていたらしく、「消さないほうが良かった!」などと騒いでいた!のを記憶している。
今では有名な「アンブレラを持ったネズミの絵」だが、その当時、見ておくべきだった!。
しかし、多くの客の対応、「製品説明」の為に、手が回らなかった状態であった。
当時、1994~1995年くらい?、だったと思う。
私の記憶では、当時のバンクシーさんは、「非常に誠実且つ、親切そうな真面目そうな青年」であったのを記憶している。
更には、「眼鏡をかけていた」のを記憶している。
多少話したが、バンクシーさんは、「UCLA」か、「MIT」出身のどちらかだったと思う。
私の記憶が間違っていなれば、確か、どちらかだったか、そのように述べていたと思う。
当時を考えても、バンクシーさんを見た感じ、話した感じでは、「非常に誠実且つ、誰であったとしても信用できる風貌の青年」であった。
おそらく、「私の記憶は間違っていない」と思う。
そういえば、バンクシーさんの作品の中で、「アンブレラを持ったネズミの絵」の中で、「眼鏡をかけたネズミの絵」は、なかったか?!。
当時のバンクシーさんは、「真面目そうな眼鏡をかけていた」のを記憶しているが、「ネズミがかけていたメガネ」と似ていたのでは?!、と、そのように思う。
しかし、バンクシー氏の絵は、素晴らしい!。
「絵自体が生きているね!」。
記事参照。
バンクシー新作公開 イスラエルのパレスチナ占領政策を風刺か
2019年12月23日 22時33分
クリスマスを前に、鋭い社会風刺画で世界的に知られる覆面アーティスト「バンクシー」が、イエス・キリストの誕生になぞらえてイスラエルを風刺する新作を公開し、話題となっています。
バンクシーの新作が公開されたのは、キリストの生誕の地とされるパレスチナ暫定自治区のベツレヘムです。
作品は、「ベツレヘムの傷痕」と名付けられ、キリスト生誕を表現したミニチュアの背後には、灰色の壁がそびえ、イスラエルとパレスチナ暫定自治区を隔てる「分離壁」とみられます。
壁の中央には、キリストの生誕を知らせたとされる「ベツレヘムの星」のように、銃弾の痕が星形につけられていて、イスラエルによるパレスチナの占領政策を風刺する内容とみられています。
作品が展示されているのは、バンクシーが手がけたホテルで、客室からは分離壁が見えることから「世界一眺めの悪いホテル」と呼ばれていて、支配人は「クリスマスの発祥地であるベツレヘムでの今の暮らしがどのようなものかを表している」と話しています。
ベツレヘムではこの時期、恒例のクリスマスのミサを目当てに、世界中からキリスト教の巡礼者や観光客が訪れていて、バンクシーからのクリスマスプレゼントだと話題となっています。
あわせて読みたい
空を見上げる謎のネズミ 描いたのは誰?News Up 1月23日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191223/k10012226101000.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
12/24 追加記事。
日本のメディアでは、「全く報道していなかった!」が、「米海軍は、今年の4月に「未来型の超高速UFO型の飛行機」の設計を行い、「特許」を取得していたようだ!」。
記事参照。



https://i1.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/SEI_63126404.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=512%2C674&ssl=1

https://i1.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/SEI_63126403.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=540%2C410&ssl=1



https://metro.co.uk/video/u-s-dod-video-f-18-super-hornet-unknown-object-1592708/?ito=vjs-link


https://i0.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/SEI_55715154.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=540%2C663&ssl=1


https://i0.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/prc_63477922-0e11.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=540%2C284&ssl=1

https://i0.wp.com/metro.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/screenshot-2019-01-17-at-13.12.45-0e6f.png?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=540%2C433&ssl=1

https://metro.co.uk/2019/04/18/us-navy-secretly-designed-super-fast-futuristic-aircraft-resembling-ufo-documents-reveal-9246755/
* しかし、「TR3B」も含め、「瞬間的移動」が出来る物体の場合、「中にいる操縦士、乗務員」などの「身体的保護」については「どのような仕組み」で問題がない状態になっているのか?!。
現状では、非常に謎だ。
やはり「これまでにない技術」の「複数の組み合わせ」で、成り立つのであろう。
「極少数の、非常に能力の高い人たち」が、地球のどこかで、「世間、社会と完全隔離状態!」、「絶対秘密厳守」の状態で「新規開発!」してきた可能性は考えられる。
米国、ネバダ州にある、米軍施設「エリア51」のような場所でだ。
しかし、「これまでにない、複数のUFOテクノロジー」を開発するまで、「現在の人間の能力だけで完成させる事が出来た?」のか?!」、と言う疑問が残る。
「この事」を考えた場合、やはり、「人間以上に高等な生物」から「教えてもらった!」と言う考えの方が自然なのではと思える。
人間の学習は、「自らよりも高度な人」に教えてもらって、「高度な人間へ成長して行く」のだ。
アフリカなどでは、「ゴリラに育てられた人間の赤ちゃん」が居るようだが、その子供は成長しても、当然ながら、人間の話は全くわからない状態だ。その代わり、嗅覚などの動物的な感覚は、「人間以上に発達」しているようだ。
そのような事も含め考えてみると、「米海軍が特許を取得した、これまでにない新たなテクノロジー、技術」については、「人間以上に高度な何者か」に「教えてもらった!」と言う方が自然ではなかろうか?!。
そのような「これまでにない、超ハイテクな技術」については、「安易な情報公開は無理であり、危険であり、してはならない!」と言える。
そのくらいの状態でないと、新規開発している米国の一部の組織も含め「世界全体が危険に曝される!」と言う事になる。
仮に中国共産党やロシアなどが「この技術」を手に入れた場合、大変な事になってしまう。
米国政府だとしても、リーダーが、ヒトラーのような人の場合も、大変な事になってしまう。
「超ハイテクな製品」を製造するならば、それが完成した場合、その後どうなるのか?!、と言う事も十分に考え抜かなければならない。
それが開発者の責任だ。
新たなUFOテクノロジーを商業ベースで使用する場合、非常にパフォーマンスの良いメリットが得られると思うが、「デメリットも考え抜かなければならない」。
「金が儲かる!」と言う事で、安易な使用を行えば、「その後、大変な事になってしまう可能性が高まる!」。
米国政府の要人の中でも、「特に能力の高い人たち」については、この事について真剣に考えていると思う。
仮に軍事利用すれば、圧倒的なパフォーマンスが得られ、企業としてライセンスを得られれば、「これまで以上にかな儲け出来る!」と言えるが、米国、米国政府としても脅かされる事にも繋がる。
その部分が、現在の人間にとって、超高度技術を扱う上で、「最も重要な部分」になると言える。
超高度技術は、多大な恩恵がある反面、これまでにない非常に危険な技術にも繋がると言う事が言える。
この事は原水爆や、原子力程度の危険性ではない事を意味するものだ。
米国政府の一部で、開発出来たとしても、地球のどこかで戦闘が起こっている状態では、米国政府としても「存在すら話す事は出来にくい」と言えそうだ。
「地球が完全に平和になった場合」、「新たなUFOテクノロジー」は公開されるべきだ。
現状の人類としては、「まだ所有するべきではない技術」なのでは?!、と言える。
製造技術が漏洩した場合、軍事利用などでも使用され、危険に晒される事になるが、その時に、止められる技術を同時に開発しておかないと、大変な事になってしまうといえる。
「新たなUFOテクノロジー」と比較して技術的には非常に原始的だが、「現在の原子力技術」も同じ状態になっている。
人類は原発を開発し、発電出来るようになったが、爆発した場合の汚染処理が完全に出来ない状態だ。
「新たなUFOテクノロジー」も、情報公開が早すぎると、「解決できない」「同じような問題」が発生する事になると予想出来る。
「製品開発」と「万が一の場合の責任」は、「バランスしている事」が非常に重要だ。
片一方だけの場合は、「技術が確立していない」事と同じだ。