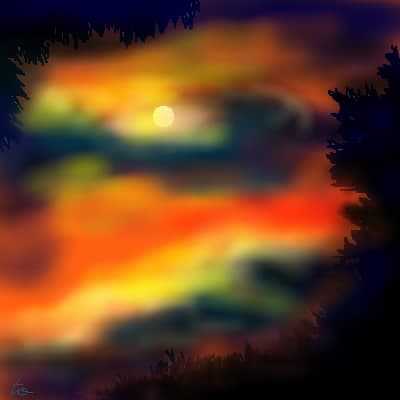望みたい、見つめて・見せて

望見、陽溜―another,side story「陽はまた昇る」
穏やかな曲が、周太の浅い眠りを覚ます。
ぼんやりとした視界の時刻は23:55、静かに通話ボタンを押した
「いま起きたとこだろ」
きれいな低い声。
浅い眠りの中でも待っていた、その声が嬉しい。周太は微笑んだ。
「…ん。仮眠とってた」
今夜の周太は当番勤務だった。
寝起きの声が恥ずかしい。けれどやっぱり、今夜はこの声を聴きたかった。
「あと4分間は眠っていいから、おやすみ」
「…いや。起きていたい」
寝がえりをうちながら、眠気の吐息がこぼれてしまう。
夢現の意識が、聴き慣れた声まで非現実に感じさせる。
もっとちゃんと、この声を感じたくて、起きていたい。
「周太、今、ひとり?」
電話の声がやさしい。
穏やかさが心地いい、つい睡魔に掴まれそうになる。
「…ん、そうだけど」
「そっか。じゃ、良かった」
なにが良かったのだろう?宮田はたまに、不思議なことを言う。
なんでなのか聴きたいのに、電話の向こうは気配が、静かになった。
待って、もっと声を聴いていたい。周太はそっと唇を開いた。
「…みやた、」
「おう、どうした?」
「でんわ、うれしいから」
電話の向こうで、きっと宮田は微笑んだ。その気配が嬉しい。
こんなふうに、電話をくれることが、うれしい。
あ、また今きっと、宮田が笑った。
そんなふうに感じた耳元に、きれいな低い声が言ってくれた。
「おはよう周太、誕生日おめでとう」
いま日付が変わった。
今日は11月3日、周太の誕生日。だからこの隣は、こうして電話を繋いでくれている。
そんなふうにいつも、自分を充たそうとしてくれる。その想いが嬉しくて、周太は微笑んだ。
「ん、おはよう…そして、ありがとう」
電話で繋いだ隣が笑う。いまきっと、きれいな笑顔が咲いている。
「あと9時間したら、新宿へ迎えに行く」
「ん、迎えに来て」
迎えに来てくれる。
自分の誕生日の為に、迎えに来てもらうこと。周太にとって初めてのこと。
こんなふうに嬉しいなんて、今まで知らない。
嬉しい。微笑んでいく心に、また隣がきれいな声で言ってくれる。
「公園を少し歩こう。それから買物をして、川崎の家へ行こう」
「…ん。ありがとう」
今日、周太の母親と宮田は会う。
警察学校時代の外泊日、一度だけ二人は会っている。
そのときの、自分のアルバムに微笑む、ふたり並んだ姿。
なんだか二人とも、とても、きれいに見えた。
親子の年の差の二人。それなのに、きれいに自然に寄り添っていた。
ほんとうは少し、妬いていたのだと、もう今なら解る。
あの時は、こんなふうになれるなんて、思っていなかった。
今日、二人はどんな話をするのだろう。
「周太、」
ぼんやりとした意識へと、きれいな低い声が、静かに名前を呼んでくれた。
名前をこうして呼んでくれる。それだけでも、嬉しい。
きれいな隣が、電話の向こうで微笑んだ。
「大好きだよ周太、一番大切だよ。だからずっと隣にいさせて」
こんなふうに名前を呼んで、こんなふうに求めてくれる。
どちらも初めてのこと。そしてどちらも幸せで、うれしい。
嬉しくて、素直に周太は頷いた。
「ん。…嬉しい。ずっと隣にいて、もう手放さないで」
「絶対に離さない、だからずっと俺だけの隣でいて」
「…ん、いる」
どうしよう。
こんなふうに求められて、嬉しくて仕方ない。
いつも強く掴まえて、離さないでいてくれる、この隣。
昨日の射撃競技大会でも、不安ごと全て受けとめて、支えてくれた。
だから思ってしまう。きっとずっと、この隣で自分は生きていける。
電話を繋げたまま眠って、AM3:00、周太は目を覚ました。
一緒に当番勤務の若林と交代して、交番表の席に座る。
眺める深更の街は、華やかなネオンも疲れて見えた。
街の気配へと意識を向けながら、当番記録を周太は開いた。
この新宿駅東口交番を訪れた人々と、管轄内で起きた事柄の記録。
道案内を求めるものが多い、駅前という立地条件では当然のことだろう。
夜間にはケンカの仲裁が多い。
周太は外へと目をあげた。
騒がしい光の色が視界へと映りこむ。
東洋の不夜城と言われる繁華街。あの街から流れだす感情が、ケンカの仲裁という業務を作りだす。
卒業配置から1ヶ月。当番勤務の夜間巡回に、もう何度かそんな業務も果たした。
ケンカする本人達を引き離して、交番で事情を聴く。
そんな時いつも、周太は茶を出してやる。先輩の柏木がする真似だった。
けれど茶の一杯で、人の表情は随分と変わる。少しほぐれた雰囲気が、彼らの頑なな口も開かせた。
時間と共感、その二つが人の心を開いてくれる。そんなふうに最近思う。
当番記録のファイルから、13年前のものを選ぶ。
父が射殺された場所は、この東口交番の管轄内。その事件の記録はもちろん、この中に綴られている。
当番勤務の夜、今のように一人きりの時間がある。
そんな時を見計らって、このファイルを周太は開いた。
父の事件と、その前後の記録のほとんどを、既に周太は記憶している。
前後に起きた事柄、訪れた人間。
それらのなかに、父の真実へのヒントが隠されている可能性がある。
記憶されたデータを整理し分析する、そうやって少しでも情報を得たかった。
このファイルを開くのはこれで3度目、今回でほぼ全部の記憶が終わる。
眺めるだけの顔をして、素早く事件と人物を記憶していく。
メモは敢えて取らない、筆記は残されてしまうから。
記憶のファイルだけでも、周太の頭脳には充分だった。
記憶が終わってファイルを棚へ戻した。
ほっと息を吐いて、外を見る。
視線の先で灰色のビルに、あわい紅色の光が射しこんだ。
奥多摩で見た、あの朝。
山の稜線が、暁の光に輝いて、木々の息吹が目覚めだす。
空の彩色が刻々と変わり、明けの明星がかがやく、美しい山の朝。
ビルに射す朝の光に、あの美しい朝が蘇ってしまう。
瞳の底が熱くなりそうで、周太はゆっくり瞬いた。
今日は11月3日、自分の誕生日。
その朝に、父の事件を追いかけて、こんなふうに朝を迎えている。
解って選んだ道、それでもこんなに、虚しさが痛い。
あの朝が、恋しい。
あの朝を抱いてくれた、あの隣が、恋しい。
どうか今すぐに、あの隣に笑って名前を呼んでほしい。
今、自分を覆ってしまう、虚しさも痛みも、全て抱きとめて笑ってほしい。
離さないと、隣にいるよと、きれいに笑って見つめていて。
「みやた、」
ちいさな呟きが唇からこぼれる。
そのすぐに、携帯がポケットで3秒間、振動した。
とりだして開いた携帯の、受信メール。求めていた送信元だった。
短く3秒間の振動。けれどその3秒が周太には幸せだった。
「…どうして、」
どうしていつもこんなふうに。
その「どうして」がいつも、あたたかい。
あたたかさが嬉しくて、微笑んで、そっと受信メールを開いた。
From :宮田
subject:誕生日の朝
File :【夜明けの奥多摩の空】
本 文 :明日朝の眺めの方がきれい、だから一緒に
きれいな夜明けの空が写っている。
今日、周太の誕生日の奥多摩は、きれいな朝を見せてくれている。
いつかこの朝を毎日見たい、あの朝からずっと、そんなふうに想っていた。
こんなふうに、求める気持ちに気付いて、写真を送ってくれる。
その心遣いが嬉しい、自分に向けられている、あの隣の想いが嬉しい。
きれいだなと眺めて、本文が気になった。
どうして「明日の朝の方が」きれいだと、今、もう解るのだろう?
「だから一緒に」って、何が一緒なのだろう?
明日の朝はたぶん、周太は実家の部屋にいる。
今日は当番明けで非番になる、そして明日は週休。
久しぶりに2日間が自由になる、だから実家で過ごす予定にしている。
誕生日の今日は、母に感謝を伝えて過ごす。
そして明日は家事を手伝って、昼過ぎには新宿へ戻る。
それから。それから今日は、宮田が実家へ来てくれる。
周太の母へ挨拶をして、父の書斎を訪れてくれる。
―俺も週休だからさ、一日一緒にいられるんだ
昨日、そんなふうに、宮田は言ってくれた。
そういえば、一日一緒って、いつまでなのだろう。ふと気になって、周太はメールの文を呟いた。
「明日の朝の眺めの方がきれい、だから一緒に」
宮田は、今日が週休だから、明日は日勤で仕事がある。
けれど、川崎から青梅署まで1時間半。明日朝に発っても、仕事の時間に帰れる距離。
「あ、」
周太の首筋が熱くなっていく。
前にも宮田はこんなふうに、「眺め」を景色以外の意味で遣っていた。
そして明日の朝に一緒なのは、たぶんきっと、そういうこと。
時計は6時前、6時には柏木が交替に降りてくる。
それまでに首筋をどうにかしたい、周太は外へ出た。
都会の埃っぽい中心、それでも南の方から森の風が吹いてくる。
あのベンチの方からそっと、清々しい空気が頬を撫でた。
すこし落着いて戻ると、柏木が笑って迎えてくれた。
「あと2時間で当番勤務は終わる、それでも疲れただろう」
そういって休憩時間を勧めてくれる。
正直、いま休憩時間は嬉しい。この首筋を赤くした本人の、声を早く聴きたい。
周太は心から礼を言って、休憩室で座りこんだ。
扉を閉めて直ぐに、着信履歴から通話ボタンを押す。
コールも待たず通話になって、きれいな低い声と繋がった。
「赤くなって困った?」
可笑しそうな声が、すこし憎らしい。
けれどやっぱり、ほんとうは、声を聴けて嬉しい。
田中を眠りに誘った、奥多摩の氷雨の夜。
あの夜にもう、自分自身にすら隠していた不安と本音を、思い知らされてしまった。
だからもう今は、ただ素直に想って、言葉にできる。
でもやっぱり恥ずかしい。けれど周太は唇を開いた。
「…ん、困った。でも…嬉しい」
電話の向こうで、わずかな一瞬だけ途惑って、すぐに笑ってくれる。
それから静かに言ってくれた。
「明日の朝も一緒にいたい、周太の隣にいたい。本当は今だって一緒に居たかった、だから明日は隣にいさせて」
こんなふうにいつも、ほしい想いも言葉もくれる。
どうしていつもこんなふうに、孤独から浚ってくれるのだろう。
そしていつも気がつくと、幸せへと浚われている。
嬉しくて、周太は微笑んだ。
「…ん。嬉しい、一緒にいて」
「良かった、」
嬉しそうな笑顔が、電話越しに伝わってくる。
こういうのは嬉しい、素直にそう思えてしまう。
けれどすぐに、悪戯そうな気配を含んで、宮田が言った。
「実はさ、周太の母さんから昨夜、電話もらったんだ」
「お母さんから?」
昨日、当番勤務へ入る前に、宮田も一緒に帰ると母へ電話した。
嬉しいなと笑って、けれど、母は特に何も言っていなかった。
なぜ電話したのだろう。考えていると、宮田が教えてくれた。
「ぜひ泊ってね、周太のベッドを準備しておくから。そんなふう言ってくれたよ」
こんなのってちょっとひどい。
なんだか罠にはめられていくみたい。
自分のしらないところで、ふたりでそんな事を決めてしまうなんて。
こんなの、あんまりにも、恥ずかしい。
「…っ」
「…あ、周太もしかして、…怒ってる?」
言葉が出てこない、こんなこと慣れていない。
ちょっとあまりにも、恥ずかしくて、どうしていいのか解らない。
けれど電話の向こう、きっと少し途惑っている。自分を、怒らせたのかと不安がって。
きっと今、きれいな端正な顔が悲しそうになっている。
こんなふうに、自分が誰かの気持ちを支配するなんて、途惑ってしまう。
けれどこういうふうに、自分の気持ちに心を動かしてくれること。嬉しくて、それが嬉しくて、あたたかい。
頬は赤いまま、周太は微笑んだ。
「…恥ずかしいだけ。でも、お願い…母の言う通りにして、」
電話の向こう、息を呑むような気配。
不思議な気配が、なんだかよくわからない。
けれどすぐに、きれいに笑って宮田が言ってくれた。
「9時に迎えに行く。そのまま明日の朝5時まで、ずっと隣にいさせて」
「…ん。迎えに来て、隣にいて」
今は6時、そして3時間したら、あの隣が迎えに来てくれる。
8時になって当番勤務が明けた。
急いで新宿署へ戻って、携行品を保管へ預けて、勤務明けの風呂を済ませる。
自室へ戻って、仕度しておいた鞄をもって廊下へ出た。
外泊許可は昨日もう取り付けたから、そのまま駅へと向かった。
卒配期間の外泊は厳しい。けれど競技大会の為にほぼ無休だった為か、思ったより楽に許可が出た。
昨日の競技大会の結果は、自分の進路を支配するのだろう。
それでも、もう信じている。どんな事になっても、あの隣は自分を離さない。
だから今日もこうして、会う約束が果たされる。
警察官の自分は、約束なんて本当は出来ない。危険に向かう仕事だから。
それ以上に、あの隣は山で生きる警察官、自分以上の危険の中で生きている。
それでも、もう信じている。あの隣との約束は、きっと全部が果たされる。
だから信じてしまう。どんな進路を選ばされても、きっと、あの隣が自分を守ってくれる。
あの強い腕で掴んで、ずっと自分を離さない。
思ったより風が冷たい。
見上げた街路樹の銀杏は、あわく黄葉をみせ始めている。
秋が深くなるなと周太は思った。
待ち合わせの改札へ行く途中で、急に誰かが周太の前に立った。
チャコールグレーのジャケットの胸と、ぶつかりかける。
驚いて見上げた視線の先で、きれいな宮田の笑顔が咲いていた。
「おはよう、」
こんなふうに急に現われるなんて。
心の準備が出来ていない、途惑ってしまう。
一瞬忘れてしまった言葉を、思い出して周太は言った。
「…あ、おはよ」
宮田の視線が、さっと周太を眺めまわす。
今日の服装、どこか、おかしかったのだろうか。
そんな心配をしながら、周太も宮田をそっと眺めた。
濃いチャコールグレーのジャケットから覗く、白いシャツはあわく紫がかって、大人っぽい。
黒紺青のスラックスに併せた、きれいな茶色のベルトや靴がこなれている。
ざっと巻いたマフラーの、深いボルドーに紺と淡いグレーのラインがきれいだった。
スーツでは無いけれど、なんだか改まった雰囲気。
昨日もあったばかり。それなのに、宮田はまた少し、大人びている。
なんだか緊張してしまう、面映ゆさを周太は持て余した。
けれど宮田は微笑んで、マフラーを外した。
「風邪ひくよ、」
自分のマフラーを、周太に巻いてくれる。
悪いよと目で言ったけれど、やさしい笑みで返してくれた。
「後で周太の買ったら、返してもらうから」
「でも、」
「いいから。あ、やっぱり似合う。かわいい周太」
どうしてこう、気恥ずかしくなる言い方するのだろう。
困ってしまう。けれど、気遣いが嬉しい。
いつもこんなふうに、そっと気遣ってくれる。
こういう繊細で、さり気ない優しさが、好きだなと思う。
それから、きれいに笑って、宮田は言ってくれた。
「あらためて、誕生日おめでとう」
そうだった、なんだか緊張して忘れていた。
今日は自分の誕生日で、そのために宮田は来てくれた。
昨日は大会の為に来てくれて、今日もまた来てくれた。
こんなふうに、誰かが来ること。周太には初めての事だった。
そしてその初めてが、この隣だということが嬉しい。
周太は口をほころばせた。
「ありがとう…うれしい」
きれいな笑顔で宮田が笑ってくれる。
きれいな低い声で、静かに周太に告げてくれた。
「周太が嬉しいと、俺も嬉しい」
いつものパン屋でクロワッサンを2個買う。
当番勤務明けで急いだから、周太はまだ、朝食を摂っていなかった。
いつもの公園のベンチに座って、缶コーヒーを開けた。
ベンチにふる木洩日が、陽だまりをつくって温かい。
少し離れたところで一叢、すすきが銀色の穂で揺れている。
熱いコーヒーの香にほっと息を吐きながら、クロワッサンを齧った。
クロワッサンは、以前はあまり食べなかった。
オレンジを使ったデニッシュが多かったかなと思う。
けれど、この隣が食べている顔が、幸せそうだから。
そんなふうに、周太はクロワッサンを好きになった
木々の葉擦れの合間から、そっと鳥の囀りが聞こえてくる。
奥多摩ではもっと、鳥の声が聞こえるのだろう。
昨日も今日もこうして座って、そんなことを考えていられる。
隣の静かで穏やかな空気が、昨日も今日も、嬉しい。
「なんだか、不思議だな」
周太の唇から言葉がこぼれた。
どうしてと、目だけで宮田に聴かれて、周太は続けた。
「昨日もここに一緒に座って、今日も一緒に座っているだろ」
「うん、」
「2日続けては、初めてだなと思って」
外泊日の時はいつも、日曜は昼を一緒に食べると、そのまま寮へ戻っていた。
続けてこうして寛げる、こういうのが毎日続いたら。
そう思いかけて、首筋が熱くなってきた。
困ったなと思っていると、きれいな笑顔で宮田が笑いかけてくれた。
「続けて周太の顔を見られて、俺は嬉しいな」
「…ん、俺も」
自分と同じ事を想ってくれている。
それが嬉しくて、短いけれど、素直に周太は言ってしまった。
きっと今、頬も赤くなっている。
公園を後にして歩きだすと、振り向いた宮田が笑いかけた。
「ちょっとさ、買物つきあってくれる?」
「ん、いいけど」
どこに行くのかなと見ていたら、アウトドア用品店の扉を開けた。
ウェアのコーナーに行くと、宮田は周太の方を少し眺めて、手早く選んでいく。
「これとこれ着て」
「…え、」
なんで自分が着るのだろう。
宮田のウェアを買うと思っていたから、周太は不意をつかれた。
「ほら早く、周太」
笑顔の宮田に、試着室へと押しこまれてカーテンを閉められた。
とりあえずやっぱり、着ないといけないのだろう。
周太は着ていたショートコートを脱いだ。
「着れた?」
カーテンを開けて、ぎこちなく靴を履く。
見上げた宮田の笑顔が、楽しそうに自分を眺めてくれる。
あわいブルーの登山用ジャケットと、緑と茶色を足したような色のカーゴパンツ。
袖の縦ラインの、白と深いボルドーがきれいだった。
この間もそうだった。宮田は周太に、きれいな色の服を選んでくれる。
暗い色ばかり自分では選んでいたから、本当は少し途惑う。
けれど、選んでくれる色は、着てみると意外に似合う気がする。
そしてどれもいつも、着心地が良い。
外へ出ると宮田は、肩から提げた髪袋のひとつを示した。
「誕生日プレゼントだから、」
なんだか嬉しそうに、笑いかけてくれる。
登山用のジャケットとパンツ、それからTシャツ。
この間も服を買ってくれた、あれは電車代の分だけれど。
けれど、いくらなんでも、貰いすぎだと思う。
「そんなにたくさん、悪いから」
遠慮がちに周太は言ったけれど、いいんだと宮田は微笑んだ。
「雲取山に連れていく約束だろ?その為のだから。約束の為だから、遠慮なく受取ってよ」
言いながら宮田は、周太の顔を覗きこんでくれる。
見上げた笑顔が、きれいで穏やかで、やさしい。そしてなんだか頼もしい。
こんなふうに笑いかけられたら、甘えてもいいのかな。そんな気持ちになってしまう。
それにやっぱり嬉しい、どうしよう。そんなふうに思いながら、周太は唇を開いた。
「近々、まとまった休暇がもらえそうなんだ。大会前はあまり休み無かったから、4日くらい貰えるらしい」
聴いていた宮田が、嬉しそうに笑って提案してくれた。
「決まったら教えて。山荘の予約するから」
山荘に泊れる。
もし晴れていたら、星の降る夜が見られるのだろう。
幼い頃の、父と母との幸せな記憶が蘇る。
もう二度と、そういう幸せは自分には無い。そんなふうに思っていた。
けれどきっと、この隣は約束を果たしてくれる。
嬉しくて、周太は微笑んだ。
「ん、うれしい」
「おう。周太が嬉しいと、俺はうれしいよ」
そんなふうに宮田が笑ってくれた。
こんなふうに言われるのは、嬉しい。でもやっぱり恥ずかしい。
首筋が熱くなってくる。マフラー巻いてもらって、良かった。
そんなことを考えていたら、この間も入った店の前にいた。
「ちょと寄らせて、」
周太に笑いかけて、宮田は扉を開けた。前の時と同じ店員が、微笑んで迎えてくれる。
宮田は彼女に笑いかけた。
「こんにちは、マフラーは出ていますか?」
「はい、先日入荷してあります」
2階へと案内してくれて、ごゆっくりどうぞと彼女は声をかけてくれた。
けれど宮田は、すぐに選んで周太に微笑んだ。
「ほら、行くぞ」
宮田は、即決力が秀でている。
こういう時いつも、本当はちょっと感心してしまう。
こうした判断の速さは、警察学校の講義や生活でも感じていた。
そしていつも、宮田の選択は的確だと思う。
こういう判断力の早さは、山岳救助隊には向いているだろう。
そんなふうに考えていたら、いつのまにか会計も済んで、外へ出ていた。
隣が楽しそうに笑いかけて、長い指でそっと周太の顎を持ち上げた。
「ほら、こっち見てよ」
襟元のボルドーのマフラーが外されて、新しいマフラーが巻かれていく。
あわいブルーにボルドー、白から黒の濃淡が、ストライプになっている。
風にゆれてのぞいた裏は、グレーに似ている水色だった。
「よく似合うよ周太、」
笑いかけてくれる、きれいな笑顔が嬉しい。
きれいな色も、嬉しいなと思う。
けれどさっきも、プレゼントだと貰ったばかりで、気が引ける。
困って周太は隣を見あげた。
「…ちょっと貰いすぎだと思う、」
「前も言ったこと、もう一度聴きたいのか?」
言いながら、隣は顔を覗きこんでくる。
きれいな端正な顔には、悪戯な笑みが浮かんでいた。
きっとたぶんまた、恥ずかしい事を言うつもりなのだろう。
それでもやっぱり、申し訳なくて引き下がれない。周太は口を開いた。
「…でも、」
「これ着た周太を連れて歩きたい。そういう俺の我儘きいてよ」
言って言い返された、その笑顔が優しい。
それにいま「わがまま」と言われた。
宮田は自分に、わがままを言ってくれるのだろうか?
訊いてみたい、周太は尋ねた。
「わがまま?」
周太の問いかけに、隣は笑って頷いてくれた。
「そう、俺の我儘」
うれしい、周太は微笑んだ。
いつも自分ばかりが、この隣に我儘を訊いてもらっている。
そんなふうに本当は、すこし後ろめたかった。
だから出来たら自分も、我儘を言ってほしい。そんなふうに思っていた。
やさしい宮田。だから多分、遠慮させない為にこんなふうに言ってくれている。
だけど多分「わがまま」も本音から言ってくれている。
宮田はいつも率直で、心に思ったことしか言わない。
言葉の裏なんて考える必要がない、だからいつも、楽に隣に居られる。
そして宮田の心はいつも、やさしくて暖かい。
そういう全てが嬉しい。周太は微笑んだ。
「ありがとう、」
「こちらこそだよ、」
きれいに笑う、この隣。
こんな時はいつも思ってしまう。ずっと隣にいてほしい。
駅まで戻ると、見覚えのある花屋が目にとまった。
父の亡くなった場所へ手向けた花束を、宮田が抱えてくれた店。
母への花束を作ってもらおうかな、そう思っていたら宮田が立ち止まった。
「ちょっと寄らせて」
周太に笑いかけると、売り子の女性へと宮田は声をかけた。
「こんにちは」
花から顔をあげた彼女は、宮田へと笑いかけた。
「またいらして下さって、ありがとうございます」
「この間は、ありがとう」
きれいに宮田が笑いかけると、嬉しそうに彼女も笑った。
マフラーを買った店でもそうだったけれど、宮田は覚えられやすい。
端正で、きれいな笑顔の宮田。自分だって見惚れてしまう事がある。
美形は得なのかな。
そんなことを考えていたら、周太を宮田が振り向いた。
「お母さんの好きな花はどれ?」
「え、」
どうしてそんな事を、訊いてくれるのだろう。
今、自分も、母への花束に入れる花を考えていた。
なんだか途惑う。けれど今もこうして、宮田は答えを待っている。
すこし考えてから、周太は口を開いた。
「このなかだと、白い秋明菊」
「そうか、」
微笑んで宮田は、売り子へと声をかけた。
「白い秋明菊がひきたつ花束、お願いできますか」
「贈りものですね、どんな方ですか?」
はい、と微笑んで宮田は答えた。
「穏やかで、瞳が美しい人です」
母の事を言っている。
どうしてなぜ、母の花束を求めてくれるのだろう。
でもたぶんきっと、その理由をもう解っている気がする。
秋明菊は、家の庭にも咲いている。
少し寂しげで、けれど凛とした花。母が好む花。
母の面影を、すこし写したような花姿。
だけれど、その花によせられる言葉は、少し悲しい。
父へ手た向けた花束にも、この花が入っていた。
きっと父は喜んだと思う。
まとめられた花束は、あわい色合いがきれいだった。
花束を持った宮田が、こちらを振り向いて笑ってくれる。
「行こうか、」
花束を携えて歩く宮田は、なんだか良い姿だった。
すれ違う人波からも、惹かれるような視線が投げられる。
父の時も思ったけれど、宮田はこういう姿が似合う。
それよりも、やっぱり訊いておきたい。
そっと周太は呟いた。
「どうしていつも、」
言いかけて、言葉が止まってしまう。
解ってもらえる、そのことが嬉しい。
それが瞳の底から熱くなって、言葉も一緒に止めてしまう。
けれど隣は顔を覗きこんで、笑って言ってくれた。
「言っただろ、大切な人のことは何でも知りたい。そして全部受け止めて、大切にしたいから」
どうしていつもこんなふうに、求める言葉をくれるのだろう。
そしていつもこうやって、そっと心に寄り添ってくれる。
嬉しくて、素直に周太は頷いた。
「…ん、」
「おいで、」
宮田が周太の手をとって、コンコースの片隅に佇んだ。
人がたくさんいるのに、不思議とこの場所だけは静かだった。
静かに顔を覗きこんでくれる、宮田の笑顔が嬉しい。
きれいで端正で、やさしい笑顔。自分だけの為に、笑いかけてくれる。
嬉しくて微笑んだ周太の唇に、そっと宮田の唇がふれた。
「俺の大切な隣を生んで育ててくれた。大切な息子を俺に託してくれた。
俺が尊敬するひとが心から愛した、素敵な女性。そんな周太の母さんに、感謝の花束を贈らせて」
きれいに笑って、宮田が言う。
うれしい。嬉しくて幸せで、微笑みの中から周太は見上げた。
「うれしい。…ありがとう」
「おう、」
きれいな笑顔が見つめてくれる。
たくさんの人が、見惚れるこの笑顔。
それなのに、自分だけを見つめてくれている。
こんなふうにずっと自分も、笑いたかった。
この笑顔をずっと、この隣へと向けていたい。そんなふうに願ってしまう。
blogramランキング参加中!