
今日は、昨日の続きで「解き」について書きたかったのですが、
実際解きながらの写真を載せるのに、今日は天気が悪くて…。
今降っています。晴れた日にしたいので、お天気待ちということにします。
で、今日はちまちまと帯留めなど作ってみました。
写真は「使ったもの」です。
帯留を手作りする…というのは、よくあります。
最近は、裏にぺタッと貼るタイプの金具もいろいろ販売されていますから、
たとえば箸置きとかブローチとかをそのまま帯留にしたり、
フェルトとかビーズなどで手作りしたものに金具をつけたりとか、
さまざまなものができるようになりました。
今回のものは、一番カンタンな、元からできあがっている金具に、
布をかぶせるだけ…というもの。手抜きともいう??はっはっは!
今回使ったのは、時々買い物する「オカダヤ」さんで購入したもの。「くるみ金具」というそうです。
手抜きはいかにもとんぼ流ですが、そうなると一番の問題は「色柄」の選び方です。
これはただの楕円で、しかもごく小さい「キャンバス」ですから、
柄のとり方でイメージが全然違ってきます。(大きさは幅4㎝高さ3㎝です)
まず、こういう作り方をするときには、自分が「ここだわっ!」っと思える柄部分を
確実にみつけられるように「逆型紙」を作ります。
つまり「穴を開けた型紙」です。こんな感じ。
左の楕円形の金属板が、帯留の本体です。
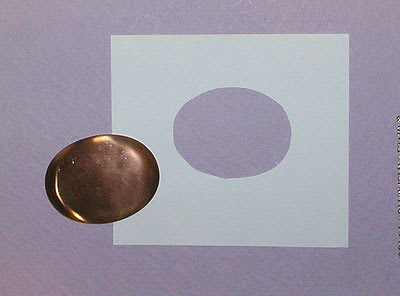
これを、これから使おうとする布のあちこちに当てて、どこを使うか決めるわけですね。
たとえば、こんな生地を出してみました。

こういうものに使うには、細かいならうんと細かい小紋柄、
大柄ならインパクトのある柄、たとえば今回は出さなかったのですが
「人形」とか「唐獅子」とか「宝尽くし」とか、
それひとつだけで柄になるもの、などがいいのではないかと思います。
今回は小紋柄ばかりですが、それでも取るところでずいぶん感じが変わる、
ということを写真で見ていただきましょう。
こちらは真ん中の二枚の小紋、縦と横にとった場合と、柄の多さ少なさでとってみました。
明るさ調整揃ってなくてすみません。




こちら写真の右端の大きな柄の小紋、地色の赤茶色を入れたのと入れないの。
全然イメージがかわりますね。


今度は左上の鮮やかな紺地の小紋と、真ん中下の渋い紬。


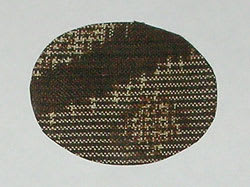
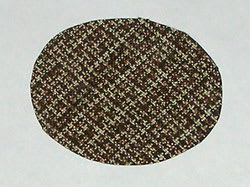
これはすでにお財布になっちゃってるものから5月向きとお正月向き


ハギレで見ていると、帯留になる気がしなくても、
小さなワクに収めると、意外なところがいい柄になります。
さて、いよいよ製作ですが、大島紬のものでやってみます。
まず、場所を決めた柄のところ、ちょっとやりにくいですが裏側に型紙をあてなおします。
「この部分で作りたい」と「それのひっくり返し」の写真です。

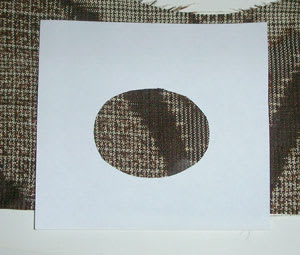
型紙どおりに線を書き写しカット、糊しろは1㎝くらい、これ、ちょっと大きすぎます。
あとで切り直しました。右は少し膨らみを出すための「ネル地」、
こちらはラインから気持ち小さめにしないと、後で本体に入れる時に苦労します。

本体にネル地をのせ、柄布をのせて裏返します。
柄布は「周りに切り込み(黄色の線)」を入れておきますが、
本体の2~3ミリくらい手前で止めます。
写真はすでにボンドをつけちゃってますが、まず真ん中を両方から。
ちょっと引き気味に表にシワがでないように。それから周りを少しずつ貼っていきます。

きちんと貼らないと、写真のように角がツンと飛び出します。
これはきれいに土台に入りませんから、裏側を張るときに爪楊枝を使って、
内側にひくようにして、ふちを滑らかに仕上げます。
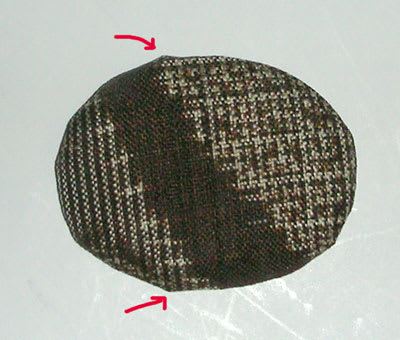

しっかり乾かしたら、土台の方もボンドをつけて、きっちりはめ込みます。
この土台へのボンドは、あまりふちに近いところに塗ると、はめ込んだときはみ出てきます。
少し内側にしておくこと、もしはみ出てきたらすばやく爪楊枝の先などで取ってください。
乾いたらできあがりです。

細かいこととして、ボンドは写真のもの、これは布と金属も貼り合わせられるもの、
商品名は「カネスチック」といいます。ご紹介のオカダヤさんのページでは、
一番上に出ています。セメダインの感じで、ボンドより粘着質なので、
たれると糸引きますし伸びますから、爪楊枝などをうまく使ってください。
ボンドを使うときは、固く絞った濡れ布巾をそばに置いておくこと。
手や指先についたら、すぐにふき取ります。これで作業がラクになります。
今回ネル地を使って膨らみを出しましたが、手芸綿とかキルト芯でも使えます。
どの場合も、生地をかぶせて裏に貼るとき、ふちにかかるとふちの厚みが出て、
土台に入らなくなります。必ず「少し小さめ」にカットします。
手芸材料についてくる説明書や、各種手芸本には「進行」があるだけで、
初心者に対しての細かいところの説明がちょっと足りないなと、いつも思います。
ちょっとしたコツが最初からわかれば「作ったけどきれいじゃない」とか、
「はめこみがうまくいかない」とか回避できると思うんですけどね。
とりあえず「渋め」の帯留がほしいと思っていましたので、これでゲット。
ひし形もほしいなと思っています。(その前に着物をきましょーね…スンマセン)
実際解きながらの写真を載せるのに、今日は天気が悪くて…。
今降っています。晴れた日にしたいので、お天気待ちということにします。
で、今日はちまちまと帯留めなど作ってみました。
写真は「使ったもの」です。
帯留を手作りする…というのは、よくあります。
最近は、裏にぺタッと貼るタイプの金具もいろいろ販売されていますから、
たとえば箸置きとかブローチとかをそのまま帯留にしたり、
フェルトとかビーズなどで手作りしたものに金具をつけたりとか、
さまざまなものができるようになりました。
今回のものは、一番カンタンな、元からできあがっている金具に、
布をかぶせるだけ…というもの。手抜きともいう??はっはっは!
今回使ったのは、時々買い物する「オカダヤ」さんで購入したもの。「くるみ金具」というそうです。
手抜きはいかにもとんぼ流ですが、そうなると一番の問題は「色柄」の選び方です。
これはただの楕円で、しかもごく小さい「キャンバス」ですから、
柄のとり方でイメージが全然違ってきます。(大きさは幅4㎝高さ3㎝です)
まず、こういう作り方をするときには、自分が「ここだわっ!」っと思える柄部分を
確実にみつけられるように「逆型紙」を作ります。
つまり「穴を開けた型紙」です。こんな感じ。
左の楕円形の金属板が、帯留の本体です。
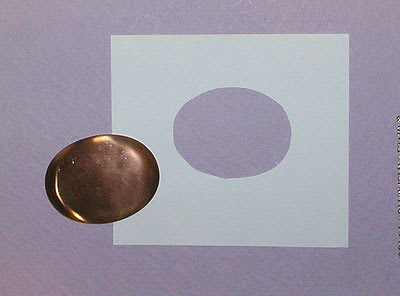
これを、これから使おうとする布のあちこちに当てて、どこを使うか決めるわけですね。
たとえば、こんな生地を出してみました。

こういうものに使うには、細かいならうんと細かい小紋柄、
大柄ならインパクトのある柄、たとえば今回は出さなかったのですが
「人形」とか「唐獅子」とか「宝尽くし」とか、
それひとつだけで柄になるもの、などがいいのではないかと思います。
今回は小紋柄ばかりですが、それでも取るところでずいぶん感じが変わる、
ということを写真で見ていただきましょう。
こちらは真ん中の二枚の小紋、縦と横にとった場合と、柄の多さ少なさでとってみました。
明るさ調整揃ってなくてすみません。




こちら写真の右端の大きな柄の小紋、地色の赤茶色を入れたのと入れないの。
全然イメージがかわりますね。


今度は左上の鮮やかな紺地の小紋と、真ん中下の渋い紬。


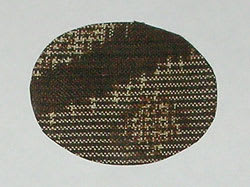
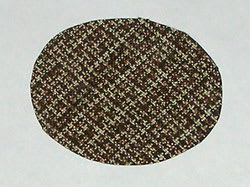
これはすでにお財布になっちゃってるものから5月向きとお正月向き


ハギレで見ていると、帯留になる気がしなくても、
小さなワクに収めると、意外なところがいい柄になります。
さて、いよいよ製作ですが、大島紬のものでやってみます。
まず、場所を決めた柄のところ、ちょっとやりにくいですが裏側に型紙をあてなおします。
「この部分で作りたい」と「それのひっくり返し」の写真です。

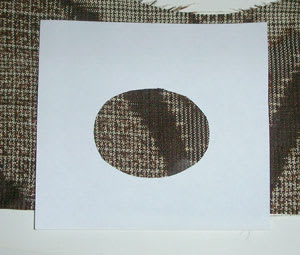
型紙どおりに線を書き写しカット、糊しろは1㎝くらい、これ、ちょっと大きすぎます。
あとで切り直しました。右は少し膨らみを出すための「ネル地」、
こちらはラインから気持ち小さめにしないと、後で本体に入れる時に苦労します。

本体にネル地をのせ、柄布をのせて裏返します。
柄布は「周りに切り込み(黄色の線)」を入れておきますが、
本体の2~3ミリくらい手前で止めます。
写真はすでにボンドをつけちゃってますが、まず真ん中を両方から。
ちょっと引き気味に表にシワがでないように。それから周りを少しずつ貼っていきます。

きちんと貼らないと、写真のように角がツンと飛び出します。
これはきれいに土台に入りませんから、裏側を張るときに爪楊枝を使って、
内側にひくようにして、ふちを滑らかに仕上げます。
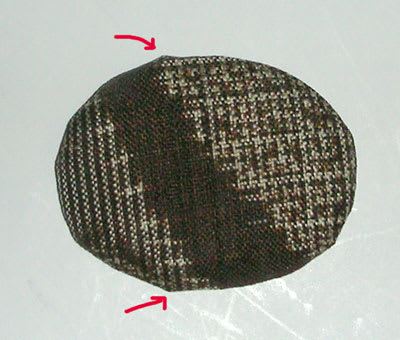

しっかり乾かしたら、土台の方もボンドをつけて、きっちりはめ込みます。
この土台へのボンドは、あまりふちに近いところに塗ると、はめ込んだときはみ出てきます。
少し内側にしておくこと、もしはみ出てきたらすばやく爪楊枝の先などで取ってください。
乾いたらできあがりです。

細かいこととして、ボンドは写真のもの、これは布と金属も貼り合わせられるもの、
商品名は「カネスチック」といいます。ご紹介のオカダヤさんのページでは、
一番上に出ています。セメダインの感じで、ボンドより粘着質なので、
たれると糸引きますし伸びますから、爪楊枝などをうまく使ってください。
ボンドを使うときは、固く絞った濡れ布巾をそばに置いておくこと。
手や指先についたら、すぐにふき取ります。これで作業がラクになります。
今回ネル地を使って膨らみを出しましたが、手芸綿とかキルト芯でも使えます。
どの場合も、生地をかぶせて裏に貼るとき、ふちにかかるとふちの厚みが出て、
土台に入らなくなります。必ず「少し小さめ」にカットします。
手芸材料についてくる説明書や、各種手芸本には「進行」があるだけで、
初心者に対しての細かいところの説明がちょっと足りないなと、いつも思います。
ちょっとしたコツが最初からわかれば「作ったけどきれいじゃない」とか、
「はめこみがうまくいかない」とか回避できると思うんですけどね。
とりあえず「渋め」の帯留がほしいと思っていましたので、これでゲット。
ひし形もほしいなと思っています。(その前に着物をきましょーね…スンマセン)





























奈良はお花見日和の最高のお天気だったんですよ。
帯留め金具はよく見ますが、くるみ金具って
あるんですね。
とんぼ様はほんと、なんでもよくご存じと
感心致します。
準備ばっちりじゃないので、
できの悪いのが多いのだけれど、
逆型紙。勉強になります。
それと、お店も載せていただけるので、
嬉しいです。
先日のみかん箱の貯金箱といい、
なんだか、
とんぼさんの真似をしてみたくなるのは、
どうしてかしら??
困った私です。
興味はどんどん膨らんじゃいます。
昨日はまだ小雨程度から始まったんですが、
夜も、今日も、寒い雨…。
桜もたいへんですねぇ。
以前はよく手芸やさんを何時間も歩きました。
みてるだけで面白いですよね。
用もないのに「もしかしたら使うこともあるかも」
なんて、買ったりして…。
最近はもっぱらネットです。
手芸やさんと生地やさんのHPは、
いくと出られなく?ので困りますー。
私もなんでもかじりたくなる性分です。
ザセツしたものが山ほど…?!
ダメですよぉ私に似ちゃぁ…。
家の中が中途半端なもので埋まりますー。