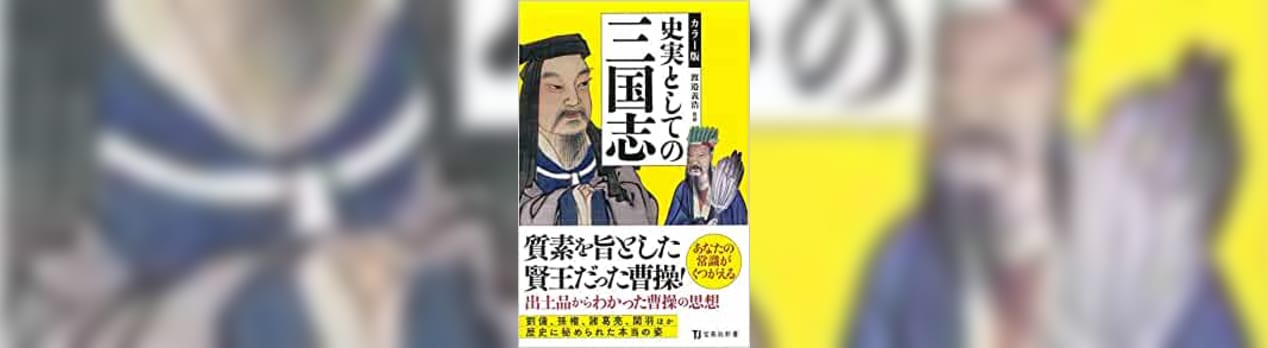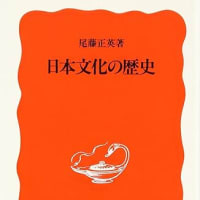1800年前の中国で実際に起きていたことを物語に仕立て上げたもの、それが「三国志演義」でこちらは600年ほど前に中国で羅貫中により書かれた。それを吉川英治が「三国志」として日本語で出版してものを読んだ日本人が多いはす。本書は、その大もとの史実を三国時代当時に陳寿がまとめた歴史書「三国志」を紐解き、その後の歴史的研究の知見を踏まえて詳らかにしようとしたもの。
物語においては、漢を再び蘇らせるという志を持った劉備玄徳が主人公であり、それを阻もうとする曹操は悪役。2009年にはその墓が発見され、埋葬は質素に行うよう指示したと言われていた曹操の墓の埋葬品が実際にも質素だったことが証明された。曹操はそれまでは儒教の徳目である「孝」「廉」を備えることが人物評価の中心だった常識に対して、薄葬令により儒教的価値観を形骸化した儀礼的な上辺の取り決めや前例として排除しようと試みていた。本書は曹操が実際には一番の英傑だったことを解き明かしていく。
私も20代に読んだ「三国志」を思い出しながら、史実を確認していったが、三英傑以外の登場人物名、例えば董卓、呂布、袁紹、馬謖、司馬懿仲達などに記憶があることに驚く。赤壁の戦いや髀肉の嘆、泣いて馬謖を斬る、三顧の礼、出師表、五丈原の戦いなどは何度も耳にしたことがあるはず。テレビの特集などでも度々取り上げられてきたからだろうと思うが、それほど三国志は日本人にも縁のある、馴染み深い歴史だと言える。
三国時代とは、後漢が黄昏を迎えつつあった西暦150年ころから幕を開け始める。黄巾の乱と董卓の乱という2つの動乱により命脈を絶たれたのが後漢。皇帝の外戚と宦官による政争が動乱の原因であった。帝国の清流であった袁紹は将軍の何進と結託し宦官一掃を試みるが、外戚勢力と宦官勢力は共倒れ、その空白に乗じたのが地方軍閥の一つだった董卓。呂布もその勢力の一角を占めた。反董卓勢力連合として頭角を現したのが曹操だった。養祖父が宦官だったため、清流派に好意的な「三国志」「後漢書」などの歴史書は曹操は恥ずべき家系として描く。しかし曹操は辺境の鎮撫で名を挙げた西北の列将たちに薫陶を受けて育ち、異民族との戦いを経験してきた。儒教の2つの統治概念「寛治」「猛政」は寛容と統制をうまく使い分ける。これを身に着けたのが曹操だったという。そして反董卓勢力のなかで抜きん出たのが曹操。力の源泉には、黄巾党の残党たる青州兵、人材の宝庫である「名士」の抜擢、土地開拓の屯田制があり、後漢の天子を奉戴し自らは宰相として権力を握った。
これが200年代で、そのころ劉備は名士の一人、劉表の客将の一人だったが、戦いへの出番がなく「髀肉の嘆」で挫折を味わう。吉川英治の三国志では貧しい農家の生まれとして描かれる劉備だが、実際は祖父は県令であり、地域の有力者の家柄。しかし曹操ほどの家柄でもなく名士とのつながりは持てず、アウトローの豪傑である関羽、張飛に支えられ、兄貴分は公孫瓚、かれも士大夫としては社会階層は低かった。劉備は公孫瓚のもとで各地を転戦し頭角を現す。必要なのは人材、そこで三顧の礼をもって迎えたのが諸葛亮孔明だった。董卓勢力が滅びた204年はまだ群雄割拠の時代であり、北には曹操以外に、高幹、袁譚、袁尚らが勢力を持ち、南には孫権、劉表、劉璋らが勢力を持っていた。
208年、劉備は長阪で曹操に戦いを挑む。劉備軍は敗れるが、その時活躍したのが張飛と趙雲、長坂坡の戦いである。逃げ道をなくした劉備は孫権に助力を求める。しかし孫権も曹操にはかなわないと考えていた。その逆境を跳ね返そうとしたのが、孫権のもとにいた魯粛と周瑜。二人は、曹操は逆賊である、呉の水軍は魏よりも強い、曹操には背後の弱みがある、曹操軍には疫病の恐れがある、曹操軍の結束は弱い、と孫権に劉備との連合を提案する。説得を受けた孫権は、曹操が丞相を名乗り最高権力者となろうとするのを見て、劉備と手を組んで戦うことを決める。そして迎えたのが赤壁の戦いで、曹操軍は敗北するが、三国志自体には詳細は記述されていない。物語では劉備軍の勝利とされているが、実際には周瑜と魯粛という二人の戦略家の読みが大いに貢献した。その結果、215年時点で三英傑の呉、蜀、魏の三国時代を迎えることになる。
219年には劉備軍は曹操軍を破り劉備は漢中王を名乗るが、盟友関羽が孫権軍に破れ斬首される。220年には曹操は病死、魏皇帝には曹操の息子、曹丕がつき、後漢が正式に滅亡する。221年には蜀の皇帝に劉備がつき、曹丕が孫権を呉王に任命する。222年には呉の陸遜が劉備軍を撃破、223年に劉備は白帝城で病死、226年には曹丕も病死する。227年には諸葛孔明が出師表を奉り北伐を開始。229年には孫権が呉の帝位につく。234年が五丈原の戦いで諸葛孔明が陣中で没する。「死せる孔明生ける仲達を走らす」である。魏では249年に司馬懿仲達がクウデターで政権を握り、252年には孫権も病死、263年には蜀が魏に降伏、蜀が滅亡する。これで三国時代には終わりが告げられ、280年には晋が中国を統一することになる。
カラー版で三国の関係や行軍など図解も多く、読みやすく記憶にも残りやすい。