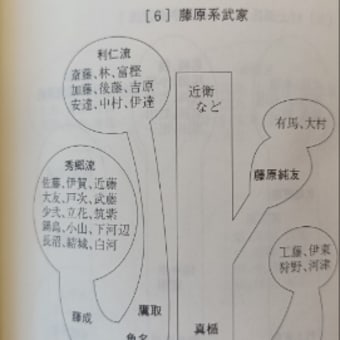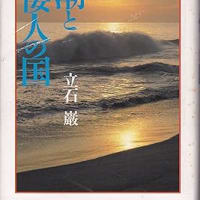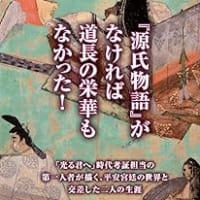電鉄ビジネス、といえば思い浮かべるのは小林一三、そしてそのモデルを関東に展開したのが五島慶太や堤康次郎。ベッドタウンとターミナルをつなぐ鉄道を作り、住宅地を作るだけではなくて、百貨店とエンターテインメントをつくって、人々の生活を豊かにした、と思っていた。本書では、その前に、社寺参詣があったというのだ。京浜急行は川崎大師と穴守稲荷、京成電鉄は成田山新勝寺、阪急電鉄でさえその前身の箕面有馬電気軌道は温泉に参詣輸送を大きな目的にしていた。
私鉄経営での最初のモデルは、日本では蒸気鉄道からの転換、二番目が寺社参詣・観光地輸送、三番目に都市間連絡、という変遷をたどっている。1930年代になって、都市計画の一環として交通調整が行われた。乱立していた交通機関の統合である。東京近郊の私鉄は、東武、西武、東急、京成の4社に集約されるという政策が取られた。
事例としては、池上本門寺もその寺社参詣モデルの寺の一つだったが、近世から江戸近郊の代表的な参詣地として栄えてきたため、新勝寺や川崎大師ほどの寺門興隆努力が不足していた。競馬場ビジネスに手を出したりしたが、それは失敗、日蓮宗の大本山であったが、そのポテンシャルを十分活かしきれずに来た。そこで池上電鉄を開業させたのが高柳淳之介、1920年代のことだった。しかしその頃には名前の上がった電鉄経営はすでに寺社参詣から通勤通学への転換を始めていた頃であり、遅きに失した感があった。そのため、池上電鉄は先行していた五島慶太の東急傘下に入っていった。池上は田園郊外的な住宅地域への変容を遂げる中で、「衛生的で健全」なイメージを掲げる戦略を掲げた。
戦後になり昭和30年代に入ると、東京では地下鉄と私鉄の相互乗り入れが運輸省主導で行われるようになった。戦前の交通調整では実現できなかった東京23区を拡大していく大東京の交通網を構築する、という試みである。同じような階層の人たちが似たようなライフスタイルで生活し、街を形成する、20世紀後半までの成長経済ではこうした画一的まちづくりが功を奏した。
しかし、人口減少時代に入り、均一的な街づくりが、高齢化による買い物困難者を生み出す。郊外型田園都市開発やニュータウン開発で、近隣商店街が廃れてしまっていたからである。20世紀型の街づくりは転換点を迎えている。多摩ニュータウンや千里ニュータウンなど各大都市郊外に開発された大規模住宅地では、住民高齢化によるさまざまな問題が表面化してきている。こうした新たな問題解決のためには、電鉄が発展してきた歴史を紐解き、高齢化時代の多様性に電鉄などの交通網がどのように変化する必要があるのかを、再び考える時が来ている。実際に電鉄経営がたどってきた塁歴のバリエーションを考えてみることである。その中の一つが寺社参詣と電鉄の関わりであり、21世紀の交通調整を再検討するヒントにもなる。本書内容はここまで。
なるほど、と思った。20世紀後半に大都市郊外に開発されたニュータウンの高齢化問題、住宅の老朽化問題は、その場所だけを見るのではなく、そこに至る交通網から考え直す必要があるということ。これこそ都市ビジョンであろう。利権と権力欲に目がない政治家の中にも、こうしたビジョンを持って、安定成長する時代の日本の住宅政策と交通政策にリーダーシップを発揮してくれる人物が出てきてくれるだろうか。