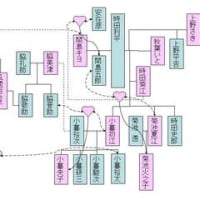1997年から2012年にかけて生まれた世代がZ世代。アメリカのこれからを支えていく世代でもある。アメリカ国内の人口構成はまさに多様性が進行した状態であり、人種、宗教観、価値観、ライフスタイル、国家観、世界認識は日本に比べると比較にならないほどに多様である。アメリカは「世界の警察官」と呼ばれた「例外主義(Exceptionalism)」時代が長く続いてきたが、今その時代は変わりつつある。アメリカ第一主義をとなえる当時のトランプ大統領は、気候変動や国連における国際的な枠組みから撤退し、MAGAを主張。アメリカにおけるZ世代は、例外主義を前提としない国家観をアイデンティティに持つ世代となる可能性がある。アフガニスタンからの撤退はその象徴であった。超大国による大義なき侵略を受けるウクライナへの軍事支援をどの範囲でいつまで続けるのかは、紛争長期化により、国内外でのこれからの大きな議論となる可能性を秘めている。
欧州での難民増加は、紛争国の問題解決のためにはある程度の受け入れが必要と判断しつつも、身の回りでの犯罪増加や治安悪化は、各国の選挙結果としてリベラル派よりも愛国主義敵勢力の増大を招き始めている。保守の内向き化傾向はアメリカだけではなく欧州、そして日本でも見えている。侵略者のリーダとなってしまったプーチンを支持する右派でさえ一定の支持を得る傾向がある。ウクライナ危機では、リベラル派から見て「差別的」な発言をする人物、特に権力者を糾弾し役職や地位から追い落とす「キャンセル・カルチャー」があるが、そうした動きに反発する勢力がある。コロナ対応のためのワクチン接種やマスク着用への反発でさえも、キャンセルカルチャーへの批判に繋がる場合がある。日本では差別的発言はコンプライアンス問題として批判されるが、行き過ぎた批判は逆に反発を招き、保守対リベラルの議論と混ざり合って、混沌とした論争となることも多い。アメリカではPC(Politicaly Correctness)として数十年前から強く認識され、差別的発言や多様性容認の意識が強く、逆にPCへの内心での反発が、トランプ大統領の「忌憚なき発言」により、「そんなこと言っていいんだ」という白人層、労働者階級における鬱憤晴らしにもなっていった。PCはBLM(Black Lives Matter)へと繋がり、Woke(常に社会的正義に覚醒している状態)勢力へと繋がり、内向きになった保守勢力と対立することにもなる。Z世代にとって現在のハリス対トランプはWoke勢力と内向き保守との対立とも表現できる。
中国での習近平体制は、領土的野望を明確に表し、香港統治を共産党化し、西側陣営からの資本主義化してきた中国への民主主義の芽生え期待を打ち砕いた。中国へのサプライチェーンとして、市場としての経済的相互依存にも一定の距離感を保つことと、未来における協調に僅かな希望を持つことのバランスは今でも存在するが、Z世代にとっては、ロシアのウクライナ侵攻はその試金石とも見られるようになってきた。
同時代のアメリカ人たちにとってはテロとの戦いは反対者のいない正義だったが、Z世代にとって9・11のテロ事件はすでに起きていた事件であり、「テロとの戦い」の後遺症とイスラムへの嫌悪感は対立感情として認識される。また世界の警察官vsMAGAでもあり、いまでは「ウクライナ侵攻への支持と民主主義の戦い」対「イスラエル支持」とも認識される。人権や人道という切り口からは、アメリカの二重基準とも意識され、アフガニスタン撤退における苦い経験とも重なって見える。白人社会におけるウクライナ難民への受け入れ支援とパレスチナ、アフリカ難民受け入れの意識的差異は、人道に潜む差別的下層意識をZ世代に意識させた。カマラ・ハリスのジェンダー平等認識はBLM運動やイスラエル支持などにおいて、人道の二重基準を認識させ、大統領選の判断基準を複雑化させる。
1973年以来中絶の権利を定めてきたロー対ウェイド判決の2022年の最高裁における破棄判決は、中絶の権利を当然の人権と考えてきたZ世代にも衝撃を与えた。アメリカ社会では圧倒的多数のプロチョイス派は、司法の権力闘争ではプロライフに負けてしまうというのが、トランプ流司法、共和党保守派の歴史的勝利として歴史に残ってしまった。アメリカは人権の担い手と言えるのだろうか、それがZ世代の抱えるアメリカ観、未来に何がつなげるのかを2024年の大統領選はZ世代に問うている。本書内容は以上。