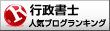さて、模試で得点が良くても、合格しない人をちょっと分析してみましょう。
宅建試験で、模試に強いが、本試験に弱い人がいます。基本ができていないわけではありません。
要は、本番に弱い人です。もともと択一が苦手な人は、練習ではあまり緊張しないので、いい点を得点できるのですが、いつもと違う本試験では、なかなか普段の力が出ず不合格、1,2点足りず落ちてしまう、ということになります。
傾向として、本試験に近づくにつれ、得点が徐々に下がってきている人は、要注意ですね。
こういう人は、時間をきちっと決めて練習し(早く解ける技術を身につけ)、1つ1つの肢では悩まず、4肢のトータルで、1つの肢が解ければいいという作戦をとるべきです。
問題を解くとき、分からない肢が出てきても、ぐじぐじ気にせず簡単に留保できるように。
また、択一は不得意ではないと思っている人がいます。でも、合格しない。では、なぜ模試でいい点を取れるのか。
模試の傾向にもよると思いますが、似た問題を解いていて、すでに答えを覚えているためにできる人です。なんとなく、過去問をやっているのでこれではないかとか、模試でも過去問を組み合わせたものなら、過去問で見た肢だから、これだろう、と解く人です。
肢の切り方として、やった肢だから(似た肢だから)・・。
こういう人の共通点は、授業の聴き方が非常に悪い点が上げられます。
それは、どういうことかというと、まあ、自分で“考える”努力をしていないということなんですが、全部覚えようとしているんです。なんでも・・・。
自分1人で勉強していても、どうしてそうだろうとか、なんでこうなるのだろうという勉強をしていない傾向があります。
授業でも、こういうつながりになっているとか、趣旨からこういう流れで覚えるといいとか、単に記憶するのではなくきちんと理由があってこのように認められているのだ、と力説していていも、後で聴いてみると、それらがいえないんです。ぼーとしているんです。
それだから、本試験で、少しひねられると知識では解けないから、落ちてしまうということになる、という悪循環です。
やっぱり、合格する人は、過去問も理解しながら解くし、授業の聴き方も抜群だし、うかる要素があると言うことです。
身に覚えのある人は、まだまだ修正できると思いますので、反省してみてください。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
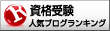
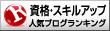
宅建試験で、模試に強いが、本試験に弱い人がいます。基本ができていないわけではありません。
要は、本番に弱い人です。もともと択一が苦手な人は、練習ではあまり緊張しないので、いい点を得点できるのですが、いつもと違う本試験では、なかなか普段の力が出ず不合格、1,2点足りず落ちてしまう、ということになります。
傾向として、本試験に近づくにつれ、得点が徐々に下がってきている人は、要注意ですね。
こういう人は、時間をきちっと決めて練習し(早く解ける技術を身につけ)、1つ1つの肢では悩まず、4肢のトータルで、1つの肢が解ければいいという作戦をとるべきです。
問題を解くとき、分からない肢が出てきても、ぐじぐじ気にせず簡単に留保できるように。
また、択一は不得意ではないと思っている人がいます。でも、合格しない。では、なぜ模試でいい点を取れるのか。
模試の傾向にもよると思いますが、似た問題を解いていて、すでに答えを覚えているためにできる人です。なんとなく、過去問をやっているのでこれではないかとか、模試でも過去問を組み合わせたものなら、過去問で見た肢だから、これだろう、と解く人です。
肢の切り方として、やった肢だから(似た肢だから)・・。
こういう人の共通点は、授業の聴き方が非常に悪い点が上げられます。
それは、どういうことかというと、まあ、自分で“考える”努力をしていないということなんですが、全部覚えようとしているんです。なんでも・・・。
自分1人で勉強していても、どうしてそうだろうとか、なんでこうなるのだろうという勉強をしていない傾向があります。
授業でも、こういうつながりになっているとか、趣旨からこういう流れで覚えるといいとか、単に記憶するのではなくきちんと理由があってこのように認められているのだ、と力説していていも、後で聴いてみると、それらがいえないんです。ぼーとしているんです。
それだから、本試験で、少しひねられると知識では解けないから、落ちてしまうということになる、という悪循環です。
やっぱり、合格する人は、過去問も理解しながら解くし、授業の聴き方も抜群だし、うかる要素があると言うことです。
身に覚えのある人は、まだまだ修正できると思いますので、反省してみてください。
では、また。