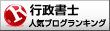問題文を正確に読めることは当然重要です。
もちろん、読むコツを身につけるのも、過去の問題をしっかり解くことで、徐々に身に付くこともあります。
ですから、良問揃いの過去問はやはり何回も解くべきです。
そこで、ひとつそのサンプルをあげておきましょう。
宅建過去問にも良問が多くありますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する)
Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。(平成16年・問10)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここは、問題文の「敷地賃借権付建物」をいかに想像できたかです。
間違える人は、「土地付建物」と読んでいるはずです。そうではないということですね。
つまり、思うことは、Bは敷地の欠陥により、買った建物に亀裂が入り建物に往めない可能性がありますね。
そこでこのような不利益をどのような方法で解消するかが問われています。
まず考えられる一つの方法は、売主への担保責任の追求ですね。
しかし、これはできないのです。
買っているのは、目に見えない債権である敷地借地権ですから、それに瑕疵がないからですね。あるのは土地の方・・。別に土地を買っているのではないし・・。
土地付き建物を買ったのなら、土地の性質上建物が壊れるような性質ですから、「隠れた瑕疵」があるわけです。おお、そうか。
もちろん、別の方法ができないかも考えておきましょうか。
Bがもし正当にそこに往めるのなら、土地所有者との関係で賃貸借が継続していきます。
そこで、Bは賃借人として敷地の欠陥を直すように賃貸人に請求することはできるのです。
瑕疵担保責任はできないが、直せとは別の方法でできる、責任の根拠が異なるということですね。
このように「あ、このように意識して読んでいなかった」と過去問を解くことで、新たな、つまりテキストではなかなか発見できない、読み方が出来るのでした。
この問題も、上記項目別過去問p58に丁寧に解説しておきましたから、参考にしてくださいね。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
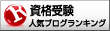
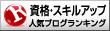
もちろん、読むコツを身につけるのも、過去の問題をしっかり解くことで、徐々に身に付くこともあります。
ですから、良問揃いの過去問はやはり何回も解くべきです。
そこで、ひとつそのサンプルをあげておきましょう。
宅建過去問にも良問が多くありますよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する)
Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。(平成16年・問10)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここは、問題文の「敷地賃借権付建物」をいかに想像できたかです。
間違える人は、「土地付建物」と読んでいるはずです。そうではないということですね。
つまり、思うことは、Bは敷地の欠陥により、買った建物に亀裂が入り建物に往めない可能性がありますね。
そこでこのような不利益をどのような方法で解消するかが問われています。
まず考えられる一つの方法は、売主への担保責任の追求ですね。
しかし、これはできないのです。
買っているのは、目に見えない債権である敷地借地権ですから、それに瑕疵がないからですね。あるのは土地の方・・。別に土地を買っているのではないし・・。
土地付き建物を買ったのなら、土地の性質上建物が壊れるような性質ですから、「隠れた瑕疵」があるわけです。おお、そうか。
もちろん、別の方法ができないかも考えておきましょうか。
Bがもし正当にそこに往めるのなら、土地所有者との関係で賃貸借が継続していきます。
そこで、Bは賃借人として敷地の欠陥を直すように賃貸人に請求することはできるのです。
瑕疵担保責任はできないが、直せとは別の方法でできる、責任の根拠が異なるということですね。
このように「あ、このように意識して読んでいなかった」と過去問を解くことで、新たな、つまりテキストではなかなか発見できない、読み方が出来るのでした。
この問題も、上記項目別過去問p58に丁寧に解説しておきましたから、参考にしてくださいね。
では、また。