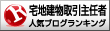今回は、法令の大きな視点を。
今年は、公的機関を押さえておきましょう。
それを3つの法律を押さえておきましょう。
まず、国土法だ。
これは、国も都道府県でも市町村でも、契約の一方に係われば、規制されない。つまり、23条なら、事後届出は不要だ。
次に、都計法だ。特に開発行為。
ここは、すべて許可が必要だ。ただし、国、都道府県、一定の市は協議すればいいという制度はある。
最後は、農地法だ。これは要注意だ。
3条と4・5条は仕組みが違うからだね。
3条は、国と都道府県なら、常に許可不要だ。市町村では、許可必要だ。
国・都道府県・そして市町村は、4・5条は、原則許可必要だ。しかし、一定の例外がある。
3つ違っているので、そこを意識して覚えておかないと行けないね。
もうあと、3日だがまだまだチェックすることがあるはず。
最後まで諦めないことだね。1点でも、安定してとれる分野を作っておこう。
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
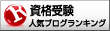
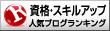
今年は、公的機関を押さえておきましょう。
それを3つの法律を押さえておきましょう。
まず、国土法だ。
これは、国も都道府県でも市町村でも、契約の一方に係われば、規制されない。つまり、23条なら、事後届出は不要だ。
次に、都計法だ。特に開発行為。
ここは、すべて許可が必要だ。ただし、国、都道府県、一定の市は協議すればいいという制度はある。
最後は、農地法だ。これは要注意だ。
3条と4・5条は仕組みが違うからだね。
3条は、国と都道府県なら、常に許可不要だ。市町村では、許可必要だ。
国・都道府県・そして市町村は、4・5条は、原則許可必要だ。しかし、一定の例外がある。
3つ違っているので、そこを意識して覚えておかないと行けないね。
もうあと、3日だがまだまだチェックすることがあるはず。
最後まで諦めないことだね。1点でも、安定してとれる分野を作っておこう。
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。